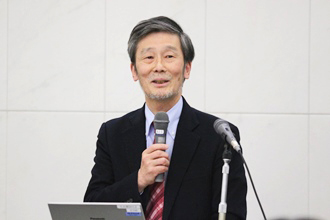| プログラム |
開会
主催者挨拶/来賓者挨拶 |
第1部
「学部におけるグローバル人材育成の
取り組みと計画」 |
第2部
学部長によるプレゼンテーション
「私の考える『国際化』」
パネル・ディスカッション
「大学の国際化とグローバル人材育成の未来」 |
グローバル人材の育成という課題に対し、各学部からいかにアプローチすべきか。
本学は文部科学省による事業「経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援」(GGJ)の採択校として、2012年より全学をあげてグローバル化を推進してきました。同事業の終了年である平成29年3月を迎えた今、総括としてグローバル化への取り組みを振り返り、2017年度以降どのように発展させていくか、シンポジウムという場をもって本学教職員および学生、来場者の方々と共に考えました。
第1部では各学部より教授・准教授と学生が登壇し、学部ごとに実施するプログラム等を紹介。
第2部では各学部長が考える国際化について発表があり、続いてパネル・ディスカッションを行いました。
会場には、本学関係者のほか他大学の学生や教職員、教育関連団体・企業、高校生、卒業生ら、定員に達する数多くの来場者が集まり、会場は活気に溢れました。パネル・ディスカッション後の質疑応答では、本学の取り組みについて来場者から賞賛や意見があったほか、学生から教員たちにグローバル人材となるためにはどうすべきかシンポジウムを通じた意見が求められ、白熱のうちに閉会を迎えました。
第1部「学部におけるグローバル人材育成の取り組みと計画」
法学部の取り組みと計画
「グローバルなリーガルマインドの育成 ~英語で法学を学ぶ~」

北井辰弥(法学部教授)
|
【学部の取り組みと計画】
◆卒業後の進路「一般企業へ就職」or「法科大学院へ進学して法律家」に合わせた学習モデルを用意。
◆法学部独自の奨学金「やる気応援奨学金」によって、自ら計画した留学プログラムを実現できる。 |
【学生の取り組み】
黒岩 瞳さん(法学部法律学科4年)
◆法律家を目指し、国際教育に力を入れている中大に入学。
◆1年次:多摩学生研究棟(炎の塔)に所属し、法律を学習。
◆2年次:留学生たちと一緒に英語で日本法を学ぶ「比較憲法」、現地法を学ぶ短期留学「アクティブ・ラーニング海外プログラム」を履修。
◆3~4年次:国際関係学を学ぶため、イギリスのブラッドフォード大学に1年間留学。
⇒世界各国の学生と過ごしたことで、平和の捉え方・正義に対する価値観の違いや多様性を知った。
備前智宏さん(法学部法律学科4年)
◆1年次:「やる気応援奨学金」海外語学研修部門を履修し、1か月間オーストラリアへ語学習得を目的に留学。
⇒他の留学生は、英語を使って自身の専門分野を高めることが目的だった。一方、自分は法律用語が英語で話せず、専門性を持つことの重要性に気付く。
◆2年次:「オーストラリア短期留学」を履修し、法律を英語で学ぶ。
⇒日本語で学んだ法律を、英語で討議できるかチャレンジ。
◆3年次:JICA「ハノイ法整備支援インターンシップ」に参加。各国の法律家が、自国の法律をベースにベトナム法について模索する現場を体感。
⇒専門性を持って世界で活躍することに魅力を感じる。会計と法律の知識を活かし、将来は海外で働くことを希望。 |

黒岩 瞳さん(法学部法律学科4年)
|

備前智宏さん(法学部法律学科4年)
|
経済学部の取り組みと計画
「経済学部から世界をひらく ~『海外インターンシップ』の取り組み~」
【学部の取り組みと計画】
◆GGJ採択後、3つのプログラムを柱にグローバル化を推進。
「海外インターンシップ」
「グローバル・フィールド・スタディーズ」
「グローバル・リーダーズ・プログラム」
◆2017年度より「海外インターンシップ」の留学先を拡大し、履修者数を増員予定。 |
【「海外インターンシップ」現地企業コースに参加した学生の取り組み】
インターンシップ先:イギリスの企業
目標:インターンシップ先にてプレゼンテーションを行う
事前学習:英語力、ビジネススキルの向上
インターン:企業理念やビジョンを学習等
プレゼンテーション内容:最終日に写真共有サービス「Instagram」のアカウント開設を提案
園川裕季さん(経済学部国際経済学科3年)
◆英語が得意ではなかった自分にとって、海外インターンシップは挑戦だった。
◆日常では知りえない自分の本質に気付く機会になった。
近藤佑美奈さん(文学部英語文学文化専攻3年)
◆ビジネスシーンでは英語力だけでなく、英語の使い方、積極的な姿勢、異文化理解が必要。
◆日本企業と異なりフランクな職場環境。文化の違いを受け入れることが、良好なビジネスに繋がると感じた。
大角美鶴さん(経済学部国際経済学科3年)
◆海外インターンシップに参加する以前の2年間は国際寮で生活。海外で活躍している寮生は、ポジティブで一人ひとりがどう行動すればいいかを考えていた。自分も彼らのようになりたいと海外インターンシップに参加。
◆インターン先では個々が自分の考えを発信し、チームワークを構築。社会では個々の個性を尊重することが大事だと感じた。
山崎 遥さん(経済学部国際経済学科2年)
◆高校生の時に1年間、カナダに留学。大学に入学して経験豊かな人々と出会う。自信が持てなくなった自分を変えるため、インターンシップに参加。
◆過去の自分が知らなかったビジネスの世界を体験し、新たな視野が持てた。 |

学生とともに登壇し、学部の取り組みを説明した
野口陽史(経済学部事務室グローバル教育運営担当職員)
|

「海外インターンシップ」の流れを
自身の“気づき”を交えて発表した学生たち
|
商学部の取り組みと計画
「双方向型商学部グローバルインターンシッププログラム」
【学部の取り組みと計画】
◆タイ・パンヤピワット経営大学(PIM)と締結し、他学部では実績のない双方向型のグローバルインターンシップを実施。留学生の受け入れ & 本学学生の派遣を行っている。
本学学生1年次:「インターンシップ入門」として講義を受講
本学学生2年次:演習/ディスカッション
実践/PIMの経営母体「CPALL株式会社」(タイでセブン-イレブンを経営)にて
2週間の海外インターンシップ
段階的なキャリア形成を実践。
お互いに母国語ではない英語をツールに協働することで、実践的な海外インターンシップを経験する事ができる。 |
【「双方向型商学部グローバルインターンシッププログラム」に
参加した学生の取り組み】
PIM学生と交流
CPALL株式会社の関連企業を訪問
CPALL株式会社でインターンシップ
福井 麗さん(商学部商業・貿易学科2年)
◆語学留学と違い、海外インターンシップではツールである英語を使って自らが働き掛けないと、状況が変わらない。「働く」ということを学べた。
岩田夏実さん(商学部商業・貿易学科2年)
◆現代社会において、近隣アジアなど英語を母国語としない国々とのビジネスは一般的。そうした国々とコミュニケーションを取る際は、文法ばかりにとらわれず、相手が何を必要としているか五感を使って相手のニーズを考えることが重要。 |

英語で発表した福井さん、岩田さん
|

齋藤正武(商学部准教授)
|
理工学部の取り組みと計画
「理工学部・理工学研究科におけるグローバル教育の取り組み」
【学部の取り組みと計画】
◆理工系は論文を英語で発表することが前提。
◆2015年度、理工学部独自で海外研修プログラム「グローバルスタディーズ」を開設。世界に対し課題発見力・探求思想を備えた人材育成に取り組む。
◆理工学部では4割の学生が大学院に進学するため、大学院のグローバル化も重視。2015年度には短期留学プログラム「海外特別研修」を開講。
2017年度の計画
学 部:派遣先の新規開拓を行い、派遣学生を増員
大学院:「海外特別研修」の派遣学生を増員
英語による理工学に関する講演「理工学英語セミナー」の実施回数を増回 |

樫山和男(理工学部教授)

宇津木春菜さん(生命科学科2年)
|
【学生の取り組み】
宇津木春菜さん(生命科学科2年)
◆1年次:「グローバルスタディーズ」にて、ハワイ大学に留学。
⇒英語に対する意識が高い理工学部生と出会えた。
◆留学後も英語を話す機会を作るため、留学したメンバーと国際交流サークル「白風(しろいかぜ)」を2016年2月に設立。メンバーは80名。3分の1は留学生。
活動内容
1) 留学生と英語で交流
2) 留学生をサポート。役所への手続き、後楽園キャンパスの案内、日本の伝統文化紹介等
3) 留学相談会の開催
4) 他団体と共同し、スポーツ大会やボランティア活動を実施
◆今後は地域自治体との繋がりの強化を目指す。 |
文学部の取り組みと計画
「文学部におけるグローバル人材育成の試み」

野宮大志郎(文学部教授)
|
【学部の取り組みと計画】
◆グローバル教育の視点から見た、文学部学生たちの課題。
⇒外国語に対する興味・自信の欠落。
⇒私的領域の中で活動し、社会に対する関心が希薄。
⇒グローバルな領域で発生している事柄に対する知識の不足。
◆現代社会において、世界にひとりで立っても対等に主張できる力を身に付ける必要がある。
◆現状を打開するグローバル人材を育成を構想。
⇒2017年度より「Global Sociology Program」を開講。 |
Global Sociology Program
前 期:グローバル・マインド授業
文法の間違い、日本語の混合も認める授業で「伝わる」ことへの自信をつける
後 期:クロス・ボーダー社会学
国境を越え発生している社会問題を発見・理解・解決提案し、
技能と知識を身につける
年度末:世界に触れる国際会議
海外大学研究者を相手にプレゼンテーションし、友人になる
実践的な取り組みにより、臆さずに対話する力を身につける
◆2016年度、グローバル・マインド授業の要素を取り入れた模擬授業を実施。
⇒最終授業日にアンケート調査を行った結果、英語技能に関し平均140%の伸び。
心の壁がなくなる、英語の機能向上等成果が見られた。 |
総合政策学部の取り組みと計画
「国際化における異文化理解の重要性 ~総合政策学部での学習体験から~」
【学部の取り組みと計画】
◆各国に存在するシステムの根底には自国の文化があり、その文化を理解することが重要。
◆海外に長期間滞在することだけが、グローバルではない。 |

鈴木崇允さん(総合政策学部政策科学科3年)
|

加藤久典(総合政策学部教授)と鈴木さん
|
【学生の取り組み】
鈴木崇允さん(総合政策学部政策科学科3年)
◆グローバル化とは人々、社会の違いを知り、理解して共存の可能性を探ること。
◆世界には異なる文化、宗教、言語がある。国際化には、これらを理解することが大切。文化の違いを知ることなしに、他国の社会のシステム、法律、経済を理解するのは難しい。
総合政策学部の国際化
独自プログラム:総合政策学部独自の海外派遣プログラムが充実
「外国語研修」「ボランティア研修」「Field Studies」
「ビジネスインターンシップ」「国際インターンシップ」
学べる言語数:9つの国と地域
英語以外の外国語カリキュラムが充実。講師はネイティブ
補助・奨学金:活動に対する補助・奨学金制度が充実
第二外国語検定の補助、自身の研究・プロジェクトに対する奨学金等
◆ゼミ合宿に参加し、インドネシアでフィールドワークを実施。
⇒インプットとアウトプットが同時に行えた。個人旅行では訪問できない宗教省、ASEAN事務局等を訪ね、学術的知見を広めた。
◆プロジェクト奨学金を利用し、インドネシア語を使って現地調査。「総合政策学部リサーチフェスタ」にて、研究結果を発表。
◆ガルータインドネシア空港にて、国際インターンシップを実施。
⇒常識と思っていることが海外では非常識であると知る。
◆これらの活動により、インドネシア社会におけるイスラムを学び、新しい世界を知る。他者を理解することが、現代社会で発生する問題解決の一助になるのでは。 |
学部横断プログラムの取り組みと計画
「Global LEAP・グローバルFLP」
【学部横断プログラムの取り組みと計画】
◆2013年度より、全学共通、横断的な教育体系を展開する「全学連携教育機構」を設置。
(1) 問題発見・解決能力
(2) 自己発見・自己認識力
(3) 情報リテラシー能力
(4) 日本語および外国語によるコミュニケーション能力
等、汎用的能力を全学を通じて向上させることを目的に、計5つのプログラムを開設。
5つのプログラムのうち
「ファカルティリンケージ・プログラム(FLP)」参加学生の意見
◆ボストンの大学で行った研修では、中国の学生が多数派だった。日本人学生はごく僅かで、海外派遣に対する日本の脆弱さを感じた。
◆ハーバード大学で社会に関するディスカッションに参加したが、答えられない場面があった。英語力の問題ではなく、社会問題に対する関心のなさが原因だった。
◆グローバル人材を目指すには、相手を納得させる論理力が英語でも日本語でも必要。
◆留学する日本人学生たちと会話をすると、アジアへの視点が不足している。今後はもっとアジアにフォーカスすることが必要なのでは。 |

武石智香子(副学長・国際センター所長)
|
全学連携教育機構によるプログラム「Global LEAP」「グローバルFLP」
◆2015年度に中長期事業計画「Chuo Vision 2025」が策定され、グローバル戦略が推進中。
⇒2017年度より、留学生と共に学ぶプログラム「Global LEAP」を開講。アジア地域で活躍できる能力を養う。
⇒2018年度より、「グローバルFLP」を開講。すべての科目を英語等で履修し、グローバル社会で発揮できる力を身に付ける。 |

FLPに参加した感想を述べる学生3名
|

全学を通じて汎用的能力を向上させる取り組みを紹介
|
第2部「学部長によるプレゼンテーションおよびパネル・ディスカッション」
プレゼンテーション
「私の考える『国際化』」

中島康予(法学部長/法学部教授)

篠原正博(経済学部長/経済学部教授)
|
中島康予(法学部長/法学部教授)
◆問題発見、原因追及、解決策の提示の能力を養うことが法学部の教育目標。
◆問題解決に必要なコミュニケーション能力、タフさを身に付けるために留学は貴重な機会となる。
◆日本社会に身を置きながら情報を聞くだけでは現実のものとして認識できない。リアルに感じる場としても海外経験は教訓を与えるのではないか。
篠原正博(経済学部長/経済学部教授)
◆経済学部は冷静な思考力、温かい心と国際的視野を持った経済人を育成している。
◆2017年度は英語によるビジネススクールのプロジェクトが開講。
◆海外で活躍するOB・OGと連携し、本学の「建学の精神」を継承する。
|
木立真直(商学部長/商学部教授)
◆常識のウソに気づくことは、大学での学びの基本。
◆グローバル企業が海外マーケットに参入するさいは現地に合わせる。グローバル人材に求められるのは土着化。
◆相手国の歴史等を相手国民の視点から捉える力が、これからのビジネスマンに求められる。商学部教育では、こうした姿勢を重視。
石井 靖(理工学部長/理工学部教授)
◆理工学部は世界に向けて情報を発信する必要があり、日ごろの研究がグローバルに通じている。
◆最先端の研究が行われている場で研究の一端を担うことで、問題解決力、想像力、コミュニケーション能力を磨いている。
◆日本と海外が共同して研究をアピールするなか、研究グループの連携をバックアップする仕組みづくりが本学のグローバル化に向け重要。
|

木立真直(商学部長/商学部教授)
|

石井 靖(理工学部長/理工学部教授)
|
都筑 学(文学部長/文学部教授)
◆国際会議においても公用語は英語の流れが強く、グローバル化の現状が感じられる。
◆文学部は言葉を大切にする学部。言語はツールであり、同時に文化、思想、歴史が背景にある。
◆認識の仕方が自己と他者で違うことを念頭に、相手の考え方に近づき、言葉の背景にあるものを理解することが重要である。
松野良一(総合政策学部長/総合政策学部教授)
◆問題解決に向けて、複数の学問からアプローチする力を養うために総合政策学部が創設された。
◆プロジェクト・ベース・ラーニングを重視。学生が自身でプロジェクトを作り、グローバル教育を自ら設計する取り組みを行っている。
◆プロジェクトを通じて、日本から世界に多様な事象を発信。
進行:武石智香子(副学長・国際センター所長)
|
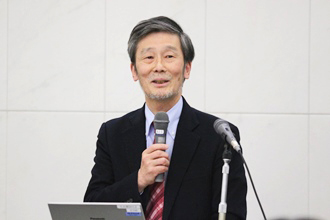
都筑 学(文学部長/文学部教授)
|

松野良一(総合政策学部長/総合政策学部教授)
|
パネル・ディスカッション
「大学の国際化とグローバル人材育成の未来」
◆中央大学では学部の特色と学生の多様性を活かしながら、全学でグローバル化を推進している。
◆他大学を含め、「留学をした」「インターンをした」学生は数多いので、それだけでは就職時の武器にはならない。この経験を通じて何を見出したか、アピールすることが重要。
◆ただ海外に行けばいいのではなく、自身の専門領域である学習と留学を両立させた内容を経験する必要がある。
◆留学生たちが日本語で授業、インターンを経験することで、日本で就職しやすくなる。彼らが母国に帰国した際は、日本のステークホルダーになる。
◆学生が自分でプログラムを構築するアクティブ・ラーニングでは、学生の力量によって充実度が異なる。専門性の付加や今後の学習への結び付け等が行えるようにする。 |

国際通用性について意見を述べた
酒井正三郎(中央大学総長・学長/GGJ構想責任者)
|

司会の小室夕里(GGJ推進責任者/学長専門員)と
学部長たちに質問を投げかける学生
|