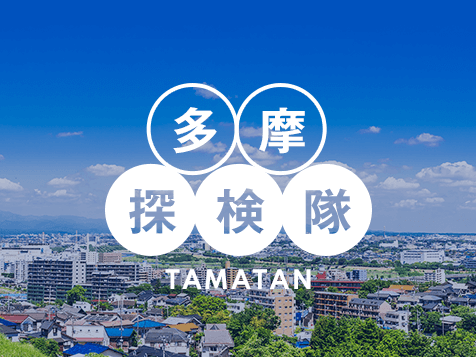ファカルティリンケージ・プログラム(FLP)
中川康弘ゼミ
| 作成年度 | 2023 |
|---|---|
| プログラム名 | 国際協力 |
| ゼミ名 | 中川 康弘ゼミABC |
| タイトル | FLP国際協力中川ゼミ論文集 |
| 目次 | 序にかえて 異文化理解と多文化共生に資する道徳教育試論―諸政策と先行研究の分析から― 日本語学習によりもたらされる技能実習生の多文化共生―ある日本語講師の語りから― 日本語教育における「正しい日本語」についての一考察―アイルランドの日本語教育現場での聞き取りから― ポップカルチャーから入る多文化共生の推進―タイでの経験から見る一考察― 「知識を増やす」とは何か―実際にジェンダーレストイレを使用して― 多様性の中での摩擦―LGBTQと宗教― 教育における水平的多様化の可能性と私自身の立ち位置―教員志望の協力者1名への聞き取りを受けて― 多様な価値を育む言語教育に関する言語教育の可能性―言語学習と教科書分析から― これまでの中川ゼミ―田中健太郎の3年間の軌跡― 多文化が交差するドバイで気付かされたこと―アラブ諸国にルーツを持つ5人へのインタビュー調査から― 定義から考える「ボランティアの自発性について」―2名のボランティア参加者へのインタビューからみえるもの― 社会規範に対する個人のアプローチへの考察―多様な性のあり方を示す2名へのインタビューをして― 「障害」を問い直す―視覚障害者のライフストーリーから― |
| 作成年度 | 2022 |
|---|---|
| プログラム名 | 国際協力 |
| ゼミ名 | 中川 康弘ゼミABC |
| タイトル | 2022年度 FLP国際協力中川ゼミ論文集 |
| 目次 | 序にかえて 多様な価値を育む言語教育に関する一考察―幼少期から複数言語に触れた大学生2名の語りから― 包摂性のある社会と教育とは―あるトランスジェンダーからの語りから― ニューヨークシティでの生活から考える多様な社会のあり方―友人とのやりとりと日本語ボランティアでの参与観察から― 他者から受ける配慮とその認識について―難聴の大学生のライフストーリーから― 社会規範への抵抗に関する考察―あるトランスジェンダーの語りから― ボランティアへの継続欲求と捉え方に関する一考察―地域日本語教室を運営する女性へのインタビューより― 社会的マイノリティに対する私たちの見方を誘導するものは何か―マレーシアにおける障害者支援経験者と現地学生の語りを受けて― マレーシアにおける日本語学習動機と学習環境に関する一考察―日本語専攻の現地学生へのインタビューとフィールドワークから― 多文化社会における言語に対する寛容性―マレー系ではないマレーシア人2名の語りから― 空間を超えて異文化に分け入る個人から学ぶこと―ナイジェリアに生きる一人の20代女性の語りから― FLP国際協力プログラム】中川ゼミの実態調査活動報告 |
| 作成年度 | 2021 |
|---|---|
| プログラム名 | 国際協力 |
| ゼミ名 | 中川 康弘ゼミABC |
| タイトル | 2020年度 中川ゼミ論文集A・B&C(卒業論文集) |
| 目次 | 2021年度 中川ゼミ論文集A・B&C(卒業論文集)の刊行にあたって 多様性を是とする社会に向かう個人の実践―ある性的マイノリティへのインタビューから― 日本手話話者のインターアクションと共生社会に関する一考察―ろう教育実践者の語りから― アイデンティティと言語の関係―複数言語話者であるマレーシア華人1名の語りから― フィリピンにおける子供支援の多様な試み―1人の日本人男性の語りから― ボランティア参加者の意識の変化に関する考察―ある大学生の1名の語りから― 地域日本語教室が果たす役割とその影響―学習者・支援者の視点から― 技能実習生への日本語教育と「働きがい」に関する考察―個人と向き合う教育従事者のライフストーリーから― 母語・母文化学習とアイデンティティ意識に関する一考察―言語形成期に来日した中国人学生2名の語りから― 自己成長のプロセスとしての国際協力は許されるのか―青年海外協力隊3名の語りを比較して― 農村地域における多文化共生―北海道秩父別町での実態調査から― 日本語教育の社会的意義についての一考察―海外及び国内の現場で教える日本語教師3名の語りから― アイデンティティの複数性意識から考えることによる他者共感の可能性についてーベトナム人女性日本語教師、タイの日本人男性同性愛者へのインタビュー調査から― 多様化する社会におけるグローバルマインドの育成―「グローバル人材」の再考から― 【FLP国際協力プログラム】中川ゼミの実態調査活動報告 卒業生からのメッセージ |
| 作成年度 | 2020年度 |
|---|---|
| プログラム名 | 国際協力 |
| ゼミ名 | 中川 康弘ゼミAB |
| タイトル | 2020年度 中川ゼミA・B論文集 |
| 目次 | 2020年度ゼミ論文集の刊行にあたって 言葉の性差とネイティブという存在から言語教育を考える―オーストラリアの日本語教師の語りから― 地域日本語教室からみた国際協力―母語教育と母語支援を実践者の語りから― 協力隊活動を通した国際協力の多様なあり方―現職参加のコミュニティ開発隊員への聞き取り調査から― JOCVの社会的意義とは―日本語教師の語りから― 日本人海外移住者の生き方の多様性と日本語教育―ドイツ在住の日本人女性の聞き取り調査から― アメリカにおける言語・人種に関する意識とそれらの「余計なこと」に関する一考察―州立大学に勤める日本語教師への調査から― 同性愛者のライフストーリーから考える国際協力と共生―同定することに抗う語りから― |
| 作成年度 | 2019年度 |
|---|---|
| プログラム名 | FLP国際協力プログラム |
| ゼミ名 | 中川康弘ゼミ |
| タイトル | 2019年度 中川ゼミA論文集 |
| 目次 | 序にかえて 国際協力としての協力隊活動の今日的意義 現場で働く日本人日本語教師の視点から見たベトナムの日本語教育の現状と考察 ベトナム人女性日本語教師のジェンダー観に関する一考察 高まる日本語需要に応えるベトナム人日本語教師の教育観に関する一考察 国際協力のきっかけとしてのラポール形成 フエ大学外国語大学日本語学科の学生との交流を通して トルコ人と日本人の知識量の差に関する一考察 FLP国際協力プログラム中川ゼミ活動報告書 八王子市立第五中学校夜間学級 見学調査 JICA地球ひろば 見学調査 FLP国際協力プログラム中川ゼミ 夏合宿報告書 ベトナム・フエの特別支援学校訪問 ベトナム・フエでの観光 独立行政法人 国際交流基金 訪問 南多摩中等教育学校出張報告 NPO法人 地球学校 訪問調査 |