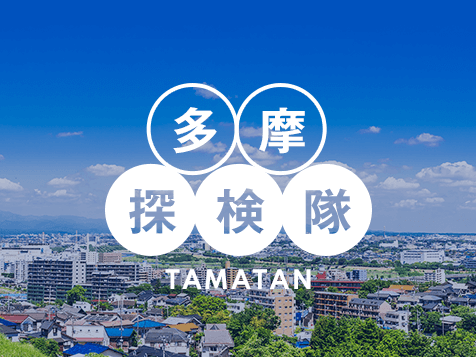ファカルティリンケージ・プログラム(FLP)
環境プログラム論文集
SUMMER SCHOOL報告書
2013年度 (8月7~9日石川県能登町での調査活動)
2010年度 (9月13~14日福島県南会津郡只見町での自然観察他)
2009年度 (9月11~12日岩手県柴波町での現地環境調査他)
2007年度 (9月3~4日富士山ビジターセンター、西湖コウモリ穴、富岳風穴、氷穴の見学及び富士山YMCAグローバル・エコ・ヴィレッジでの体験学習)
2006年度 (9月4日「世界の巨大恐竜博2006」の見学及び幕張メッセ国際会議場での講演会)
2005年度 (9月12日~14日「愛・地球博」の見学及び名古屋大学での講演会)
環境プログラム論文集
| 作成年度 | 2019年度 |
|---|---|
| プログラム名 | FLP環境プログラム |
| ゼミ名 | 西川可穂子ゼミ、ハリスンゼミ |
| タイトル | 2019年度(第十五期)論文集 |
| 目次 |
SDGsアイコンを利用した企業のSDGs活動とSDGsウォッシュの分析 |
| 未整備私有林の解消を目的とした現行政策の改善可能性について ―森林所有者の経営インセンティブに着目して― |
|
| 仮想評価法(CVM)を用いたマグロの経済価値評価 | |
| The effect of China’s problem with particulate matter (PM2.5) on the air quality in Japan | |
| The Effect of River-crossing Structures. |
| 作成年度 | 2018年度 |
|---|---|
| プログラム名 | FLP環境プログラム |
| ゼミ名 | 西川可穂子ゼミ、ハリスンゼミ |
| タイトル | 2018年度(第十四期)論文集 |
| 目次 | 東京都内医師会による抗菌剤適正使用の啓発活動 ~ホームページから見る活動状況~ |
| 東京都内の表層水に含まれる薬剤耐性菌に関する調査 ~薬剤耐性の傾向と分布から見えてくる現状~ | |
| How should Japan manage e-wastes? | |
| Action of Companies and Local Governments to Reduce and Recycle Garbage |
| 作成年度 | 2017年度 |
|---|---|
| プログラム名 | FLP環境プログラム |
| ゼミ名 | 佐々木創ゼミ、西川可穂子ゼミ、ハリスンゼミ、横山彰ゼミ |
| タイトル | 2017年度(第十三期)論文集 |
| 目次 | ESG投資と企業の成長性 |
| 市民参加型の自治体規模の再生可能エネルギー利用 ―NRWザーベックを例に― | |
| The Best Renewable Energy for Japan | |
| 藻類バイオマスの早期普及 |
| 作成年度 | 2016年度 |
|---|---|
| プログラム名 | FLP環境プログラム |
| ゼミ名 | 田中廣滋ゼミ、西川可穂子ゼミ、ハリスンゼミ |
| タイトル | 2016年度(第十二期)論文集 |
| 目次 | ESG投資と持続可能な発展 公正な投資活動とESG投資 福島県産水産物の風評被害の改善へ向けて Water Management in the Murray-Darling Basin |
| 作成年度 | 2015年度 |
|---|---|
| プログラム名 | FLP環境プログラム |
| ゼミ名 | 牛嶋仁ゼミ、田中廣滋ゼミ、ハリスンゼミ、横山彰ゼミ |
| タイトル | 2015年度(第十一期)論文集 |
| 目次 | 2015年度牛嶋仁ゼミ活動報告 ESGから学ぶ環境投資 COAL COMBUSTION PRODUCTS FLP環境プログラム横山ゼミ 2015年度 |
| 作成年度 | 2014年度 |
|---|---|
| プログラム名 | FLP環境プログラム |
| ゼミ名 | 牛嶋仁ゼミ、ヘッセゼミ、星野智ゼミ、佐々木創ゼミ、田中廣滋ゼミ、谷下雅義/中澤秀雄ゼミ、横山彰ゼミ |
| タイトル | 2014年度(第十期)論文集 |
| 目次 | 2014年度 ゼミ活動記録 Agriculture Reform in Sub-Saharan Africa A Theoretical Study of Traditional, Organic and Sustainable Agriculture 日本とドイツの環境政治比較 日本におけるエネルギー政策のあり方 なぜ日本ではドイツ緑の党のような市民政党が生まれないのか? 我が国における観光業のグローバル化とその戦略 多様化する働き方 青梅市の環境政策について ~環境基本計画からみる「緑」と「ごみと資源」~ カーボンフットプリントを活用したカーボン・オフセット商品を普及させるために ―相互学習型プラットホームの構築の必要性― 東日本大震災津波被災地における漁村集落復興のあり方と意思決定制度の考察 ―防潮堤問題に着目して― 日米の環境政策比較 南三陸ツーリズム ~3年間の活動を通して~ 2014年度 横山ゼミ演習A・B |
| 作成年度 | 2013年度 |
|---|---|
| プログラム名 | FLP環境プログラム |
| ゼミ名 | ヘッセゼミ、横山彰ゼミ |
| タイトル | 2013年度(第九期)論文集 |
| 目次 | Environmental Impacts of China's Steel Industry and Japan's Potential Response Effective use of thinned wood in Japan 都市のコンパクトシティ化による環境負荷への影響分析 日本における予防原則の適用に際する問題の所在 -適用段階別の整理- 貨物自動車におけるエコカー減税・エコカー補助金に関する一考察 ―自動車重量税をベースとした新・エコカー減税― 食品ロス削減社会構築のために ―サプライチェーン全体の考察― |
| 作成年度 | 2012年度 |
|---|---|
| プログラム名 | FLP環境プログラム |
| ゼミ名 | ヘッセゼミ、武田直邦ゼミ、横山彰ゼミ |
| タイトル | 2012年度(第八期)論文集 |
| 目次 | Sustainable Cities for Tohoku Alien species in Japan: Harm and Possibilities for Efficient Use Effects of the Tohoku Earthquake on University Students’ Awareness of Energy Policies: Statistical Comparison of Students at Chuo University, Iwate Prefectural University, and Matsuyama University ウーパールーパーの変態誘導に関する研究 程久保川における水域環境の実態 日本の安楽死問題を考える 道路建設における住民運動 ―圏央道高尾山の住民運動との比較― 埼玉県深谷市における住民参加による防災 ―消防団の意義の再考― メガソーラー事業の継続条件 ―固定価格買取制度継続に関するコミットメントの必要性― 環境配慮的行動1に対する情報提供の有効性調査 自動車の社会的費用の試算 ~自動車交通による大気汚染の社会的費用~ |
| 作成年度 | 2011年度 |
|---|---|
| プログラム名 | FLP環境プログラム |
| ゼミ名 | 星野智ゼミ、ヘッセゼミ、ハリスンゼミ |
| タイトル | 2011年度(第七期)論文集 |
| 目次 | 原発のある町、原発のある国 East Asia Regionalism For Dealing With Climate Change: Learning From EU Energy Policy 「農作物と放射性物質」~福島第一原子力発電所事故による影響~ The Need For Early Childhood Education For Sustainable Development in Japan: Suggestions Based on a Comparison of Environmental Education in Japan and Sweden The Significance and the Problems of Smart Cities in Developing Countries in Asia: An example of the Tianjin Eco-city in China Using Information About Nuclear Accidents: Official Announcements and Internet Media Achieving a“ZERO Waste society”in Japan Landfills and Garbage -Ways of Reducing Garbage- |
| 作成年度 | 2010年度 |
|---|---|
| プログラム名 | FLP環境プログラム |
| ゼミ名 | ヘッセゼミ、田中廣滋ゼミ、武田直邦ゼミ、鹿島茂ゼミ、横山彰ゼミ |
| タイトル | 2010年度(第六期)論文集 |
| 目次 | Nori Cultivation and Environmental Issues 有機農業~農薬における危険性~ 世界の水問題と日本の関係について-仮想水の観点から- 北極海の現状と展望 ~海洋汚染がクジラ類固有種に与える影響~ Aquaponics: Integrating Aquaculture and Hydroponics for Food Production FLP田中廣滋ゼミナール論文集 第1章 世界のエネルギー情勢 第2章 欧米諸国と比較した日本のCSRおよびSRIの現状分析 第3章 BRICsの環境問題 ウーパールーパー 飼育法と変態誘導実験 程久保川における水域環境の実態 大学環境報告書の基準モデル作成 地球温暖化による異常気象への適応策 ~水災害へのソフト面適応策の一考察~ 再生可能エネルギー余剰電力についての考察 ~揚水発電は二次電池として機能するか~ 世帯のセグメント別環境配慮行動促進の模索 ―京都議定書目標達成に向けた、世帯ごとの取り組み― |
| 作成年度 | 2009年度 |
|---|---|
| プログラム名 | FLP環境プログラム |
| ゼミ名 | ヘッセゼミ、武田直邦ゼミ、ハリスンゼミ |
| タイトル | 2009年度(第五期) 論文集 |
| 目次 | Promoting Water Business for Japanese Companies in Saudi Arabia 竹林の土壌動物相について 多摩キャンパスにおける防災池の環境調査 Eco-cars Driving toward the world in which people and cars can co-exist in an environmentally-friendly way. The concern with global warming and climate change |
| 作成年度 | 2008年度 |
|---|---|
| プログラム名 | FLP環境プログラム |
| ゼミ名 | 星野智ゼミ、田中廣滋ゼミ、鹿島茂ゼミ、ハリスンゼミ |
| タイトル | 2008年度(第四期) 論文集 |
| 目次 | 市民参加とEU景観政策 日本と中国、隣国の環境問題と地方自治体における環境国際協力の展望 ISO14001と環境関連法について 食料輸入と環境負荷 -フード・マイレージが示す消費者に求められる行動- エコツーリズム -オーストラリアと日本- 中国 -西部大開発にみる退耕環林と民族問題 -生態移民とは真に自然を守るためのものであるか- 水資源の考察 -オーストラリアの分析から- バイオエタノールと食糧問題 ロンドン混雑課金制度と大気環境 中国の大気汚染の現状と対策 中央大学 環境報告書(2008年度版) 中央大学から割り箸ゼロを目指して Are forests needed in Tokyo ? |
| 作成年度 | 2007年度 |
|---|---|
| プログラム名 | FLP環境プログラム |
| ゼミ名 | 星野智ゼミ、田中廣滋ゼミ、武田直邦ゼミ、西田治文ゼミ、ハリスンゼミ |
| タイトル | 2007年度(第三期) 論文集 |
| 目次 | 京都議定書を巡る国際関係 ~京都議定書の形成過程とその後の展開を巡る各国の利害関係について~ 日中のCSRの国際的動向 ゲンジボタルの発光器の組織学的研究 ヤマアカガエルの変態に及ぼす内分泌攪乱物質の影響 植物化石から過去の環境を探る People in Chernobyl 21 Years After the Accident |
| 作成年度 | 2006年度 |
|---|---|
| プログラム名 | FLP環境プログラム |
| ゼミ名 | 星野ゼミ、田中廣滋ゼミ、藪田雅弘ゼミ、ハリスンゼミ、田中努ゼミ |
| タイトル | 2006年度(第二期) 論文集 |
| 目次 | Environmental Politics in the Transition to a Civil Society -One proposal for an althemative environmental movement- CSRと日本の企業 アジアにおける将来の水遍迫度緩和に向けて -モンゴル国の事例研究- 海洋(漂流・漂着)ごみ問題に関する研究 -越境する廃棄物への対策をめぐって- 地域ナショナルリズムと環境 -ガリシアのヌンカマイス運動を事例として- 日本おける水産物自給率向上の一手段としての水産養殖業の環境経済的考察 日本の企業の海外進出 -インセンティブは何なのか- 開発途上国における熱帯林減少について 危険な気候変動を避けるための国際的枠組みと合意形成 |
| 作成年度 | 2005年度 |
|---|---|
| プログラム名 | FLP環境プログラム |
| ゼミ名 | FLP環境プログラム |
| タイトル | 2005年度(第一期) 修了生論文集 |
| 目次 | 発展途上国における持続可能な人間開発と先進国の援助 日本人口と環境問題 三島・沼津コンビナート反対運動の意義 -環境アセスメントの先駆的事例- 環境会計と環境経営指標 栃木県佐野市・三杉川分水路周辺水田における水田生態系の生物多様性 -水田生態系保全に向けての課題と今後の対策- ビオトープの考え方 What is the best way to conserve forests? -Towards the susutainable forest- 熱供給事業の冷熱源としての雪氷冷熱エネルギー 環境と交通 -京都市における環境配慮型交通政策- |