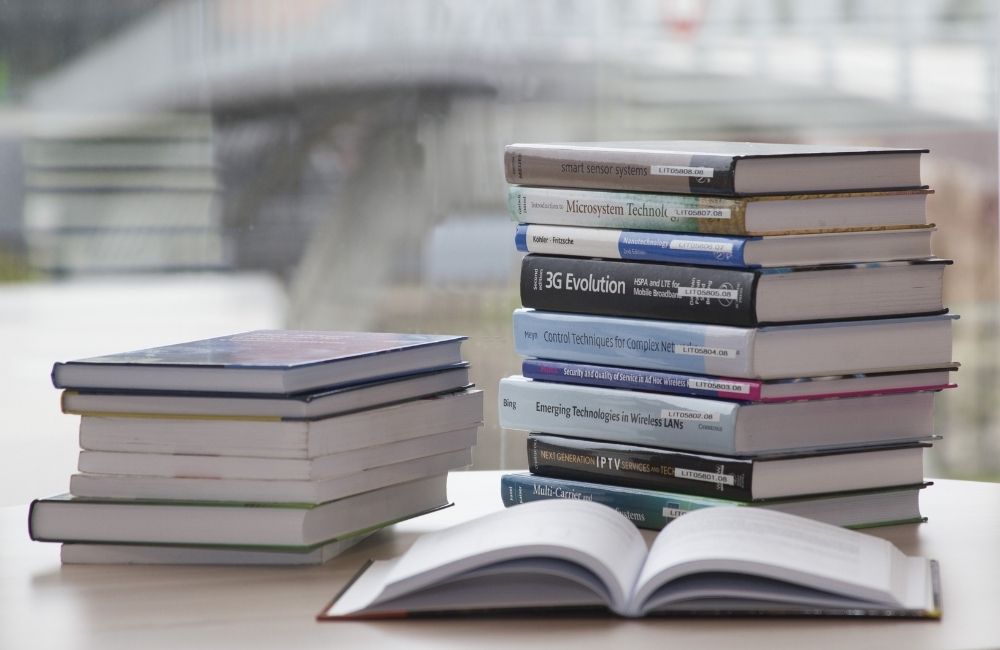自身の研究内容を深めたい人や専門性を高めたい人は、大学院への進学が1つの選択肢になります。
入学してから後悔しないよう、まずは大学院について知っておくことが重要です。
ここでは、大学院への進学を検討している人向けに、大学院の種類や制度、進学にあたってすべきことについて解説します。
大学院は大きく分けて2種類
大学院には主に2つのタイプがあります。目的や研究内容が異なるので、各々の特徴を解説します。
一般的な大学院
一般的な大学院は、研究者や大学教員として研究活動に取り組む高い研究能力と、その基礎となる学問的な知識を養うことを目的としています。大学院で学ぶことで、特定の分野に対する高い専門性を身に付けられます。
修士課程と博士課程
一般的な大学院は、修士課程と博士課程に分かれています。修士課程は2年間あり、高度な研究力や専門性が必要とされる職につくために必要な能力を身につけることを目的としています。区分制の博士課程の場合は、博士前期課程が修士課程に相当します。修士課程と博士前期課程では、修了時に「修士」の学位が取得可能です。
修士課程を修了した人が進む博士課程は、区分制の博士課程での博士後期課程に相当し、いずれも修了すると「博士」の学位が取得できます、また、一貫制の博士課程5年では博士課程を修了した際に博士学位が授与されます。博士課程では、さらに専門性の高い研究力を身につけ、自立して研究活動を行うことが目的です。
専門職大学院
専門職大学院は、従来の研究者養成を目的にせず、高度で専門的な職業能力のある実務家を養成する大学院のことです。現場での問題解決を図るために、必要な知識と技能の獲得を目指した教育が行われます。
例えば法科大学院は、弁護士や裁判官、検事として働くための専門性の高い知識や能力を培うことに特化しています。法科大学院を修了すると、司法試験の受験資格を得ることが可能です。
他にも以下のような専門職大学院があります。
・教職大学院
・MBA大学院
・ビジネス、MOT大学院
・臨床心理系大学院
内部進学と外部進学の違い
ここからは、大学院のいわゆる内部進学と外部進学の違いを説明します。
内部進学とは
卒業した大学と同じ大学院に進むことを内部進学と言います。同じ大学の先輩から受験準備や大学院での研究活動の様子などを聞けるため、指導教授選びや研究室選び、受験準備の情報を得やすいです。
外部進学とは
大学院での学びの制度
大学院では、自分のライフスタイルに合った学び方ができるよう、様々な学びの制度が用意されています。ここでは、大学院の通学方法と学びの制度について解説します。
一般的な昼間の通学制
平日昼間と土曜に開講している一般的な形式です。現状、多くの大学院では、昼夜開講制や通信制と比べて開講されている科目が多い傾向にあります。
通信制大学院
自宅や職場から通える距離に通いたい大学院がないなどの理由から、通学が困難な人が在宅等で講義を受けられる大学院です。1998(平成10)年3月に制度化されたため、比較的新しい学びの在り方です。通信制大学院では、印刷教材等による授業や放送授業などを活用して学びます。しかし最近では、一般的な大学院でも一部の講義がリモートで実施されており、学び方の幅は広くなる傾向にあります。
長期履修制度
修士課程の履修期間を3〜4年の長期に定める制度です。通常だと修士課程は2年で修了しますが、4年を上限に長期で履修計画を立てることで、仕事や家事などと並行して大学院での学びを深めることができます。大学院によって長期履修制度の対象になる条件は異なるので、あらかじめ確認してみてください。
早期修了制度
通常2年の修士課程を、1年という短い期間で履修できるのが早期修了制度です。できるだけ早く就職したい学生や、早く単位を取得して会社へ復帰したいと考える社会人を対象にしています。大学院によって早期修了制度を利用できる条件は異なり、場合によって制度自体がないこともあるので、事前に確認しておくことが必要です。
科目等履修生・聴講生
大学院でかかる学費
大学院へ進学する前にすべきこと
大学院へ進学を決めるにあたって、事前の準備は欠かせません。ここでは大学院へ進学する前にやるべきこと5つを紹介します。
1.大学院の情報収集
まずは、大学院のHPやパンフレットなどを活用して情報収集をしましょう。情報収集をしながら、特に自分の研究したいことが実現できるかを確認してください。大学院を選ぶ上でチェックしておきたい項目は、以下の通りです。
・大学院・研究科で研究できる・学べる内容・設置授業科目(カリキュラム)
・教員の専門分野
・学費
・試験科目
・入試日程 など
収集した情報を比較しながら、最終的な志望大学院を絞り込んでいきましょう。
2.大学院説明会に参加・研究室への訪問
大学院によっては説明会を実施しており、参加すると学生の様子や研究内容への理解が深まります。また、研究室への訪問を依頼すれば、研究の様子を見学できたり、自身の研究内容について教員に相談したりすることが可能な場合もあります。
訪問できない場合は、指導を希望する教員に連絡をとり、自身の希望する研究テーマについて指導してもらうことが可能か確認しておきましょう。
中央大学大学院では、大学院進学検討者に向けて進学説明会を実施しています。大学院進学説明会については、以下のページを参照してください。
https://www.chuo-u.ac.jp/admission/gschool/consultation/
3.受験方式を決める
4.出願するための必要書類を準備する
受験形式が決まったら、出願に必要な書類を揃えていきます。提出が求められる書類は以下の通りです。
・入学願書
・卒業証明書(または卒業見込み証明書)
・成績証明書
・研究計画書
・志望理由書
・推薦書(推薦入試などで求められる場合) など
研究計画書は、大学院に入ってから研究するテーマや研究内容の概要をまとめたもので、口述試験ではその内容についての質問も受けます。作成時には、研究の意義や内容を分かりやすく整理し、自分の経験やこれまでの学習内容等を踏まえたオリジナリティのある研究内容にすることが重要です。研究計画書の作成は時間がかかるため、早めに取り掛かりましょう。
5.入学試験に向けて準備
最後に入学試験の準備をしましょう。大学院入試では、筆答試験(筆記試験)と口述試験(面接試験)が行われます。
筆答試験では、外国語と専門科目の2つが課されます。外国語試験はTOEICやTOEFLなどの結果で免除になる場合もあるので、事前に入試要項などを確認しておくとよいでしょう。専門科目の試験は、研究科ごとに異なる内容が出題されます。専門分野の知識を問う問題もあれば、論理的な文章を書く力を試すような論述の試験もあるため、事前の対策が欠かせません。
口述試験では、主に志望動機と事前に提出した研究計画書に対しての質疑応答が行われます。面接までに、研究計画書を何度も見直しておくとよいでしょう。また口述試験は、受験者全員に実施する場合と筆答試験合格者だけに実施する場合があるので、事前の確認が必要です。
まとめ