本学では、2019年度より「にほんごサポーター」を実施しています。
「にほんごサポーター」とは、本学で開講している留学生向けの日本語クラスにおいて、担当教員の指導の下で、留学生の授業サポートを行うというもので、「留学生が教員以外と日本語を話す機会を提供する・日本語学習のモチベーションアップ・異文化理解の促進」を活動の目的としています。主な活動としては、スピーチ、ディスカッション、会話セッション、日本の社会文化を留学生に紹介すること等を行っています。
2023年度に日本語クラスの授業において「にほんごサポーター」を活用した実績は、前期・後期共に、約30科目で100回を超え、延べ200人を超える学生が「にほんごサポーター」に登録しました。本学で学ぶ留学生には、交換留学生と4年間学部に在籍する学部留学生がいますが、留学生の日本語レベルはさまざまで、さらに多様な背景をもっています。留学生を支援・応援する活動は、国内学生にとっても、異文化理解とコミュニケーション能力を養うことができる意義のあるものだと、「にほんごサポーター」を経験した学生たちは、参加後にこの活動を評価しているそうです。
この活動に参加経験のある、八十川 珠鶴さん(総合政策学部国際政策文化学科3年)、市瀬 百々果さん(国際経営学部3年)、池田 さくらさん(文学部人文社会学科英語文学文化専攻1年)に、活動に参加した感想や経験から学んだこと等についてお聞きしました。また、留学生の日本語授業を担当する先生方に、「にほんごサポーター」の導入によって変化を感じた点や、サポーター参加学生に期待したいことについて、コメントしていただきました。
「にほんごサポーター」とは、本学で開講している留学生向けの日本語クラスにおいて、担当教員の指導の下で、留学生の授業サポートを行うというもので、「留学生が教員以外と日本語を話す機会を提供する・日本語学習のモチベーションアップ・異文化理解の促進」を活動の目的としています。主な活動としては、スピーチ、ディスカッション、会話セッション、日本の社会文化を留学生に紹介すること等を行っています。
2023年度に日本語クラスの授業において「にほんごサポーター」を活用した実績は、前期・後期共に、約30科目で100回を超え、延べ200人を超える学生が「にほんごサポーター」に登録しました。本学で学ぶ留学生には、交換留学生と4年間学部に在籍する学部留学生がいますが、留学生の日本語レベルはさまざまで、さらに多様な背景をもっています。留学生を支援・応援する活動は、国内学生にとっても、異文化理解とコミュニケーション能力を養うことができる意義のあるものだと、「にほんごサポーター」を経験した学生たちは、参加後にこの活動を評価しているそうです。
この活動に参加経験のある、八十川 珠鶴さん(総合政策学部国際政策文化学科3年)、市瀬 百々果さん(国際経営学部3年)、池田 さくらさん(文学部人文社会学科英語文学文化専攻1年)に、活動に参加した感想や経験から学んだこと等についてお聞きしました。また、留学生の日本語授業を担当する先生方に、「にほんごサポーター」の導入によって変化を感じた点や、サポーター参加学生に期待したいことについて、コメントしていただきました。
留学生と共に日本語を学ぶ姿勢をもって活動しています
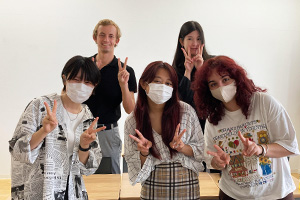
▲日本語クラスの留学生・サポーターと。前列左が八十川さん
八十川 珠鶴さん(総合政策学部国際政策文化学科3年)
ゼミの教授が担当している「現代ドイツの歴史と社会」という授業を受講し、ドイツでは言語教育が盛んだということに興味をもち、2年生の後期から活動に参加しました。留学生の日本語クラスでは、授業の内容やサポート方法は担当する先生によって異なりますが、先生方が指導する様子から自分なりの留学生への接し方や伝え方等を覚えていきました。私たちが話す日本語を、簡単で分かりやすい日本語の言葉に変換して伝えるとか、留学生が答えを出せるようにヒントを出して待つとか、日本語学習のサポートにはそのような技術が必要で、日本人だからといって日本語を簡単に教えられるものではないと実感しています。また、サポーターは日本語を教える側でありながらも、私たちも授業を受ける身だという意識をもって、留学生と一緒に理解を深めることが大切だと思うようになりました。日本語が上達した留学生から、最後の授業で「ありがとう、楽しかった」と言われたり、授業を離れて共通の趣味で語り合えたり、帰国後に日本語でSNSを使い連絡をくれる留学生もいて、国際交流ができることも活動のやりがいのひとつです。そして、この活動がゼミで行っている「日本語教育教材の研究」にとても役立っていて、「このような表現だとわかりにくい、こっちのほうが良いかな」など、活動の経験を反映させながら研究しています。卒業まであと1年、ゼミの研究とサポーター活動の経験を活かせるような教育関連の業界を視野に入れて、就職活動を進めているところです。
サポーター経験が留学先での日本語授業アシスタントに役立ちました

▲アメリカでも交流している元留学生と
市瀬 百々果さん(国際経営学部3年・2023年8月~アメリカに交換留学中)
にほんごサポーターには、2年後期と3年前期に参加しました。現在、ノースカロライナ大学シャーロット校(アメリカ)に長期留学をしていますが、留学前に留学生の様子や事情を知りたかったことや日本語教育のプロセスに興味をもったことが活動に参加した理由です。留学生と一緒に日本語クラスの授業を受けてみて、日本語は動詞の変形や助詞、語尾など、さまざまなルールがいろいろあって、私はそれらを自然と身に付けながら成長してきたことを実感し、留学生が母語でない言葉を学ぶ難しさや大変さを知りました。
留学先の大学では専門分野を学ぶとともに、秋学期に日本語クラスのランゲージ・アシスタントを担当しました。先生の助手として宿題を見たり、漢字の書き方を指導したり、時には私が授業を担当したこともありました。このときは、中大で日本語クラスの授業を受けたことがとても参考になりました。
また、中大のサポーターの活動中に仲良くなったアメリカ人留学生のひとりが、私が現在留学中の大学に在籍していて、彼女の帰国後に私が留学しました。今もたびたび交流していて、「アメリカで日本を感じよう」と、寿司屋さんや日本食スーパーに一緒に行ったり、日本語と英語で会話して楽しい時間を過ごしています。そのほかにも欧州からの留学生がシャーロットに来ていて会うことができたり、にほんごサポーター活動でのご縁が世界に繋がっていることに驚いています。いろんな国の留学生との交流や日本語教育に興味があったり、留学を考えているなら、ぜひ参加してほしいと思います。
留学先の大学では専門分野を学ぶとともに、秋学期に日本語クラスのランゲージ・アシスタントを担当しました。先生の助手として宿題を見たり、漢字の書き方を指導したり、時には私が授業を担当したこともありました。このときは、中大で日本語クラスの授業を受けたことがとても参考になりました。
また、中大のサポーターの活動中に仲良くなったアメリカ人留学生のひとりが、私が現在留学中の大学に在籍していて、彼女の帰国後に私が留学しました。今もたびたび交流していて、「アメリカで日本を感じよう」と、寿司屋さんや日本食スーパーに一緒に行ったり、日本語と英語で会話して楽しい時間を過ごしています。そのほかにも欧州からの留学生がシャーロットに来ていて会うことができたり、にほんごサポーター活動でのご縁が世界に繋がっていることに驚いています。いろんな国の留学生との交流や日本語教育に興味があったり、留学を考えているなら、ぜひ参加してほしいと思います。
日頃から正しい日本語とコミュニケーションを意識するようになりました

池田 さくらさん(文学部人文社会学科英語文学文化専攻1年)
国際色豊かな高校に通っていたこともあり、海外で働くことや日本語教師という職業に興味を持っていました。大学入学直後に「にほんごサポーター」の活動を知り、将来の進路選択に役立ちそうだと考えて参加しました。1年の前期と後期に参加した中で印象に残っているのが、先生の指導方法です。日本語の学習を初めて間もない初級クラスの留学生に対して、助詞の使い方 「に」と「へ」など、助詞の意味や機能のわかりやすい説明の仕方や、日本語を使って日本語を学んでもらうための関わり方を学びました。活動中は基本的に日本語を使うルールなので、留学生から英語で質問されても英語で返さずに、日本語に変換して答えるように心がけています。それにより自分の日常会話で正しい日本語を話すことに気を付けるようになりました。また、私自身は積極的な性格ではないのですが、授業中には留学生との会話をリードしたり質問したりする場面が多いし、沈黙しないように工夫するなど、人と話すということが勉強になっています。
そして、留学生から母国の話を聞く中で、海外の文化に対する興味が深まっただけでなく、日本にも素敵な文化がたくさんあることに気づかされました。3年次での海外留学を目指して準備を進めているので、これからもサポーター活動を続けていき、自分が留学する際の参考にしたいと思っています。また、サポーターの活動だけでなく、キャンパスで留学生を見かけたら話しかけてみて、中央大学に学びに来てくれた留学生をサポートしたいと思っています。
そして、留学生から母国の話を聞く中で、海外の文化に対する興味が深まっただけでなく、日本にも素敵な文化がたくさんあることに気づかされました。3年次での海外留学を目指して準備を進めているので、これからもサポーター活動を続けていき、自分が留学する際の参考にしたいと思っています。また、サポーターの活動だけでなく、キャンパスで留学生を見かけたら話しかけてみて、中央大学に学びに来てくれた留学生をサポートしたいと思っています。
日本語教育の教員が感じる「にほんごサポーター」制度の導入による変化と
サポ―ト活動に参加する学生に期待していること
【吉田 千春/法学部助教】
サポーター制度の導入により、日本語学習の場が「実践的な日本語使用、リアルなコミュニケーション、異文化理解、交流の場」などのように、大きく広がったと感じています。留学生は、サポーターとの活動を毎回楽しみにしています。サポーターの皆さんにとっても、新たな気づきや学びを得る機会になることを願っています。
【中川 康弘/経済学部教授】
サポーターの存在が留学生の学習動機につながる一方で、サポーター側にも留学生への理解が深まっていると感じています。サポーターの皆さんには、ぜひキャンパス内にいながらも交流することの少ない留学生とかかわってほしいと思います。そして留学生の日本語に触れることで、自身の外国語学習を振り返る機会を得てほしいと思います。
【二宮 理佳/商学部教授】
教員にも変化がありました。「『支援する人・される人』、『留学生・日本人』のような意識は気がついたら消えていた。そんな体験が生まれる場をつくるには?」という視点からも授業構成を考えることが多くなりました。サポーター学生には、自分なりのコミュニケーションの取り方を試行錯誤しながら見つけてほしいと思っています。
サポーター制度の導入により、日本語学習の場が「実践的な日本語使用、リアルなコミュニケーション、異文化理解、交流の場」などのように、大きく広がったと感じています。留学生は、サポーターとの活動を毎回楽しみにしています。サポーターの皆さんにとっても、新たな気づきや学びを得る機会になることを願っています。
【中川 康弘/経済学部教授】
サポーターの存在が留学生の学習動機につながる一方で、サポーター側にも留学生への理解が深まっていると感じています。サポーターの皆さんには、ぜひキャンパス内にいながらも交流することの少ない留学生とかかわってほしいと思います。そして留学生の日本語に触れることで、自身の外国語学習を振り返る機会を得てほしいと思います。
【二宮 理佳/商学部教授】
教員にも変化がありました。「『支援する人・される人』、『留学生・日本人』のような意識は気がついたら消えていた。そんな体験が生まれる場をつくるには?」という視点からも授業構成を考えることが多くなりました。サポーター学生には、自分なりのコミュニケーションの取り方を試行錯誤しながら見つけてほしいと思っています。
「にほんごサポーター」活動は『オープンバッジ』の対象科目です

本学では、2021年度から一般財団法人オープンバッジ・ネットワークが発行するオープンバッジを導入しています。オープンバッジは、人生のさまざまなシーンで身に着けたスキルや経験を、
一覧で他者に対しても示すことができる仕組みであり、本学では、新たな学修履歴・学修成果の
可視化ツールとして位置付けています。
「にほんごサポーター」は対象科目の一つで、活動に参加して一定の条件をクリアすると、「オープンバッジ」参加証明書(ブロンズ)が授与されます。
●「にほんごサポーター」応募に関するお問い合わせ先 → 国際センター事務室
サポーターの募集は毎学期行っています。 ※2024年前期(春学期)活動希望者の登録締め切り:4月5日(金)17時。
応募について問い合わせる際には、件名に『にほんごサポーター』と記載し、本文に学籍番号と名前を記載してください。
サポーターの募集は毎学期行っています。 ※2024年前期(春学期)活動希望者の登録締め切り:4月5日(金)17時。
応募について問い合わせる際には、件名に『にほんごサポーター』と記載し、本文に学籍番号と名前を記載してください。

