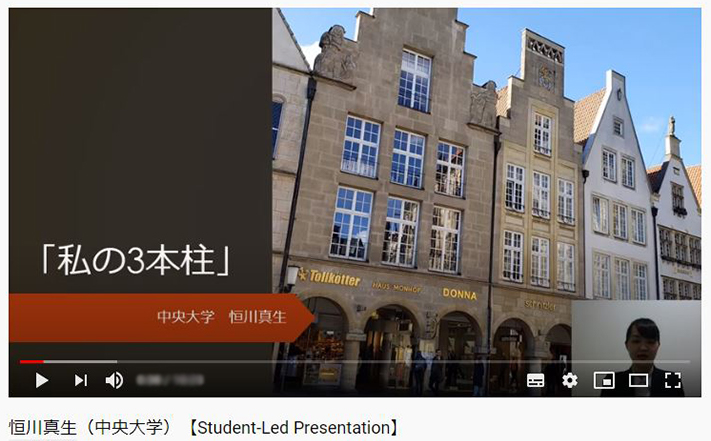恒川 真生 さん
中央大学 文学部 ⼈⽂社会学科ドイツ語⽂学⽂化専攻 3年
[FLP] 国際協力プログラム:中川康弘(経済学部准教授)
[学部専門演習]ドイツ文化論:デトレフス,ハンス ヨアヒム 教授
ドイツ語学:林明子 教授、藤縄康弘 教授
<学会発表> JALT(全国語学教育学会)
Study Abroad SIG Online Conference 2020(海外留学SIG Conference):2020年9月26日実施
<発表の内容> ドイツ留学の経験で築き上げた「私の3本柱」
Study Abroad SIG Online Conference 2020(海外留学SIG Conference):2020年9月26日実施
<発表の内容> ドイツ留学の経験で築き上げた「私の3本柱」
<留学期間> 2020年3月2日~2020年3月15日
<留 学 先> ミュンスター大学の教室で実施された語学学校(ドイツ・ミュンスター)
<留 学 先> ミュンスター大学の教室で実施された語学学校(ドイツ・ミュンスター)
ドイツで見て感じたこと、ドイツのコロナ禍社会

▲極寒のアーゼー湖(ミュンスター)にて
これは、学会発表の一次選考に提出した要約の冒頭部分です。
2020年3月1日、語学留学のために9人の仲間と共にドイツへ渡りました。当時、ヨーロッパではイタリアとスペインでコロナが流行し始めた頃で、ドイツでの感染者はごくわずかでした。しかし、たった2週間の滞在中に状況は一変しました。バスに乗車したり、電車で都心へ行ったりすると、「アジア人」という枠組みで人種差別的行為が行われているように感じました。私は、バスの座席に座っていた時に少し避けられていると感じる程度でしたが、定期券の購入を躊躇されたり、路上で突然叫ばれたりしたなど、怖い経験をした友人もいたようです。
このように、先輩たちから聞いていた留学の様子とは全く違う環境での留学となってしまいましたが、すべてがマイナスだったというわけではありません。語学学校では、ドイツ語でドイツ語を教わり、語学学習に関して新たな発見をしたり、他国からの留学生とマーケットや買い物に行き、多言語が飛び交う中で異文化交流をしながら、他国の文化を学ぶことができました。たった2週間の留学では辛いことも多かったですが、それに負けないくらい楽しく、学びの多い留学になりました。
「学会発表」という大きな経験を、新たな挑戦への『糧』に
自分自身を信じること・自分らしさを忘れないこと・挑戦し続けること
今回、私の留学体験談から「私の3本柱」をいう題で、学会において発表させていただきました。3本すべての柱に共通することは、「少しでも多くの学びをこの留学から得たい」という自分自身の強い気持ちであり、そのような自分がいたからこそ、築くことができたのだと思います。「自分から行動するために」 どのような心構えが必要であったのか、そこを軸に分析を行いました。
まさか自分が選ばれるとは思っていなかったため、採用通知が来たときはとても驚きました。
発表のための準備として行ったことは、2週間の留学期間に自主的に書いていた「ドイツ留学日記」に沿って、1日ずつの出来事を振り返りました。私は人と話すことが好きなので、一緒にドイツへ行った友人や電話で近状報告を行っていた母親とビデオ通話をして、実際にどのような感じであったのか、第三者の意見を聞いて日記の内容を見直しました。さらに、FLPゼミ指導教員である中川先生からは、「発表内容を充実させるための具体的なエピソードを入れるとよい」と助言をいただくことができました。また、動画を制作する際には、「これから留学する人」に向けて、「コロナ期の留学」について「届け!」という思いで作り上げ、発表に備えました。
このように今回の学会発表は、決して私一人だけでやり遂げたことではなく、多くの人からの協力があって作り上げることができたと言えます。
実際の発表は、「制作した動画を専用のサイトに先に投稿して、学会で質問される」という新しいオンライン形式で行われました。この日、参加した人たちの多くは他大学の先生方で、海外から参加された先生もいらっしゃいました。質疑応答のセッションでは、多くの質問をいただき、コロナ期に留学に行ったからこそ見えた利点や体験談の振り返り方法など、自分が言語化できていなかった部分を指摘されたりしました。それにより、再び自分の体験談と向き合うことができたと感じています。
この学会で発表した経験と学びは、これからの就職活動だけでなく、今後の活動をする中での「自分の芯」として、新たな挑戦への「糧」になると信じています。
まさか自分が選ばれるとは思っていなかったため、採用通知が来たときはとても驚きました。
発表のための準備として行ったことは、2週間の留学期間に自主的に書いていた「ドイツ留学日記」に沿って、1日ずつの出来事を振り返りました。私は人と話すことが好きなので、一緒にドイツへ行った友人や電話で近状報告を行っていた母親とビデオ通話をして、実際にどのような感じであったのか、第三者の意見を聞いて日記の内容を見直しました。さらに、FLPゼミ指導教員である中川先生からは、「発表内容を充実させるための具体的なエピソードを入れるとよい」と助言をいただくことができました。また、動画を制作する際には、「これから留学する人」に向けて、「コロナ期の留学」について「届け!」という思いで作り上げ、発表に備えました。
このように今回の学会発表は、決して私一人だけでやり遂げたことではなく、多くの人からの協力があって作り上げることができたと言えます。
実際の発表は、「制作した動画を専用のサイトに先に投稿して、学会で質問される」という新しいオンライン形式で行われました。この日、参加した人たちの多くは他大学の先生方で、海外から参加された先生もいらっしゃいました。質疑応答のセッションでは、多くの質問をいただき、コロナ期に留学に行ったからこそ見えた利点や体験談の振り返り方法など、自分が言語化できていなかった部分を指摘されたりしました。それにより、再び自分の体験談と向き合うことができたと感じています。
この学会で発表した経験と学びは、これからの就職活動だけでなく、今後の活動をする中での「自分の芯」として、新たな挑戦への「糧」になると信じています。
中川康弘先生(経済学部准教授/FLP国際協力プログラム担当教員)からひとこと
<恒川さんが発表した学会JALTとは>
JALT(全国語学教育学会)は、日本国内及び国外における語学の教育及び学習の向上を目指して活動するNPO法人です。35の支部と26の分野別研究部会からなり、約3,000人の語学専門家が参加する学術団体です。
恒川さんが発表を行った「JALT Study Abroad SIG Online Conference 2020(海外留学SIG Conference)は、海外留学の実践・研究、学生の海外留学経験に興味を持つ研究者、教師、学生の発表および学びの場として開催されています。今年度のテーマは「海外留学の新しい日常」。
▶ 公式ホームページ|JALT Study Abroad SIG Online Conference 2020