インターナショナル・ウィーク
第9回 国際機関
第9回 国際機関

2017年11月14日(火)には、国際連合世界食糧計画WFP協会で理事を務める忍足 謙朗(おしだり けんろう)氏をゲストスピーカーとして招き、「食糧を届ける-貧困、災害、紛争の中で-」と題した特別公開授業を実施しました。
忍足 氏は30年以上に渡り国連に勤務し、国連WFP(World Food Programme:世界食糧計画)ではボスニア、コソボ、カンボジア、スーダンなど、紛争や内戦が続く中で人道支援、緊急支援を行ってきました。
今回の授業では、世界の飢餓の現状や国連WFPの活動内容のほか、2006~2009年までスーダン局長として務めた経験を例に、現地での活動の様子を紹介しました。
また、この日の講義に備えて、FLP国際協力プログラムおよび経済学部の林光洋ゼミの授業では、国際連合世界食糧計画WFP協会の本村 佳子 氏と西平 久美子 氏を招き、ワークショップおよび講義を行い、飢餓とはいかなる状態かについて事前学習をしました。
特別公開授業「食糧を届ける-貧困、災害、紛争の中で-」概要
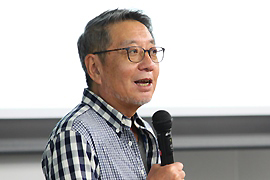
国際連合世界食糧計画WFP協会 理事 忍足 謙朗 氏
自然災害に関するデータを見ると、1970年代以降から発生率は3倍ほどに増加しています。しかし、この自然災害より悪質なものがあります。紛争です。世界ではアフガニスタン、シリア、パレスチナ、イエメン、イラク……等、紛争マップを見ると、世界中で紛争が起こっていることが分かります。2017年現在、6000万人以上の人が自分の家を追われ、避難生活をしています。この数字は第2次世界大戦以来の最多の数字です。国連の中で一番予算を使う部門はPKO(国連平和維持活動)で、年8000億円近くにも上ります。WFPはそれに次いで第2位の予算規模、年6000億円ほどで、その80%が紛争地で使われています。建設的な使われ方ではないと感じています。自然災害ではなく人間が起こしている紛争はコントロールできるはずですから。しかし、なくなりません。
飢餓が発生している南スーダン、ソマリア、ナイジェリア、イエメンの4か所は、すべて紛争に関係しています。世界が平和であれば、貧困や飢餓はもっと減らせるんです。国連で採択されたSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)の1つとして、2030年までに飢餓を撲滅するという目標を掲げていますが、紛争が続く限り達成は難しいでしょう。
私は2006~2009年まで、世界最悪の人道危機と言われたダルフール地方で、WFPのスーダン事務所長として活動していました。食糧支援では現地を視察し、支援基準に従って配分量を決定します。現場からは様々な希望が上がりますが、すべてを叶えることはできません。また、過剰な援助は自立を妨げてしまいますが、支援を受ける人々としては、できるだけ援助を続けてもらいたいという思いがあります。だからこそ、直に話し合い、理解してもらう必要があると考えています。
世界では様々な紛争が現在でも起こっています。これを、遠いところで起こっている出来事と捉えて欲しくはありません。関心を持ち、思いやりを持ってほしいと願っています。世界に対し関心を持ち、不平等を知る。これがグローバル化の進む世界で生きていく私たちに求められていることではないでしょうか。
ワークショップ「『栄養』から考える飢餓」
本村 氏によるワークショップでは、各国の食事の写真から栄養価を見比べたほか、栄養不足から引き起こされる悪影響や飢餓について、グループに分かれて話し合い、それぞれのグループの結果を発表し、本村 氏からコメントをもらいました。
続いて行われた西平 氏の講義では、こうした飢餓に対し国連WFPがどのような活動を実施しているのか、マラウイ共和国を例に実際の支援活動について紹介してもらいました。
| 飢餓とは?
飢餓とは、体に対して適切な体重を保ち、軽い運動に必要なカロリー量がとれない状態が続くことです。飢餓が続くと免疫力が落ち、下痢などの軽い病気で命をおとしてしまうこともあります。
国連WFPパンフレットより抜粋
|
栄養が不足すると……
 グループワークで連想した学生たちの答え
グループワークで連想した学生たちの答え↓ 成長不良
| 病気になりやすい
| 働けなくなる
| 生活するお金がなくなる
| 子供に教育が受けさせられない
| 食料が買えない
↓ 栄養が不足する
※これらの要因が絡み合い、連鎖していく。
飢餓に陥ると、免疫力が低下し生命が危険に晒されたり、身体・知能の発育の遅れ、精神的・身体的障害などにより、学習能力や収入の低下が引き起こされたりします。こうして経済的損失が発生し、貧困が連鎖してしまいます。
●世界の9人に1人、8億人が飢餓に苦しんでいる
●世界の食料の3分の1はロスされている
等の現状があり、国連WFPでは下記の5つの柱で活動しています。
・緊急支援
・母子栄養支援
・学校給食支援
・地域支援
・輸送支援
なお、経済学部およびFLP国際協力プログラムの林 光洋ゼミで学ぶ学生(4年生を中心に、3年生も含む)は、こうした飢餓や貧困など世界が抱える問題、持続可能な開発について、高校生たちに関心を持ってもらうため、11月に本学の附属高等学校(中央大学高等学校、中央大学杉並高等学校、中央大学附属高等学校)等を訪問。学生らが昨年9月にフィリピンで2週間にわたって行った海外実態調査に基づいて、訪問授業を実施しました。






