私の夢は日本人としての誇りを持ちつつ、世界で活躍できる人材になること。そのため大学では外交官を目指す学生が集まる外交研究会に所属しています。主な活動は室員によるゼミ活動ですが、外交研究会では2年に1度、OB・OGを招いた総会があり、私は2年生の時に幹事をやりました。これまでの反省点を踏まえて、案内状の締め切りを早く設定したり、名簿に誤字脱字の確認など、事務作業でミスをしないように心がけました。準備段階から当日まで、同期の仲間の協力のおかげで総会を無事盛会で終えることができ、自分も現役外交官の方をはじめ、さまざまな職種の方々のお話を伺い、視野を広げることができました。こうした会を通して考え方が変わった室員も多く、とても貴重な機会となっています。
大学では外交研究会に所属
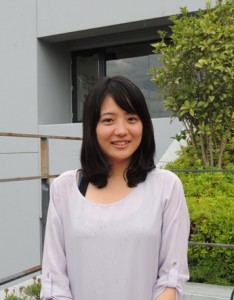
マレーシアでボランティア活動に従事

近代的なマレーシアの教会
1年生の春休みには、海外インターンシップ事業を運営する学生団体「AIESEC(アイセック)」を介してマレーシアのキリスト教孤児院で2カ月間、ボランティア活動に従事しました。ここではスタッフ2名が24時間体制で年齢も話す言葉も違う子どもたち男女それぞれ約20人の面倒を見ています。私は日常のお手伝いと英語と日本語を教えていました。ちょうど東日本大震災が起こった時だったのですが、教会には2000人くらいの人たちが集まって、日本のためにお祈りをしてくれました。とてもありがたい気持ちになり、感動したのを覚えています。マレーシアでは、宗教を中心としたコミュニティが社会を構成していて、信条に基づいて人、モノ、カネが動いています。2ヵ月間の滞在を通じて、宗教が持つ社会的な組織力、助け合いの心の強さを感じました。
国際インターンシップ制度を活用してインドへ

インドのスラムにて
2年生の夏休みには中央大学法学部の国際インターンシップ制度を活用して、約2週間インドへ行きました。実際は貧困や開発問題について学ぶフィールドワークに近いもので、訪問先は3カ所。寄付金の少なさに苦しむNGOから資金豊富で私立学校を運営するNGO、そして村ごと開発してしまうNGOまで、規模も事業もさまざまでした。キリスト教系のNGOが運営する農村で見た、ヒンドゥー教徒の村民がマリア様を飾り、コーランを読む姿はとても印象に残っています。その瞬間、宗教は必ずしも一人一つではなく、人々の選択の自由なのだと実感しました。また、別途インド総領事館にも訪問させていただき、外交官の方から直接話を聞くこともできました。
インドでのインターンシップを通して感じたのは、貧困の定義は難しいということ。物理的な貧困と精神的な貧困はまた別問題です。当時私は開発援助にも興味がありましたが、まずは身近な日本で苦しんでいる人がいるということに対して、きちんと目を向けるべきだと思いました。インドもマレーシアと同様宗教的な繋がりがあり、それが相互扶助のもとでとなって社会的な機能を有しています。一方、日本ではそのような意識が希薄な分、より一層厳しい環境に置かれています。だからこそ、国が動かなければなりません。
アメリカン大学へ長期留学

東京都から送られたワシントンDCの桜(101周年)
マレーシアとインドで宗教の持つ社会性を学び、その結果として宗教が与える国際政治への影響力に興味を持った私は、国際政治の心理的側面や外交政策についてもっと知識を深めたいと思い、海外留学を決意。国際インターンシップに引き続き、やる気応援奨学金の長期部門をいただいて、3年生の8月から4年生の5月まで、ワシントンDCにあるアメリカン大学に長期留学。秋学期はイスラム世界について、春学期は外交政策について学びました。アメリカン大学独自のワシントン・セメスター・プログラムとは、週2日はインターンシップ、残り3日は授業というカリキュラムとなっています。私は運よくヨルダン大使館でのインターンシップに受かり、1日8時間、広報課で4カ月間働きました。広報課では、アメリカの主要メディアや政府機関から情報収集をし、要約して本国に送る仕事を担当しました。他にもホームページの改訂に向けたリサーチや、ツイッターアカウントを通してのQ&Aのサポートを行っていました。私はヨルダン大使館初の非アメリカ人インターン生だったらしいのですが、英語での実務経験を積むことができ、とてもよい経験になりました。
一方、授業では、毎回NGOやシンクタンク、大使館など、各界で活躍する人をゲストスピーカーに招いてレクチャーを受け、その後、質疑応答を行いました。そのための準備をするのもかなりのプレシャーでした。
留学の傍ら、アメリカン大学の「座論(ざろん)」という日本人学生団体に所属していました。その繋がりで世界銀行・IMFを見学することもでき、日本を最前線で支えている社会人の方々から貴重なお話を伺うことができました。また、「座論」の催し(日本人学生と社会人の交流を目的とするネットワーキングレセプション)を通して、元世界銀行東アジア・大洋州地域局シニアエコノミストで、現米州開発銀行(IDB)日本政府代表部の河内祐典氏と知り合い、中央大学で講演をしていただく機会も得ることができました。
中央大学にはたくさんのリソースとチャンスがあります。法学部にはやる気応援奨学金もあり、私は国際インターンシップと留学で2度頂きました。学生の皆さんもこれらをフル活用して自分の力に変えてください。
