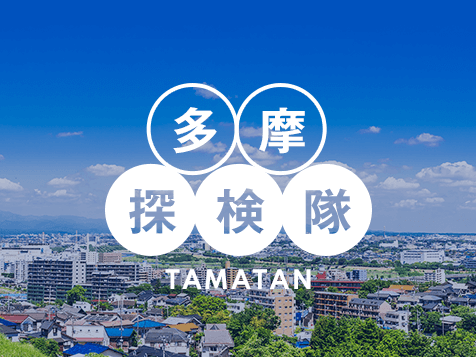ファカルティリンケージ・プログラム(FLP)
伊藤晋ゼミ
| 作成年度 | 2023 |
|---|---|
| プログラム名 | 国際協力 |
| ゼミ名 | 伊藤 晋ゼミC |
| タイトル | 2023年度 伊藤ゼミ論文集 中央大学FLP国際協力プログラム |
| 目次 | 日本の鉄道インフラの海外展開に今後求められること スマートフォンやパソコンによる水防災情報提供と住民との合意形成に向けたマニラ流域水マップの開発 非集住地域で暮らすフィリピンルーツの子どもたちはいかなる困難を抱えアイデンティティを形成しているのか アフリカの奇跡、ルワンダの経済発展について フィリピンの一村一品運動と日本企業の関わり方 フィリピンの地方分権化~バランガイに焦点を当てて~ |
| 作成年度 | 2022 |
|---|---|
| プログラム名 | 国際協力 |
| ゼミ名 | 伊藤 晋ゼミBC |
| タイトル | 2022年度伊藤ゼミ論文集 |
| 目次 | 巻頭言 近年のフィリピン大統領と国民の政治に対する考え フィリピンで貧困削減をするためにできる持続可能な観光とは 日本における難民~難民受け入れ課題とその改善に向けて~ 生理の貧困を考える―社会は生理の貧困をどう捉えているのか― 外国人児童生徒の教育問題 教育の充実と多文化共生社会に向けて必要な支援策とは インドにおける子どもの権利の現状と児童労働撤廃への取り組み 日本が紛争復興支援で果たすべきあり方 地域社会の多文化共生のあり方~やさしい日本語の普及に向けて~ モビリティ面からのインドの大気汚染問題の改善方法の考察 |
| 作成年度 | 2021 |
|---|---|
| プログラム名 | 国際協力 |
| ゼミ名 | 伊藤 晋ゼミABC |
| タイトル | 2021年度伊藤ゼミ論文集 |
| 目次 | 「持続的な質の高い教育を実現するためには~『アフリカの奇跡』ルワンダ~」 「持続可能な排水再利用と地域住民」 「フィリピンメトロセブにおける廃棄物問題は解決できるのか」 「フィリピンにおけるBOPビジネスの課題と解決策~取り残された人々を包摂するビジネス~」 「フィリピンの中古服地場産業であるウカイウカイはファッション産業をよりサステナブルなものとすることに寄与するか」 「海外就労と経済成長―労働力輸出大国フィリピンの将来―」 「日本は外国人労働者受け入れをより一層推進すべきか~少子高齢化時代における外国人労働者受け入れのあり方~」 「開発独裁は発展途上国の経済発展に寄与するか―韓国とインドネシアを例に―」 「より豊かな共生社会のための公共哲学のあり方について」 「男性と女性がともに働きやすい社会へと形成していくためには」 「再生可能エネルギー分野における日本のインフラシステム輸出」 |
| 作成年度 | 2020年度 |
|---|---|
| プログラム名 | 国際協力 |
| ゼミ名 | 伊藤 晋ゼミABC |
| タイトル | 2020年度 伊藤晋ゼミ論文集 |
| 目次 | 「日本社会におけるESG投資の課題と改善策」 「フィリピンにおけるポストハーベスト・ロス削減の分析と考察」 「カンボジアにおける追加クラスの汚職性と廃止可能性について」 「武力紛争下の教育支援の課題と検討」 「女性の労働とエンパワーメント~バングラデシュ縫製産業による女性雇用の拡大を事例として~」 「政府による防災対策が進む中でフィリピンが防災力をさらに強化するには」 「マニラ首都圏の交通渋滞―交通渋滞緩和させる道路・鉄道計画とその実施の在り方―」 「フィリピンのストリートチルドレンを包摂する医療システムとは」 「先住民族の土地権侵害問題を引き起こす4つのアクターについて~マレーシア・サラワク州の森林伐採の闇~」 「日本におけるフェアトレードの普及」 「アフリカ農業と技術普及 アフリカの技術普及システムを向上させるためには?」 |
| 作成年度 | 2019年度 |
|---|---|
| プログラム名 | FLP国際協力プログラム |
| ゼミ名 | 伊藤晋ゼミAB |
| タイトル | 2019年度 伊藤ゼミ論文集 |
| 目次 | 巻頭言 【プラスチック問題と日本―国際協力の視点から―】 序章 第1章 世界規模のプラスチック問題 第1節 海洋プラスチック問題 (1)海洋プラスチックとは (2)マイクロプラスチックとは (3)生態系への影響 (4)海洋プラスチック排出国 第2節 プラスチックごみの輸出 (1)世界の輸出状況 (2)日本の輸出状況 (3)東南アジア諸国の現状 第2章 国際的な取り組み 第1節 国際的な取り組み (1)EUの取り組み (2)G7の取り組み (3)G20の取り組み 第2節 世界各国の取り組み (1)フランス (2)台湾 (3)タンザニア 第3節 海外企業の取り組み (1)企業の取り組み①(パタゴニア) (2)企業の取り組み②(エビアン) (3)企業の取り組み③(Nestle Ltd) 第3章 日本の現状 第1節 ごみの排出量 第2節 一般廃棄物におけるプラスチックごみの排出量 第3節 プラスチックごみ排出量の内訳 第4節 シングルユース(single-use)プラスチックごみの排出量 第4章 日本の取り組み 第1節 行政 (1)レジ袋有料化に関して (2)プラスチック資源循環戦略 (3)令和2年度環境省重点施策 第2節 企業 (1)ペットボトルに関して (2)弁当容器に関して (3)商品の包装に関して (4)販売店のレジ袋に関して 第5章 海外との比較でみる問題点 第1節 日本政府の問題点 第2節 企業 (1)企業の比較でみる問題点①(ストライプインターナショナルとパタゴニア) (2)企業の比較でみる問題点②(セブン-イレブン・ジャパンとエビアン) (3)企業の比較でみる問題点③(株式会社ワタミとNestle Ltd) 第6章 提言 第1節 行政 (1)日本政府 (2)地方自治体 (3)行政と企業 (4)行政と消費者 第2節 企業 (1)取り組むべき課題 (2)小売企業 (3)産業廃棄物処理業者 (4)一般社団法人日本経済団体連合会(経団連) 第3節 消費者 (1)ごみの捨て方 (2)Refuse (3)購買行動による意思表示 (4)意識を行動につなげる 終章 参考文献 【難民が日本社会に自立基盤を築くためには】 Ⅰ 序論 1.テーマの設定の理由 2.難民の定義 3.難民に関する人々 4.難民グローバルコンタクト Ⅱ 日本における難民の概要受け入れまでの流れ 1.認定率 2.条約難民として認められない理由 3.資金援助の規模 4.第三国定住事業の状況 Ⅲ 日本における難民支援の現状 1.政府による難民支援実施枠組み 2.民間団体による難民支援実施事業 Ⅳ 海外の現状 1.ドイツ 2.カナダ Ⅴ 難民の自立・その課題 Ⅵ 提言 Ⅶ 参考文献 【フィリピンにおける金融包摂の課題と展望~マイクロファイナンスを中心に~】 第1章 はじめに 1-1.フィリピンの基本情報 1-2.高度経済成長期 1-3.世界のマイクロファイナンスの変遷 1-4.フィリピンのMFの変遷 1-5.フィリピンでのマイクロファイナンスの位置づけ 1-6.貧困の定義 1-7.現在のフィリピンにおけるマイクロファイナンスシステム 1-8.本論文の意義 第2章 各機関の評価 2-1.NGO 2.1.1.CARD 2.1.2.MCPI 2.1.3.カサガナカ 2.2.政府系機関 2.2.1.BSP 2.2.2.Land Bank 2.2.3.CDA 2.2.4.MNRC 2.2.5.NEDA 2.3.国際機関 2.3.1.ADB 2.3.2.世界銀行 2.4.問題提起 第3章 マイクロファイナンスの課題 3.1.規制・連携の課題 3.2.金融商品 3.3.金融教育 3.4.インフラ 第4章 解決策 4.1.各機関の規制・連携 4.2.金融商品 4.3.金融教育 4.4.インフラ 第5章 結論 |
| 作成年度 | 2018年度 |
|---|---|
| プログラム名 | FLP国際協力プログラム |
| ゼミ名 | 伊藤晋ゼミABC |
| タイトル | 2018年度 FLP国際協力プログラム 伊藤ゼミ 論文集 |
| 目次 | 巻頭言 外国人技能実習制度の課題点の検討と改善案 フィリピンにおける中等教育機会の拡大 -課題の分析と政府による政策の検討- 開発支援と平和構築の間 -ミンダナオ紛争を通して- 結びに代えて -75憶人分の8人- |