オランダ人戦争被害者と学生が戦争体験を共有し、記憶を未来へつなぐ


2025年9月25日(木)、後楽園キャンパス新1号館にて、「中央大学日蘭交流会」が開催されました。外務省の「日蘭平和交流事業」により6名のオランダ人の方々が来訪し、本学法学部の学生、東海大学の学生、教職員や関係者合わせて約50名と交流しました。世代や国を超えた対話を通して、平和について考える貴重な機会となりました。
プログラムの様子
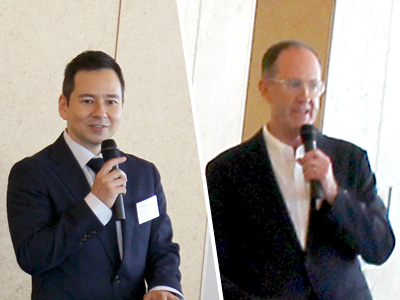
左:ピーター・ソーントン准教授/右:スティーブン・ヘッセ教授
司会を務めたピーター・ソーントン准教授は、長年続く本交流会の開催を喜びつつ、来日したオランダ人ゲスト6名を拍手で迎えました。
開会の挨拶を行ったスティーブン・ヘッセ教授は、20年近く続く本プログラムの歩みを振り返りながら、外務省やオランダ大使館をはじめ関係者への感謝を伝えました。そして、「オランダからお越しいただいたゲストの皆さんは、幼少期に戦争という非常に過酷な現実を経験されました。その体験を語ることは、決して容易なことではありません」と語り、ゲストへの敬意を表しました。さらに、「法を学ぶ皆さんにとって、他者の経験を理解し、共感することは教科書以上に価値のあることです」と学生たちにメッセージを送りました。
オランダ人戦争被害者によるスピーチ・意見交換
リーベルトさんはスピーチの冒頭で「昔の敵は今の友であり、その逆も然りです」と語り、日本政府による平和交流プログラムへの感謝を示しました。
幼少期、オランダ領東インドで家族とともに強制収容所で過ごした経験を持ち、日本に対する強い嫌悪感から来日することはないと考えていました。しかし、東京の大学生と相互の交流や対話する機会があることに魅かれ、参加を決意しました。
戦後も長年、家族は日本軍の行為による心の傷に苦しみ、自身も精神的治療を受けてきました。その一方で、戦後の日本が産業を発展させ、世界経済に影響を与えていく様子を新聞やテレビを通して見つめてきました。
いま世界では、モンテスキューの三権分立が揺らぎ、司法の独立が脅かされています。平和に向けた第一歩として、すべての国が2022年の国連決議(核兵器の使用だけでなく保有も禁止する内容)に署名することが重要です。日本の良き力を結集し、国連で独創的で賢明な提案を行うことができれば、現在世界が抱える問題の緩和に大きく貢献できると期待をしています。
続いての意見交換では、学生たちが積極的にオランダ人の方々のもとへ歩み寄り、戦争体験や平和への思いについて率直な意見や質問を投げかけました。

戦時中と戦後のつらい経験を涙ながらに語ってくれたリーベルトさん
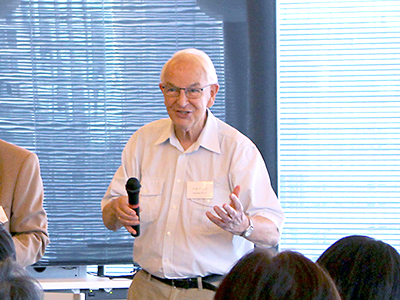
学生たちに熱心に語りかけるベルナルドさん

学生と意見交換をするアンさん(左)とアッケさん(右)
質疑応答

まず、このプログラムへの参加理由について、オランダ人の方々はそれぞれの思いを語りました。
ベルナルドさんは、過去を語るだけでなく若い世代と直接対話することの重要性を強調しました。リーベルトさんは「長く迷いもあったが、終わりが近づく今だからこそ変わりたいと思った。日本の若者と話す機会を逃さなくてよかった」と率直に伝えました。幼い頃から家族の影響で日本に否定的だったというアッケさんは、「忘れることも許すこともできないが、一度立ち止まり、前に進む選択をしたかった」と心境の変化を明かしました。ヨセフさんも当初は参加に消極的でしたが、日本人との出会いを重ねる中で印象が変わり、「親切で礼儀正しい日本人に触れ、この国と人々を好きになった。だからこそ、過去を乗り越えると決めた」と語りました。
続く、学生たちからの質問に、丁寧に耳を傾けお答えくださいました。
「日本が戦争について行動を起こすべきこと、考えるべきことがあれば教えてください」という学生の質問に対し、「オープンなコミュニケーションの重要性」を挙げました。オープンな対話があれば、お互いの会話が増えることで関係再構築に繋がります。この日蘭交流会も、まさにその対話を生む場として意義を持っています。
また、「若い世代の責任や役割とは何だと思いますか」という別の学生の質問に対し、「何でも自分の思い通りにしようとせず、周囲の人の意見に耳を傾け、尊重すること」、さらに「若い世代が政治や社会の動向に関心を持ち続けることも大切」と答えました。
東海大学 国際学部のマルガリット・ファーデン教授は、自身のゼミ生と共に参加し、「戦争体験を直接聞く機会は多くの学生にとって初めてであり、大変貴重な学びになりました」と語りました。そして、関係者への感謝とともに、「オランダから来て伝えてくださった体験は、ここにいる若い世代によって未来に活かされることでしょう」と締めくくりました。
懇親会
親睦会では、乾杯の合図とともに和やかな交流がスタートしました。軽食を楽しみながら、学生とオランダ人の方々が自然と打ち解け、会場のあちこちで笑顔があふれました。途中、記念品として贈呈した風呂敷の使い方を宮丸教授が伝授。バッグやボトルラッピングなどの結び方を披露すると、会場から大きな拍手が湧きました。
温かな交流の中で交わされた言葉や笑顔は、平和への思いを未来へとつなぐものになりました。

学生がゲスト一人ひとりに記念品を手渡すと、ゲストからもお返しの記念品をいただきました

乾杯で懇親会がスタート

テーブルを囲み、言語や文化の壁を越えて自然と会話が広がりました

ジョイスさんは学生一人ひとりに丁寧に応じました

ヨセフさんの親しみやすさが会場の雰囲気を和ませました

宮丸教授が風呂敷の結び方を実演し、参加者は興味津々
■「日蘭平和交流事業」とは
第二次世界大戦時、日本の支配下にあったインドネシアにおいて、オランダ人の方々が旧日本軍の捕虜・民間人拘留者となった過去がありました。戦争が終結して平和条約が交わされたのちに、日本とオランダの間で平和と友好のために、1995年より「日蘭架け橋事業」が開始されました。2005年からは外務省欧州局が主体となり、「日蘭平和交流事業」として事業が引き継がれました。以降、オランダ国内に今も残る日蘭間における過去の問題に向き合う試みを続けてきました。 この事業は、戦争の捕虜や拘留などに関わりのあるオランダ人の方々を毎年日本に招聘し、観光や交流を通じて日本および日本人についての理解を育むとともに、両国の理解を深める日蘭間の平和交流の事業のひとつです。
■「中央大学日蘭交流会」とは
かつて外務省に所属していた元法学部教授・元駐英大使 折田正樹(2022年逝去)の発起により、中央大学国際センター主催、外務省欧州局西欧課の協力を得て、2007年より本学で「中央大学日蘭交流会」を実施しています。「日蘭平和交流事業」を通じて日本に招聘されるオランダの戦争被害者の方々を本学にお招きし、学生達に戦争時の体験をお話しいただくというものです。学生達は戦争経験に触れることにより学修の動機づけを得るだけでなく、平和理解と国際交流の場にもなっています。また、招聘者にとっては学生との対話から現在の日本の姿を知っていただく良い機会にもなります。 折田元教授が退任した2014年以降は、法学部教授 宮丸裕二、法学部准教授 ピーター・ソーントンがこの事業を引き継いで継続しています。
参加学生の感想(終了後のアンケートより)
 涙ながらに過去の話や私たち次世代に期待することをお話しくださいました。実際に戦争を経験された方から、直接お話を伺ったり交流する機会はとても貴重なものなので心に残りました。今日伺ったような戦争のお話を、さらに次の世代に伝える役割を担うのは、私たちの世代のやるべきことだと強く感じました。(法学部1年)
涙ながらに過去の話や私たち次世代に期待することをお話しくださいました。実際に戦争を経験された方から、直接お話を伺ったり交流する機会はとても貴重なものなので心に残りました。今日伺ったような戦争のお話を、さらに次の世代に伝える役割を担うのは、私たちの世代のやるべきことだと強く感じました。(法学部1年)
 強制収容所における日本の残酷さに驚きました。自国の加害性は関心が低い、加害性を知る機会が少なかったので、とても良い経験になりました。講演では英語を聞き取れない部分があって悔しかった。また英語を使って質問できるようになりたいと思いました。(法学部1年)
強制収容所における日本の残酷さに驚きました。自国の加害性は関心が低い、加害性を知る機会が少なかったので、とても良い経験になりました。講演では英語を聞き取れない部分があって悔しかった。また英語を使って質問できるようになりたいと思いました。(法学部1年)
 戦後の日本経済に関する内容が興味深いと感じました。私は日本人なので戦後復興の歴史を良いものと捉えていましたが、ヨーロッパ諸国から見ると、決して良いものとは思えませんでした。見る視点によって歴史は良いものと悪いものにも捉えられると改めて感じました。
戦後の日本経済に関する内容が興味深いと感じました。私は日本人なので戦後復興の歴史を良いものと捉えていましたが、ヨーロッパ諸国から見ると、決して良いものとは思えませんでした。見る視点によって歴史は良いものと悪いものにも捉えられると改めて感じました。
初めて知ることが多くあり、自分の知識不足を実感しました。歴史を学ぶことは、未来を良くすることであると感じます。より多くの事を学び、またこのような機会があった際は、もっと深く理解できるといいなと思いました。(法学部2年)
 今回初めて戦争体験者の話を直接聞いて、戦争は絶対に起こしてはならないと思いました。将来、政治関係の仕事に就きたいので、オランダ人の方々の言うように、民主主義を守りたいと思いました。(法学部2年)
今回初めて戦争体験者の話を直接聞いて、戦争は絶対に起こしてはならないと思いました。将来、政治関係の仕事に就きたいので、オランダ人の方々の言うように、民主主義を守りたいと思いました。(法学部2年)
 今まで原爆のことを学ぶにも、日本が受けた壮絶な出来事しか学んだことがなかったので、日本がした壮絶なことを直接当事者の方に聞けて、言葉にできないほどの衝撃を受けました。今後は、日本の中で戦争関係について知る時があれば、その裏にある海外の方たちの背景・生活についても目を向けてみたいです。(法学部2年)
今まで原爆のことを学ぶにも、日本が受けた壮絶な出来事しか学んだことがなかったので、日本がした壮絶なことを直接当事者の方に聞けて、言葉にできないほどの衝撃を受けました。今後は、日本の中で戦争関係について知る時があれば、その裏にある海外の方たちの背景・生活についても目を向けてみたいです。(法学部2年)
 オランダ人の方々にとって、日本は敵であるはずですが、日本の若者に対して今後戦争をなくすために取り組んでほしいことをお話ししてくださいました。お話を伺う中で、「平和」を作るためには協力が必要であると思いました。また、涙ながらにお話をする姿に戦争を二度と起こしてはいけないと今まで以上に強く思うようになりました。(法学部3年)
オランダ人の方々にとって、日本は敵であるはずですが、日本の若者に対して今後戦争をなくすために取り組んでほしいことをお話ししてくださいました。お話を伺う中で、「平和」を作るためには協力が必要であると思いました。また、涙ながらにお話をする姿に戦争を二度と起こしてはいけないと今まで以上に強く思うようになりました。(法学部3年)
 スピーチの中で、ご両親が戦争を経験され、ご本人もその影響を受けて長い間精神疾患を患っていたというお話を受け、戦争の悲惨さや、日本のしたことの重大さを知りました。一方、そのような経験から日本を恨んでいたけど、今若者に経験を伝えようと自分の気持ちに区切りをつけて話しに来てくださったことに感銘を受けました。(法学部3年)
スピーチの中で、ご両親が戦争を経験され、ご本人もその影響を受けて長い間精神疾患を患っていたというお話を受け、戦争の悲惨さや、日本のしたことの重大さを知りました。一方、そのような経験から日本を恨んでいたけど、今若者に経験を伝えようと自分の気持ちに区切りをつけて話しに来てくださったことに感銘を受けました。(法学部3年)
 日本人から見た第二次世界大戦の歴史と、オランダまたはインドネシア等での日本による支配を受けていた側からみるストーリーは違うものであるということを感じました。多くの方が“話し合い”の重要性を話してくださっていたため、私も今後意識していきたいです。また、もっと海外の方との交流の機会を持ちたいと思いました。(法学部4年)
日本人から見た第二次世界大戦の歴史と、オランダまたはインドネシア等での日本による支配を受けていた側からみるストーリーは違うものであるということを感じました。多くの方が“話し合い”の重要性を話してくださっていたため、私も今後意識していきたいです。また、もっと海外の方との交流の機会を持ちたいと思いました。(法学部4年)
