「究める」では、大学院に携わる人々や行事についてご紹介します。今回は「在学生の声」として文学研究科の浅岡志津子さんへのインタビューをお届けします。大学院でのご自身の研究をはじめ、進学した理由や大学院での研究活動・課外活動など、大学院の様子が伝わる様々なエピソードを伺いました。
浅岡 志津子(あさおか しづこ)さん
研究科:文学研究科
専 攻:日本史学専攻
課 程:博士前期課程2年
大学院でのご自身の研究について教えてください
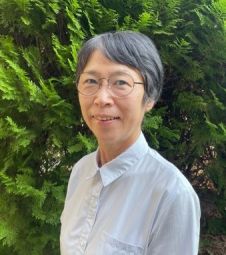
「歌木簡に見る日本古代社会―歌を書くという文化―」というテーマで、歌を書くことを目的にしたとされる「木簡」の存在から、なぜ書かれて、どのように使われたのかについて明らかにしたいと考えています。
木簡と言えば実用的なものが多い中、歌を書くという行為は明らかに異なるものです。考古学的に出土場所について確認し、国文学的に和歌史、文字の表記について知るところから、歴史の中のその存在が示すことに迫りたいと思っています。
大学院へ進学した理由と、中央大学大学院を進学先に選んだ理由を教えてください
大学を卒業し教員になった時から、学び続けたいという気持ちはあったのですが、仕事を始めると専門的なことを学ぶ余裕はなく、定年したら興味のあった歴史を学び研究したいと考えていました。
中央大学文学部国文学専攻で学び教員免許を取得したとき、よい環境であったことが印象に残っており、定年を前に改めて歴史を学ぶにあたって、学士入学について調べていたところ、中央大学を受験できることがわかり、入学することができました。先生方は皆さん熱心に丁寧にご指導くださり、研究室、事務室の方等職員の方々も、親切に対応してくださったおかげで卒業することが叶いました。
「木簡」そのものを専門とされる先生はいらっしゃらなかったのですが、日本史の知識をしっかり得るためにご指導いただける先生方はいらっしゃり、他大学との連携も充実していることを知り、引き続き中央大学の大学院で学ばせていただきたいと考えました。
実際に入学してみて、大学院はいかがでしたか
少人数なので、先生から直接指導していただけてよかったと思います。ただ、はじめは、研究テーマである歌木簡とは関係がないと思われる授業の準備に追われ、研究したいことに時間を費やせていないようで修論に向けて焦りを感じたこともありました。しかし、次第に、学んでいたことがつながってきて、研究したいことの素地になっていたことに気づくことができました。
大学院の授業はどのように行われていますか。学部との違いや特徴を教えてください
まずは、授業の準備に時間はかかるのですが、その分学ぶことはとても多いです。そして、特に自分の知識の足らないことに関する参考文献を紹介してもらえることで、学ぶ機会をもらえます。さらに、先行研究が正しいわけではなく、問題となることはどういうことかという、研究に向けての姿勢を指導してもらっています。
実際に履修した授業について、印象に残っていることを教えてください
古代史に関する先行研究紹介の授業は、各自の研究テーマに沿ったものなので、時代もさまざまで、普段の授業では全く触れない領域についての発表ばかりであるといってもいい内容です。が、予め読んだ時点ではよく理解できなかったことも、授業での質疑応答を繰り返す中で何が問題であるのかが明確になっていきます。
それぞれの院生が取り組んでいる専門性の高いテーマの研究意義を垣間見ることができるので、直接、自分の研究に繋がらなくても、ものの考え方を学ぶという意味でとても参考になります。
中央大学大学院に進学してよかったことについて
とにかく参考文献が揃っていること。中央図書館は言うまでもなく、共同研究室の書庫には検索すると古いものから新しいものまで大抵のものがあります。そして、自分の先行である日本史学では、日本文学に関する本や中国の本に資料を求めることも多いのですが、国文学共同研究室、東洋史学共同研究室の利用を、それぞれの室員の方々のお陰でスムーズに行うことができます。
授業以外の時間はどのように過ごしていますか
中央大学に週3日、他大学に週1日登校していますが、発表前などはそれ以外の日に図書館や共同研究室に行くこともあります。土、日は合気道の指導と自分の稽古で体力維持に努めています。あとは、日常的な家事と授業準備と研究ということになりますが、文章を打つことには未だに時間を要し、研究に関する検索をすることにもなかなか慣れず、かなりの時間をかけてしまっています。研究のための史料や資料は、読む度に気づくことがあり、考えながら読んでいると、あっという間に時間が過ぎています。
大学院進学を目指すみなさんへ
大学院には、大学ではできなかった学びがあります。自分の興味・関心があることばかりを学ぶわけではないこともあるかもしれません。でも、物事はつながっています。きっと、全ての学びは活かされます。そして、そうできるかは自分次第です。ぜひ、研究に対する強い思いを大切にして、自己実現につなげてください。
