「究める」では、大学院に携わる人々や行事についてご紹介します。第20回は文学研究科日本史学専攻の山崎圭教授の「史料管理学研究」を学ぶメンバーからの見学・実態調査の報告です。


作業風景

歴史資料の保全活動報告

作業風景
2019年11月30日・12月1日の2日間、長野市立博物館にて、10月の台風19号で被災した歴史資料の保全活動に参加しました。この活動は、台風19号で多くの歴史資料(未指定文化財)が被災したことを受けて結成された、信州資料ネットを中心に進められています。今回、私たちはこの活動にボランティアとして参加し、地元の参加者の方などと共に、ペーパータオルを用いて、水損した歴史資料から水を吸水し乾燥させる作業に取り組みました。
私たちが保全した歴史資料は、地域の歴史と地域住民が生活してきた証を示すものであり、地域住民が暮らす地域がどのような歴史をたどって現在に至るのかを知る上で欠かせないものでした。その点で、歴史資料の保全活動は、地域と地域住民の存在を強く念頭に置いた活動であることを改めて実感しました。
この保全活動は今後も長期にわたることが予想されます(カビの発生を抑えるため、真空凍結乾燥のために大量の歴史資料が冷凍されていました)。また、保全した歴史資料の目録作成や分析などを通じて、地域への還元を進めていくことも必要になると思われます。私自身にできることは僅かであるのかもしれませんが、今後も継続的に保全活動に参加していきたいと思います。
そして自分が保全活動に参加する一方で、参加した経験を多くの人に伝えることも重要であるように思います。保全活動では歴史資料(古文書)を読む力が必要とされているわけではありません。このような、活動の経験を多くの人に伝えることで、保全活動に参加しようとする人の障壁を低くし、活動に参加する仲間を増やすことができると考えます。それは、長野県外にいる私たちが継続的に保全活動に参加していくことに繋がるのではないでしょうか。
今後も歴史学・歴史資料にかかわる者として保全活動に参加していきたいです 。
文学研究科博士課程前期課程
大銧地 駿佑(おおこうち しゅんすけ)
参加者のコメント
台風の被害を受けてしまった史料を後世に残すための史料レスキューに今回参加させていただきました。活動を通して、改めて史料の重要さと史料を残していくことの難しさを痛感しました。今後も機会があればこのような史料保全活動に参加していきたいです。
文学研究科博士課程前期課程
西村 英之(にしむら ひでゆき)
この度、はじめて史料レスキューに参加をさせていただきました。被害の状況を漠然と聞くだけなのと、赴いて実状を観て作業をおこなうのでは感覚が異なり、史料保存の重要性、人手の必要性が感じられました。
文学研究科博士課程前期課程
玉土 大悟(たまど だいご)
今回の史料レスキューでは、水没した史料を乾かすために一枚一枚にキッチンペーパーを挟む作業などをしました。史料を水没させてしまうと修復に多大な労力がかかるので、水没させない対策が大切であることを実感しました。
文学研究科博士課程前期課程
鈴木 祐太郎(すずき ゆうたろう)
今回史料レスキューにはじめて参加し貴重な経験をすることができました。日本は災害大国であるため今後も史料が被災する可能性は高いです。次回このような機会があれば積極的に参加し今回の経験を生かしていきたいと思います。
文学研究科博士課程前期課程
福島 怜(ふくしま りょう)
普段講義で聞くことしかなかった、被災した資料のレスキューを行いました。 現地では、水没した区有文書をキッチンペーパーではさみ乾燥させ、カビが生えていたら取り除くという作業を行いました。講義で学んだ水没資料の乾燥方法が量の多さなどの関係で現場ではできず、実地で経験すること大切さを学びました。 被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
文学研究科博士課程前期課程
小林 康平(こばやし こうへい)
山崎圭(やまざき けい)教授からのコメント
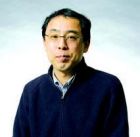
山崎圭教授
大学院の日頃のゼミでは、授業を教室で行う都合上、文献や活字史料、古文書写真等を中心に扱って授業を進めています。その点、大学の補助を受けて実施する見学実態調査では、歴史資料が残された現地を訪ねて、活字ではない生の史料を取り扱うことができます。今回は、2019年10月の千曲川洪水で被害を受けた地域資料の被災実態と、それを救う取り組みを実見し、実際に作業に参加することで史料保存の方法について学びました。災害が多発する現在にあって、史料レスキューの経験は欠かせないものになっています。
※信州資料ネットのTwitterをご紹介します。以下のリンクよりご覧ください。
