ネパールのヒマラヤ山脈にそびえる未踏峰「プンギ」の登頂に成功!
芦沢 太陽さん|Taiyo Ashizawa
文学部4年
山岳部主将
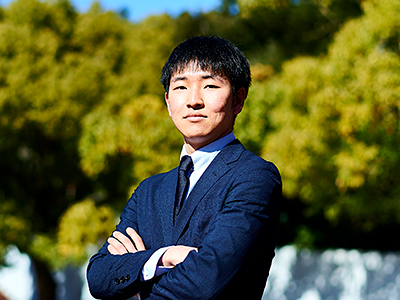
2024年秋、山岳部主将の芦沢太陽さん(登頂時3年)が日本山岳会学生部プンギ遠征隊の一人として、ネパールのヒマラヤ山脈にそびえる未踏峰「プンギ」(6524メートル)の登頂に成功しました。ほぼ全員が大学から登山を始めたという4大学の山岳部員5人がチームを組み、学生だけで初登頂という快挙を成し遂げました。遠征期間は9、10月の計58日間にわたりました。
帰国した芦沢さんに、登頂の様子や心境、仲間とのチームワーク、現地でのコミュニケーションなどを振り返りながら語っていただきました。そして、今回の遠征を経て「挑戦したいことがあるのに失敗を恐れてやらないなんて、どれほどもったいないことをしているんだと、以前の自分に伝えたい」と海外で何かをやりたい、挑戦したいと思っている後輩達にメッセージを送りました。
(ネパール現地での写真は全て芦沢太陽さん提供)
ロープを結び命を預け合う仲間、応援してくれる人々
人とのつながりが一番の財産
- 他大学の学生と共にヒマラヤ未踏峰を目指した理由は?
- 昨今、大学山岳部というものは衰退の傾向にあります。全盛期は部員数が何十人もいるような時期もありましたが、現状、大学山岳部の多くは部員数の減少が目立ち、かつて名門と呼ばれた山岳部が廃部になってしまったケースもあり、単一の大学山岳部だけでヒマラヤ登山の遠征隊を組織するということは難しくなっています。そのような背景があり、合同隊を組んで未踏峰に挑戦しないかということになりました。また、未踏峰に挑むという分かりやすい目標を掲げ、それらをSNSなどの媒体でアピールしていくことで、大学山岳部を再び盛り上げていきたいという思いもありました。
- 今回のメンバー5人が知り合った経緯を教えてください
- 日本山岳会学生部という、主に首都圏近郊の大学山岳部が加盟している組織があり、その定例会で、今回の遠征で総隊長を務めた井之上巧磨さん(青山学院大体育会山岳部=当時)が合同隊を作って未踏峰を目指そうと呼びかけたところ、未踏峰に憧れを抱いていた今回の5人が集まりました。
経験豊富な山岳部OBに同行する方が登頂の可能性は高くなります。しかし、それで自分たちの力で登ったといえるのかどうか。ただ後ろをついていくだけの登山にはしたくない。これまで山岳部で学んできたことを存分に発揮したい。そんな思いから、今回は学生だけで登るということにこだわりました。
■日本山岳会学生部プンギ遠征隊(学年は登頂時)
井之上巧磨さん|総隊長|青山学院大体育会山岳部主将(4年)
尾高涼哉さん|登攀隊長|東京大運動会スキー山岳部主将(4年)
横道文哉さん|渉外、会計、記録担当|立教大体育会山岳部副将(4年)
中沢将大さん|装備全般担当|立教大体育会山岳部主将(4年)
芦沢太陽さん|会計担当|中央大学友会体育連盟山岳部主将(3年) - プンギにターゲットを絞った理由は?
- 今回の遠征隊はほぼ全員が大学から登山を始めたこともあり、技術や経験はまだまだでした。そこで、登頂できそうな未踏峰はないかと探した結果、プンギに辿り着きました。衛星写真などから、プンギは登攀ルート上に急峻な岩壁など、通過に高度な技術を要する箇所がないと予想され、我々の実力でも勝負できると考えたからです。 もちろん、2022年秋に同じ日本山岳会のヒマラヤキャンプ隊が挑んだことも知っていました。プンギ登頂を目指すと決めてからは、ヒマラヤキャンプ隊の皆様にもお話を伺い、山の写真や遠征時の情報などを快くご提供いただきました。
- プンギ山頂に立った時の心境、様子を教えてください
- 山頂に立った瞬間はやはり嬉しかったです。登頂できたこと自体よりも、登頂に向けてそれまで取り組んできた様々なことが実を結んだということが嬉しかったです。それまでは緊張した面持ちだったメンバーも、頂上では笑顔を見せていました。しかし、山頂はあくまでも中間地点であり、下山も気を抜けないルートだったため、すぐに気持ちを切り替えました。
6000メートルの世界は、平地と比べて酸素濃度と気圧が約半分、気温は約30度下がります。何をするにも息が切れ、気圧の関係か頭痛にも悩まされ、とにかく寒い。普段の常識が全く通用しない世界でした。
―― 最もすがすがしい気持ち、うれしい気持ちになったのは?
登頂後、無事にベースキャンプに下山した瞬間です。ベースキャンプで待機してくれていた現地トレッキング会社のスタッフに登頂したことを告げると、盛大に祝福をしてくれました。無事に生きて安全圏まで戻ってくることができたという安心感も相まって、何にも代えがたい最高の気分でした。
―― 一番怖かったと感じたのは?
セラック(氷河上の巨大な氷の塊)の下を通過しなければならない場面が一番怖かったです。セラック崩壊に巻き込まれればまず助からないため、もっとも崩壊のリスクを避けることのできる、早朝の気温が低い時間帯に通過しました。しかし、いつ崩壊するかは誰にもわかりません。
- 仲間との役割分担を教えてください。チームワークはどうでしたか?
- 事務的な役割だと私は保険と会計を担当しましたが、実際には役職にとらわれずにメンバー内で協力し合って様々な仕事をこなしていました。これは登山中も同様で、登攀が得意な者は先頭でルートを切り開き、体力に自信がある者は少し重い荷物を背負ったり、その場にあった役割分担をしていました。私は5人の中では比較的高所でも元気だったため、とにかくラッセル(雪をかき分けて進むこと)を頑張りました。高所だとすぐ息が上がってしまうために、あまり言葉をかわすことはありませんでしたが、誰かが辛そうにしていたら、他のメンバーで代わりに荷物を分担して持つなど、助け合いながら進んでいきました。
ヒマラヤ遠征では、長期間ともに生活することになるため、チームワークが非常に重要になります。そのため、遠征前の冬シーズンでは複数回、長期間にわたってトレーニング山行を実施し、チームワークの向上に努めました。その甲斐もあって、2か月にわたる共同生活の中でも1回も喧嘩になることはなく、今回の遠征隊は世界中の登山隊をみても最高のチームワークだったように思います。 - 現地で英語や現地語でのコミュニケーションはありましたか?
- 英文専攻で英語は好きですが、語学力は全くありません。メンバーの1人である横道文哉さん(立教大体育会山岳部=当時)が英語が得意だったため、コミュニケーションをとる上で頼りになりました。
ネパール人は皆フレンドリーだったので、身ぶり手ぶりとパッションでも通じました!
また、ベースキャンプのネパール人のコック、ジャガティス・グルンさんは日本語が得意だったので、コミュニケーションでは苦労しませんでした。彼は日本で山小屋で働いた経験があり、すき焼きなど日本食を作ってくれました。 - 芦沢さんにとって今回の経験で得られたもの、一番の財産は何ですか?
- 今回の遠征で得たたくさんのもののなかでも一番の財産は、人とのつながりです。ロープを結びあって命を預けあう仲間、応援していただける先輩方、企業様など、今回のプンギ峰登頂には数えきれないほど多くの人が関わっています。その多くは、今回の遠征がなければ、今ほど交流できる機会はなく、または出会うことはできませんでした。

日本山岳会学生部プンギ遠征隊メンバーの5人

プンギ山頂にて。チュー王子も一緒でした!

山は『心を洗濯できる場所』
もやっとしている時に自然と触れ合うと浄化されることを多くの人に知ってほしい
- 登山を始めたきっかけと中大山岳部に入部した理由は?
- 高校入学のタイミングで部活を選ぶ際、卓球か、登山かで悩み、卓球部に入部。3年間卓球漬けの日々を過ごしたために大学では新しいことをしようと考え、高校時代は選ばなかった登山をしてみようと思ったことがきっかけです。
中大山岳部は、中大で唯一冬山に登ることができる部活だからです。未踏峰への漠然とした憧れは当時からあり、冒険的な登山をしたかったので山岳部一択でした。 - 登山への恐怖心、自然への畏怖心を感じることはありますか?
- 登山が自然を相手にするスポーツである以上、もちろんあります。そのなかでもリスク最小限にするためにトレーニングをしたり、自然に対する知識をつけて登山を楽しんでいます。 普段は家の近くの河川敷を走っていますが、合宿前は2リットルのペットボトルをたくさん入れたザック(リュックサック)を背負って、近くの低山に登りに行きます。たまに部員同士でクライミングジムに行ったりもしています。
- 登山家としての自分の強みと今後の課題は?
- 強みは大抵の環境で熟睡できることだと思っています。今回の遠征では6200メートルの最終キャンプ地でも熟睡できました。 今後は難しい壁を突破するために、登攀力を鍛えたいと思っています。
- 登山や山の魅力について教えてください
- 登山の魅力はたくさんありますが、私が常々思う魅力は『足るを知る』ことができるということでしょうか。長期間山に入ると、日々の暮らしで当たり前になっている電気、ガス、水道、インターネットといったインフラなど、いかに便利で素晴らしいものに囲まれていたのかを再認識することができます。
また、山は『心を洗濯できる場所』であり、もやっとしている時に自然と触れ合うと浄化されることを多くの人に知ってほしいです。 - 今回の経験で、芦沢さん自身が変わったことは?
- 以前までは、何事にも失敗を恐れて挑戦しないような消極的な考え方をすることが多かったですが、それは大きく変わりました。今回の遠征ではたくさん失敗したことがありますが、振り返ってみればそれ以上に大きな成功を掴むことができました。挑戦したいことがあるのに失敗を恐れてやらないなんて、どれほどもったいないことをしているんだと、以前の自分に伝えたいです。

多摩キャンパス第1体育館の山岳部の部室前

山岳部の倉庫にて

部室の書棚には山や登山に関する書籍が並ぶ
■中央大学学友会体育連盟 山岳部
1926(大正15)年創部。吉田一貴監督、芦沢太陽主将。部員数8人(男性7人、女性1人)。日本アルプスをメインフィールドに、季節ごとに夏山縦走、ロッククライミング、冬山登山などの活動を行う。部員の大半は大学から登山を始めている。登山にはリスクもあるが、それを最小限にとどめながら最大限に山を楽しんでいる。1、2年生の部員を募集中。
「登山は競技などと違って競い合うスポーツではないため、山岳部では全員がレギュラーとして活躍することができます」と芦沢さんが山岳部の魅力を語りました。
2026年に創部100周年を迎える山岳部では、OBや現役生を交えて海外への遠征計画が検討されているそう。
学生記者が取材編集する大学広報誌「HAKUMON Chuo」
 2025年4月2日発行の「HAKUMON Chuo No.285」2025春号の巻頭では、芦沢太陽さんを特集しています。
2025年4月2日発行の「HAKUMON Chuo No.285」2025春号の巻頭では、芦沢太陽さんを特集しています。
2024年2月、多摩キャンパス第一体育館の部室で芦沢さんの取材が行われ、学生記者の合志瑠夏さん(経済学部4年)と金岡千聖さん(商学部3年)がインタビューしました。山岳部のこと、トレーニング方法、現地での生活など、同じ大学生の視点で学生記者が切り込みました。ぜひご覧ください。



