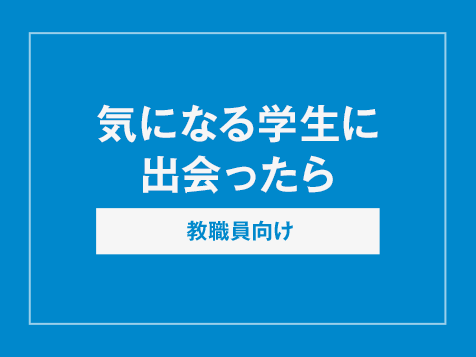FD・SD活動
FD・SDミニセミナー
FD・SD講演会と同様、教育活動の質的向上に資する授業実施スキルやTipsの共有、そして本学が質の高い大学運営を行うにあたって必要となる知識・技能を教職員が効果的に習得することを目的として、2024年秋より「中央大学FD・SDミニセミナー」を実施しています。1テーマあたりの説明時間を15分程度にまとめ、「短時間で」「端的に」情報を取得することをコンセプトにしており、オンデマンドやLIVE配信を使い分けながら教職員が「すき間時間」で必要な情報をキャッチアップできる点が、FD・SD講演会との違いです。(講演/説明者の所属・身分等は講演会開催時のものを掲載)
2024年度
第9回
| テーマ | 生成系AIを考慮した評価とどう向き合うか?(「生成系AIと授業」シリーズ 第2回) |
|---|---|
| 日時 | 2025年3月21日 |
| 開催形式 | オンライン形式(Webex) |
| 講演者 | 教育力研究開発機構専任研究員/文学部特任助教 澁川 幸加 氏 |
| 内容 | ・生成系AI対策の評価はどのようにデザインできるか? ・生成系AI活用も射程にした評価はどのようにデザインできるか? |
| 参加者数 | 113名 |
第8回
| テーマ | オープンサイエンスへの対応(「研究」シリーズ 第3回) |
|---|---|
| 日時 | 2025年3月21日 |
| 開催形式 | オンライン形式(Webex) |
| 説明者 | 副学長/研究推進支援本部本部長/理工学部教授 石井 洋一 氏 研究支援室 河原 卓巳 氏 |
| 内容 | ・「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」および本学における対応状況について ・目的、対象となる研究費、対象となる研究成果、オープンアクセスの方法 ・研究データ管理ポリシーの策定、中央大学研究成果オープンアクセスポリシーおよび中央大学学術リポジトリ要綱の改正について |
| 参加者数 | 54名 |
第7回
| テーマ | 生成系AIを授業でどう活用するか?(「生成系AIと授業」シリーズ 第1回) |
|---|---|
| 日時 | 2025年3月14日 |
| 開催形式 | オンライン形式(Webex) |
| 講演者 | 教育力研究開発機構専任研究員/文学部特任助教 澁川 幸加 氏 |
| 内容 | ・授業準備や教材づくりに生成系AIを活用するためのアイディア ・授業中に生成系AIを活用するためのアイディア |
| 参加者数 | 125名 |
第6回
| テーマ | 研究インテグリティの確保に向けて(「研究」シリーズ 第2回) |
|---|---|
| 日時 | 2025年3月14日 |
| 開催形式 | オンライン形式(Webex) |
| 説明者 | 副学長/研究推進支援本部本部長/理工学部教授 石井 洋一 氏 多摩研究支援課 山田 寛子 氏 |
| 内容 | ・研究インテグリティとは何か?信頼される研究者になるための基本 ・研究インテグリティ確保のために国の施策を知る ・中央大学はこう動く!研究インテグリティ確保の取り組み ・実際に起こった!?研究インテグリティに関するヒヤリハット事例と教訓 ・研究者として実施いただきたいこと:信頼を築くために必要な心構えと運用 ・押さえておきたい研究インテグリティの最新トピックと動向 |
| 参加者数 | 54名 |
第4回・第5回
| テーマ | 大学全体の研究力の分析 (「研究」シリーズ 第1回) |
|---|---|
| 日時 | 2025年2月5日(水) |
| 開催形式 | オンライン形式(Webex) |
| 説明者 | 本学URA 成毛 治朗 氏 |
| 内容 | ・本学全体の状況 ・本学研究者に着目した状況 ・本学の個別研究者のケーススタディ ・研究成果の社会実装に向けた課題(大学発ベンチャー、特許関係) |
| 参加者数 | 82名 |
第2回・第3回
| テーマ | 生成系AIを利用した語学授業で進めたいこと、気をつけたいこと |
|---|---|
| 日時 | 2024年12月6日(金) |
| 開催形式 | オンライン形式(Webex) |
| 講演者 | 法学部准教授 中村 文紀 氏 |
| 内容 | ・英語(語学)と生成系AIの相性はどう考えているのか。 ・教員の代わりにいくらでも付き合ってくれるTAとしての生成系AI ・生成系AIなしの英語力を測るのか、生成系AI込みの英語力を測るのか。 ・具体的な考え:「初めて」「その場で」「創造的に」「技能として」 ・初心に返り、授業内容と評価の対応関係は何度でも伝えよう。 |
| 参加者数 | 105名 |
第1回
| テーマ | 中央大学が行う「SD」とは? |
|---|---|
| 日時 | 2024年11月18日(月) |
| 開催形式 | オンライン形式(Webex) |
| 講演者 | 学長 河合 久 氏 FD・SD推進委員会委員長、理工学部教授 山西 博之 氏 |
| 内容 | ・なぜ「SD」を行うのか? ・どのような活動が 「SD」 なのか? ・本学が行うSD活動について –中央大学FD・SD推進委員会を中心に- |
| 参加者数 | 140名 |