
法律家を志す学生らが日夜、猛勉強に励む多摩学生研究棟「炎の塔」。
この棟に在籍する研究室の中でも
80年以上の長い歴史を持つ「真法会」に所属し、
仲間たちと切磋琢磨して学生時代を過ごしてきたのが登島氏だ。
卒業後は「真法会」で磨いた知識を活かして企業法務の道に進み、
法務部門の役職者として名だたる企業を渡ってきた。
現在はアジア太平洋地域を相手に、組織責任者として法務を統括する。
今回、紹介するのは、そんな登島氏が歩んできた道のりだ。
企業が抱える法律問題を解決し、多くの若手を育ててきたからこそ
語れる登島氏の経験は、学生たちの道しるべとなるだろう。
好奇心旺盛に過ごした学生時代。真法会に所属しながら、大臣事務所でアルバイト
1981年、神戸から上京した当時は、高尾の多摩御陵(現武蔵陵墓地)の近くにあった中央大学協力下宿にお世話になっていました。大家さんの蔵書がたくさんあり、さまざまな本をお借りして読書に熱中していました。なかでも阪本勝氏の著書「流氷の記」には、特に感銘を受けました。その著には彼の思索と生き様がまざまざと描かれていて、彼が影響を受けた多くの古典・名著を彼と同じように読み漁りました。
大学2年次に、法律家を目指す学生たちが集う「真法会研究室」に入室を許され、4年次には委員長を務めました。元学長の戸田修三先生の商法ゼミでは幹事長を引き受け、仲間たちと大いに議論し、また酒も飲みました。
学外での活動としては、1年生の春休みから中央大学の大先輩、保岡興治先生(元法務大臣)の議員事務所でアルバイトをしていました。また、保岡先生と盟友であり同じく中央大学の大先輩、稲見友之先生がともに、ロッキード事件で逮捕された田中角栄元首相の弁護団に加わっておられたことから、裁判資料の整理などもお手伝いしました。角栄氏が公判で熱心にメモを取っていた様子は、いまだに鮮明に覚えています。
学生時代は、とにかくいろんなことにチャレンジして、本当に楽しかったですね。
勉強量と熱心さに驚かされた「真法会研究室」
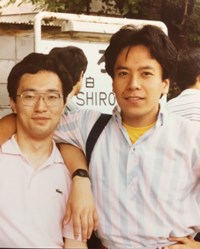
「中央大学真法会」の同期 小早川龍司氏(現小早川法律事務所 所長・弁護士/写真左)と一緒に
真法会研究室に入室した当時は、とにかく先輩方の勉強量と熱心さに驚かされました。とくに夏場、エアコンもない旧学生研究棟(今の“炎の塔”はホントに素晴らしくうらやましい限りです)の研究室で、「よく集中力が持つなぁ」と感心しました。
入室ほどなく、菊池則明先輩(現東京高裁判事)に基礎ゼミで民法総則を教わり、真法会の先輩で当時東京地検特捜部におられた宗像紀夫先生には刑法の基礎を教えていただきました。
毎年恒例の長野県での夏合宿では、谷口好幸先輩(現株式会社東京ドーム専務取締役・弁護士)の刑法ゼミに加えていただき、竹村眞史先輩(現成蹊大学法科大学院客員教授・弁護士)には、朝練で頭脳ではなく肉体を鍛えていただきました(笑)。そういえば、当時真法会では定期的に精神修養のために座禅会などもやっていましたね。
4年次には、諸先輩方への恩返しとばかりに研究室の委員長選挙に立候補し、委員長として真法会研究室の運営に携わりました。当時、学生たちの指導にあたられていた、今は亡き兼平雄二先生からは研究室の予算作りなどで多くのことを学ばせていただきました。兼平先生の事務所に伺うと、いつもデスクの上は事件関連の書籍や資料が山積みで、弁護士の実務の厳しさを目の当たりにしました。
真法会には厳しい規律の中において、先輩が後輩を導く素晴らしい伝統があります。また、同じ目標に向かい励まし合いながら勉強に勤しむ同期が強い絆で結ばれます。特に委員会を構成したメンバーとは、とても太い絆ができます。
真法会では、
・法律に対する真摯な姿勢
・リーダーシップとフォロワーシップ
・同期の固い結束
が培われ、醸成され、今の仕事に間違いなく生きている。私はそう確信しています。
中央大学で学生時代を過ごしたおかげで、多くの優れた方々とお会いでき、社会に出てからもさまざまな場面で助けられました。
真法会研究室に入室したときの委員長だった佐野晃生先輩(現日本電産法務部部長・弁護士)は同じ企業法務の道を歩んでこられた目標とすべき素晴らしい先輩。私の企業法務人生の節目、節目で本当に助けていただきました。
皆さんも学生時代の先輩・後輩、友人関係を大切にしていただきたいと心から思います。
検察官、弁護士という夢から、企業法務の道へ転進
学生時代は検察官か弁護士になりたいと思っていました。だからこそ、中央大学の法学部に入学して真法会研究室に入り、卒業前は一切就職活動を行いませんでした。ところが、諸事情により卒業2年目で司法試験を断念。
戸田ゼミの先輩で、中央大学の職員となられた方に理工学部の就職課でのアルバイトを紹介していただき、さらに、その就職課でも多くの職員の方々に大変お世話になり、正社員の就職先までご紹介いただいたのですから、本当に中央大学は情誼に厚い方々が多い素晴らしい学校だと思います。
最終的に、「勉強してきたことを活かしたい」と思い、法務部門のある企業に絞って就職活動を行いました。企業法務への就職に舵を切った後は迅速に動き、スタンレー電気株式会社の総務部庶務課法務係に法務担当者として採用していただきました。
ここでの面接で印象に残っているのは、英文で書かれた会社紹介の記事を読むように言われ、“Company Profile”を「カンパニー・プロフィール」と読み「プロファイル」ですねと、面接官の広報課長からダメ出しされたとき。さすがに恥ずかしかったですね。今は外資系企業の法務責任者として大きな顔をしていますが、最初はホントその程度の英語力だったんです。よく採用していただきました(笑)。
当時からの信念は、「一生この企業法務の道で自分は生きていくんだ」ということ。企業法務のフィールドはとても幅が広いため、多くを学ぶには転職もあり得るだろうと思っていました。実際、何度か転職をしましたが “企業法務”という一点においてブレることなく、30年以上働いています。
現地役職者とのロングインタビューを経て、外資系関連企業に転職

インヴェンティヴ・ヘルス・ジャパン合同会社財務部長 アラン・ウォード氏(左)と登島氏(右)
今のインヴェンティヴ・ヘルス・ジャパン合同会社(外資系製薬関連企業)には2014年5月から勤務しています。前職場の社長がインヴェンティヴ・ヘルス・ジャパン合同会社で社長となられた際に、企業法務機能強化のためにお声をかけていただいたのがきっかけです。
就職面接では、若干苦労がありました。部長陣の面接後、2、3週間して米国本社のDeputy General Counsel*と電話による長いインタビューがあり、ようやく終わったかと思っていると、その数週間後にGeneral Counsel*との電話面接がありました(*General Counselは、企業<または企業グループ>の法務部門のトップ。Deputy General Counselは、No.2)。
その数週間後、再びDeputy General Counselとの電話面接があり、最初の面接から最終的にオファーをいただくまでに3か月ほどかかりました。
社長から聞いた話によると、「法務は営業サイドに対して、牽制的な機能を果たさなければならないこともある。その観点から、営業サイドのトップでもある社長の紹介で来た法務担当者がその任務を果たせるか、慎重に確かめたかったようだ」とのこと。確かに、そうですよね。
外資系ならではの仕事のやりがいは、幅広さと難易度
現在はインヴェンティヴ・ヘルス・グループの日本法人と雇用契約を結んでいます。しかし活動範囲は日本の枠を超え、同グループのアジア太平洋地域の法務統括責任者として、アジア太平洋地域全域の契約・コンプライアンス・コーポレートガバナンス等に及びます。各国の事業に関する法制度等の情報は、適時適切にアップデートしていくことが欠かせません。
外資系法務における、仕事のやりがい
私が考える現在の仕事のやりがいについて、下記の3点をご紹介します。
【仕事の性質上の幅(Variety)】
予防法務(コンプライアンス・契約法務・ガバナンス)、臨床法務(訴訟・紛争解決)、戦略法務(M&A、その他事業戦略立案等)と幅広いです。そのため、果たすべき責任は大変重いですが、経営に深く関与できるところが最大の魅力です。
【地理的テリトリー(Geographical Territory)】
通常、日本で外資系企業の法務部門に勤務すると、日本の子会社での法務責任者が最高位だと思います。しかし現職ではアジア太平洋地域も任されており、その意味で「大変やりがいのあるポジションに就かせていただいている」と日々感謝しながら職務にあたっています。
【仕事の難易度(Difficulty/Hardness)】
仕事の難易度は、やはり軽くはないですね。昨今、さまざまな法改正が行われ、行政庁からの情報発信も一昔前に比べると段違いのボリュームです。事業に影響する情報を適時に把握して、法務戦略を立てていくことが求められます。
米国本社サイドからも、法改正に伴う対応や背景の説明等を求められることがしばしばあります。そうした説明責任は、外資系ならではかもしれません。
外資系ならでは、ということで言えば、事業提携・企業買収などは日常茶飯事です。一日たりとも安穏と過ごしてはいられない緊張感がありますが、生来怠惰な自分にはこれくらい緊張感ある職場の方が人生を無駄にせずに済むという意味で、向いているようにも思います。
若手に実行してほしい、2つのこと
部門管理について付け加えると、私は現在、組織責任者として6名の部下(日本の法科大学院卒3名・外国ロースクール卒兼ニューヨーク州弁護士資格者1名・法学部卒1名を含む)を率いています。
特に若手に日々、重要だと言っているのは、
・自分の頭で考え抜く癖をつける
・多量の業務を迅速にこなすために必要な知識を早く身に着け、業務スキルを向上させる
ということ。
こうした後進の育成にあたることができるのも、今の仕事のやりがいのひとつですね。本人の希望も聞き、また各メンバーの適性も考えながら、各人に業務を割り当て、日々の業務にあたってもらっています。
仕事で使えるコミュニケーションレベルとは。学んで練習すれば、習得できる

米国、シンガポールの法務部門エグゼクティブが来日
一人だけで完結できる仕事は、世の中に存在しません。仕事の依頼を受け、自分のなすべきことを行い、依頼人にフィードバックする、あるいは次の工程の人に引き継ぐ。
それが仕事というものですから、人とのコミュニケーションが絶対に必要です。
仕事のコミュニケーションレベルは、相手が欲していることを正確に聞き取り、自分がすべきことを明確化できなければなりませんから、相当高いレベルが求められます。
そして、グローバルに働くためには、ドメスティックなフィールドで働く場合に比べ、より高いコミュニケーションスキルが求められます。なぜなら、お互いが伝えようとする内容を理解するための背景、文化や習慣などが異なりますから。
世間では“コミュニケーション能力”とよく言われますが、その本体はスキルです、技術です。基本的には、学んで練習すれば、習得できるものです。
しかし、そのための講座やセミナーは世の中にあまり普及していません。そのため、私は昨年頃から“新企業法務倶楽部”というクラブを私的に立ち上げ、企業法務を目指す人たちを支援するため自ら社外セミナーを開催しています。
学生時代に英語のレベルを上げないと、就職先を自ら狭めてしまう
英語については、もうあれこれ言う時代ではないと思っています。英語をまったく必要としない産業が、世の中にどれだけあるのでしょう。特に私のいる企業法務の世界は、英語が読めて、書けて、聞けて、話せるのが当然の世界。法曹の世界でも、トップレベルの方々は普通に英語を操っておられるというのが私の実感です。
英語の学習方法は、世間にあふれています。自分に合う方法を探して学生時代に一定のレベルまで引き上げなければ、就職先の選択肢を狭めます。昨今の大手有名企業は社内公用語が英語のため、入社後に大変な思いをするのではないでしょうか。
就職活動で悩んだら、過去の体験を振り返り自分の価値観を探る
私は学生時代、いわゆる“就職活動”を行わなかったので具体的なアドバイスはできませんが、学生の皆さんが就職活動に備えるなら、大学生活で経験してきたこと――授業、ゼミ、サークル、アルバイト、ボランティアなどを一度棚卸してみてください。
そして、それらが自分にどのような意義があるか、また、その事柄に関わった先生、先輩、後輩、友人、その他関係者の方々から見て、自分はどのように見えていたかを想像し、自分が成長してきた過程を一つのストーリーにしてはどうでしょうか。この作業を通して、自分が本当にやりたいことも見えてくるかも知れません。
難しい選択を迫られた時の、回答を導くヒント
もう一つ。就職活動中には、難しい選択を迫られることがあると思います。そんな時には、哲学者のRuth Chang(ルース・チャン)氏の考え方を一つの参考にしてはいかがでしょう。
長さや重さは客観的に測ることができるけれど、価値観の世界では優劣はない。「on a par(同等・互角)」なのだから、“どちらがより優れた選択肢か”ということで悩み患うことはない、と彼女は言います。そして、選択の理由を外に探すのではなく、自分の内側に見出せ、と言います。
『自分の下した困難な決断からわかるのは、自分が何に主体性を持って取り組みたいかということです。そして困難な決断を下していくことで、下した決断どおりの自分になるのです』
『私たちは自分の選択に自分だけの理由を生み、それを通じて自分自身になることができるのです』
いい言葉だと思います。あなたの人生の主人公はあなた自身なのだから、あなたが何に主体性を持って取り組みたいかということに素直に従えばよいのだと思います。
学生が“一目置かれる社会人”になるための方法
学生たちに、「自分の“ブランド”を確立しろ」と言いたいですね。セルフ・ブランディングという言葉を最近耳にすることが多いですが、起業家だけが意識すべき言葉ではなく、企業に就職し、組織の一員となった人にも大切な言葉です。
たとえば、月曜日に上司から「金曜日までに報告書を仕上げろ」と言われたら、あなたはどうしますか。言われた報告書を1週間後に提出するだけでは、あなたはあなたのブランドを作ることはできません。
上司から仕事の命令を受けたら、
| すぐ | 「この報告書作成の目的はxxxですか」 |
| 1時間後くらい | 「この報告書の概要と組み立て、ボリューム感はこれくらいでよろしいですか」 「情報収集すべき関係者はこの方々でよろしいですか」 |
| 2日後くらい | 「現時点で概ねこのような内容なのですが、 ご確認いただいて、アドバイスをいただけますか」 |
| 期限一日前の木曜日 | 「アドバイスをもとにこのように仕上げました」 「補足資料はこのとおりです」 |
といった具合に仕事をすすめると、上司は数ある部下の中からあなたを“仕事ができる部下”として認知します。
そうした仕事ぶりが続けば、より大きな仕事を任せてくれるようになり、あなたの名前は他の部門でも有名になっていくでしょう。
また、自分の“ブランド”を確立するには、是非、自分の仕事のアウトプット(報告書、提案書、プレゼン資料等々)について、“自分の作品だ”という意識を是非持ってもらいたいですね。芸術家にとっての絵画と同じように。
基本的に社会であなたは“アウトプット”でしか評価されないと、覚悟すべきです。家族であれば、「○○ちゃんはよく頑張ったよね」と言ってくれるかも知れませんが、社会ではそうはいきません。あなたがどのような態度で仕事に取り組んでいるかなど、まったくの評価外です。
| アウトプット例:取引を実現するために契約書を作り、営業部に提出する。 →営業部は、自分たちの関心事を中心にレビュー。 (販売する製品モデル、数量の記載が正しいか。価格、納期、支払条件などは、営業部の思惑通りに主張できているかetc.) ※契約書の作成にあたり…… 想定されるビジネスリスクについて営業部以外の関連部門からもヒアリングを行ったことや、当該製品に関連する外国特許を調査したり社外弁護士や米国本社の法務部門と協議・調整したりした“過程”は顧みられない。 評価されるタイミング例: 上記アウトプット後、取引先が当社から購入した製品について第三者から特許侵害だと訴えられ、当社にその損害賠償を求めてきたとき。 →「大丈夫ですよ。その特許権はすでに存続期間を終了していると調査済です」と営業部に回答できる。 |
先に述べた仕事の進め方「上司から仕事の命令を受けたら」は、優れた“アウトプット”を生み出すための方法論の一つです。
是非、皆さんには自分の仕事にプライドを持って、「セルフ・ブランディングをしていくんだ」という意識を持って社会に飛び出してほしいと思います。
AI、IoTといった第4次産業革命によって世の中の変化はますます速くなり、国際間競争もますます激化します。その中で生き抜くには、皆さんは見えている敵だけでなく、見えない敵とも戦いながら自己を磨いていくしかありません。
自分を信じ、つらい時こそ前を見据えて、自己のブランドを確立すべく奮闘してほしいと思います。
皆さんの今後のご健闘・ご活躍を心からお祈りしています!!
■プロフィール■
インヴェンティヴ・ヘルス・ジャパン合同会社
アジア太平洋地域法務責任者
登島 和弘(としま かずひろ)さん
1961年生まれ、兵庫県出身。スタンレー電気株式会社 総務部庶務課法務担当を皮切りに、日本AT&T株式会社 契約課長、松下冷機株式会社 法務室主事、セジデム株式会社コーポレートサービス部統括部長・法務部長兼任等を歴任。現在はインヴェンティヴ・ヘルス・ジャパン合同会社にて、アジア太平洋地域法務責任者を務める。
