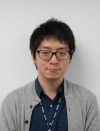
藤井 翔
大学院に進学してからの五年間、自由に研究をさせていただいた。この研究活動を支えているのが、理工学研究科の支援制度である。リサーチアシスタント、学会旅費、留学支援、これらのサポートは日本の大学内でもトップクラスで、他大学の方からうらやましく思われることが頻繁にある。肝心の研究では、コンパクトなキャンパスの利点を生かし、学科内はもちろん、他学科との協力体制を築いている。大学院では副専攻という制度もあり、学科の垣根を越えた横断的な学習を行っており、私はこの中央大学のサポートや利点を大いに活用してきた。今回は新設された短期留学支援制度を利用して、2011年8月11日から三カ月間、ペンシルベニア大学に留学させていただいた。
留学を希望するに至った経緯は主に二つある。一つは、自分の研究の発展である。二つ目は、世界で活躍出来る研究者になりたいということである。これまでに、国際学会での発表を何回か行ってきたが、国際社会での議論の質の向上、世界をリードするためには、日常からの訓練が必要であると痛感していた。そんな時に留学支援制度が新設され、即座に申請を行った。

ペンシルバニア大学の留学生仲間と
研究室では、研究に関すること以外にも一般的な科学の疑問点や政治、文化に関することなど、さまざまな議論が日常的に行われており、個人の意見を求められた。基本的に、学生はさまざまなことに興味、関心を持っている。また、研究で分からないことは分かる人に聞く。研究室間、学内、更に大学間に垣根はほとんどないように感じた。実際、私もジョンズ・ホプキンス大学の先生とスカイプで研究討論を行ったりした。このような環境に身を置くと、研究者ネットワークが瞬時に広がり、お互いの研究が進展していく過程を実感出来る。
ペンシルベニア大学は日本人のノーベル賞受賞者である白川英樹博士、根岸英一博士が在籍して研究を行っていた機関であり、化学科には大きな写真が掲げられている。その割には、日本人の学生を見掛ける機会は一度しかなく、ほかのアジア圏に比べると圧倒的に留学をする人数が少ない。中央大学の学生も留学するチャンスをつかみ、もっと海外進出して多くの糧を得てきてほしいと思う。
帰国後、留学の経験は研究に関することだけではなく、さまざまな機会をもたらした。中でも、留学経験が評価され、4th HOPE meeting という国際会議に採択していただいた。この会議は主にアジア・太平洋地域から選抜された化学系の大学院生を対象としており、私も運良く日本の代表の一人として参加することが出来た。この会議では研究発表のほか、ノーベル賞受賞者八人が参加し対談する機会があり、また、各国の大学院生とチームを組み、課題に対する議論を重ね、成果を発表する機会がある。このような機会に留学経験を生かすことが出来、同世代の研究者ネットワークが広がり、大変貴重な体験をすることが出来た。
以上の経験から、留学は失うものがなく、得られるものばかりであったと断言する。今後も、積極的に後楽園キャンパスから世界へ飛び出す学生が増えることを心から願う。最後に、理工学研究科の支援制度に深く感謝申し上げる。
