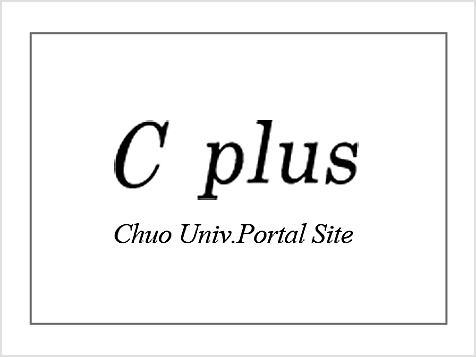学部・大学院・専門職大学院
研究と教育の日々
Das europäische Gespräch der Kunst/Hans Joachim Dethlefs
(日本語訳はこちら)
Seit mehr als zwei Jahrzehnten beschäftige ich mich mit der frühneuzeitlichen Kunsttheorie in der Periode zwischen L. B. Alberti (1404-1472) und Goethe (1749-1832). In den letzten Jahren hat sich mein Interesse zunehmend Fragen der Kunstterminologie zugewandt, und zwar besonders der Evolution der nordeuropäischen Kunstsprache im Anschluss an die italienische Kunstliteratur. Insbesondere ein deutsch-holländischer Terminus der Rembrandt-Zeit, nämlich Houding/Haltung, beschäftigt mich seit längeren. Der größte Teil meines Buchs "Der Wohlstand der Kunst" ist ihm gewidmet. Um ‚Haltung' ging es auch in der Fachtagung des Exzellenzclusters ‚Languages of Emotion' des Philosophischen Instituts der Freien Universität Berlin, das in dem September 2015 stattfand. Im Frühjahr 2017 ist ein Sammelband zu dieser Veranstaltung unter dem Titel "Was ist Haltung?" erschienen. Dieselbe Arbeitsgruppe, der ich angehöre, hat sich zu einer Tagung im Februar 2017 im Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Paris getroffen. Das Thema unserer "journée d'études" hieß "Le Liber de bona fortuna dans la culture textuelle latine (13e-18e siècles)". Es ging in einem fächerübergreifenden Ansatz um spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Fortuna-Vorstellungen, in denen der Begriff des ‚Impetus' eine Rolle spielte. Mein Betrag behandelte das Buch De Fortuna (1512) des neapolitanischen Humanisten Giovanni Pontano und seine Einflüsse auf die italienische Kunsttheorie des 16. Jahrhunderts. Die Publikation der Beiträge in Buchform ist in Vorbereitung.
Seit 2013 stehe ich in ständigem Kontakt mit dem Team von Michele-Caroline Heck, Université de Montpellier, die ein großes, vom European Research Council finanziertes Projekt "LexArt" leitet. Dieses Projekt will eine Kartographie der Kunstterminologie in Europa nördlich der Alpen von 1600 bis 1750 erstellen und hat viele Mitarbeiter. Im Juni 2012 fand in Montpellier der erste Teil eines einwöchigen internationalen Symposiums unter dem Titel "Words for theory, words for practice" statt, der zweite Teil folgte im Januar 2017 in Paris. Mein Beitrag behandelte Leonardo da Vincis Reflexionen zur Figur-Grund-Relation in der Rezeption von J. G. Sulzer (1771). Die Tagungsbeiträge werden im Herbst 2017 in Buchform erscheinen. Unter der Direktion von M. C. Heck wird zur Zeit die Arbeit an einer Enzyklopädie der zentralen nordeuropäischen Kunsttermini für die Periode 1600-1750 koordiniert, die schon im Sommer 2018 gedruckt erscheinen soll. Ich werde ca. 10 Lemmata beitragen, darunter Artiste, Caprice, Champ, Groupe, Houding, Haltung, Harmonie, réveillon, Wohlstand.
Im akademischen Jahr 2016-2017 gestattete mir die Philosophische Fakultät der Chuo großzügigerweise ein freies Forschungsjahr in Europa. So hatte ich Gelegenheit, kurzfristige Einladungen anzunehmen und mit einer Reihe von bekannten Forschern in Kontakt zu treten. Im Februar erhielt ich eine Einladung zur Teilnahme am Current Research Program des Zentralinstitut für Kunstgeschichte der Universität München, das in Form von Lektüre-Seminaren unpublizierte Forschungsergebnisse zur öffentlichen Diskussion stellt. Mein Thema lautete: "Der Capriccio-Streit: Positionen einer ästhetischen Debatte im Zeitalter Vasaris".
Das 16. Jahrhundert, also die Periode der italienischen und deutschen Renaissance, wird auch im kommenden Jahr der Schwerpunkt meines Interesses bleiben. Im Frühjahr 2018 bin ich zur Teilnahme an der seit 2013 bestehenden Forschungsgruppe ‚Pouvoirs de l'imagination. Approches historiques' der École des hautes études en sciences sociales (EHESS) in Paris eingeladen worden, die von Elizabeth Claire (CNRS) und Béatrice Delaurenti (EHESS) geleitet wird. Ich werde über Magie und Faszination in dem lateinischen Plinius-Kommentar von W. H. Rivius (1548) sprechen. Außerdem plane ich, diesen bisher unbekannten Text des deutschen Vitruvius-Übersetzers zu edieren, einzuleiten und zu kommentieren.
(Juni 2017)
------------------------
ヨーロッパの美術対話/ハンス・ヨアヒム・デートレフス
私は20年以上、レオン・バッティスタ・アルベルティ(1404-1472)からゲーテ(1749-1832)にまたがる時代の、近世美術理論を研究しています。近年は美術用語の諸問題、とりわけイタリアの美術書に依拠した北ヨーロッパの美術用語の発達に、ますます関心を持つようになりました。なかでも、レンブラント時代のオランダ語・ドイツ語の専門用語である「Houding/Haltung」(訳注1参照)については、長い間研究してきました。私の著書『芸術の適切さ(Der Wohlstand der Kunst)』(訳注2参照)の大部分は、この用語について論じています。「Haltung」は、ベルリン自由大学哲学専攻のエクセレンス・クラスター「感情の言語」が、2015年9月に開催した学術会議のテーマでもありました。2017年の春には、この会議の論集『Haltungとは何か』が刊行されました。この会議を企画準備した、私が所属するワーキング・グループのメンバーは、2017年2月にパリのフランス国立科学研究センター(CNRS)で開かれた会議に集いました。私たちの会議のテーマは、「ラテン語テクスト文化における『幸運についての書』(13-18世紀)」で、「Impetus(激しさ、勢い、衝撃)」の概念が重要な役割を果たした中世と近世の「フォルトゥナ」の観念について、学問分野を横断しての研究発表が行われました。私はナポリの人文主義者ジョヴァンニ・ポンターノの著書『フォルトゥナについて』(1512)と、それが16世紀のイタリアの美術論に与えた影響について発表しました。論集が出版準備中です。
2013年以来、私は、欧州研究会議の助成を受けた「LexArt」という大プロジェクトを率いる、モンペリエ大学のミシェル=カロリーヌ・ヘック氏の研究チームと絶えず連絡を取っています。このプロジェクトは、1600年から1750年までのアルプス以北のヨーロッパにおける美術用語の地図を作成することを目指し、多くの研究員を抱えています。2012年6月にはモンペリエで、1週間にわたるシンポジウム「理論のための言葉、実践のための言葉」第1部が開催されました。第2部は2017年1月にパリで開かれました。私は、ヨハン・ゲオルク・ズルツァーの受容(1771)における、図と地の関係についてのレオナルド・ダ・ヴィンチの考察について発表しました。同シンポジウムでの研究発表は、2017年秋に論集として出版される予定です。目下、ヘック氏の指揮のもと、1600年から1750年までの北ヨーロッパにおける中心的な美術用語の事典の編集作業が、2018年夏の刊行に向けて進められています。私は「Artiste」「Caprice」「Champ」「Groupe」「Houding」「Haltung」「Harmonie」「réveillon」「Wohlstand」など、約10項目を執筆します。
中央大学文学部のおかげで、2016年度はヨーロッパで1年間の研究生活を送ることができました。それによって、学術会議への急な招待に応じ、数々の著名な研究者たちと知り合う機会を得ました。今年2月には、ミュンヘン大学中央美術史研究所のカレント・リサーチ・プログラムへの参加招待を受けました。このプログラムでは、講読セミナー形式で、まだ出版されていない研究成果についての公開討論が行われます。私のテーマは「カプリッチョ論争:ヴァザーリの時代における美学討論の諸立場」でした。
16世紀、つまりイタリアとドイツのルネサンスの時代は、来年も私の関心の中心でありつづけるでしょう。2018年春には、エリザベト・クレール氏(CNRS)とベアトリス・ドゥロロンティ氏(EHESS)の指揮のもとに2013年から続いている、パリの社会科学高等研究院(EHESS)の研究グループ「想像の力:歴史的アプローチ」への参加招待を受けています。私は、ヴァルター・ヘルマン・リヴィウスのプリニウス注釈(1548)における魔術と魅惑について発表する予定です。加えて、ウィトルウィウスをドイツ語に翻訳したリヴィウスの、これまで知られていなかったこのテクストを編集し、序と注釈をつけることを計画しています。
訳注1:一般的には「姿勢、態度、振舞い」を意味する「Houding/Haltung」は、色彩論の用語としては、奥行きのある空間における前から後ろへの物体の配置を指し、色彩を見る際の連続性に関連して、知覚理論上の意味も持つ。
訳注2:美術用語としての「Wohlstand」は、アルブレヒト・デューラー(1471-1528)が、事物の非の打ちどころがない外観を指す言葉として使い始めた。16世紀には、「aptum(適切さ、礼儀作法にかなっていること)」「decorum(適切さ、礼儀作法にかなっていること)」「concinnitas(調和、均整)」の訳語として用いられた。
(2017年6月)
クリスティーネ・ナーゲルさんをゼミに迎えて/羽根礼華
中央大学に着任した今学期、初めてゲストをゼミに迎えた。ベルリン在住の作家・映画監督クリスティーネ・ナーゲルさんである。ナーゲルさんが脚本を執筆し、監督を務められた『私が住む場所 イルゼ・アイヒンガーのための映画』(2014)が日本で公開されることになり、上映会に合わせて初来日されていた。アイヒンガーは1921年生まれのオーストリアの作家。ナチス支配下のヴィーンで青年期を過ごし、ナチスの迫害によりユダヤ系の母方の親族を失った。戦後、その経験を反映した長編小説『より大きな希望』(1948)を発表し、名を知られるようになる。暴力的過去に取り組む戦後ドイツ文学を扱うゼミにナーゲルさんをお招きすれば、議論を深めることができるに違いない。そう考えてお願いしたところ、快諾してくださり、学生たちと共にゲーテ・インスティテュートでの上映会を訪れた後日、ゼミでお話しいただくことになった。
アイヒンガーの作品、特に伝統的な語りの作法から離れていく1950年代以降の作品は、必ずしも取っ付きやすいものではない。不意の展開を見せる物語、なじみのないモチーフ、思いもよらぬつながり方をする言葉、切り詰められた文。初めて読んだ時には、私はドイツ語ができなくなってしまったのではないかと焦った。その難解な筆致が、「言葉は、それがそこにあるときには、アンガージュマンそのものです。言葉がアンガージュマンを描写する必要はないのです」と言うアイヒンガーのアンガージュマンの形であり、歴史上の暴力とそれをめぐる議論への応答であることを徐々に理解するようになったのは、研究を通して作品に深入りしだしてからである。
ナーゲルさんの映画のタイトル『私が住む場所』は、1955年に発表されたアイヒンガーの同題の短編小説に由来する。この小説を下敷きにした映像を核に、アイヒンガーの生と作品にとって重要な場所の映像、アイヒンガーの声と言葉、アイヒンガー自身が撮影した8ミリ映画からの抜粋などが複雑かつ精緻に組み合わされた映画は、ナーゲルさんが長年に渡ってアイヒンガーの作品、及び作家自身と対話を重ねた末に完成した。ゼミでの講演では、その過程を振り返りつつ、アイヒンガーについて、またご自身の映画についてお話しくださった。離別の経験から生まれた、瞬間に対する覚醒した意識が、アイヒンガーの作品を特徴づけていること。作品に書き込まれた場所が、歴史において、またアイヒンガーの人生において持つ意味。それらの場所や、アイヒンガーの文学のモチーフを、どのような仕方で映画に取り入れたか。そういったことについて、アイヒンガーの言葉を引きつつ、ヴィーンの地図を示しつつ語り、アイヒンガーの世界への道案内をしてくださった。学生たちからは、それまでの授業で扱ったアイヒンガーの詩と小説、講演に引用されたアイヒンガーの言葉、ナーゲルさんの映画の細部などについて、意見や質問が発せられた。それぞれの仕方で映画と講演を咀嚼したことがうかがえる内容だった。活気を帯びた遣り取りが続き、気がつけば予定の時間を過ぎていた。
人前で話す機会には事欠かないナーゲルさんだが、ゼミという場での学生との対話は初めてだったそうである。実は少し緊張していた、でも素晴らしい時間だったと、授業後にやや上気した顔で伝えてくださった。学生たちからの質問の全てを丁寧に書きとめ、時間をおいて改めて考えてみるつもりだと、ドイツに持ち帰られた。今回は短い滞在だったが、新たなプロジェクトとの関わりでぜひ再来日したいとのこと。次回はどのような出会いがあるか、楽しみである。
翻訳で読むことができるイルゼ・アイヒンガーの作品:
『より大きな希望』(矢島昂訳、月刊ペン社、1981年)
『縛られた男』(眞道杉/田中まり訳、同学社、2001年)*「私が住む場所」所収。
(2015年9月)
『ドイツと日本を結ぶもの―日独修好150年の歴史―』展へのエクスカーション/川喜田敦子
前期のテストも無事に終わり、夏休みに入った8月4日、独文基礎演習(1年生)のクラスの有志と千葉県佐倉市にある国立歴史民俗博物館に行ってきました。国立歴史民俗博物館では、今夏、『ドイツと日本を結ぶもの―日独修好150年の歴史―』という企画展示があり、それを見学するエクスカーションです。
展示は、Ⅰプロイセンおよびドイツ帝国と幕末維新期の日本、Ⅱ明治日本とドイツ、Ⅲ両大戦下の日独関係、Ⅳ戦後の日本とドイツ、Ⅴエピローグの全5部からなります。オイレンブルク使節団の訪日と日孛(日普)修好通商条約の締結にはじまり、紆余曲折をへて今日にいたるまでの150年にわたる日独関係を、文書史料、図像資料、映像資料をとりまぜて見せる充実した歴史展示でした。
参加した学生の声を聞いてみましょう。
- 私が一番興味をもった展示は、幕末期の日本とプロイセン、ドイツ帝国のものです。日本とドイツの外交関係がはじまった最初の時期である幕末は、日本史で一番好きな時期でもあるので、ドイツを中心とした幕末の歴史史料をたくさん見られたのは、とても興奮しました!!外交慣れしていない当時の江戸幕府が、外国との交渉や条約締結に苦戦する様子が、展示資料の手紙、プロイセン王国の書簡からよく読みとれます。(安川優華)
- 私は世界史が大好きなので、展示前半の歴史史料がとても興味深かったです。シーボルトの娘であるウメの顔写真が見られなかったのが残念でした。(海野遥)
- 特に印象に残っているのは、ドイツ人が描いた日本の絵の展示で、他の絵は写実的なのに、富士山の絵【注:Wilhelm Heineの作品でミュンヒェン五大陸博物館蔵の「富士山」】だけは妙に急勾配に描かれていて、ドイツ人でも富士山には何らかのイメージを抱き、描こうとしたのかなと思いました。(中山清楓)
- 私が驚いたのは、日本からドイツへ留学に行った人が何を学ぶことを目的として渡航したのかということです。日本はドイツの憲法から大きな影響を受けているため法学を学びに行く人が最も多いのかと思いきや、多い方から医学・哲学・法学という結果で、面白いなと思いました。(山本裕子)
初期の日独関係が大人気だったようですが、私もこの時期の展示は質量ともに大変充実していると感じました。この時期の日独関係に関心をもった方には、福岡万里子『プロイセン東アジア遠征と幕末外交』(東京大学出版会2013)がお勧めです。工藤章・田嶋信雄(編)『日独関係史一八九〇-一九四五』(全三巻)(東京大学出版会2008)はもちろん定番の文献です。この時期に限らず、1945年までの日独関係史に関する大事な論考がたくさん収録されています。
展示では、戦間期の日独関係にもかなりのスペースがさかれていました。
- 第一次世界大戦と三国干渉で日独の関係が悪化した頃の時期について、ドイツ人戦争捕虜と捕虜収容所の地元の人々の交流の資料がたくさんあり、ひとつひとつ興味深く、楽しく観賞しました。ワイマール期にゾルフ【東京駐在ドイツ大使を務めたWilhelm Solf(1920-28年在任)】が民間の文化交流に尽力し、第一次世界大戦によって冷え込んだ日独関係によい影響を及ぼしたと知って、狭い意味の外交のみではなく、文化にも影響を与えたのはよいことだと思いました。(藤原汐里)
- 今回の展示で最も印象に残った点は両大戦下の日独関係です。特に第一次世界大戦でドイツに宣戦布告し、攻撃したにもかかわらず、日本側はドイツ人捕虜に対しては寛大であったと知り、改めて日独関係の深さを感じることができました。(バッドクリストファー大樹)
展示会場では、2015年度前期に本学でも上映会が開かれたブリギッテ・クラウゼ監督の映画「敵が友になるとき 徳島・板東収容所のドイツ人捕虜」の映像が流れていました。映像といえば、ナチ・ドイツの青少年組織ヒトラーユーゲントの来日時の映像も印象的でした。
- 最近、ヒトラーやアデナウアー【西ドイツの初代首相Konrad Adenauer(1949-63年在任)】について授業で学んだところだったので、彼らのことも展示で見ることができてよかったです。(久保萌笑)
第二次世界大戦期までの日独関係史と比べると、戦後日独関係史の研究はまだ緒に就いたばかりですが、2014年には工藤章・田嶋信雄(編)『戦後日独関係史』(東京大学出版会)が刊行されました。これを読むと、戦後の日独関係史のなかで今回の展示では取り上げられていない側面についても知ることができ、視野がぐっと広がることでしょう。
展示を見た後は、館内のレストランで一緒に昼食をとりながら、展示の印象を交換したり、この機会に1年生の前期を終えた感想を聞いたり、夏休み中のドイツ語学習についてアドヴァイスをしたり…。ひとしきり話をして帰ってきました。佐倉という遠方まではるばる出かけてきたせいか、はたまた夏休みに入ったからか、教員と学生の距離感もいつもよりさらに近づいて、楽しいエクスカーションになりました。
※展示会のカタログがドイツ語文学文化専攻研究室にあります。ご関心のある方はぜひご覧になってください。
(2015年8月)
読んだ本はとっておこう/縄田雄二
さきごろ、私の大学院の授業を受けてくれている学生たちと、雅楽の公演にでかけた。芝居か何かに行こう、といくつかの候補を私が挙げたなかから、珍しいものを、と学生が選んだのである。
昼食をともにしたそば屋で、雅楽についての講釈を私は始めた。午後には東京楽所という楽団が源氏物語にちなんだ曲を演奏するはずであった。私は源氏物語の該当箇所や、東アジアの音楽理論の原典とも称すべき『礼記』楽記篇の冒頭を解説した。
源氏物語は、自分が大学院に通っていたころ、はなからしまいまで一文一文読み進めた新潮日本古典集成本。いよいよ大尾が近づくにつれ緊張し、読みなづんだのを想いだす。礼記は、ベルリン・フンボルト大学での研鑽を終え、中央大学に着任した年に読み上げた明治書院新釈漢文大系本。定職を得てゆとりができ、この儒学の経典の原文に読みふけることができた夏休み、私はしあわせであった。
これらの本は、書架の貴賓席の一角を占めている。手に取り、開くだけで、当時の生活が眼前によみがえり、私は眩惑される。書籍はタイムカプセルなのだ。
むかし読んだ本について、いま青年と語ることにより、むかしを私の前に現出させた本は、いまと未来に繰り込まれ、私を混乱させた。青海波の管弦を、喜春楽の舞いを、学生と堪能した日曜日、その混乱のために私の心はたかぶった。
大切に読んだ本はとっておくべし。せまい部屋に本が収まりきらず、古本屋に幾度かまとめて売り払ったのは間違いであった。たとえば高校時代に読んだゲーテ。私を幸福感で満たした新潮文庫の『ヘルマンとドロテーア』を私は手放してしまった。一気に読み終え茫然とした岩波文庫の『ファウスト』も。これらの本は私の進路を決める力さえ持ったのに。大学に入ってからもそうだ。レクラム文庫の“Die Entführung aus dem Serail”やKlopstock: “Der Tod Adams”でドイツ語原書を読み通す喜びをおぼえたのではなかったか。取る幅はいくらも無いのだから、本棚の片隅に置いておけばよかったのに。鉛筆で真っ黒にした洋書を引き取る古本屋は無い。処分したのだろう。何たるあやまちか。しかし卒業論文で取り組んだニーチェのdtv版全集はとってある。最初の著書『悲劇の誕生』。代表作『ツァラトゥストラかく語りき』。晩期の諸篇。みな書き込みだらけである。これらは私の宝というよりも、私の一部だ。ゆめ捨てるまい。
今年度の講義を締めくくるに当たって私は学生たちにお願いした。この授業では十冊ほどの文庫本を取り上げ、すべて読むことを義務づけたが、この講義で読んだ、と、できれば私の名とともに本に書き込んでいただきたい。これらの本は売ったり捨てたりしないでほしい。数年後、数十年後も読むに価する本を選んだ。将来読み返してほしい。そのときそこに皆さんが私の名を見、ああ、縄田の授業で読んだな、と憶いだしてくださるならば、それは教師としての私にとって大きな名誉である。お願い致したい、と。
読み返してくれたころ、邂逅し、それらの本について語り合えたならば、いかに嬉しかろうか。私はまた混乱するであろう。それはすばらしい混乱に違いない。2014年、学期も大詰めの一月末にしるす。
(2014年1月)
Kunst und Kunsterfahrung in der frühen Neuzeit/Hans Joachim Dethlefs
○Vita
Hans Joachim Dethlefs wurde nach Studienaufenthalten in Florenz und Paris an der Philipps-Universität Marburg zum Dr. phil. promoviert. Es folgte zehn Jahre Lehrtätigkeit in Genua, Italien, zunächst als DAAD-Lektor, dann als Assistent am Germanistischen Institut der Università degli Studi. Ab 1989 erfolgte die Ernennung zum Associate Professor an der Hitotsubashi University, Tokio, und später die Berufung an die Chuo University, ab 1999 als ordentlicher Professor.
○Forschungsschwerpunkte
Kunsttheorie und Kunstterminlogie der klassischen Bildtradition zwischen L.B. Alberti und der Goethezeit. Besonderes Interesse für den frühneuzeitlichen kulturellen Transfer zwischen Italien und Deutschland.
○Aktuelles Forschungsvorhaben
Leonardo- und Vasari-Studien, Studien zur Farbentheorie um 1800, Kooperation am Projekt: Word for art. The rise of a terminology in Europe (1600-1750) unter der Direktion von Michèle-Caroline Heck, Université Montpellier.
○Publikationen
Zahlreiche kunsttheoretische und kunstterminologische Publikation, Beiträger in Zeitschriften wie Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Germanisch-Romanische Monatsschrift, Oud Holland , Das Achtzehnte Jahrhundert u.a. Zuletzt die Buchpublikation: Der Wohlstand der Kunst Ökonomische, sozialethische und eudämonistische Sinnperspektiven im frühneuzeitlichen Umgang mit dem Schönen, Tokio 2010.
(Dez. 2013)
------------------------
近世における美術/ハンス・ヨアヒム・デートレフス
○経歴
フィレンツェならびにパリで学んだ後、マールブルク大学にて博士号を取得。ジェノヴァ大学(イタリア)にてDAAD講師、独文学科助手として10年間勤務。1989年に一橋大学助教授に就任し、1999年より中央大学教授。
○重点研究テーマ
L・B・アルベルティからゲーテにいたるまでの時代の古典主義美術を対象とする美術理論ならびに美術概念。主たる関心領域はとくに近世イタリアとドイツのあいだで生じた文化的影響関係。
○現在の研究
レオナルド・ダ・ヴィンチならびにジョルジョ・ヴァザーリ研究
1800年頃の色彩論をめぐる研究
ミシェル・カロリーネ・ヘック教授(モンペリエ大学)を研究代表者とするプロジェクト "Word for art. The rise of a terminology in Europe (1600-1750)" に協力。
○出版物
美術理論ならびに美術概念について研究成果を数多く公表してきた。Journal of the Warburg and Courtauld Institutes、Germanisch-Romanische Monatsschrift、Oud Holland、Das Achtzehnte Jahrhundertなどの学術雑誌に論文が掲載されている。著書にDer Wohlstand der Kunst Ökonomische, sozialethische und eudämonistische Sinnperspektiven im frühneuzeitlichen Umgang mit dem Schönen(中央大学出版部2010)がある。
(2013年12月)
卒業論文提出・審査の時期に思うこと/林明子
今年度も卒業論文提出そして審査の時期を迎えました。毎年、12月中頃に提出期日が設けられていますが、出来ばえはどうあれ、とにかく提出にこぎ着けた4年生は、提出前とは打って変わって明るい表情です。提出を受けた教員は、年末年始から査読にとりかかり、1月下旬の口頭試験までに、主査の論文、副査の論文を読み上げなければなりません。
常々、思うことですが、卒業論文の執筆と教育実習ほど、学生が目に見える大きな成長を遂げる活動はありません。日ごとに伸びる豆の木の蔓を観察しているような気持ちになります。特に卒業論文は、学生たちが初めて臨む創造的な活動です。これまで身につけて来た知識や教養を最大限活用して、最初から最後まで自分で論を組み立てていかなければなりません。論文は実に忠実で、決して自分を裏切りません。つまり、投資した分だけ見返りはあるけれど、手を抜けば抜いただけ正直に形になるということです。論文の構想から提出、そして口頭試験まで約1年間をかけて準備するわけですが、若い学生たちにとって、それまでの人生でおそらく一二を争う密度の濃い期間であると思います。くじけそうになったり、絶望的な気持ちになったりもするでしょう。私のゼミでは、先行研究のリサーチと言語データの収集をひとまず終え、分析をしている時期を「クリエイティブ・カオス」と呼んでいます。指導教員からみれば、学生たちは面白い結果が見え隠れするエキサイティングな作業に従事しているのですが、当の本人たちは、急に語り出したデータの整理にあっぷあっぷで、深い森に迷い込んだ気分になるようです。森の番人の助言を受けながら最後まで自分の足で歩き通して、明るい太陽の下に出た瞬間、数ヶ月前には見ることのできなかった情景が広がります。言語分析を通して見えて来た新しい世界です。
卒業論文提出時は、当然その時点で最高のものに仕上げている訳ですが、同時に、ひとまず結論に達したことで見えて来る次の課題もあります。口頭試験に向けて、あるいは長い目で見た自分の将来の課題として、自分自身に新しい問題を提起することになります。論文執筆中の中間発表に並んで、口頭試験も自分を育てる大切な機会です。専門的な内容を論理的に説明し、他人に理解してもらわなければなりません。また質問を受けて修正することも学びます。社会に出る前に受ける教育の総仕上げとも言えます。
学生たちには、「卒論提出までは全面的にバックアップするけれど、論文審査に入った瞬間から敵味方ですからね。」と言って、口頭試験の準備を十分整えるよう伝えます。しかし、実際は、査読も口頭試験も、それまで指導にあたって来た教員自身に対する評価が下される時でもあるのです。前述のように、完成した卒業論文は学生たちが初めて自分の足で歩き、長い旅路の末に到達したゴールです。それぞれが自分自身のテーマ設定の下、たった一人で歩き通しました。その間、陰に隠れて、しかし影のように寄り添いながら、実は教員も一緒に歩いています。遥か彼方の北極星のように旅人に現在地を知らせたり、お遍路さんをもてなす茶屋のように、しばし休憩の場を提供したりもします。個々の学生たちが持っている潜在的な能力を、どのくらい見つけ出し、伸ばすことができたか、教員の力量が試されます。
きつい口調で厳しいことを言っているふだんの授業からは想像できないかもしれませんが、そんなことを考えながら卒論指導にあたっています。
(2013年12月)
Görlizを訪れて/川喜田敦子
9月初旬にドイツとポーランドの国境の町Görlizに行ってきました。オーダー=ナイセ川のほとりに位置するこの町は、第二次世界大戦までは川の両岸がひとつの町を形成していたのですが、ポツダム協定でオーダー=ナイセ川がドイツ=ポーランド間の暫定国境とされたため、西岸Görlizと東岸Zgorzelecに分かれ、Görlizは東ドイツ、Zgorzelecはポーランド統治下に入りました。オーダー=ナイセ川が国境になるということは、ドイツは大戦前の領土の五分の一を失うということでした。東ドイツは建国後まもなく新国境を認める条約にこのGörliz/Zgorzelecの町で調印しましたが、西ドイツは―実際には国境を接していなかったにもかかわらず―新国境を認めず、東西ドイツ統一後にポーランドとのあいだで国境条約が結ばれるまで、領土問題は西ドイツとポーランドのあいだの深刻な懸案でした。しかし、国境問題が解決し、ポーランドがEUに加盟した今では、オーダー=ナイセ川にかかる橋も自由に行き来ができます。検問のない国境というのは―しかもそれが領土問題の焦眉の地であったことが知られているだけに―あっけなさに気が抜けるような、それでも独特の感慨をどこかで呼び起こすような、何とも言えない場所です。
今回の調査の目的は、西岸Görlizでこの地域の歴史を展示するシュレージエン博物館でした。私たちは日本の歴史を自国史と考え、外国の歴史をよその国の歴史と考えます。自国史と他国史という感覚は、ドイツやポーランドにも同じようにあります。そこでは、ドイツの町、人物、事件はドイツの文化と歴史の発展のなかに、ポーランドのそれはポーランドの文化と歴史の発展のなかに位置づけて語られます。それぞれの自国史のなかで語られると、同じできごとについて全く違ったとらえかたがされることもあります。たとえば、同じひとつの戦争を、片方は侵略した側、片方は侵略された側としての立場から語ることになります。ナチ・ドイツのポーランド侵略はまさにその例です。逆に、どちらの国とも関係のある同じひとりの知識人の功績を自国の功績に数えようとして二つの国が取り合うこともあります。有名な例としてはコペルニクスの存在があります。
領土問題のある国境地域では、その地域がいかに自国と歴史的につながりが深いかを示す史実を両側が必死に探すことになります。それが高じると、同じひとつの地域の歴史が、国境の両側で全く違った語られ方をすることになります。そうなったら、Görlizのように帰属が変わった町、それによって二つに分かたれてしまった町の歴史はいったいどのようになってしまうのでしょうか。自国史=他国史という枠組みに固執し、自分たちの国の歴史を自分たちの理屈だけで語るという歴史記述には限界があることを、国境地域の歴史は如実に示しています。シュレージエン博物館の展示は、そうした自国史=他国史の枠組みの限界を意識的に乗り越えようとするものです。この地域は、ドイツでもポーランドでもなく、しかしドイツでもポーランドでもあり、両者を含む様ざまな地域からの様ざまな時代における影響が交錯し、新たな文化が生まれる地として描かれます。国境のなくなった今日のヨーロッパの新しい歴史認識の萌芽を見るようで大変面白い経験になりました。
(2013年9月)