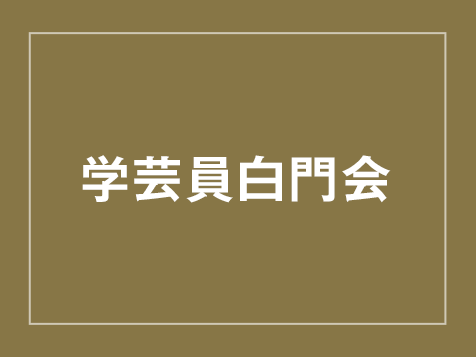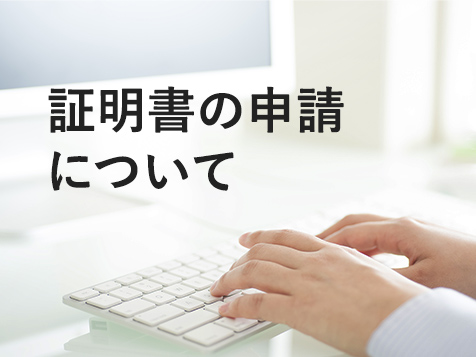文学部
文学部長挨拶

緑川 晶 中央大学文学部長
多様性を高める場としての文学部
中央大学文学部は第二次世界対戦終結から間もない1951年に開設され、今年で72年目を迎えます。法律や政治、ビジネス、産業界などから距離を置いて、人を知る/人について考える学部を設置することが叶ったのも、平和な時代が訪れたからかもしれません。70年以上にわたって文学部が歩んできた歴史は、日本が平和であり続けることができた証です。文学部の卒業生や中退された方の中には、新聞の連載マンガや世界の人々を魅了した映画、毎日どこかで目にする歌手グループなどに関わった方々がいて、現代日本文化の一躍を担われています。このような多彩な人材をはぐくむ場が文学部であり、また、それが許される世の中であり続けることを願っています。
文学部は表向きは1学科ですが、その中には13の専攻と1つのプログラム、そして700を超える科目を擁する実に多彩でカオスな学部です。学部の名称こそ「文学」と冠されていますが、学部内には文学に留まらず、歴史学や社会学、哲学や教育学、心理学と専門分野は多岐にわたっていますし、共通科目には宗教から宇宙まで揃っていて、きっと自分の興味を見つけ出すことができると思います。
文学部という名前は、流行の名前とはほど遠く、古くさいと思われる方もいるかもしれません。しかしその内実は、時代の最先端をいく分野、論理的思考力を鍛える分野、いにしえや世界各地の人々について知り今を顧みることができる分野など、いつの時代にも対応可能であり、けっして陳腐化することがない学部が文学部です。
生きものの生存戦略の一つに生物の"多様性"が指摘されています。多様性や複雑性があることで、環境変化に対しても生き残ることができるという考え方です。それまで無駄と思われていたものが環境や時代が変わることで有益になったりします。まさに多彩な文学部は多様性を地で行く学部と言えます。先の見通せない現代社会においては、このような場で考え経験したことが多様性を高め、人生を豊かにしてくれることと思います。
文学部長 緑川 晶