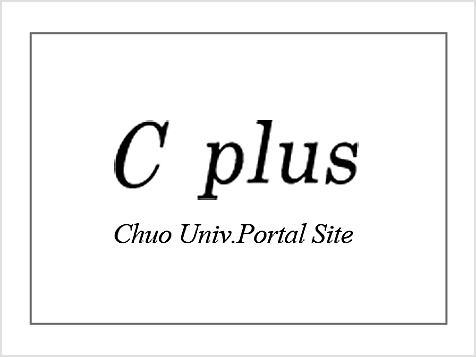学部・大学院・専門職大学院
ドイツにおけるプロテスタンティズム音楽とその周辺の調査
文学部人文社会学科 ドイツ語文学文化 2年
阿部 広果
私は2014年9月6日から15日まで、ドイツのライプチヒ、アイゼナハ、ベルリン、ポツダム、ハンブルクを訪れ、プロテスタンティズム音楽の調査を行った。私は長年クラシック音楽が好きで、自分の専攻でドイツの文化史を学んでいる際に、音楽と文化史の繋がりに興味を持ったことがきっかけとなった。特に日本ではあまり触れることのできない、教会音楽を肌で感じたいと思ったし、音楽の原点とも言われる教会音楽について調査をすることで、私を魅了するこれらの音楽の本質に迫りたいという思いにより、今回の調査に至った。
調査方法としては、日本にて参考文献を熟読し疑問点を取り上げ、プロテスタンティズム音楽の構築に重要な人物や建築物にまつわる場所、博物館を訪れ、質問をするというものである。
ドイツのプロテスタンティズム音楽
初めに、ドイツのプロテスタンティズム音楽について述べる。1517年、マルティン・ルターが「九十五か条の意見書」を発表し、信仰のよりどころを聖書のみに求め、ローマ教皇の免罪符販売と教会の腐敗を批判したことから、宗教改革が行われた。これによって、教会はカトリック(旧教)とプロテスタント(新教)に二分された。プロテスタントは、礼拝にはより多くの人が参加することを望み、音楽もオルガンや聖歌隊のみではなく皆が声を合わせて歌うべきだとした。(これに対し、カトリックでは、オルガンや聖歌隊が目立って活躍した。)そしてプロテスタントの中でも更に、ルター派とカルヴァン派に分けられた。これらには音楽に関する相違点がある。ルターはあらゆる手段を用いて神を賛美すべきだと主張し、コラールを採用し、聖歌隊もオルガンも残した。一方、よりプロテスタントに厳格であったカルヴァンは、伴奏なしで斉唱をする詩篇歌を採用したために、こちらの党派では聖歌隊もオルガンも用いられなくなった。なお、今回私が焦点を置いたのは、ルター派のプロテスタンティズム音楽である。ちょうどこのころから、ルター派のバッハが教会音楽で活躍し、その土台を築いた。(金澤2007 p15-30参照)
ヨハン・セバスティアン・バッハ
ドイツプロテスタント音楽はバッハにより築かれた。彼が最も多くの教会音楽を残したライプチヒのトーマス教会、そして彼にまつわる資料を探すためにバッハミュージアム、アイゼナハのバッハハウス、ポツダムのサンスーシ宮殿を訪れた。
1)アイゼナハ
バッハは父のアンブロジウス、父の従兄のクリストフをはじめとする、音楽一家に生まれた。生誕の地は、アンブロジウスが音楽監督を務めた、アイゼナハである。アイゼナハはライプチヒからICE(特急電車)で約2時間のところにあり、バッハの生誕地のほか、ルターの活躍の地としても名高い、小さな町である。町の中心部のマルクト広場では、300年以上前に、ここで少年のバッハが遊んでいたのだろうか、と想像を膨らませながら歩いた。

写真:街の中心部、マルクト
バッハ一家は、パン焼き職人であったファイトを初めとし、一家のほぼ全員が聖歌隊や楽器職人を含む音楽家であった。ファイトの故郷ヴェヒマールを中心に、アイゼナハ、エアフルト、アルンシュタット、マイニンゲンの各地にバッハ一族が栄えていった。
父アンブロジウスは、アイゼナハの音楽監督であった。彼は熱心なキリスト教徒で、ルターを敬愛していた。ルターは、ヴァルトブルク城にて聖書のドイツ語訳をし、15歳から17歳には、この町の聖ゲオルク教会の付属学校に通っていたため、ルター派プロテスタント教徒にとって、この町は非常に重要な都市なのである。ヴァルトブルク城には、ルターの部屋が残されている。城の中心部から離れた、小さな部屋で、壁に向かっている木製の机と椅子からは、当時のルターの勤勉さと、長時間にわたる作業の厳しさが感じられた。

写真:ヴァルトブルク城と街並み

写真:ルターが聖書をドイツ語訳した部屋。
アンブロジウスは教会にて徒弟たちに聖歌を教えるという仕事をしており、またその教会の一つである、聖ゲオルク教会での礼拝では、兄のクリストフがオルガンを演奏した。こうしてバッハはこの町で、幼少期から自然と、プロテスタント音楽に触れていたのだ。七歳になると、ルターが通った学校と同じ、聖ゲオルク教会の付属学校に進学し、週末にはクレンデと呼ばれる小編成の合唱隊として、この町を歌い歩いたという。 10歳になると、父が他界したため、この町を去り、兄がオルガニストを務めていたオールスドルフへと移住することとなった。
短い期間ではあったが、バッハがプロテスタント音楽家となったのに、間違いなく大きな影響を与えたのは、このアイゼナハであろう。
・バッハハウス
アイゼナハには、バッハの博物館である、バッハハウスがあり、世界中から観光客が集まっている。

写真:バッハハウスの前にあるバッハ像
(バッハの死から100年後に、この町が、像を作ることを決めた。作成にはリストやクララ・シューマンらも協力した。彫刻家は、アイゼナハのルター像やドレスデンのフラウエン教会の製作者と同じである。当時からバッハが人々にどれだけ愛されていたのかがみてとれる。)
この家は、1674年にアンブロジウスが購入した家で、1905年に新バッハ協会が購入し、博物館として利用できるように整備したものである。アイゼナハは第二次世界大戦での被害を受けて大火事に見舞われたため、この家も焼失しかけたが、1946年に博物館として再び蘇らせるために改修工事をすることが決定された。なお、新バッハ協会購入当時はこの家でバッハが誕生したと思われていたが、実際に誕生したのはここから少し離れたところにあるため、生家自体は残っていない。

写真:バッハハウス 外観
この博物館は、二階建ての木造建築で、一階には古楽器のミニコンサートが開催されている、小さなホールがある。展示品は、バッハの生涯についての記事や楽譜、バッハファンが夢中な数学的視点から見たバッハの解説など、多岐にわたっている。館内にいるスタッフは、英語が流暢だったので、質問にも親切に答えてくれた。
・バッハ時代のチェンバーオルガン
バッハ時代の古楽器のミニコンサートでは、スタッフが説明しながら音色を聞かせてくれた。

写真:バッハ時代のチェンバーオルガン ミニコンサートにて

写真:チェンバーオルガンのふいご
ルター派の礼拝に、オルガンは必需品である。オルガンは紀元前3世紀にギリシア領アレクサンドリアで発明され、当初は「音の出る珍しい仕掛け」として、キリスト教の弾圧などの道具として使われていた。313年のミラノ勅令によりキリスト教が公認され、392年には国教として認められ、その後徐々にオルガンに対する反感も忘れ去られていった。教会の記録にオルガンが見られるようになったのは、9世紀以降のことであったが、礼拝としてではなく、鐘として使われていて、未だ道具として用いられていた。その後、修道院や教会学校での教育が盛んになるにつれ、聖歌隊の補助のために、ようやくオルガンを楽器として扱うようになった。楽器としてのオルガンは、大きく分けて、ポジティフとポルタティフという二つのタイプがある。ポジティフは、一段鍵盤でペダル付きで、主に普通の町や村の教会で使用された。ポルタティフはふいごがついており、このふいごは演奏者が右手で演奏しながら左手でふいごを引くタイプや、他の者がペダルを足で踏んでふいごを引くタイプがあり、大きな教会で使われた。
この写真は、他者がペダルを踏むタイプのポルタティフである。観客のうちの一人が、実際にペダルを踏む体験をしていたのだが、演奏中はずっとペダルを踏み続けなければならないため、体力が必要であると思われた。
展示コーナーでは、書籍を読んでいただけでは分からなかった、バッハのこの時期の私生活について質問することができた。
・幼少期の生活
バッハ一家の当時の生活は、貧しくはないが贅沢な生活を送れたわけでもなかった。教会で音楽の仕事をしながら、家庭で農業を営む、という二本の軸があった。というのも、poor taxを支払うという義務が課せられていたからだ。この税は、町の貧困層のために、一定以上の収入がある土地の保有者に課せられるものであった。この税のおかげで、音楽家としての仕事のみでは厳しく、農業も営んでいたということだ。
また、この時代のバッハの学生生活は、聖ゲオルク教会の付属学校にて、宗教、文法、算数の基本的な科目に加え、聖書の勉強が重点に置かれていた。時間は、午前が、6:00~9:00または7:00~10:00で、午後は13:00~15:00であった。また、choir of the Latin schoolのメンバーでもあったため、ラテン語の聖歌に幼少期から親しみがあったという。
父の死によって、バッハはアイゼナハをあとにし、兄のヨハン・クリストフがオルガにストとして活躍していたオールドルフへと移る。ここから、バッハはオルガンに興味を持ち始め、その才能を開花させていくこととなる。その後、ヴァイマール、アルンシュタット、ミュールハウゼン、ヴァイマール、ケーテンを経て、ライプチヒへと至る。
2)ライプチヒ

写真:ライプチヒ 聖トーマス教会前

写真:聖トーマス教会

写真:聖トーマス教会の床にあるバッハの墓
聖トーマス教会は、現在も礼拝堂として使用されており、礼拝の時間以外は、一般客向けに開放されていた。左の写真奥には、パイプオルガンがあるが、残念ながらこれはバッハ時代のものではない。教会内では人々が椅子に座り、ゆったりと物思いにふけっている姿が印象的だった。私もここに腰かけ、激務をこなしていたバッハの姿を思いうかべ、時間があっという間にたっていた。教会の一番前には、バッハの墓がある。遺骸は1894年にヨハネス教会の墓地から発見され、その後1900年からヨハネス教会にて埋葬されていた。第二次世界大戦によりヨハネス教会が破壊されたため、1949年にトーマス教会に移された。
・激務の時代
ライプチヒは、バッハが人生で最も多くの作品を残した地であり、バッハが人生の最期を迎えた地でもある。彼はライプチヒにて、トマス・カントルとライプチヒ市音楽監督を兼任した。一教会歴年中約59日の祝祭日に、市内の主要四教会にて教会音楽を提供し、聖トマス教会に付属する寄宿制のラテン語学校であるトマス学校の生徒を教育することが、彼の職務であった。(トマス学校は音楽専門の学校ではなく、ギムナジウムの前身のルター派プロテスタントのラテン語学校で、基礎科目のほかは、古典語と宗教教育、音楽が三位一体となるべきであるとしていたため、学業もぬかりなく指導する必要があった。)主要教会とは、聖トマス教会、聖ニコライ教会、聖マタイ教会、聖ペテロ教会の四つの教会である。これらの教会で行われる毎週日曜日と祝日の礼拝の奉仕のために、トマス学校の生徒の聖歌隊が各教会に派遣され、その歌声を披露していた。バッハは、これらの聖歌を毎週一曲のペースで作曲し、週末の礼拝のために聖歌隊を指導した。聖歌隊を四つの教会に割り振る作業もあり、演奏に人数が足りないこともしばしばあったため、その都度エキストラを調達することも仕事であった。
・「マタイ受難曲」
ライプチヒにおける激務の時代に、バッハの声楽曲の最高峰とされる「マタイ受難曲」がうまれた。受難曲とは、聖週間のミサにおいて、福音書に書かれた救世主キリストの受難の箇所を朗読するにあたって、それを劇的に行うことから発展したものである。17世紀にはいると、受難曲はルター派のドイツの教会のために作曲されることが多くなり、ルター派特有のコラールを挿入するようになった。 この曲は全二部から構成されていて、第一部ではイエスの捕縛までが歌われ、第二部では捕縛、ピラトによる裁判、十字架への磔、刑死後、墓の封印 が歌われるといった、イエスの受難の物語となっている。これらの歌詞は、聖書から引用されている。
当時は今日ほどの評価を得ていなかったが、この曲を復活させたのは、1989年にメンデルスゾーンが行った復活上演であった。この上演は成功をおさめ、これ以降、バッハのほかの多くの器楽曲もが注目されるきっかけとなった。
3)ポツダム
ライプチヒ時代に、フリードリヒ大王に謁見し、大きな評価を得たのが、ポツダムにあるサンスーシ宮殿である。
・「音楽の捧げ物」
マタイ受難曲と同様、音楽史上重要である、「音楽の捧げ物」も、この時代にうまれた。このきっかけとなったのが、1745年にポツダムのサンスーシ宮殿にてフリードリヒ大王を来訪したことである。フリードリヒ大王は父親の軍隊王と呼ばれたフリードリヒヴィルヘルムとは異なり、音楽や文学をこよなく愛した人物であった。長年、バッハの来訪を心待ちにしていたが、オーストリア継承戦争の勃発によりかなわず、ようやく機会を得たのである。バッハの死のわずか五年前のことだ。サンスーシ宮殿は、夏の避暑地として利用された宮殿であり、多くの来客が訪れた。大王はこの宮殿に滞在中は、毎晩19:00~21:00に演奏会を開き、自身もフルートを演奏した。

写真:サンスーシ宮殿 外観

写真:音楽の間…ピアノフォルテとフルート
バッハは部屋にある七台のピアノフォルテすべてで、それぞれ異なった即興演奏を披露し、その出来に大王も聴衆も大変感動したのだという。そして、大王がバッハにあるお題を提示し、バッハはそれを三声のフーガにしてみせ、これも大変好評であったので、さらに六声のフーガにした。この一連の即興演奏は、高く評価されたため、バッハはライプチヒに戻った後、この即興をもとにして、「音楽の捧げ物」とし、後日フリードリヒ大王に贈った。
音楽の間は、イラストや解説から想像していたものより、はるかに小さな部屋で、客室と同じくらいの大きさであった。壁には絵画やろうそく、シャンデリアなどがかけられていて、かなりきらびやかであった。教会に缶詰の生活を送っていたバッハにとって、緊張する場だったのではないかと思われた。
-プロテスタントとユダヤの狭間で-
フェーリクス・メンデルスゾーン・バルトルディー
メンデルスゾーンは、ユダヤ教から改宗して活躍をし、死後反ユダヤ主義の影響を大きく受けた作曲家である。ライプチヒはメンデルスゾーンが就任した、ゲヴァントハウスがあるため、ゆかりの地だ。反ユダヤ主義との関係性を調べるため、メンデルスゾーンハウスを訪れた。(なお、これはドイツに到着して初めて訪れる場所であったので、とても緊張していた。)

写真:メンデルスゾーンハウス 入口
メンデルスゾーンは、幼少期にユダヤ教からプロテスタントに改宗し、以降、プロテスタントとして、19世紀のドイツ音楽界をリードした人物である。その活躍は、多くの作品を残しただけでなく、ゲーテと親交のあったこと、またドイツ初の音楽学校の創立や、ゲヴァントハウス就任、そしてバッハの「マタイ受難曲」の復活演奏を成し遂げたことなど、華々しいものであった。

写真:作業部屋の複製(左奥の棚の上にある胸像は、彼が敬愛したゲーテとベートーヴェンである。)
1809年、ハンブルクにて誕生したメンデルスゾーンは、ユダヤ人の祖父モーゼスのもと、宗教的に寛容な教育を施されて育った。当時のプロイセンではユダヤ人も国民として平等の権利を有する布告がなされていた。1815年のウィーン会議によって安定していたヨーロッパでは、政権を王政に奪われたブルジョワ階級の人々が盛んに文化活動や学問に力を注ぐようになっていた。このような時代において、さらなる平等の権利獲得に励むユダヤ人は、幅広い教養を身に着けることが将来成功するのに必要であると考えており、メンデルスゾーンはヒューマニズムに基づく理想的な教育を受けた。そして、モーゼフは将来余計な障害に煩わされないために、1816年にメンデルスゾーンに洗礼を受けさせ、ベルリンにて、プロテスタントに改宗させた。
こうして、プロテスタントとして、前述のとおりドイツを代表する音楽家として活躍をして一生を終えたが、死後、ユダヤ教であったことが問題視された。
ワーグナーによる反ユダヤ主義
死後、音楽界においても、ワーグナーによって反ユダヤ主義が盛んになっていた。1850年、ワーグナーは「音楽におけるユダヤ教」の中で、「メンデルスゾーンの作品は、深く心に訴えかけるものでもなければ、高い精神性も感じられない」と、メンデルスゾーンに対しての中傷を述べた。この一言は、次第に広まり、メンデルスゾーンの作品は不評を買うようになり、無視されるようになった。ブラームスなど、彼を高く評価をする音楽家も多く存在したが、1933年以降、ナチズムの台頭により、ドイツ国全体に反ユダヤ主義が高まったため、再びワーグナーの言葉が注目を浴びることとなった。というのも、ナチスがワーグナーの反ユダヤ主義論を積極的に採用したからだ。その結果、12年もの間、メンデルスゾーンの作品の演奏禁止、業績の封じ込め、記念碑の打ちこわしが行われた。序曲「真夏の夜の夢」の書き直しを要求することもあった。
戦後、メンデルスゾーンの演奏や研究は徐々に復活していった。わかりやすい例が、打ち壊された記念碑の再建の取り組みだ。この取り組みは1947年、没後100周年記念の音楽祭にて、胸像の除幕式が行われたことに始まり、1993年には、第三帝国時代に取り壊されたものを取り戻そうとする市民の動きが発端となり全身像の再建の取り組みが始まった。これには市民からの資金援助や、ゲヴァントハウスの支援もあった。2005年にようやく記念碑が完成した。
生涯、メンデルスゾーンはユダヤ教に対し、どう考えていたのか、自分を真のプロテスタントとしてみなしていたのかは、定かになっていない。
-ドイツ語版レクイエムの製作とその意図- ヨハネス・ブラームス
ドイツのキリスト教音楽で、マタイ受難曲に次いで重要なのが、ブラームス作の「ドイツ・レクイエム」である。なぜ、ブラームスはプロテスタント教徒であるにもかかわらず、本来カトリック教徒にむけられた作品である、ラテン語で書かれたレクイエムをドイツ語版で作ったのか、という問いを探求すべく、ブラームスの生誕地、ハンブルクにてブラームス博物館を訪れた。
・ハンブルク
まず、ハンブルクの魅力について述べたい。というのも、私にとって、とても魅力的な都市であったからである。ハンブルクはドイツ最大の港湾都市で、ICEを降り駅のホームに降りた瞬間から、地面から湧き出るような活気を感じた。市内の電車からは、港を一望できる線もあり、移動時間も心を躍らせて過ごした。音楽に関しては、ブラームスのみでなく、メンデルスゾーンが生まれた都市でもあり、また、ビートルズが下積時代に活躍した地としても有名である。活気と音楽に満ち溢れており、いたるところでビールを片手に、ジャズ演奏やアコーディオン演奏が行われて、多くの人が一緒に演奏を楽しんでいる姿が印象的だった。

写真:港の様子

写真:滞在先の最寄り駅で行われていた、JAZZ TRAIN というイベント。この日は各車両でジャズコンサートが行われながら電車が走っていた。地元の人々に絶大な人気があるようで、この電車に乗るために長蛇の列であった。
ハンブルクの肌で感じた魅力について述べたところで本題に戻る。
・レクイエムとは
レクイエムは「死者のための典礼式文」を用いているために、「死者のためのミサ」として知られている。これは、カトリック教会が採用している祝日、「諸聖人の休日(万聖節)」(11/1)に次いで行われる「諸死者の休日」(11/2)におけるミサ向けて書かれた曲である。諸聖人の休日では、亡くなった聖人全員を記念し、諸死者の休日では亡くなったキリスト教徒全員を記念し、ミサを行う。これは日本のお盆と性格が似ているといえるだろう。なお、レクイエムという名前は、このミサでは導入の聖歌の歌いだしが「永遠の安息を(Requiem aeternum)」という言葉で始まることに由来している。そして、この祝日のみではなく、あらゆる葬儀におけるミサ曲としても次第に普及していった。(金澤2007 p.32-42,156-159参照)
・ブラームスの時代
このようなレクイエムをドイツ語で書いた理由を探求するには、まず当時の音楽史の動きが重要となってくる。
1860年代のドイツは、ビスマルクの政策により不安定で、人々は"ドイツらしさ"を重要視し、求めていた。ここでいうドイツとは、言語と文化、領土を指す。こうした時代背景に応えるべく活躍したのが、ブラームスとワーグナーで、それぞれ、「ドイツ・レクイエム」と「ニュルンベルクのマイスタージンガー」を同年1868年に初演した。
二人の音楽は対をなしていて、当時の音楽界はブラームス派とワーグナー派に分かれていた。ただし、ブラームスはワーグナーのことを尊敬していて嫌っていたわけではなかったし、ワーグナーも同様であったという。一般的に、ブラームスは古典伝統を重視する保守的な音楽家で、ワーグナーはモダンで革新的な音楽家であり、反形式主義であったといわれる。 ワーグナーは、「ニュルンベルクのマイスタージンガー」にて、バッハ風の対位法を用いることによって、ドイツらしさを取り込んだ。このオペラの主人公である、ハンス・ザックスは民主主義の象徴として登場する。そして、プロテスタントのコラールを用いて、反ユダヤ主義を徹底している。
ブラームスは、「ドイツ・レクイエム」にて、カトリックのコラールとネオ・バロックの対位法を用い、古典的なドイツらしさを取り込んだ。タイトルにわざわざ付けた「ドイツ」からは、本来書かれているラテン語を意図的に避けたことを意味していることが見て取れる。
・ブラームスの宗教観
ブラームスの母は熱心なプロテスタントで、父はおそらくユダヤ人であったといわれている。ブラームスは家族構成からしても、特定の宗教に固執していたわけではなかった。信仰はプロテスタントであった。 フォイエルバッハは『キリスト教の本質』にて、「聖書には"人間のことば"が述べられている。」と主張しているが、これに対しブラームスは「魂の不滅など信じない」と主張している。彼は神的な絶対的な何かを信じなければ生きられない、人間という弱い生物を信じているとし、人間を愛に飢えた悲しい生き物であるとする。(須藤 p.46 参照)
・ドイツ・レクイエムに込めた想い
1856年の、敬愛なるシューマンの死と、1865年の母の死に大きなショックを受けた影響で、この二人を祈んで構想された。このことは第二曲「人は皆、草のようで」というフレーズからみてとれる。 キリスト教音楽の最高峰とされる『マタイ受難曲』は、人類の罪をあがなうためになされたイエス・キリストの受難が内容となっている。これに対して、『ドイツ・レクイエム』では、個々の魂におけるキリスト(=光)といかにして出会うか、を内容としている。苦悩に満ち、「生きることの意味」を必死に求めている魂が、ついに光と出会って「永遠の生命」を自覚し、その尽きることのない喜びを知るまでのプロセスが描かれている。
・解釈
歌詞はルターがドイツ語訳した、旧約聖書と新約聖書からとられている。これは、ブラームスが自国で書かれた最も神聖な書物は聖書であると考えていたからであり、また、聖書を詩的な芸術の源泉であると捉えていたからである。
しかし、曲中にはイエス・キリストの名前は一切登場せず、その内容は無神的である。キリストを崇める宗教的な曲ではなく、生きている者への慰めを与えるための賛歌としてこの曲を構想したからであり、自分は宗教家ではなく、音楽家である、という信念を貫いた。
これに対し、批判的な意見もみられる。初演時の指揮者、ラインターラーは、この曲は宗教的でなさすぎる、と批判して、ヘンデルの『メサイア』から"I know that my redeemer liveth"という一節を挿入している。音楽評論家、アーネスト・ニューマンは、この曲は「神学上の物語ではなく、人間の証を音楽の最終目的にしていた」と指摘している。
このような風潮に反して、ブラームスはタイトルの"ドイツ"のかわりに"人間の"を入れ替えようと提案している。それほどにブラームスは、最愛なる二人の女性の死を尊んでこの曲を書いたのであろう。
・ブラームス博物館
小さめの一戸建てに、ブラームスの展示が所狭しと並んでおり、図書館も併設されていた。ブラームスは日本人に人気なので、来場者は日本人観光客が最も多いのだという。私が訪れた際も、四人中三人が日本人であった。係の女性はとても親切で、私の質問にも丁寧に答えてくれた。ドイツ・レクイエムについては、詳しい展示がなかったので、ほとんどが直接説明してもらった内容である。それでも足りなかった部分は、併設されている図書館の文献を一緒に探してもらった。

私がつっこんだ質問をするので、その女性も嬉しかったようでとても仲良くなることができた。そのおかげで一生忘れられない経験をさせてもらった。展示されていたピアノフォルテを弾かせてくれたのである。これはブラームスが下積時代に実際に使用していたものなのである。楽譜は図書館の棚にあるから、好きな曲を弾いてよいよ、と許可してくれたのだ。

写真:この時の感動は鳥肌ものであった。
調査を終えて
まず、無事にドイツでの計画を遂行することができ、心からほっとしている。海外に一人で行くのは二度目であったが、英語圏以外の国は初めてで、自信がなく、とても不安であった。担当の縄田雄二教授に調査内容から移動の仕方まで、直前までアドバイスをしていただいて、大変お世話になった。
今回の調査で最も肌で感じたことは、ドイツの音楽に対する親密さだ。町のどこを訪れても音楽であふれていて、そこに人が自然と集まる。これはクラシック音楽に限ったことではなく、ジャズやテクノも同様であった。
教会や博物館に赴いて、日本で文字からしか学べなかった沢山のことを実際に知識とすることができた。バッハに関する研究は日本でも盛んにおこなわれているので、さらに深めるために関連した文献を読みたいと思う。メンデルスゾーンは子供のころから好きな作曲家で、反ユダヤ主義との関係を知った今聴き演奏してみると、新たな発見があってとても面白い。また今回は、プロテスタンティズムをテーマにしたが、新たに、ワーグナーの反ユダヤ主義音楽に興味を抱いた。それに付随して、ワーグナーとブラームスの比較にもとても興味を抱いている。
8泊10日の現地滞在の中で、音楽を通じた素敵な出会いがあった。ライプチヒのバッハ像の前で、互いにバッハが好きであるという共通点によりお会いした日本人、その話に共鳴して会話に入ってきてくれたスペイン人。バッハハウスの受付で隣に並んでいて、互いの好きな音楽について会話をした南アフリカの男性、ベルリンフィルハーモニー鑑賞の際、隣の席に座っていたイスラエル人。そしてブラームス博物館で出会った日本人の医師。このうち日本人の二人には特に良くしていただいて、その日の調査を一緒に回ってもらったり、語学を助けてもらったりもした。ベルリンフィルで会ったイスラエル人とは音楽の話からお互いの国の話まで至り、日本がいかに平和であるか、そして音楽はどんな状況下の国でも人々に感動を与えていることを思い知らされた。これらの人々との出会いは全て音楽が好きという共通点によるものである。 自分の関心分野を深めることができたとともに、かけがえのない経験となった。自分の探求心を掘り下げて、一から計画を立て、それを遂行することができたのは、自分の糧として、大きな自信につながった。今後に生かしていきたい。

参考文献
- 井上太郎『レクイエムの歴史 死と音楽との対話』平凡社(1999)
- 岡田暁生『西洋音楽史 「クラシック」の黄昏』中公新書(2005)
- 金澤正嗣『キリスト教と音楽 ヨーロッパ音楽の源流をたずねて』音楽之友社(2007)
- 関根裕子「ドイツレクイエム」『赤いはりねずみ No.30』日本ブラームス協会(2001)
- 樋口隆一『カラー版作曲家の生涯 バッハ』新潮文庫(1985)
- 三宅幸夫『カラー版作曲家の生涯 ブラームス』新潮文庫(1986)
- カール・ガイリンガー『ブラームス 生涯と芸術』芸術現代選書(1997)
- W.フリッシュ「リベラルなモダニスト・ブラームスと反動的保守主義者ワーグナー」『赤いはりねずみ No.25』日本ブラームス協会(1995)