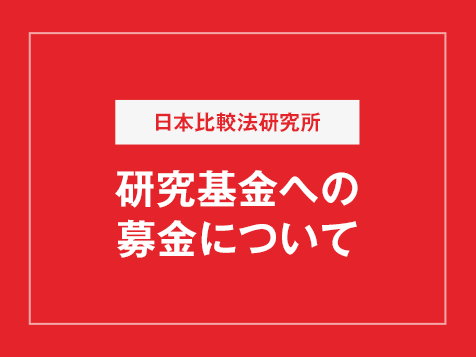日本比較法研究所
2024年度 講演会・スタッフセミナー 概要
テーマ:判決自動化システム:人間とAIの思考プロセス
ハイブリッドの方式により、表記の題名で訪問研究者により1時間の報告がなされ、その後10分の休憩の後、50分程度質疑がおこなわれた。質疑については、オンライン参加者と会場参加者からの両方された。AIを裁判に利用した場合に用いたデータについて裁判参加者がその要約に納得できない場合はどう考えるか、日本においては、裁判は減少傾向にあるので、ポーランドと違ってAIを利用するメリットがすくないのではないかという、指摘があり、参加者が納得できる形が考えられる、国によるという、回答がされて、その後議論がされた。
テーマ:法学教育等における生成系AIの利用の可能性
ハイブリッド方式により、表記の題名で訪問研究者により1時間の報告がなされ、その後10分の休憩の後、1時間程度の質疑応答がされた。法的推論や法的三段論法における生成系AIと人間の思考との差について、突っ込んだ議論がおこなわれた。
テーマ:欧州連合の司法制度
本講演会では、まず欧州司法制度とりわけEU司法裁判所を紹介し、次いで同裁判所が現在かかえている課題を考察した。その要旨は次のとおり。
1.EU司法裁判所の紹介
EU裁判所は、諸条約の解釈・適用における法の遵守を確保することを任務とし、「ヨーロッパ統合の促進」のためにこの任務を果たしてきた。第2次世界体制後、ヨーロッパ諸国は持続的平和の実現を求めた。欧州統合の提唱者であったJean Monnetは、偉大な理想や理念を語るよりも「諸事実の連帯」を築こうとした。EU司法裁判所は次のような独自の制度的特徴をもっている。①先決裁定(欧州連合運営条約267条) ②条約違反手続(同258-260条) ③取消訴訟(欧州連合運営条約263条) ④不作為確認訴訟(同265条) ⑤報告裁判官:事件の当初に指名され、指示を出し、裁判の構成や審問や追加書類が必要かどうかを提案する。これらを決定するのは裁判所全体である。その後報告裁判官は、判決案を作成し、それらは裁判官全体の審議に付される。 ⑥法務官:フランスの最高行政裁判所の「公の報告者」に由来。公の報告者は結論を作成し解決方法を裁判官に提示する。法務官は11名。
2.EU司法裁判所が現在かかえている課題
(1)制度的課題(裁判官および法務官の指名方式)
EU司法裁判所裁判官の候補者を選ぶのは加盟国政府である。EU司法裁判所の裁判官および法務官は、255条に定める小委員会との協議の後に加盟国政府の共通の合意により任命される。小委員会は、EU司法裁判所の元裁判官および各国の最高裁判所の現職裁判官から構成され、EUが中欧、東欧に拡大し始めたときに設立された。その任務は新加盟国からの裁判官候補者の質、能力、独立性を確保することだった。しかしながら、この小委員会がフランスやギリシアからの裁判官候補を拒否するという現象も生じた。EU司法裁判所は政治的役割を有さないことになっているが、実際には一定の政治的役割を果たしている。
(2)判例的課題(EU司法裁判所の判例および構成が有している政治的影響力)
現在、ポーランドやハンガリーにおける「法治国家の侵害」という問題が生じている。これはヨーロッパ的価値の尊重にかかわる深刻な問題である。EU司法裁判所は、同裁判所が「裁判官の独立を評価するという権限、独立した裁判官を有さない国家を罰するという権限」を有している、とする解釈を引き出した。ここにおいてEU司法裁判所は、総力を動員して、深刻な問題を解決するためにEUの活動を政治的に方向づけたのである。同裁判所は、政治問題の解決するための法的手段を見出した。
(3)言語的課題(言語とりわけフランス語の地位)
EUにおける言語システムとは? EUには24の言語が存在し、EU司法裁判所において原告はこれら24の言語のいずれかにより訴えを提起することができ、そこで選ばれた言語が訴訟手続における手続言語になる。他方で、EUの諸機関が効率的に任務を遂行するためには、1つまたは複数の共通語が必要になる。政治機関においては英語が共通語になった。EU裁判所においては、作業言語は当初から常にフランス語である。このことは重要な政治問題になっている。何人かの裁判官、元裁判官は、このようなフランス語支配の状況を「裁判所における文化的支配」であると批判している。この問題は「多様性を尊重しつついかにして統一性を確保するか」というEU全体の問題につながっている。報告後、報告者と学生との間に活発な質疑応答がなされた。
テーマ:欧州連合における文化多様性と多言語主義
本報告は3つの部分から成る。それらは(1)EUにおける文化・アイデンティティ保護の法的枠組、(2)EUの言語制度、(3)現在の課題である。それぞれの要旨は下記のとおりである。
(1)EUにおける文化・アイデンティティ保護の法的枠組
この問題についてEU司法裁判所は、まず憲法的アイデンティティを考慮し、国内裁判所判事が行う定義および性質決定を尊重する。文化と言語は、共通規則の例外として扱われる。実際、文化政策、言語政策は加盟国権限に属する場合が多い。EUは文化政策を漸進的なやり方で導入した。その基礎にあったのは文化多様性と文化間対話の促進だった。連合条約は前文で欧州の文化的・宗教的・人道主義的遺産から示唆を引き出すという原則を掲げる。同条約3条は、連合の基本目的として「文化的・言語的多様性の豊かさを尊重し、欧州の文化遺産の保護・発展に配慮する」と述べる。文化分野でのEUの権限は支持権限である。EUは他の加盟国言語の習得を奨励しているが、必ずしも言語的多様性とりわけ地域言語の尊重を奨励しているわけではない。それでもEUは一般に多言語主義を尊重しているとみなされている。
(2)EUの言語制度
EU言語制度の源は、ローマ条約発効前に採択された政府間宣言であり、それはEU派生法に継承される。言語制度にかんする条約上の規定としては、EU条約3条3項(連合は文化および言語の多様性の豊かさを尊重)、55条1項(条約正文の平等)。EU運営条約20、24条(欧州市民は、EUの公用語の1つにより、欧州議会への請願権、オンブズマンへ申請権、EU機関と連絡する権利を行使)。基本権憲章21条1項(言語における非差別)。EU運営条約342条(理事会は全会一致で諸機関の言語制度を採択)。1958年にCEEの言語制度を定める規則1号が採択された。
いかなるEU機関も作業言語を明示していないものの、委員会は、EU職員の募集にかんする争訟事件のさいに、EU司法機関にたいして3つの作業言語(英語、ドイツ語、フランス語)を用いるという行政慣行を常に維持している。このようにEU諸機関の言語制度は複雑であり明確さを欠いている。この透明性の欠如のせいで、EU諸機関の正当性が損なわれている。
⑯これら一連の条項からは、規則第1号を支える一般論理を導き出すことはできない。そもそも同規則には、同規則の目的を理解し得るような冒頭説明が欠けている。
(3)現在の課題
1)EU諸機関における英語支配
EU職員の募集要項は24言語で作成。採用試験の第1段階:EUの公用語24言語のうち、候補者が選択した言語(=第1言語)による3つの試験。口述、説明、抽象的論述。4番目の試験は状況判断。仏語、英語、独語のいずれかにより行われる。第2段階:ケース・スタディーと口頭試験(プレゼン、グループ行動、組織化された対話)。これらは、仏語、英語、独語のうち候補者が選択した言語(=第2言語)により行われる。実際には英語が第2言語として選択されるケースが増えている。これらの言語制限は、応募者が採用された場合に果たす任務の観点から必要性あり、明確、客観的、予測可能な基準に依拠しなければならないが、それらは明確ではない。
2)EU司法裁判所における仏語支配
裁判所の正当性を支えるものは裁判所の安定性、理解しやすい法概念、判例における一定様式の反復である。仏語使用も裁判所の安定性を確保するために変化なく継続されているのではないかと思われる。フランス語が作業言語として維持されていることの結果、裁判官全員がフランス語を話す。フランス語圏出身の法律家は、ロー・クラークに就く可能性が高くなる。このことは政治的に重要な問題を提起する。現職あるいは元裁判官のなかには、この仏語支配を公然と批判する人がいる。
3)欧州における地方言語・少数者言語の地位
この分野におけるEU権限は、支持・調整権限。排他的権限でも混合権限でもない。Minority Safe Pack(一般裁判所の2022年11月9日判決)
地方言語・少数者言語の保護:欧州審議会の役割:地域言語・少数者言語欧州憲章は1998年に発効。欧州審議会の発議による。同憲章は、欧州地域・地方当局恒常会議が提案した条文案にもとづき作成され、1992年6月25日に欧州審議会の閣僚委員会により採択される。今日まで、25ヵ国がこれを批准。そのうちEU加盟国は17ヵ国。署名したが批准していない国が8ヵ国あり。この8ヵ国のなかにフランスとマルタが含まれている。欧州審議会加盟国のうち13カ国が同憲章に署名も批准もしていない。それらの13ヵ国のうち、8ヵ国がEU加盟国である。同憲章は約80の地方言語・少数者言語に適用されている。同憲章は、これらの言語を教育、裁判所、行政機関、メディア、文化、経済社会生活、脱国境的な協力において用いることを促進している。同憲章はこれまでの30年間の活動により、この分野における主要な準拠枠組になっている。しかしながら、フランスは同憲章を批准していない。欧州における言語がかかえる逆説がそこに見受けられる。それは国家言語の保護・国民的アイデンティティと、国家内部における地域言語の保護・地域的アイデンティティとの対立である。報告後、報告者と参加者との間に活発な質疑応答がなされた。
テーマ:欧州連合における法的文書の翻訳:AIの可能性
EU委員会の翻訳サービスは、世界でもっとも広範囲に行われるサービスである。同時にそれは、翻訳という知的作業に占めるAIの地位を考えるうえで、大変有用である。このようなテーマの報告を日本比較法研究所で行う意義は何だろうか? 報告者はその意義を次のように述べた。比較法研究は、1つの言語から他の言語への、1つの法文化から他の法文化への翻訳の作業を伴う。比較法は、EU法およびその解釈の発展において、中核的役割を担っている。というのも、EU法は各国の国内法に着想を得て、形成・発展してきたからである。現在のEUの重要な政治プロジェクトの1つは、多分野においてと同様、翻訳作業においても決定的な影響を及ぼすことになるAIに取り組むことである。こう述べたうえで、報告者は、次のようなプランにもとづいて、興味深い報告を行った。(1)EUと法、(2)EUと言語、(3)EUの法的文書の翻訳とAI。報告後、報告者と参加者との間に活発な質疑応答がなされた。
テーマ:インドネシアにおける環境保全・環境管理に関する法改正とその課題
地政学的に戦略的な位置にあるインドネシアは、産業・経済の発展と環境保全の間で差し迫った課題に直面している。本セミナーでは、インドネシアにおける環境保護法の最近の発展に関するいくつかの重要な問題について、自然地理学的および法社会学的観点から検討した。
テーマ:インドネシアの気候変動対策
この公開講演では、学部生を主な対象として、インドネシアの視点から気候変動とその適応・緩和に関する課題を探った。さらに、インドネシアの気候政策の妥当性とその実施について報告した。
テーマ:スパイスの道(海のシルクロード):インドネシアにおける世界遺産保護の歴史をたどる
インドネシアは、日本同様、スパイス・ルート(海上シルクロード)の一部である。したがって、インドネシアにおける文化遺産(特に、無形文化遺産)の保護を、その豊かで長い香辛料貿易と戦争の歴史に基づいて強化することは、有意義である。本セミナーでは、そのような観点からスパイス・ルートについて興味深い説明がなされた。
テーマ:ドイツにおける法学教育について
本講演では、ドイツの法学教育において中核におかれている鑑定スタイル(Gutachtenstill)の文書作成について取りあげた。まずは、鑑定スタイルがローマ法に遡ることや、論理学とのつながりについて説明した。そしてその上で、その具体例として、法学部の第二セメスターの学生向けの民法から素材をとり、詳細に紹介していただいた。全体を通じて、鑑定スタイルで文章を書けるようになる能力の育成が学術としての法学の基礎にある点が強調された。
テーマ:中国における法学教育について
ドイツ・テュービンゲン大学のT・フィンケナウアー先生に、ドイツの法学教育、特に鑑定スタイルでの文書指導のあり方について報告をいたただいた。その講演に続く形で、中国の法学教育の変遷について詳細に説明いただいた。
テーマ:ローマ法と中国法の居住権
本講演では、居住権(ususfructus, habitatio)の価格算定がテーマであった。用益権や居住権は、原則として無償で設定されるため、価格算定には工夫が必要となる。この工夫について、報告者は古代ローマ法、フランス法、ベルギー法、そして現代中国法を紹介した上で、今後のあるべき法制について提言している。その中で、日本の配偶者居住権制度についてもとりあげられた。
テーマ:ソ連・ロシア民法と政治経済
本講演は、主として1922年と1964年のソ連民法典と政治経済学との関係性を取り上げるものである。伝統的な民法の基本思想は、政治経済学と結びついたものではないが、社会主義圏においてはこれを結びつける独特な発想がある。この講演では、ソ連民法の展開の中でこの結びつきがどのような変遷を辿ったかが詳細に示された。またその関連から今後の中国の民法のあり方についての展望も示された。
テーマ:ドイツにおける被害者保護:理論と実務
講演会においては、予め訳出した講演原稿のうち、性犯罪を中心に展開されてきたドイツの立法経緯を省略し、ドイツの実務において、犯罪被害者が、個々の事件の具体的状況に即して、様々な権利を行使できるようにするために、犯罪被害者にこのような権利及び支援団体により支援を受けることができるといった情報提供を確実に行うことの重要性、及び、ベルリン市で行われている警察と連携したプロジェクトに限って、講演が行われた。その後、参加者との間で活発な質疑応答が行われた。
テーマ:大学は法が求めるよりも言論をより規制すべき又は規制すべきでないか
ハインツ教授は、大学が学内の言論について(学外の)社会一般の法規制より厳しく規制していることに疑問を提起した。たとえば、ホロコーストがなかった、または、ナチスを支持するという主張は、少なくともイギリスでは合法であるにもかかわらず、大学でそのような主張を公開で行うことが規制されることは多く、(学外の)社会一般の法規制と同程度どころか、より厳しい規制がなされているという(この現象は、他のいわゆる民主主義国でも見られる。)。同教授は、これに対して、学内でのより厳しい規制の正当化根拠などを批判的に検討した上で、大学では、その性質上、社会一般の法規制よりも緩和した基準で言論の自由を保護すべきであると主張した。
このような問題提起に対して、日本や米国の現状、議員の免責特権との比較、学内での表現の自由と犯罪行為、理念と実務の関係などについて、参加者間で活発な議論が行われた。
なお、本セミナーには、コメンテーターとして、欧州連合司法裁判所調査官のジュリアン・スターク(Julien Sterck)博士とクィーンズランド大学研究員のルカ・マン(Luke Munn)博士も参加した。
講演:朴 仁煥(仁荷大学校法学専門大学院・教授)「意思決定支援の制度化と立法方向」
テーマ:犯罪捜査における弁護人の文書閲覧権に関する台湾の最近の動向
上記講演においては、台湾の捜査手続における弁護人の文書閲覧権の動向が紹介された後、活発な質疑応答が行われた。質疑応答においては、台湾の刑事訴訟法は、ドイツの刑事訴訟法の強い影響を依然として受けているが、わが国及びアメリカ法の影響も強いことが確認され、また、被疑者の権利保障と事案の真相解明のバランスを模索する台湾の動向が明らかとなった。
テーマ:犯罪捜査の対象:スマートフォン
本講演においては、スマートフォンは我々(被疑者にとっても)の日常生活の一部となっていることをスタートラインとしたうえで、ドイツにおける犯罪捜査の一環としてスマートフォンに対する捜査の在り方につき、捜索差押えの文脈で有体物としてスマートフォンを取り扱ういわゆるバインダーモデルを批判し、現行のオンライン捜索(刑事訴訟法100条b)の規定を改正し、同条により認められるべきとしている。また、質疑応答においては、ドイツにおいては、虹彩認証、指紋認証によりロックされているスマートフォンの内容を見る場合には、被疑者の同意がなければ、強制の処分(Zwangsmaßnahme)として、被疑者の意に反して、捜査官がつぶった被疑者の目を開けさせた被疑者の顔面にスマートフォンを近づけたり、被疑者の指をスマートフォンに押しつけることが、被疑者に対する身体検査について定める同法81条aの規定により認められるとする見解もあるが、自己負罪拒否特権に反するといったことが紹介され、さらに、2024年9月に開催された第74回ドイツ法曹大会の刑法部会に提出されたトリアー大学のモハメド・エル=ガージ教授(Prof. Dr. Mohamad El-Ghazi)によるスマートフォンに対する干渉を同法100条dの規定に沿うべきとする内容の鑑定書を批判し、引き続きスマートフォンに対する干渉の在り方を議論すべきとし、フロアとの間で活発な議論が行われた。
テーマ:弁護士の利益相反:利益相反となる代理の禁止に関する改正後の残された課題
その源流をローマ法のPraevaricatioにさかのぼる弁護士の利益相反(利益衝突)の禁止は、弁護士の独立性およびその守秘の義務とならぶ弁護士の基本的義務の一翼を担っている。その趣旨はいうまでもなく、依頼者との信頼関係を確たるものにし、弁護士の独立性とともにその職業実践の実直性を確保することにある。弁護士を法治国家の守護者、人権の擁護者と位置付ける国においては、その規定の形式は異なるし、またわが国のように必ずしも利益相反禁止の範疇には入らないものが規定上混在していることはあっても、利益相反代理禁止はいわば弁護士職業法には必置の規律である。
ドイツも連邦弁護士法はその43条aにおいてこれを規定しているが、従前は同法上の限りでは「弁護士は相反する利益を代理してはならない。」とのみするに止まっていた。しかしながら、2022年における1994年以来の大改革と呼ばれる改正により、利益相反自体についての規定を大幅に拡大した。
今回のデッケンブロック准教授(教授資格者)を招いてのセミナーは、同氏の、2022年改正のいわば「目玉」の部分を切り取った報告を踏まえ、その内容に検討を加えたものである。同氏の報告の詳細は、後日同氏の報告の翻訳を公表するのでそれを参照願いたいが、簡単に述べると、今回の改正で取り込まれた、弁護士が共同して弁護士業務を営むにあたっての規律のあり方とそれにともなう様々な問題である。興味を引かれたのは、コンフリクト・チェックについて、デジタル化が推奨されている点である。巨大事務所内でのチェックはこれなしではうまくいかないという指摘は、もっともである。このほか、参加者からの問題提起のあったところでもあるが、利益相反禁止解除のための当事者双方から同意を得る際における説明は、守秘義務と絡み、これにどのように対処すべきかは、わが国でも悩ましい問題となっているところである。質疑をつうじてその真の問題の所在が浮き彫りにされた点は、今回のセミナーの大きな成果であった。
利益相反をめぐる問題は彼我ともに多い。日独のこの点に関する法制比較は緒に就いたばかりであり、同様のセミナーが今後回を重ねることを期待したい。
テーマ:プラットフォームワークの雇用法上の規制:ドイツとヨーロッパにおける展開
プラットフォームワークの雇用法上の課題とその解決に向けた法的枠組みについて、ドイツおよび欧州における最新の展開を踏まえ、ケルン大学労働法経済法研究所(ニッパーダイ研究所)の元所長であるヘンスラー教授に講演いただいた。
テーマ:ドイツにおける労働協約法の危機:ドイツおよび他の先進国において労働組合と労働協約の自律性を強化するために講じるべき措置とは?
ドイツにおける労働協約法の危機の問題について、とりわけドイツおよび他の先進国において労働組合と労働協約の自律性を強化するために講じるべき措置を中心に講演が行われ、日本の研究者との間で議論が行われた。