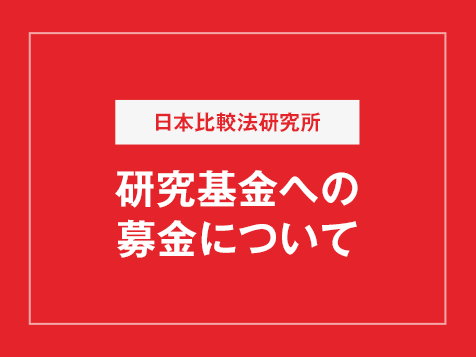日本比較法研究所
沿革
- 日本比較法研究所は、日本の比較法学の泰斗、故杉山直治郎博士を初代所長として、1948年(昭23)12月に発足した。この種の研究所としては、東洋で最初に設立された機関である。当研究所は、中央大学によって設置されたものの、当初は、中央大学の枠を越えた全国的な規模の研究機関として組織され、広く海外の同種の諸機関と密接な連携を保ち、国際的な比較法研究の推進の一翼を担うという遠大な構想をもっていた。設立当初の研究所規則は、「日本比較法研究所は、その名の如く、一大学の独占的施設ではない。日本の、東洋の、ひいては世界の、志を同うする研究及び実践に協力し、比較法学の進歩に寄与することを切念するものである」(前文)と謳っている。発足後、杉山所長の主宰の下で、比較法雑誌の刊行、内外の著名な学者による講演会・研究報告会の開催、重要資料の翻訳など、活発な活動が展開された。1951年(昭26)には、西ドイツのマックス・プランク外国私法国際私法研究所の機関誌が当研究所の設立および活動の模様を紹介している。そして 1962年には、欧文の比較法論集2巻が刊行された。この論集(Problemes contemporains de droit compare)は、当研究所創立10周年を記念して編纂されたもので、国内および海外14か国の著名な研究者計43名が寄稿している。2巻合わせて1,000頁を超えるこの大著は、杉山所長の世界的な名声をもって初めて実現が可能となったものであり、そして「文字通り比較法の一大記念碑である」(野田良之)と評価されている。
- 10周年記念論集の刊行後、当研究所の組織は大幅に変更された。すなわち、1963年(昭38)に新たに制定された日本比較法研究所規則は、研究所は学校法人中央大学が設置するものであることを明示し、そして中央大学の専任教員をもって所員とすることとしている。この改正作業を通して研究所の新しい運営体制の礎が築かれ、研究所は新時代を迎えることとなった。この前後には、比較法雑誌の刊行も暫時途絶えるなど、沈滞の時期があったが、同誌は1968年に8年ぶりに復刊され、新組織の研究所は漸く活力を回復した。そして1977年には、世界ムスリム連盟およびイスラミック・センター・ジャパンの後援の下に、当研究所の主催でイスラム法講演会を開催した。この講演会のために、世界ムスリム連盟長官、同副長官、その他4 名の高名なイスラム法の権威者が遠路はるばる来日し、講演を行った。講演会の初日には、三笠宮崇仁親王殿下、最高裁判所裁判官3名、駐日外国大使3名等の貴賓も列席し、4日間に亘る講演会は連日中央大学内外から200名を超える参加者を得て、大きな成功をおさめた(この講演会の記録は、「イスラム法への招待」と題して、当研究所から刊行されている)。この大規模な国際的行事の経験は、当研究所にとって貴重な財産となっている。この経験に学んで、その後当研究所では多様な国際交流が活発に展開されるようになった。
- 当研究所は、中央大学の法律科目担当の教員を主な構成員としている。そのほか、共同研究のプロジェクトに参加する他大学の研究者を客員研究所員または嘱託研究所員として迎えており、研究活動は中央大学の枠を越えて拡がっている。共同研究は、「米国刑事法の動向の研究」、「犯罪学・被害者学の比較研究」「憲法裁判の基礎理論」等、数多くの主題別にそれぞれのチームを編成して行われており、その成果は比較法雑誌に掲載され、または当研究所の叢書として刊行されている。また、外国人研究者による講演会も度々開催されている。交流協定に基づいて来訪する客員教授による講演会・セミナー、特定の講演のために招いた研究者による講演会等は毎年十数回に達する。講演会の開催は、国際交流の一つの形態であるが、そのほか、国境を越えての共同研究、専ら自分の研究に従事する外国人研究者の長期受入れ、外国法曹関係者の訪問を受けての意見・情報交換等、多様な交流が行われている。
- 1998年に創設50周年を迎えた当研究所は、この機会に三つの記念事業を行った。まず第一が50周年記念論文集“Toward Comparative Law in the 21st Century”の刊行である。10年毎に当研究所が刊行してきた記念論文集の5冊目にあたる本書は、当研究所とかかわりの深い世界各国の研究者から寄せられた53論文を含む77論文を登載した約1,600頁の大部のものとなった。これは、当研究所が積み重ねてきた交流の成果を示すものであり、同時に国際的評価にたえうるものであると自負している。第二は、『日本比較法研究所50年史』の編纂・刊行である。わが国の比較法研究の発展に重要な役割を果たしてきた当研究所の軌跡を辿ることにより、将来の当研究所及び日本の比較法研究のあるべき姿を探るうえで貴重な資料となりうるものである。第三は、スタンフォード大学フリードマン教授、ミュンスター大学グロスフェルト教授、さらに最高裁判所園部判事を講師に迎えての記念講演会と記念式典の挙行である。この行事は、各界から多数の方々の参加を得て盛会裡に終了した。なお、記念講演の内容は、講演録集として刊行している。
- 創設50周年を迎えて6年後の2004年、わが国では新たな高等教育システム・法科大学院制度がスタートし、本学においても同大学院が誕生した。これにともなって本学では法学系専任教員が増加したことから、当研究所においても所属所員数が倍増し、同時に、同大学院が市ヶ谷校舎に開校されたことにより所員の所属地が単一でなくなるという大きな変化を見ている。そのようななか、2011年現在、当研究所に設置された共同研究グループは42グループにのぼっている。
2008年12月、当研究所は創設60周年を迎え、これを記念して、2009年3月6日に、「比較法研究の将来」と題した60周年記念シンポジウムが、海外からの講演者を迎えて開催された。また、2011年の3月には、国の内外、また各方面研究者から寄せられた39本の多彩な論稿を集めた創設60周年を記念する論文集が刊行されている。
一方、2011年10月1日、2日の両日、日本比較法研究所第6回シンポジウムが開催された。シンポジウムでは、国内に加えて中国の北京大学、人民大学、清華大学等から講演者を迎え、日中両国において刑事法上の議論を集める諸テーマをめぐって、日中それぞれ第一線で活躍する研究者の報告をもとに、会場参加者も交えての充実した議論が展開された。本シンポジウムの内容を載せた報告集は、2011年末に刊行された。
なお、本学は2010年に、創設125周年を迎えた。これを記念して開催された一連の行事中、2010年11月6日、7日の両日行われた「法律系4部局合同・連続公開シンポジウム 英吉利法律学校の125年-現在、過去、そして未来-」の当研究所所管第4セッション「グローバル時代の法律学・国境を越える法律問題」においては、多数の会場参加者を得て、海外からのパネラーによる報告とこれらをめぐっての活発な討議が行われた。シンポジウム当日の報告の内容は、その後の関係者各位の要望を受けて、2011年に報告集として刊行されている。 - 2014年2月21日(金)・22日(土)の2日にわたり、独日法律家協会(DJJV)との共催でシンポジウム「債権法改正に関する比較法的検討」を開催した。債権法改正について、先に法改正が行われていたドイツと、中間試案を経て改正要綱案の検討に入っている日本、双方の検討に関わる第一線のメンバーによる意見交換が行われ、その成果は同年、研究叢書として刊行された。また、2015年10月4日(日)には、ふたたび独日法律家協会(DJJV)との共催でシンポジウム「裁判員裁判に関する日独比較法の検討」を開催した。開始から6年を経過した我が国の裁判員裁判について、日独双方の研究・実務の専門家が両国の制度の推移や問題解決の方法について討議が行われた。このシンポジウムについても、2016年、研究叢書でその成果が刊行された。
- 2014年度から、「法化社会のグローバル化と理論的実務的対応」をテーマとして中央大学学術シンポジウム開催のための共同研究を開始した。「裁判規範の国際的平準化」「リーガルサービスのグローバル化と弁護士法」「サイバースペースの法的課題と実務的対応」「環境規制のグローバル化と実務的対応」「生命倫理規範のグローバル化と実務的対応」「決済取引のグローバル化と実務的対応」という、6つの個別研究プロジェクトを設けて研究を深め、2016年12月17日(土)多摩キャンパスにおいてシンポジウムを開催した。その成果は2017年11月に刊行された中央大学学術シンポジウム研究叢書として刊行された。
- 2017年 4月 8日には、後楽園キャンパスにおいて、日本弁護士連合会 ケルン弁護士法研究所 ドイツ連邦弁護士会 ドイツ弁護士協会との共催で「日独弁護士職業法シンポジウム―弁護士の独立と利益相反の禁止―」を開催した。
- 2018年、創設70周年を記念し、11月24日にシンポジウム「グローバリゼーションを超えて-アジア・太平洋地域における比較法研究の将来」を開催した。