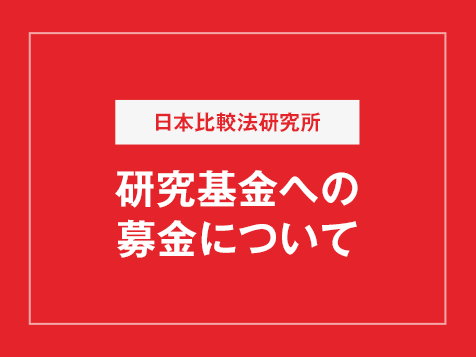日本比較法研究所
2025年度 講演会・スタッフセミナー 概要
テーマ:サプライチェーン規制の法と経済学
コルヒ教授の講演は、国際的なサプライチェーンにおける問題を、法と経済学のアプローチを用いて分析し、欧州の企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令がこれらの問題を解決できるのか、またどの程度のコストで解決できるのかを分析するものであった。一つの商品(例えばTシャツ)であっても、その製品が出来上がって市場で販売されるまでの過程は、国際的な生産分業・流通を前提にしている。そこには、発展途上国での劣悪な労働環境あるいは自然環境の破壊といったダークサイドが存在する。このダークサイドをめぐる問題は、単なる道徳的・倫理的な問題ではなく、経済的な問題である。
こうした問題について、本講演は、経済学的な分析、国際法的な視点からの法規制の可能性について意欲的な仮説が示された。
講演を踏まえて、行政法的視点、労働法制の視点、経済法的視点等々をめぐって、参加者との間で予定時間を超えて活発な議論が行われた。
テーマ:韓国における仮釈放なしの終身刑導入をめぐる議論の状況
韓国における死刑問題に関心をもつ多くの研究者と実務家を集めて開催された。安氏は、30年にわたり、韓国が死刑制度を廃止せず、存置したままで、その執行のみを行わないという方法(いわゆるモラトリアム)をとってきたが、その過程で、死刑を正式に廃止した上で暫定措置として仮釈放のない終身刑制度を設けるという法改正が試みられたが、何度もそれが死刑廃止を反対する世論により妨げられてきたこと、近年では、死刑を存置したまま(つまり、執行を行わない状態)をそのままにした上で、仮釈放のない終身刑制度を設けようとする重罰化の主張も有力に展開されていることなど、きわめて興味深い韓国の現状について説明された。とはいえ、死刑の執行を再開すべきだとする意見は決して強くなく、執行の再開には至らないであろうという見込みを安氏は示された。質疑においては、死刑問題に関心をもち、とりわけ日本でも死刑の代替刑としての重無期刑を提案する日弁連の会員が多数参加していたことから、韓国における今後の死刑廃止の見込みや、これまで韓国で提案されてきた終身刑制度の内容などをめぐり、盛んな質問が出され、安氏はそれらに対して明快な答えを与えておられた。講演会は、当初の予定を越えて、2時間ほど行われたが、それは参加者の関心が強いことを示すものであった。
テーマ:韓国のオンラインプラットフォーム犯罪に対する刑事法的対応
サイバー犯罪やオンライン犯罪に関心をもつ一線の研究者と、警察関係者が参加し、質疑においては高いレベルの議論が行われた。講演後には、関心をもった警察関係者が残り、雑誌への投稿を求めるといった光景が見られ、それは、安氏の講演がそれだけ強い関心をもたれたことを示すものであった。安氏は、新しい観念である「オンラインプラットフォーム犯罪」の定義と概念内容、類型化からはじめられ、伝統的なサイバー犯罪の概念とも異なる、その幅広く、多彩な内容について説明された。次に、それを取引型犯罪、情報拡散型犯罪、人格侵害型性犯罪に分けてそれぞれの特色を説明し、さらに現状と動向について統計資料を用いて紹介された。韓国はこれらの犯罪の規制に積極的であり、ディープフェイクに対する処罰など、日本でも大いに参考になる規定を多く制定している。今後、安氏の論稿が比較法雑誌に紹介されれば、日本の議論にも大きな刺激と影響を与えることが予想される。
テーマ:AIにおけるプライバシー規制の試み
今回のセミナーは、アメリカ合衆国におけるPrivacyと技術に関する法学研究の第一人者Woodrow Hartzog教授をお迎えして、2025年4月21日に対面とオンラインを併用して開催された。当日は延べ20名近い参加者を得て、活発なディスカッションがなされたが、ここではその概要をご紹介する。
セミナーは約1時間の講演とその後のディスカッションからなっているが、Hartzog教授は最初に近時のAIの発達が社会に与えている状況について概観することから講演を始めた。
一方では明るい側面をもつAIであるが、他方では既に多くの企業がAIを利用して活動しており、その結果、現実的なプライバシー侵害リスク等の害悪が生じている。しかし、現行の法システムができることは決して多くない。これは、法システムが、(1)軽微な損害を無視する、(2)実体よりも手続を重視する、(3)技術的中立性を装う、といった特徴があることに起因する。そこで、新たなチャレンジが必要であるとの視点から、教授は、いくつかの具体的課題を提示して議論を展開する。
1つめは、AIが学習するために行う大規模なデータ取得(スクレイピング)の問題である。AIは、ウェブ上のデータをスクレイピングして学習に利用するが、これは個人情報取扱についての公平原則(fairness doctrine=情報主体の合理的期待を超えて個人情報を扱ってはならない)を侵害し、自己情報コントロールを失わせる。また、同意原則の形骸化、透明性の要請、利用目的の特定、二次利用の制限、必要最小限のデータ収集・利用、第三者提供、データセキュリティ等々の個人情報保護に係る全ての原則と衝突するのである。AIの学習目的の大規模データ収集は、これまで企業活動が遵守してきた個人情報保護の枠組みを破壊する傾向がある。この点に留意する必要があるのである。
2つめは、公表されている情報が本当に自由に使いうるものかという問題である。時に既に公表されている情報には、プライバシーの利益は認められないというものがあるが、これは、道徳的にも法的にも誤りである。公共空間にある監視カメラによって撮影された顔画像について、人の行動追跡に用いることに制限があるのと同様に、ウェブ上から取得されたデータを同じように用いるのにも制限が必要である。つまり、データ収集・利用の利益とプライバシーの利益の調整をいかに図るかを改めて考える必要があるのである。
そこで教授は、4つの原則に基づく調整を提案する。
(1) 害悪に対する合理的リスクの原則:スクレイピングされた個人情報の収集・利用・提供は、個人、不利な立場にあるグループ及び社会に「不合理な害悪リスク」をもたらすものであってはならない。
(2) 比例的利益の原則:スクレイピングされた個人情報の収集・利用・提供は、個人、不利な立場にあるグループ及び社会に、リスクを上回る十分な利益を提供し、スクレイパーへの利益と比例するか、またはそれを超えるものでなければならない。
(3) 手続原則:スクレイピングされた個人情報の用途を決定するプロセスは、公正、公開、説明責任、代表性、公平性、および熟慮を伴うものでなければならない。
(4) 保護原則:スクレイピングされたデータは、プライバシー法の下で他の個人データと同様の保護を受けるべきであり、特定の保護措置が実行不可能である場合を除き、その保護が適用されるべきである。
このようにして、Hartzog教授は、これまで見過ごされていた公共空間たるWebにあるデータをAIがスクレイピングする場合に生じる課題について、その問題構造を明らかにし、かつ、解決に向けた現実的な方向性を提案したのである。とりわけその提案に際して、教授が「我々にはreconciliationが必要である」とされたことは、極めて重要な指摘である。企業と個人だけでなく、国家と個人、AIと人、技術と法といった様々な間でのreconciliationを含意する教授のコンセプトに対して、調整、調和、和解等どのような訳語を与えるべきかは大変悩ましい問題であるが、今後益々重要となる問題提起と解決への方針示唆であったといえよう。
テーマ:ヨーロッパ人権裁判所による人権の保護
ヨーロッパ人権裁判所による人権の保護と題される本講演は、ヨーロッパ人権条約とヨーロッパ人権裁判所の成立の背景、同条約に規定される権利の内容と構造、そして同裁判所の法理論(とりわけ比例原則や評価の余地)や権限について包括的に解説するものである。本講演ではヨーロッパ人権条約が「生きている文書」としてヨーロッパ人権裁判所によって発展的・動態的に解釈されてきたことが称賛される一方、同裁判所が扱う事件件数が非常に多く課題も多いことが指摘された。参加した学部生から質問も出て、有意義な講演会となった。
テーマ:最高裁判所と「第4の権力(行政機関)」の終焉(The Supreme Court and the End of the "4th Branch"?)
Over the last several years the Supreme Court has been strengthening the President’s control over federal regulatory agencies in order to limit the autonomy of the so-called “4th Branch” of the U.S. government. This presentation discussed some of those recent cases as well as how far this movement to strengthen presidential control over the executive branch was likely to continue.
テーマ:国際人権裁判所・機関における環境・気候変動事例
健全な環境に対する権利と気候変動との闘いは、人権裁判所や人権機関も含めて、国際的なに大きな関心事となっている。しかし、この問題へのアプローチの仕方はフォーラムによって異なり、それぞれのシステムの法的特質が必然的に反映される。例えば、ヨーロッパ人権裁判所とヨーロッパ人権委員会は、条文上の規定がないにもかかわらず、環境の悪化から個人を保護することを実現させてきた。一方、米州人権裁判所は、個人の権利への悪影響に関わらず、環境に対する自律的な権利を発展させてきた。アフリカでは人及び人民の権利に関するアフリカ憲章における良好な環境への権利の明示的保護に恩恵を受けて同じ道を辿りつつある。これらの人権裁判所や人権機関における環境事例はますます拡大し、気候変動との闘いは、それら機関の勧告的・争訟的な機能を通じて、現在でも係争中である。本報告は、気候変動問題に関して拘束力のある判決を下したのはヨーロッパ人権裁判所だけであることに注目して、同判決に向けられた賞賛と批判の両方を分析するものである。本報告に対して、ロンドン大学クイーンメアリーのマルゴシア・フィッツモーリス教授からコメントをしていただいた。その後の質疑応答では、学内外の参加者から数多くの質問が出て、活発な議論がなされた。
テーマ:ヨーロッパ人権裁判所の判例における戦争
ヨーロッパ人権条約は、主に平時に適用されるよう起草されたが、緊急時の適用除外に関する同条約第15条に示されるように、戦争の可能性を無視するものではない。本報告の目的は、ヨーロッパ人権裁判所が戦争の状況下で人権侵害の疑いについて判決を下すことを求められる態様について概観し、このような状況において同裁判所が直面する諸課題に焦点を当てることである。本報告では、個人対国家および国家間の申請事例を通じて、戦争前、戦争中、戦争後にヨーロッパ人権裁判所がどのように介入し、被害者への正義の実現に貢献できるのかが取り上げられた。本報告は中央大学国際関係法研究会第103回定例研究会の第二報告として行われ、質疑応答では国際法研究者を中心とする同研究会の会員から多くの質問が出て、活発な議論がなされた。
テーマ:「弱い」政府による産業政策は可能か:合衆国が考えるべきこと(Industrial Policy in a "Weak" State: Implications for the U.S.)
The social science literature on industrial policy and East Asian economic development focused on the “strength” of national governments like Japan’s and South Korea’s, and argued that only “strong” states were able to carry out industrial policy effectively. The U.S. is now interested in trying to pursue a national industrial policy but I’m concerned that this is a mistake because our national government is too “weak.” We don’t have effective industrial policy bureaucracies and our political system is very open to special interest groups who will influence industrial policy to benefit them, rather than the overall national interest. If I’m correct then the U.S. should continue to pursue a more free-market approach to economic policy and keep the government’s role limited.
テーマ:行政機関による法解釈の司法審査(Judicial Review of Agency Legal Interpretations)
The Supreme Court recently overturned its 1984 Chevron decision, which established a framework under which judges were supposed to uphold agency interpretations of law so long as they were “reasonable.” This presentation discussed the history and functioning of the Chevron framework, and highlighted possibilities for the future now that Chevron has been overturned.
テーマ:国際的多国間主義の危機
まずマルキ准教授は多国間主義を次のように定義する。多国間主義とは「複数の国家を結びつけるような協力のモード及びプロセスの一形態」である。帝国主義、勢力均衡、同盟システムなどもまた、国際秩序を創り出すことを使命とするものであるが、多国間主義はそれらとは異なり、特定の国際秩序を約束する。それは覇権より主権平等を、差別より包摂を、強制より交渉を、単独主義より相互主義を、二国間主義より集団的体制を優先させる。マルキ准教授は多国間主義をこのように定義した上で、その歴史的変遷をたどり、現在の多国間主義の危機を「グローバルなアプローチの拒絶・反リベラリズム・反制限主義」と特徴づける。そして、この危機を克服する可能性を「国際アクターの重層的関係の構築」および「普遍的多国間主義に代わる地域的多国間主義の発展」に見出そうとする。
テーマ:イギリスにおけるエビデンスに基づく警察活動:その発展と課題
エビデンス・ベースト・ポリシングとは、効果的な犯罪予防活動を、科学的な根拠に基づいて実施するという警察政策の考え方ないし実践のことをいう。本講演は、英国において、研究者と警察が協力して、いかにしてエビデンス・ベースト・ポリシングを展開しているかについて紹介するものである。エビデンス・ベースト・ポリシングの基礎になるのは、問題志向型警察活動という、犯罪多発地点とそこで何故犯罪が多発するのかを特定し、多発の原因に対して効果のあると思われる対処方策を実施し、さらにその後で効果検証を行うというプロセスを経る犯罪予防のための警察活動である。日本の警察は、戦前から犯罪の原因に予防的に対処する活動は行ってきたところであるが、現在でも足りていないのは効果検証の部分である。その意味で、本講演は、今後における日本の警察活動の改善につながるものであると言える。
テーマ:EU法における種の絶滅防止対策(The De-Extinction of Species in European Union Law)
The ongoing Anthropocene debate opens up a new perspective on humanity’s potential role in improving nature by means of technological manipulation. Technologies such as climate engineering and de-extinction have been considered as innovative measures to face the climate crisis and biodiversity loss. In the human-dominated geological era these innovative technologies can be qualified as “anthropocenic technologies”. Indeed, the urgency, stressed by the concept of planetary boundaries, and the growing evidence that traditional measures have not been sufficient, may even demand the deployment of such interventions. On the one hand, the potential need of anthropocenic technologies for repairing planetary boundaries, triggers new challenges for contemporary Environmental Law and, in particular, for legal environmental principles, such as the precautionary principle. However, the prospect of anthropocenic technologies to manipulate the environment may necessitate the consideration of new principles, such as the “innovation principle”.
テーマ:国際法秩序における司法的紛争解決の多様性
マルキ准教授の報告要旨は次のとおりである。このテーマは、国際法の断片化というより大きなテーマの一要素である。国際紛争の司法的解決の多様性を下記のように位置づけている。冷戦終結後の1990年代、さまざまな紛争解決機関が新たに誕生した。それらは旧ユーゴスラビア刑事裁判所、ルワンダ刑事裁判所、WTO紛争解決機関、国際海洋法裁判所、多くの投資裁判所、地域的裁判所などである。それにともない、小田、ジェニングス、シュウェーベル、ギヨームなどの国際司法裁判所判事は、これらの紛争解決機関が同一の国際法規範に異なる評価を下すことにより、国際法の統一性が損なわれるのではないかという懸念を表明した。このような懸念を受けて、国連国際法委員会は「国際法の断片化から生じるリスク」という問題を審議することに決め、2000年に報告書を出している。→ « Risks ensuing Ensuing From Fragmentation of International Law », Report of the International Law Commission, U.N. Doc. A/55/10, 2000). ただ、国際法の断片化が現実の問題になることはほとんどなかったため、研究者たちのこの問題への関心は次第に薄れて行った。それでも、国際紛争解決機関の増加がこの時期に始まったことは事実である。それらの紛争解決機関(司法的・非司法的)の紛争解決方法はきわめて多様であるが、次の5つのカテゴリーに大別することができる。 1)国家間紛争(ICJ, ITLOS, WTO, Artibrations);2)個人・企業間紛争(国内裁判所、仲裁);3)混合的紛争(投資仲裁、地域的人権裁判所ー欧州人権裁判所、米州人権裁判所、アフリカ人権裁判所ー、国際行政裁判所ーUN行政裁判所、ILO 行政裁判所ー);4)刑事裁判所(国内裁判所、ICC、特別・ハイブリッド裁判所);5)非司法的方法(調停、仲介、斡旋、独自手続ーICANNー)。本報告では、これらの紛争解決機関を、おもに以下の方法および視点から、分析・考察した。1)これらの紛争解決機関が採用する紛争解決方法の紹介。2)とりわけ国家を当事者とする紛争解決機関の紛争解決方法の、次の観点からの分析・考察。①多様性の範囲。②多様性・分断が司法システムに及ぼす影響。③多様な中にも共通する要素。④そこに生起している問題・課題。これら①~③が本報告の中心になり、多くの質問が寄せられ、マルキ准教授からの回答がなされた。
- 1. the extend of diversity, which affects all aspects of litigation
- 2. the impact of this diversity, or fragmentation, on the overall judicial system
- 3. the elements that can nevertheless be considered as common
- 4. the major questions or challenges that arise, perhaps leading to points for our discussion.
テーマ:国際法における共通利益:概念と現行法
国際法におけるCommon good (以下CGと略称。この和訳としては公共財、共通善、共通利益がある)は、数世紀におよぶ学説上の議論の対象となり、さまざまな形態、内容、変遷を経てきた。ヴィトリアやスアレスの時代から学説はCGを扱っていたが、この概念を国際秩序と国際法の主要なメカニズムにとりこむことは、困難だった。マルキ准教授の本報告は、CGの概念がこれまでどのような概念として共有されてきたか、この概念がどのように国際法システムに包摂されてきたかを考察するものだった。その考察は、おもに次の2つの観点から行われた。 1)地球環境の保全という目標をもった国際環境法において、CGがどのような意味内容を与えられ、どのような概念として国際環境立法に採用され、紛争解決機関によりどのように解釈・適用されてきたか?2)CGという概念がインパクトをもつことを可能にする規範・手続は、どのようなものとして成立し、どのような成果をもたらしたか?
テーマ:国民参与裁判の現状と問題点
韓国の国民参与裁判は、日本の裁判員裁判と導入の時期が近く、国民の司法に対する信頼の確保を狙いの1つとする点などで共通する側面がある一方、裁判員裁判よりも対象事件が広い点や、被告人の申請を前提とする点、陪審員のみで有罪・無罪と量刑の判断を行う点、陪審の判断は勧告的効力を持つにとどまる点など、重要な相違も存在する。文助教授は、韓国の国民参与裁判の導入の経緯や、こうした裁判員裁判との制度の違いを指摘した上で、統計資料等をもとに、国民参与裁判の運用状況を紹介され、制度に存在する問題点と、講ずべき改善策について詳細な報告をなされた。運用状況に関しては、例えば、被告人の申請率が低く、申請をした場合でも裁判所の排除決定により国民参与裁判の実施に至らない場合が少なくないこと、陪審の判断とは異なる判決を裁判官が下す事例が割合は少ないながら存在すること、陪審員として参与した市民や裁判関係者からは制度に対して肯定的評価も多い反面、市民からは心理的・身体的疲労の大きさや法律用語の難解さ、裁判関係者からは業務負担の増大などの困難が述べられていることなどを指摘された。その上で、現行の制度の背後には、①陪審員の評決の法的効力の問題、②制度の活性化を阻害する複合的な要因、③陪審員の選定及び参与過程の限界、④特定犯罪類型における審理上の困難という、制度の実効性と持続可能性を脅かす構造的な問題が存在すると分析され、これらに対処し制度を実質的に発展させるために、①制度の活性化のための法・制度の改善、②充実した裁判の運用のための方策の実施、③陪審員の参与環境の改善及び保護の強化の各観点から、改善策を講ずべきとし、それぞれ具体的な内容を論じられた。質疑応答では、日本の裁判員裁判の課題との相違や上訴制度との関係など、活発な議論・意見交換が行われた。
テーマ:ヨーロッパ社会政策
本講義では、ヨーロッパ社会政策、つまり大まかにいってEU労働法の基本枠組みについて、学部生・院生向けに解説いただいた。内容的には、EUの社会政策領域での政策展開手段をハードローとソフトローの観点から整理してご解説いただくもので、その点でオーソドックスなものであったが、加えて、前提知識としてヨーロッパ各国における福祉国家感の多様性が語られ、この点において特徴的なものであった。政策に対する基本的な考え方の理念的な相違をご解説いただいたことで、聴講学生も自然と問いを発することができたようである。時間の関係で質疑を途中で打ち切らざるを得ないほど、活発に議論が交わされた。
テーマ:フリーランスの労働法・社会法上の保護:ドイツ/EUにおいて
本講演は、ドイツ・EUにおけるいわゆる「一人自営業者(solo self-employed)」の保護政策に関するものであった。ここでいう「一人自営業者」とは、わが国で近年しばしば用いられる用語でいうと、「フリーランス」を意味するものである。本講演は、第一に、ドイツおよびEUにおいてフリーランスの人々が置かれた経済的・社会的状況を、いくつかの実態調査に基づいて明らかにした。第二に、そうした実態を踏まえて、ドイツにおいて展開されている社会保険制度改革の議論が紹介された。そして第三に、労働法についてのEUレベルでの政策展開が紹介された。この点では特に、フリーランスに団結や団体交渉を可能にする、集団的労働法上の措置に焦点が置かれた。フリーランス保護は、我が国にも共通の政策課題でありながら、ドイツ・EUでの議論や実際の政策展開には独自の側面も認められ、大変興味深いものであった。その証左に、講演後の質疑応答も活発に行われ、講演会終了後も、講師への個別質問が続いた。
テーマ:租税手続におけるアルゴリズムの利用:発展と法治国上の課題
本セミナーにおいては、租税手続におけるアルゴリズムの利用に関して、これによって租税手続をより効率的、効果的及び均一的に行うことができること、その利用における世界的な状況、他方でアルゴリズムによる決定の誤りが違法な行政活動をもたらし、特定のグループに属する者に差別的に働くリスクがあること、伝統的な権利保護制度ではこのリスクに十分に対応できないこと等が説明された。その上で、アルゴリズムの利用に関する透明性の向上、品質基準及び認証手続の策定、人間による管理権限の強化、完全で集団的な権利保護制度の実現等が必要であることが議論された。
テーマ:グローバル・ミニマム課税(GloBE)
エングリッシュ教授のご講演においては、グローバル・ミニマム課税 (GloBE)に関して、これがミニマム課税によって多国籍企業の租税計画に対抗しようとするものであること、GloBEの主な設計上の特徴、これが最低15%の実効税率を達成しようとするものであること、GloBEを実施している国は48か国でその大半が先進工業国であり、米国、中国、インドが含まれていないこと、米国によるGloBEへの反対等が説明された。そして、結論として、GloBEは国際的な租税競争の抑制に大きく貢献することがなく、また高いコンプライアンスおよび執行のコストを要することから、批判的に見直されるべきであるとされた。質疑においては、米国トランプ政権の下での今後の展望や、欧州憲法との適合性に関して議論がされた。
テーマ:暗号資産に対する付加価値税/売上税の取扱い
本セミナーにおいては、暗号資産が発行形態や取引の仕組み、利用目的において多様であることから、従来の付加価値税概念を画一的に適用することには一定の限界があるとの基本的な問題意識が示された。個々の暗号資産取引について、どのような方法で発行され、どのような価値の移転が生じているのかを把握する必要があること、その検討は、財政中立性、最終消費課税、仕向地課税という付加価値税の基本原則に照らして行われるべきであるが、現行制度は必ずしもこれらの原則を十分に反映しておらず、税務執行上、コンプライアンス上の課題を内包していることが論じられた。さらに、EUの共通付加価値税制度(EU VAT)を参照しながら、暗号資産取引に適した課税のあり方を検討し、グローバル化・デジタル化の進展を踏まえた今後の制度的課題と対応の方向性を展望した。質疑応答では、暗号資産取引に係る課税関係についてEU制度との比較法的観点から意見交換が行われ、エングリッシュ教授からも予定時間を超えて丁寧な回答が示され、示唆に富む議論が展開され、本講演は盛会のうちに閉会した。
テーマ:韓国における伝統と法の交錯:宗中なる血縁団体を中心に
今回の講演会では、金教授から「韓国における伝統と法の交錯――宗中なる血縁団体を中心に」というテーマでお話があった。以下、講演内容を要約する。
「宗中(ゾンジュン)」とは、次のように定義される。「宗中は韓国においてだけ存在する親族団体として、特別な設立行為なく成立し、一定の子孫が完全になくなるまで存続する。自然発生的な団体であり、出生と同時に本人の意思にかかわらずに複数の段階の宗中に自然に属する」。
朝鮮時代には田畑等の耕作地の私有を認めたが、山林と川沢は共有という儒教理念上の原則に基づき、山地(林野)の私有は認められなかった。ところが、特定の山地に祖先のお墓を作り、その周りの山地を他人が侵犯できないように使用権(禁養権)を独占することによって次第に私有の形となり、その他の土地のように売買や相続の対象となっていった。これに対し、国は公有か私有かについて明白な立場を示さなかったため、「山訟」(山林の利用をめぐる争い)が頻発した。朝鮮後期に多発した山訟は、厳密にいえば排他的な所有権をめぐる紛争ではなく、祖先の墳墓を根拠に周辺の林野の禁養権を確保するためのものであった。
宗中は、「報先修睦」の目的を徹底的にするために、一定の共同財産を保有した。また、朝鮮時代に祖先の墳墓がある山野の禁養権は幅広く認められ、近代的な登記制度の導入後に近代的な所有権として確立した。その結果、宗中が有する土地の登記名義人がこれを売却することに伴う法律問題が発生した。これを受けて土地の所有者が宗中と登記名義人である代表者個人のどちらであるかが争われたが、日本統治下の朝鮮高等法院は、所有権は対内的には移転しないが、対外的には移転するという信託的譲渡論を採用した。
戦後、韓国大法院は、宗中所有財産の「名義信託」を受けた者が第三者に不動産を譲渡した場合、譲受人は完全な所有権を取得する旨の判決を下した。その後、宗中の構成員に既婚女性が含まれるか、宗中に関する訴訟は必要的共同訴訟か、誰が宗中の代表者となれるか等の法的問題が生じており、いずれも大法院で判断が示されている。
金教授は、以上のような歴史的な展開をふまえ、「近代的なあるいは西洋法的なものとして落ち着くためにはそれなりに時間がかかるといった好例が宗中である」との言葉で講演を締めくくった。
講演後は、フロアから日本の入会(いりあい)との相違点等を含めて、活発な質疑応答がなされ、盛会のうち閉会した。
テーマ:国連恣意的拘禁作業部会の現在と日本
まず初めにユドキウスカ・ガンナ氏より国連恣意的拘禁作業部会(WGAD)の役割や手続に関する報告が行われた。WGADの設立経緯、活動方法、審査の基礎となる法的枠組といった概要について説明が行われた後、WGADにおける「拷問」とは何か、またいつ「拷問」は「恣意的」になるのかについて解説された。その上で、どのようにして通報が可能かが示された。次にWGADによる勧告を基礎に国内裁判を行っている弁護士髙田俊亮氏の報告が行われた。具体的には、WGADでの通報を行った背景、そこで出された勧告の具体的内容、またその勧告に依拠しながら国内裁判を提起した経緯、さらには2025年6月17日に東京地方裁判所で出された判決について報告された。それを受けて、ユドキウスカ・ガンナ氏から今後のアドバイスを含めたコメントが行われた。その後、フロアからの質問を受け付け、活発な議論が行われた。
テーマ:抽象的危険犯の限定的解釈の方法をめぐって:台湾最高裁の最近の判例を中心に
2025年11月27日(木)午後4時から、中央大学駿河台キャンパス1620号室において、台湾成功大学法律学系教授古承宗教授をお招きし、「抽象的危険犯の限定的解釈の方法をめぐって---台湾最高裁の最近の判例を中心に」と題するテーマで講演会が実施された。講演会では、古教授から、台湾の最高裁判所の最近の判例を素材として、台湾における抽象的危険犯の現状とこれに対する解釈が紹介され、その上で、限定基準としての「適性性」、すなわち「法益侵害を生じさせるに足りる性質」を用いることで、とかく広範囲に及びがちな抽象的危険犯の成立範囲を限定する解釈手法を取り上げて、古教授の私見が詳細に展開された。その後、会場並びに台湾及びわが国らのオンライン出席者との間で、現代社会における抽象的危険犯の在り方、わが国ではあまり紹介・検討されていない適性犯の基準と内実、適用から得られる結論等をめぐって活発な議論が繰り広げられた。講演と質疑応答を含めて2時間に及ぶ講演会となり、わが国の第一線の研究者たちが参加し、きわめて有益な講演会となった。古教授の講演は、比較法雑誌に掲載されてより広く読まれることにより、日本の議論にも影響力を持つことが予想される。
テーマ:EU司法裁判所判例における法の支配
法の支配の要素として「EU機関による権原行使が恣意的にではなく適法になされていること」「独立した組織によりEU機関の権限行使がチェックされていること」「EU法が平等に適用されていること」の3つを挙げ、それぞれがEUにおいてどのように実施されているか、そこにどのような課題があるかを、豊富なEU司法裁判所の判例を通じて考察するものだった。講演後、講演者と参加学生との間で活発な質疑応答が行われた。
テーマ:EUからみたエネルギー憲章条約:気候変動への対処と投資保護のはざまで
エネルギー憲章条約が化石燃料への投資保護を規定していることから、気候変動への対処が重視されるにともない、化石燃料への投資保護と気候変動への対処が相容れないとの批判が高まり、EUは同条約がから脱退したが、加盟国は残留する国と脱退する国とに分かれたため、そこに複雑な法的問題が生じた。報告内容は、この法的問題の発生経緯とそれへの対処を考察するという興味深いものだった。報告後、報告者と参加者との間で活発な質疑応答がなされた。
テーマ:自律走行車の商用化時代における刑事法の役割と対応
今回、中央大学と韓国国立警察大学の全学協定締結後、初めての共同国際学術セミナーとして、「ポストフィジカル時代における刑事法の論点」と題するシンポジウムを開催しました。午前中は両大学の大学院生を中心とする若手研究者のセッション、午後は両国から2名ずつの報告者と討論者を置き、それぞれ有意義な議論を行うことができました。
日本比較法研究所において招聘した講演者である李東熹先生からは、「自律走行車の商用化時代における刑事法の役割と対応」というタイトルの下、自動運転車のレベル(一般的には0~5で分類)に応じて、運転者が刑事責任を負うのか、あるいは管理者や開発者が刑事責任を負うのかなど、緻密なご検討内容をご報告いただきました。討論者としては、新潟大学の根津洸希先生よりコメントいただき、とりわけ、技術の発展や自動運転車の普及(可能性)に鑑みて、誰かに「刑事責任」を問うべきなのかという観点からも議論がなされました。また、閉会式では、国際情報学部・平野晋先生からも、民事不法行為法の観点からの講評があり、非常に学際的な場となりました。