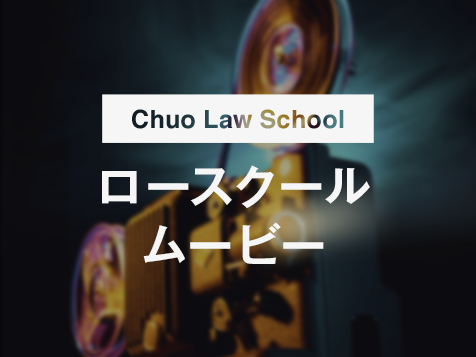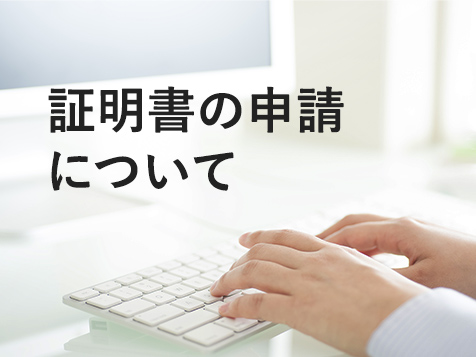ロースクール
法務研究科長挨拶

宮下 修一 教授・法務研究科長
「白門」の先にある未来への絶え間ない挑戦――中央大学法科大学院へのいざない
「法は社会を映す鏡」――法を学んでいると、こんな言葉を聞くことがあります。
かつての民法では、親が亡くなった場合、親を同じくする子であっても、法律上の結婚をしていない親の子である「非嫡出子」の相続分は、法律上の結婚をしている親から生まれた「嫡出子」の半分であると規定されていました。これが憲法14条の「法の下の平等」に反するとして何度も違憲訴訟が提起されましたが、2000年・2003年・2009年に出された最高裁判決では、反対意見や補足意見があるものの、いずれも合憲の判断が下されました。
ところが、2013年に出された最高裁判決では、両者を区別する合理的根拠は失われており、上記の規定は憲法14条に違反し無効であると判示されました。これを受けて、2013年末に、両者の相続分を同一にすることを内容とする民法の改正法が成立しています。
民法に上記の規定が定められた当時は、その内容に疑問をもつ人は少なかったでしょう。しかし、時代が進み、社会における家族に関する考え方が変わり、子どもを尊重しその権利を保障すべきであるという潮流が強まる中で、最高裁は従来の判例を変更することになりました。換言すれば、変更された最高裁判例は、まさに社会の中にある人々の意識の変化を映し出した鏡であるといえるでしょう。
中央大学法科大学院の源流は、今から140年前に創立された英吉利法律学校にさかのぼります。学校を創立した18名の法律家たちは、新聞に出した設置広告に「實地應用ノ素ヲ養フ(実地応用の素を養う)」という理念を掲げました。イギリスは、アメリカと並んで、判例を積み重ねて法を生み出していく判例法の国であり、法の適用のあり方を知るためには、過去の判例を丁寧に検証し、実際にどのような処理がなされているのかを知る必要があります。実際の事件における経験や判断(実地)を学ぶことこそが、新たな課題に挑戦(応用)するための力(素)を身につける(養う)ことにつながる――建学の精神にもなっているこの言葉は、まさに、単に机上で法の知識を得るだけではなく、社会を映す鏡である判例に接し、実践的に法を体得することが、法を学ぶうえで必要不可欠であることを如実に物語っています。
中央大学法科大学院は、これまで培ってきた「法科の中央」の伝統を受け継ぎながら、絶え間なく続く法曹養成制度の変革という現実を前にして、新たな挑戦を続けてきました。
学部・大学院を通した5年一貫教育を行ういわゆる「3+2」制度、さらに司法試験の在学中受験の導入を受けて、学生目線で授業カリキュラムを全面的に見直し、研究者教員と実務家教員が密に連携しながら、司法試験受験へ向けたきめ細かな対応を行っています。授業外でも、本学の修了生である若手弁護士が実務講師としてゼミを実施したり相談を受けたりする機会を設け、さらに、中央大学の課外講座である法務研修プログラムを同じキャンパス内で受講できるようにするなど、学修サポート体制も充実しています。
また、全国に5,000人以上いる中央大学法曹会員とタイアップしたエクスターンシップの実施や、多様な進路選択を可能とするキャリア支援体制の強化など、司法試験合格後の進路を見据えた取組みにも力を入れています。
さらに、全国11大学の法律系学部(中央大学法学部を含む)と連携協定を締結し、地方を含めて法曹の裾野を広げるための挑戦も続けています。
中央大学の別名は、「白門」です。時代とともに歩み、常に実務の最前線に立ってきた白門の門戸を叩いてみませんか。その先には、法を通して社会と向き合う未来が広がっています。ともに、その未来を切り拓いていきましょう。