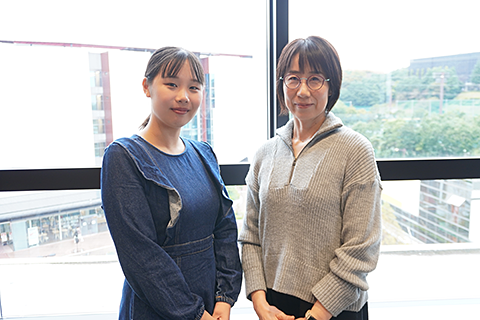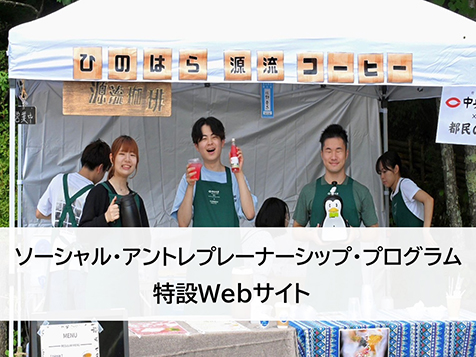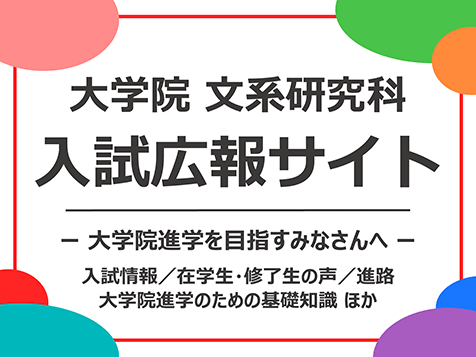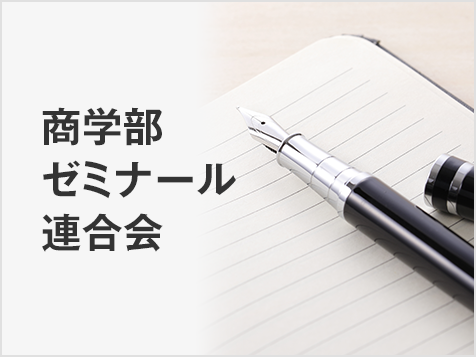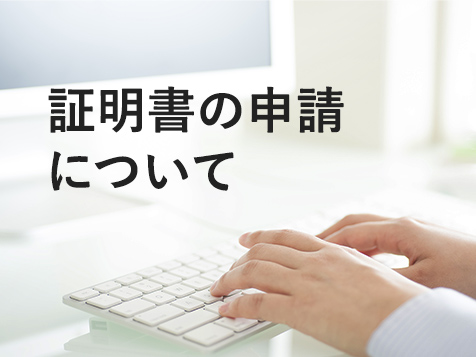商学部
Vol.2 酒井 麻衣子 准教授
―Profile―
酒井 麻衣子

京都大学教育学部教育心理学科Cコースを卒業後、法政大学社会科学研究科経営学専攻マーケティングコースにて修士号、法政大学経営学研究科経営学専攻にて博士号を取得。
その後、他大学での勤務を経て、2017年4月より中央大学商学部に着任。
研究分野はサービス・マーケティングや消費者心理。
出身地:兵庫県宝塚市
趣味:ピアノ、絵を描く・何か作る、観葉植物のお世話
好きな本や映画: 特定のこだわりなし
好きな休日の過ごし方:家族と過ごす
尊敬する人:他者の良いところに自然に目を向けられる人、いつも笑顔で穏やかな人
小さい頃の夢:美術の先生
―Interview―

ここからは前回(Vol.1)に引き続き、商学部生の平松さんとともに、インタビューをしていこうと思います。
平松さん:こんにちは!本日はよろしくお願いします。
酒井先生:こんにちは!こちらこそ、よろしくお願いします。
平松さん:それでは早速ですが、インタビューをはじめさせていただきます!
出身
平松さん:ご出身はどちらですか?
酒井先生:兵庫県宝塚市、「宝塚歌劇団」があるところです。幼いころは西宮市にいましたが、転居してきてからは社会人1年目まで住んでいました。
趣味
平松さん:趣味はありますか?
酒井先生: なにかに没頭するタイプではないのですが、昔からピアノをやっていて、数年前に娘にピアノに習わせるのをきっかけに、また弾き始めました(今は忙しくて習えていませんが・・・)。
あとは、中高大と美術部に所属していたので、絵を描いたり、ものを作ったりするのが好きです。
また最近は、観葉植物を育てています。育てていると芽が出てきて、かわいいな~、生きているんだな~と思い、霧吹きをかけるのが日課です。
平松さん:私の母もちょうどいま観葉植物を育てることにハマっていて(笑)最近では、植物に名前を付けたりしてみたり(笑)
好きな映画や音楽

平松さん:好きな映画や音楽はありますか?
酒井先生:なにかこれ!というものはないんです。だから、せめて流行りのものは観てみたり、ネットニュースでチェックしたものを観ようとするんですが、観る時間がなくて・・・。そして、気づいたころには、流行りも去っているし、自分も忘れているし・・・。(笑)
平松さん:そうなんですね(笑)かなり忙しいのですか?
酒井先生:そうですね。というのも、プライベートと仕事を切り分けづらい職業なんです。
本当は意識的に「この日は、好きなことをする!」とスケジュールすればいいのですが、目の前のことに追われてしまい、うまく切り分けができていません。
平松さん:私が想像していたよりお忙しいようでびっくりしています。
酒井先生:そうですね。学生さんから見ると、大学教員は「授業やっていないときは暇だろう」とか「夏休みなにしてるんだ?」とか思われているかと思うんですけど、実は忙しくしているんです。
でもそれは、例えば会社員のような、ある程度決められた勤務時間の中の“忙しさ”とは違うんです。自分の基準で探究を続ける研究活動には終わりがなく、仕事に区切りがつけにくいんですね。
好きな休日の過ごし方
平松さん:休日はどのように過ごされているんですか?
酒井先生:先ほどお話した通り、休日という考え方があまりないです。そうは言っても家族がいるので、世の中でいう休日には、やはり家族と過ごす時間が増えます。日曜日の夕食は家族で楽しめるイベント料理をします。あとは、今はとくに、子どもの入っているスポーツクラブの役員やら試合引率やらに時間を費やしています。(笑)でも、仕事は忙しいものの自身で仕事をコントロールできるからこそ、家族との時間も確保できているように感じます。
尊敬する人
平松さん:先生の考える尊敬する人はどんな人ですか?
酒井先生:自身がなにかに固執するタイプではないので、「この人!」という人はいないのですが、いままで会ってきた人のなかで尊敬できる人は、他者の良いところに自然に目を向けられる人や、いつも笑顔で穏やかな人です。
小さい頃の夢
平松さん:小さい頃の夢は?
酒井先生:小学校の卒業文集で、美術の先生か、(「起業」とかはもちろん知らないのに)会社員ではなく自分で仕事をしたい、と書いた覚えがあります。みなさんが一度は夢見る職業「ケーキ屋さんやお花屋さん」は一度も考えなかったです(笑)
平松さん:小さい頃からしっかりされていたのですね!(笑)
酒井先生の幼少期から学生時代について教えてください
幼少期

小学1年生、自宅近くにて
酒井先生:活発な方で、低学年のときは、男の子を引き連れて近所を駆け回って、公園で遊んだり、空き地で探泥(タンドロ)したり。高学年では女子とゴム飛びとか縄跳びとかして、いつも外で遊んでました。
中高生

中学2年生、親戚の集まりにて
酒井先生:地元から離れた中高一貫校に進学しました。習い事のピアノを続けつつ、美術部、バスケットボール部、吹奏楽部(クラリネット)など、いろんな活動に取り組みました。何でも自由に任せてもらえる学校だったので、運動会も文化祭も全力でやって、とても充実した日々でした。一方で、スポーツ万能で頭が良くて人柄もよい、みたいに天に何物も与えられた別次元のような人が結構いたりして、何においても自分よりうまくできる人たちが必ずいたので、世の中というものを少し達観したのもこの時期です。他者と比べても仕方ない、自分の軸で自分を判断しようと思えるようになったのは、そのおかげかもしれません。同時に、何かをやりたければ自分で道を切り開けばいい、という姿勢も身に付いたと思います。
大学生

恩師の坂野登先生と研究室にて
酒井先生:最初は歴史や考古学に興味があり、文学部に進みました。でも歴史の真実に向き合うと言うよりも、「学説」や「権威」に左右される部分もある学問の一面を知り、学ぶ目標を失いかけました。その際、1年生の一般教養で履修していた精神医学という分野に強い関心を持ち、いろいろ調べたところ、臨床心理学という近い分野を教育学部で学べることが分かり、転学部しました。その後、心理学全般と臨床心理学の学びに没頭しました。大学院への進学を検討しましたが、社会に出る経験のないまま、他者の生き様に深くかかわる臨床心理で身を立てることに不安を感じ、1年卒業を遅らせて一般企業への就職を選びました。総じて、迷いながらも常に目標を定めていろいろ試し、その時の自分が納得できる道を選んできたと思います。また、大学生から一人暮らしをさせてもらったので、自立に向けての準備もできた時期でした。
研究・専門分野について
なぜ研究者の道へ進まれたのですか。
酒井先生:実は「研究者になろう」と目指したことはなく、不思議な縁でこうなりました。最初の企業では心理学の知識を活かして適性検査を開発する仕事に携わり、そこでデータ分析の面白さを知りました。その後は、データ分析で身を立てるべく、前向きな転職をしていきました。2つ目の統計解析ソフトの開発企業で、顧客サポートや製品のローカライズに携わる中で、データ分析に詳しくなることができました。そのソフトの利用企業から声が掛かって転職し、ECサイトのレコメンドシステムの背後で動く予測モデルの開発と実装や、顧客データの分析結果に基づいたマーケティングに携わりました。その企業にいるときに、前職で知り合っていた出版社の方からお声がけいただき、データ分析に関する書籍を出版させてもらいました。勉強のため、大学が主催する企業人向けのマーケティング・データ分析のセミナーを受けていたら、書籍を出版していたこともあり、講師くらい詳しいよねと言われて、その後は講師側として参加するようになりました。その間に、4つ目の企業に転職し、顧客データを分析するためのシステム構築を担う企業でコンサルタントとして働きながら、社会人大学院に通うようになっていました。修士2年目のとき、上述の大学から、修士が終わったら大学教員になって学生を育てないかと声をかけていただきました。考えてもいなかった大学教員という職業に迷いながらも、データ分析のできる人材が不足している実業界の現状を変えられるかなと、その道に飛び込んでみることにしました。その後、最初の大学に勤めている間に研究を進め、博士号を取得しました。さらに、教育だけでなく研究にもより力を入れたいと思うようになり、中央大学に移り、現在8年目になります。
長い転職履歴となってしまいましたが、常に、このような自分になりたい、と前向きに目標に向かって努力している途中に幸運なご縁をいただき、自然と今に至ったという感覚です。
酒井先生が商学やマーケティングに興味を持たれたきっかけを教えてください。
酒井先生:3つ目の職が家電量販店のCRM(顧客関係管理)部門だったのですが、そこで顧客マーケティングのデータ分析の実務に初めて関わったことがきっかけです。それまでほとんど知識のなかったマーケティングについて理解を深めたいと、働きながら社会人大学院(MBA)に進学しました。もともと大学生の時に心理学を学んでいたので、消費者の心理に関わるテーマに惹かれ、今もサービスの継続利用に関わる消費者行動を研究しています。
授業について
現在教えている授業(ゼミを含む)について教えてください。

酒井先生:最近、『草のみどり』 (346号)にゼミ紹介の記事を載せていただいたので、ゼミ活動の詳細についてはこちら(496KB)をご参照ください。そのほかの担当授業は、マーケティング・リサーチと、サービス・マーケティングです。マーケティング・リサーチでは、基本的なデータ分析のフレームワークと技術を学ぶとともに、実業界でよく行われる、アンケートによる定量調査の企画、実施、分析、マーケティング施策の提案までを行う演習に取り組み、実践的な力を身に付けています。サービス・マーケティングでは、モノのマーケティングとの違いを理解しながら、サービスならではのマーケティング戦略について、身近な実例を分析しながら学んでいます。サービス・マーケティングが開講される前は、マーケティング入門も担当していました。
平松さん:授業ではどんな試験を課しているのですか?
酒井先生:実はあまり筆記テストは好きでないので、できるだけレポート課題の配点を多くしています。というのも、筆記テストの対策として知識を覚えてもすぐ忘れてしまうし、そもそもネットで調べたらすぐわかってしまいますよね。なので、暗記をさせるのではなく、物事について自身で考察することに重きを置いています。
平松さん:システムとして、核心的に学ぶ機会が備わっているのですね。履修生からの反応はどうですか?
酒井先生:アンケートなどをすると、「こんなにしっかり学んだのは初めて」などと言ってもらえることもあり、非常に嬉しいと感じます。その分、授業をする側、受ける側も大変なのですが・・・(笑)
平松さん:そうなんですね!私も再来年、先生の授業を受けてみたいと思います。
大学でマーケティングを学ぶ意味とはなんでしょうか。

酒井先生:マーケティングは生きた学問です。実業界での実践の方が常に進化していて、その成功や失敗から法則を見出し、それを説明できる理論化や体系化を行い、アップデートしていくのが、学問としてのマーケティングの役割であると思います。社会に出れば、マーケティングがあらゆる場面で実践されていますが、その中に入りこんでしまうと、目の前の戦術や成果に捉われがちになります。より俯瞰した視点からマーケティングを捉え、トライアンドエラーのさなかでも、きちんとした方向性をもって実践できるようになることが、大学でマーケティングを学ぶ意味だと思います。
商学部教員である酒井先生の考える「ビジネス」とは何ですか。
酒井先生:「志」を実現しつづけるための仕組み、だと考えます。お金が儲かることも大事だし、起業して成功すれば格好いいかもしれませんが、それだけは、ビジネスではないと感じます。誰かのため、何かのためになりたいという「志」がまずあり、それを持続的に実現する手段が、ビジネスなのではないでしょうか。
最後に在学生の皆さんへメッセージをお願いします。
酒井先生:大学時代は、長い人生の中でたったの数年ではありますが、後にも先にも、二度とは得られない貴重な時間です。大人としての意思と自由をもちながらも、まだ誰かに守られている存在だからです。正解をあらかじめ探して、周りに認められることや、間違わないことを選択することは、これから先いつでもできます。ただ純粋に、自分、他者、そして社会と向き合うことができるのは、おそらく今だけです。無意識に自分にはめているかもしれない枠を、ほんの少し、はみ出してみてください。もし道に迷ったときは、思い切り考え、できることをし尽くし、その時点でもっとも納得できる道を選択してください。進む前に分かる「失敗しない道」なんて存在しません。進んだ先で迷いながらも努力を続けていれば、振り返ったときに、必ずそれが、あなた自身が形づくった「正解」になっています。
やらない安心より、やる勇気。大切にしてほしいと思います。
平松さん:ありがとうございました。