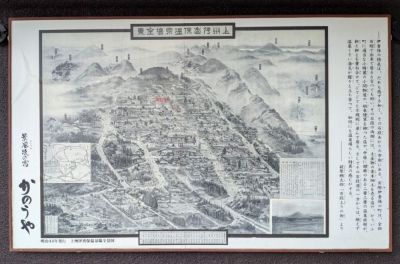商学部の高次裕 准教授が担当する科目の学生が2025年9月9日(火)に伊香保温泉街(群馬県渋川市)を訪れ見学調査を行いました。(9月8日~10日まで2泊3日の合同合宿が行われ、本見学調査はその2日目に実施されました)
調査内容について
ベルツは明治期のいわゆるお雇い外国人の一人で、1876年(明治9年)27歳のときに明治政府に招聘され来日、東京帝国大学教授として医学を教えました。その講義は森鴎外も聴いていました(7月に実施した森鴎外記念館への見学調査の様子はこちら)。夏目漱石の『三四郎』にもベルツの名が出てきます。「二人はベルツの銅像の前から枳殻寺[からたちでら]の横を電車の通りへ出た。銅像の前で、この銅像はどうですかと聞かれて三四郎はまた弱った」。ベルツは日本各地の温泉地を訪れ、伊香保にも滞在しました。各地の温泉を分析し、『日本鉱泉論』(1880年)を執筆して政府に助言もし、伊香保の発展に寄与しました。『ベルツの日記』にも伊香保への言及が見られます。
[一八八〇年]八月五日——
人力車で朝の七時、前橋出発。九時、渋川(三里)。徒歩で伊香保へ。例によって大いに歓待された。[…]
伊香保の鉱泉は非常に薄く、少量の鉄分に、若干の食塩とソーダを含んでいる。湯の温度は四十六度で、長時間の持続には適しない[…]。自分は今年、日本の温泉の状態と、これをいかに改善すべきやに関して、内務省に提出した建白書中に述べておいたように、一種の改革者として伊香保に現れたわけである。内務省ではこの建白書に対して「大いに感謝」し、これを翻訳させ、印刷の上、頒布せしめたのであるが、残念なことに、これらの改革を実施する資力がない。ところで自分は、ちょうど伊香保を一例にとり、必要な改善の詳細を述べておいたから、土地の人たちが自力でできることや、しようと思っていることを、実地に試してみるつもりだ。
八月十七日(伊香保)
過去二週間にはいろいろと不満もあったが、また満足も少なくなかった。なかんずく、自分の計画が伊香保で確実な基礎を見出したことがそれだ。まず源泉湯元への道路を手入れせねばならないし、つぎに蒸湯と榛名湖方面へ通じる正常の道路に取りかからねばならない。[…]
『ベルツの日記』(岩波文庫)
このように伊香保とベルツは非常に深い関係にあり、伊香保温泉の湯元(伊香保温泉第二号源泉噴出口)付近にはベルツ像があります。本見学調査ではベルツの足跡を実地に確かめ知見を深めました。事前に伊香保温泉街の歴史とベルツについてある程度把握したうえで、有名な石段街を中心に温泉街の様子を見学し、ベルツが「源泉湯元への道路を手入れせねばならない」とした道を歩きました。そして途中にある飲泉所でベルツも飲んだであろう伊香保の温泉を実際に試飲し(「鉄の味がする」と学生たち)、源泉噴出口まで行きベルツ像を見学しました。温泉街だけでなく、『日記』で言及されている榛名湖へも足を延ばしました。



伊香保温泉飲泉所
見学調査後の振り返りでは学生たちから「その土地の歴史を踏まえながら見て回ること」や「今回のように目的意識を持って訪れる」ことで「普段なんとなく観光地を訪れるのとは見えてくるものが違うと感じた」という意見が出ました。実地に見学調査をすることの重要性を実感することができた良い機会となりました。また、明治期に日本を訪れたドイツ人が日本の有名な温泉地に大きな影響を与えているという日独交流史の観点からも知見を深めることができました。