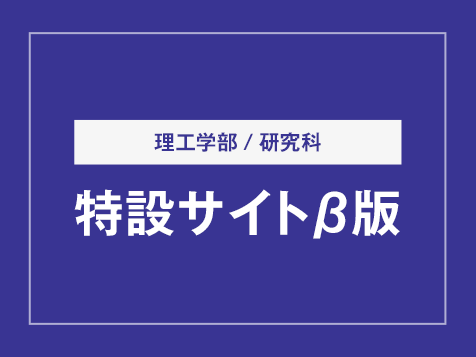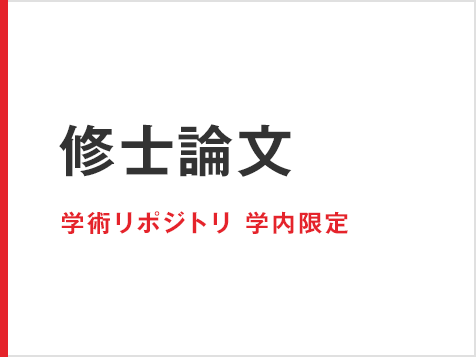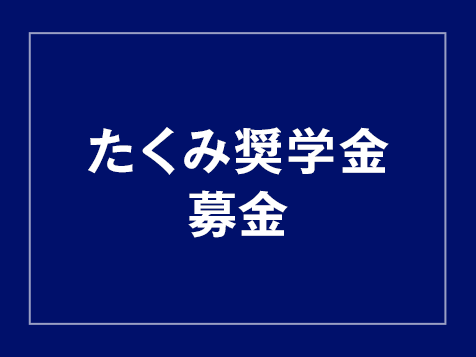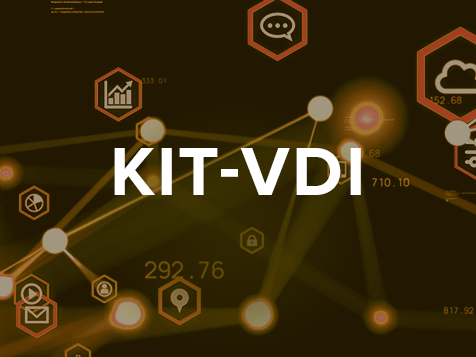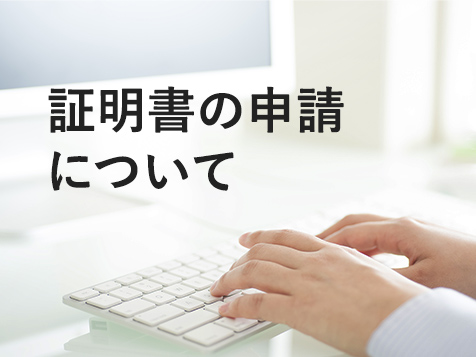理工学研究科
三つの方針
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
理工学研究科において養成する人材像
理工学研究科では、建学の精神「實地應用ノ素ヲ養フ」に基づく「実学重視」教育の立場から、理学、工学及びその関連諸分野に関する理論並びに諸現象にかかる高い研究能力と広く豊かな学識を有し、専攻分野における教育研究活動その他の高度の専門性を必要とする業務を遂行することのできる人材を養成します。その意味するところは、科学技術分野の諸課題、並びに現代社会が抱える複雑な課題に対して、新しい視点を持って自ら取り組むべき問題を明確化し、その問題を多面的に考察し、最適な解決策を見出すこと、そしてそのような能力の向上に向けて継続的に努力する姿勢を持つことのできる人材の養成です。また、産業界で働く社会人に対しては、各専攻が関与する専門分野の学習・研究能力向上の機会を提供することで、より高レベルの技術課題解決能力を有する人材を養成します。
理工学研究科を修了するために身に付けるべき知識・能力
理工学研究科では、所定の教育課程を修め、次の8つの知識・能力を獲得した人材に対し、修士(理学、工学)、博士(理学、工学)の学位を授与します。
1.コミュニケーション力:様々な説明の方法や手段を駆使し、意見の異なる相手との相互理解を得ることができる。
2.問題解決力:新しい視点を持って自ら問題を発見し、最善の解決策を選択し、計画的に実行できる。その結果を多面的に検証し、計画の見直しや次の計画に反映することができる。
3.知識獲得力:継続的に深く広く情報収集に努め、取捨選択した上で、知識やノウハウを修得し、関連付け、他者が思いつかない形で活用することができる。
4.組織的行動能力:チーム、組織の目標を達成するために何をすべきか、関係者の利害を複数の視点から幅広く考慮したうえで適切な判断を下し、自ら進んで行動を起こすだけでなく、目指すべき方向性を示し、他を導くことができる。
5.創造力:知的好奇心を発揮して様々な専門内外のことに関心をもち、それらから着想を得て科学技術の発達に貢献するような独自のアイディアを発想することができる。その際、関連法令を遵守し、倫理観を持って技術者が社会に対して負っている責任を果たすことができる。
6.自己実現力:自らを高めるため、常に新しい目標を探しており、見つけるとその達成のために最短の道筋を考えてそれをたどるために努力する。失敗してもあきらめず、繰り返し挑戦する。
7.多様性創発力:多様性(文化・習慣・価値観等)の相互理解を得て適切に対応しつつ、自分が何を望むか、まわりが自分に何を望んでいるのかを総合的に判断し、行動できる。加えて、複数人の協同により、相乗効果を生み出すことができる。
8.専門性:専攻に応じた専門性を身に付けている。(詳細は、専攻・課程ごとに別途定める)
教育課程の編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
理工学研究科において展開するカリキュラムの基本方針・構成
理工学研究科では、学位授与の方針に掲げる知識・能力を修了時点で確実に身につけられるよう、論文研修科目、主専攻科目、共通科目、副専攻科目、自由科目を設置します。
論文研修科目:博士課程前期課程における論文研修では、教員の助言に基づいて、自立した研究に取り組みます。博士課程後期課程における特殊論文研修では、教員の助言を得つつ、自立した研究を実践します。高度な研究への取り組みを通して、課題の発見から解決方法の提案と検証、情報の発信までを深く体得し、コミュニケーション力、問題解決力、知識獲得力、組織的行動能力、創造力、自己実現力、多様性創発力、専門性を総合的に、かつ高いレベルで身につけます。
主専攻科目:各専攻にはそれぞれの専門分野に特化した科目を設置し、コミュニケーション力、問題解決力、知識獲得力、組織的行動能力、創造力、自己実現力、専門性を身につけます。
共通科目:幅広い見識を身につけるために設置し、コミュニケーション力、問題解決力、知識獲得力、創造力、自己実現力、多様性創発力を身につけます。
副専攻科目:学際的融合分野の学習のために設置し、コミュニケーション力、問題解決力、知識獲得力、組織的行動能力、創造力、自己実現力、多様性創発力、専門性を身につけます。
自由科目:異なる専門分野を専攻する際の基礎的知識を充実させるために設置し、コミュニケーション力、問題解決力、知識獲得力、創造力を身につけます。
なお、一定の範囲内で、本学内の他専攻科目、他研究科科目、オープン・ドメイン科目を履修可能とします。さらに単位互換協定を結んでいる他大学院の授業科目や留学等による認定単位の制度を設けます。
カリキュラムの体系性
博士課程前期課程においては、主専攻科目では修了生が科学技術の第一線で活躍する力を身につけることを目指し、高い研究能力と広く豊かな学識を教授できるカリキュラムを展開しています。講義科目では高度な専門知識の獲得と問題解決力の伸長を目的に、専門分野について最新の知識を多角的に学ぶことができます。これらの知識をもとに、論文研修は、高度な研究への取り組みを通して、課題の発見から解決方法の提案と検証、情報の発信までを深く体得し、ディプロマ・ポリシーに掲げる8つの知識・能力を総合的に、かつ高いレベルで身につけます。
さらに、副専攻では、複数の専攻にまたがる領域の講義科目と特別演習科目を通じて広く豊かな学識と、その応用に資する素養を涵養することができます。異なる専門分野を専攻する際に必要となる基礎知識については、自由科目の履修により充実を図ることができます。
博士課程後期課程においては、研究倫理・特論(必修)およびジョブ型インターンシップ(選択)のコースワーク科目を設置し、リサーチワーク科目である特殊論文研修と組み合わせることにより、社会のニーズに対応した高度な研究能力を身につけます。
入学者受け入れの方針(アドミッション・ポリシー)
理工学研究科の求める人材
理工学研究科は、将来の科学技術基盤を担う研究者・技術者の養成をすべく、基礎に重点を置きながらも最先端の理論と技術を修得するための教育を提供しています。また、実学を念頭におき、産学連携教育、産学連携研究を通じて、価値観の多様化、研究領域の多様化を考慮した創造的視点からの問題解決能力の育成、早期に社会的貢献ができる人材を輩出することを目標としています。そのため、次のような学生を求めています。
- 国際的第一線で活躍できる研究者・技術者となりたい人
- 広い視野と学部で修得した基礎学力の充実を深めて、より高度な専門知識と研究遂行能力を修得したい人
- 深く広い思考力と問題発見・定式化能力に基づく先端的研究能力を向上させるための理論と応用力を修得したい人
- 高信頼性を保持した、安全で豊潤な社会情報基盤を築くことに関心のある人
- 理工学の分野だけでなく、社会科学・人文科学との連携も視野に入れた境界領域の学問分野に関心のある人
以上に基づき、理工学研究科では次のような知識・能力等を備えた学生を多様な選抜方法によって受け入れます。
- 博士課程前期課程においては大学理工系学部卒業程度の基礎学力を持ち、専門分野における知識と応用力を備えている。(知識・技能)
- 博士課程後期課程においては博士課程前期課程修了程度の基礎学力を持ち、それを発展させる能力を有している。(知識・技能)
- 学部卒業水準以上のコミュニケーション力、問題解決力、知識獲得力、組織的行動能力、創造力、自己実現力、多様性創発力、ならびに専門性を発揮しており、入学後も自らそれらを向上させる意志を有している。(能力)