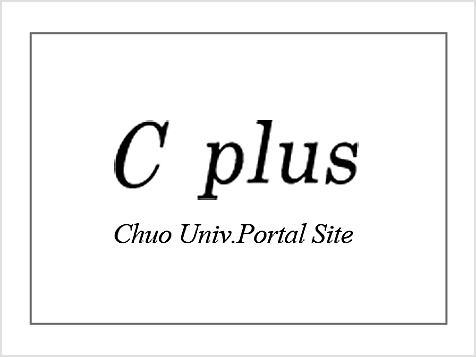法学部
【活動レポート】山本 太郎 (法律学科4年)
「やる気応援奨学金」リポート(31) 国連の人権小委でインターン 人権理解と侵害の認識が大切
はじめに
かつては国際連盟の本部が置かれていたスイス・ジュネーヴの国連ヨーロッパ本部、パレ・デ・ナシオン。2006年の8月3日から15日まで、私は、ほか五人の国際インターンシップ受講生と共に、このパレ・デ・ナシオンで開催された人権小委員会の会合において、小委員会の委員である本学法科大学院教授の横田洋三先生のアシスタントとしてインターンシップを行う機会に恵まれた。

国連人権小委員会、正式な名称でいえば国連人権保護促進小委員会は、国連憲章第68条に基づいて経済社会理事会の下部機関として設置された人権委員会の活動を補助することを目的として、1947年に設立された。国家代表としてではなく個人資格で、地理的配分を考慮したうえで人権委員会によって選出された、26人の専門家から成る。
現在、国連は人権保障システムの改革を進めており、2006年の3月には、人権委員会が発展的に廃止され、新たに、総会の下部機関として人権理事会が設置されている。このような状況の中、人権委員会の下部機関である人権小委員会の存廃はあいまいなままに残され、2006年の会期が、8月7日から25日まで、小委員会最後の会期として開催されると決まったのは、会期の開始直前になってからのことであった。今回私たちがインターンシップをする機会を得たのは、国連人権小委員会の58回目にして最後の会期、その最初の1週間であったということになる。
予想との違い―政治的独立性を巡って
私が初めて足を踏み入れた国際会議の舞台である人権小委員会の会議室には、委員の席を幾重にも取り巻くように、オブザーバーとして会議に参加する各国政府代表やNGOのための席が用意されていた。各国政府の代表者や、経済社会理事会による認定を受けたNGOが、小委員会の会議への参加を許可されているのである。このような社会への開放性が、小委員会を特徴付ける要素の1つであるといえる。小委員会は、単なる人権委員会のシンクタンクではない。国連システムの中にあって、広く市民の声をその内部に吸い上げる役割をも担っているのである。
会期初日である8月7日は、午前中に開会に当たっての会合があり、午後には、レバノンにおける大規模な人権侵害を非難する議長声明が採択された。私たちが人権小委員会を訪れていたころは、イスラエル軍がレバノンに侵攻していた時期と、ちょうど重なっていたのだ。最終的には、半ば強引ともいえる議長の主導もあり、コンセンサスによって採択されたこの声明だが、その採択までの過程には、非常に興味深いものがあった。各委員の出身国政府のイスラエルに対する政治的立場の差異から、このレバノンでの人権侵害状況について、イスラエルだけではなく、それと対立するイスラム系武装勢力・ヒズボラをも非難の対象として含めるような文言を用いるかなどを巡って、白熱した議論が交わされたのだ。
実際に会議を傍聴するまで、私は国連人権小委員会について、政治的背景の差異を超えて、人権の普遍的保障のために一致団結して知恵を出し合う世界的な人権専門家の集まり、といったものを想像していた。人権小委員会の委員は、政府の推薦を受けてとはいえ、個人としての資格で選任された専門家であり、それだけに、政治的に中立的な立場から種々の人権問題を検討することが求められている、と理解していたからである。ところが、どの当事者を非難する言葉を用いるのかという問題を巡って委員同士が激論を戦わせる様子は、私が想像していた「非政治的な」人権小委員会とは懸け離れており、むしろ、国際政治交渉の現場における国益のぶつかり合いといったイメージであった。実際、小委員会の委員の中には、各国政府の政治的利害を直接代表するような委員もいるのだという。非公開の会議の場では、国家間の激しい政治的対立が顕在化することもあるということである。

それはそれで、自然なことではあるのかも知れない。文化的・政治的対立が完全には回避し難いものであるからこそ、委員の選定に当たっても、地理的配分に基づいた考慮が必要となるのだろう。また、国家や政治という枠を完全に撤廃して人権上の諸問題に対処することは出来ないに違いない。ただ、やはり小委員会の委員は各国政府の政治的利害関係からは独立した存在であるべきであるということは、委員の間で意識されているようである。国連の人権保障システムの改革に当たっては、国家の政府による支配から独立した専門家の機関を創設することが要請されるということが、会議においてしばしば主張されていた。
人権に格差を知る
会期2日目の8月8日からは、人権上の具体的な各分野についての議論が始まった。「人権問題」という、実に広範にわたる分野について議論される人権小委員会では、主に、前年の会期において策定された計画に基づく、幾つかの議題に沿って議論が行われる。私が傍聴した会議の中では、人権侵害者の免責などの法執行の問題、多国籍企業の活動と人権、テロリズム・反テロリズムと人権といった問題について議論が行われた。議論を理解するための前提となる基本的知識・認識の欠如や、英語力の不足を痛感したことはいうまでもない。しかし、それでも、目の前で繰り広げられる議論から、多くの新しい認識や、認識するための示唆を得ることが出来たように思う。
全体としていえば、特に、国家間の力の格差や、そのために生じる対立を問題とするような議論が多くなされ、その問題の深刻さを改めて感じさせられた。中でも私が最も大きな衝撃を受けたのは、テロが発生する原因についての議論の中での、ある議員の発言であった。開発途上国には、人がはえのように死んでいく状況がある。それを我々は、そばにいながらただ見ていただけではないのか。経済的な自己実現手段は何も持てず、自らの命しか捨てるものもない、そのような貧困が存在する現状を是正しなければならない――。
貧困がテロの原因となっているということも、知識としては知っているつもりだった。しかし、国連という場において、人権の専門家が強い口調で、しかも“people dying like flies”というショッキングな表現でもって訴えたこと、そして、それに対する会議場の反応が重い沈黙であったことは、その言葉に何よりの説得力を持たせていたと思う。各委員の間に背景の違いはあっても、やはり人権小委員会としての方向性には共通のものがある。そう思わされた一幕でもあった。
ILO本部にて
国際都市とも、the Heart of Europeとも称されるジュネーヴには、国連ヨーロッパ本部のほかにも、国連難民高等弁務官事務所や世界保健機関など、数多くの国際機関の本部が置かれている。研修中の8月10日の午後には、パレ・デ・ナシオンから徒歩ですぐの所にある国際労働機関(ILO)の本部で、職員の方にお話を伺う機会を得た。
今から考えると浅はかだったと思うが、私はILOを訪問するまで、労働に関する問題に対して、難しそう、取っ付きづらい、といった先入観を持っており、大学での勉強においても敬遠してしまいがちだった。しかし、今回ILO職員の方にお話を伺うことが出来て、「まともな仕事」を持つということが、人間が社会生活を営むに当たっての中核的な「人権」なのだということを認識出来た。特に私にとっては、これから就職活動を始めるという時期であったということもあり、非常に良い刺激を受けることが出来たと思う。

ILOでの研修では、また、抽象的な人権の議論を現実の状況に適用していくプロセスにおける、駆け引きの難しさも感じた。幼い子供が学校へ行かずに児童労働に従事している。そのような状況は是正されなければならない。しかし、開発途上国においては、子供が働かなければ、家族全体がその日の食料も得られないなど、ある程度の児童労働を必要悪として容認せざるを得ない状況が、事実として存在する。それでも、子供には危険な仕事はさせてはならないなど、絶対に譲れない部分、保障されなければならない権利の中核がある。例えば、禁止する児童労働の対象年齢を本来よりも引き下げるなどして、国際的な基準からの逸脱を許してでも、最悪の形態の児童労働は阻止しなければならないのである。そうするためには、段階的なプロセスを経て、徐々に状況を改善させていくことが必要なのだ。
開発途上国の子供の権利保障を国際レベルにまで高めること。それは恐らく、長い時間を要するプロセスである。だが、少しずつでも、状況は改善させることが出来るし、させなければならないのだと思った。そして、その長いプロセスを担うのは、それが出来る先進国の責務であり、そのプロセスを受け継ぎ、継続していかねばならないのは、私たちの世代であるのだとも。
認識することから
ジュネーヴへの渡航前の、事前準備の段階から思ってはいたが、約2週間の研修を終えて日本に帰国してから、改めて驚かされたことがある。人権小委員会に関して、あるいは国連による人権保障システムに関して、一般に報道されている情報が、少なくとも日本においては、非常に少ないということである。思えば私自身、初めて国連人権小委員会という機関の存在を知ったのは、恥ずかしながら、このインターンシッププログラムの海外研修先としてであった。わずかに人権NGOなどが小委員会の活動の情報を伝えてはいるのだが、一般論としては、人権保障活動という分野自体、報道の表立った対象となることは非常に少ないといって良いのではないだろうか。
人権小委員会の活動に関しては、国連を通じて情報が発信されてはいる。しかし、発信された情報も、受信者がいなければ、受信しようとしなければ、コミュニケーションとしての意味を成さない。レバノンでの人権侵害を非難する国連人権小委員会の議長声明を、いったいどれだけの人が知っているだろうか。
もちろん、人権小委員会の活動は、広く一般に知らされなければ意味を持たないというものではない。しかし、人権という、人の存在の基盤となる問題の重要性に不釣り合いとも思われる無関心な態度は、再考されても良いはずである。現実に行われている人権侵害の状況を周知することが、それに対する有効な対抗手段であるからだ。常態となってしまっている人権侵害状況を、当然のこととして看過することは出来ない。認識するということから、すべては始まる。その大切さを今、改めて思う。
人権を語るということ
私が今回の研修全体を通じて、人権というものについて考え、感じたこと。それは、人権は何も難しいことではないのではないか、ということである。
難しくない、といったら語弊があるかも知れない。人権小委員会は人権一般にかかわる、非常に幅広い分野の問題をその活動の対象としており、複雑に絡み合った問題群は難解で、その解決が極めて困難であることには疑う余地がない。そのことは、会期の初めの1週間を傍聴するだけでも分かったつもりではあるし、また、創設以来、半世紀以上にわたって人権侵害と闘い続けてきた、小委員会それ自体の存在と歴史が示していることであるといえよう。
しかし、小委員会の会議で繰り広げられていた議論が、全く私の理解の範囲を超えていたかというと、そういうわけではないような気がする。もちろん、今回の会議の中で私が理解出来たことは、議論されていたことのうち、ごく限られた一部分ではあろう。会議を傍聴して、新しく意識するようになった問題も多い。しかし、それは、今までは考えてもみなかっただけで、「考えれば分かる」ことでもあったのではないかと思うのである。
ある意味では、それは当然のことであるのかも知れない。人権を侵害されるということは、人として当然認められるべき権利を否定されるということだ。もちろん、何が人権の範囲として認められるかという問題は、それ自体として非常に難しい問題ではある。しかし、人権侵害が疑われる状況があるということに気付き、この現状を放置してはならないのではないか、という問題意識を共有することは、専門的な知識の有無にかかわらず出来ることだと思うのである。
人権を単純化することは出来ない。特に、この言葉が持つ至高性や、思考停止語ともいえるようなその性格からは、この言葉を軽々しくは使えない、ある種の危うさが見え隠れする。しかし、それでも、人権は議論されねばならないし、語られねばならない。人が人らしく生きられない状況を放置しないこと、そのような人権侵害の「傍観者」とならないこと、それこそが人権を語るということの本質的な意味であるとするならば、これほど普遍的な共感を呼べることはないといえるのではないだろうか。
結び-より多くのことに「気付く」ために
今回のインターンシップでは、多様な人権の在り方に触れることで、そして国際社会で活躍する、あるいは活躍することを目指している人たちとの出会いを通じて、私は、一種の危機感を抱くようになった。もっとこの世界で起きていることを知りたい。知らなければならない。このインターンシップを通して、自分という人間がいかに自分の住む世界というものに関して無知であったか、今までいかに狭い、自分とその周りだけの「世界」の中で生きてきたかを、思い知らされたような気がするのである。自分の「世界」を広げるための、広く深い視野の必要性を再認識して、私は自分と、そしてその自分が暮らす広い世界と、向き合いたい。
人権小委員会のある委員が、会議の中で言っていた。我々は象牙の塔の中にいるのではない。現実に起こっている問題と向き合い、それに対処しなければならないのだ、と。多様かつ深刻な人権問題が現実に存在することが感覚としても認識出来、それに「気付く」ことの大切さを知った今、私はこれまでの私のままでいることは出来ない。常に「気付く」ということを大切にし、他者の声に耳を傾けて、自分とは別の思考や感情の可能性を探っていこうと思う。そして、それをありのままに受け入れることこそが、結局は人権を尊重することにつながるはずだ。
人権が否定された状況の「傍観者」にならないように。人を「はえ」としてではなく、「人」として扱うことが出来るように。そうすることが、たくさんの人の力を得て、国連人権小委員会でのインターンシップという、ほかでは望み得ない経験への機会を与えられ、それに裏付けられた新しい視座を得ることが出来た私の、1つの義務であると思っている。
ジュネーヴから帰国して、半年がたつ。
この間、インターンシップでの経験は、思い出すたび、書き起こすたびに、私に新しい示唆を与えてくれ、そこで感じたことをより確かな思いにしてくれた。

思い返せば、インターンシップ履修の前年度、私がこのインターンシップに参加しようと決心したのは、実は応募締め切り間際のことであった。全く新しいことに挑戦することに、ちゅうちょしていたのである。しかし、ほんの少し勇気を出し、一歩を踏み出すことで、国連人権小委員会でのインターンシップ、そしてそれを実現するための「やる気応援奨学金」というチャンスを頂いた。そのチャンスを基に、私はほかでは望み得ない経験と、それに裏付けられた新しい視野を得ることが出来た。
周りを見渡しさえすれば、恐らく、持て余すほどの可能性が散らばっている。それなら、受け身でいるのはもったいない。さまざまな出会いの機会や可能性に気付かないのは、自分から行動して得ようとしないのは、もったいない。当たり前のことではあるが、それが、このインターンシップを通して私が得た、もう一つの教訓でもあったのである。
草のみどり 205号掲載(2007年5月号)