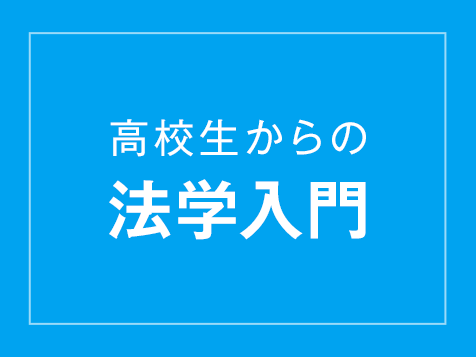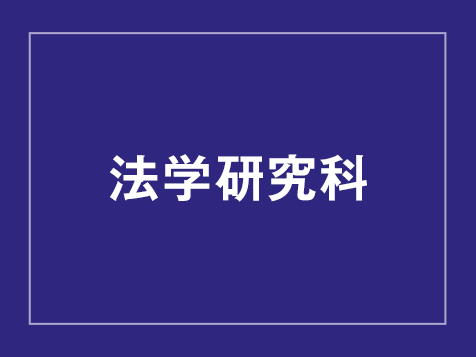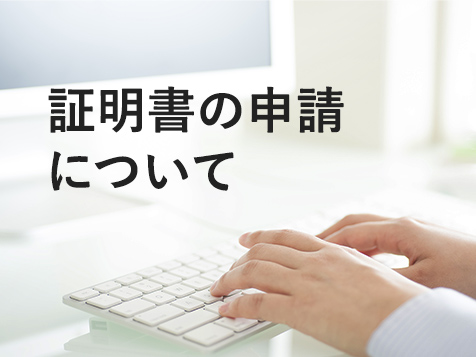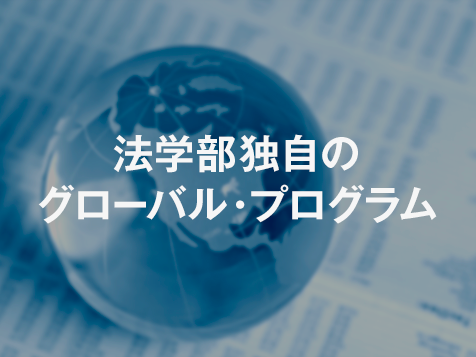法学部
法学部長挨拶

遠藤 研一郎 中央大学法学部長
「法」は、例えば、ウル・ナンム法典(古代メソポタミア)やハンムラビ法典(古代バビロニア)に見られるように、古代社会の時代から絶えず存在します。また、「法学」は、古代ローマに遡り、様々な思想を取り込みつつ発展してきたという歴史があります。さらに、「法学部」という研究・教育機関も、専門家を養成する場所として、医学部および神学部とならび、最も古くからあるものの1つとして位置づけられます。そのような意味で、「法」、「法学」、「法学部」には、伝統的で厳格なイメージがあります。
しかし、実際には、法も、法学も、法学部も、堅い面ばかりではありません。「社会あるところに法あり」と言われるくらいですから、法は、常に私たちの社会生活の傍らにあります。出生、入学、就職、結婚、居住、旅行、交通、所有、相続・・・。どの場面を切り取っても、私たちは法に依拠して社会生活を営んでおり、法と切り離すことはできません。法は、時には社会を統制し、時には私たちの活動を促進し、時には紛争を解決し、時には限りある資源を分配するなど、重要な役割を果たしています。ですから、法学は、将来、どのような職業に就いても、どのような場面でも役立つ、身近な「実学」なのです。
さらに、法には、ダイナミズムがあります。近時の日本は、曲がり角に差し掛かっていると言えるでしょう。拡大から維持・縮減へ転換し、様々な格差が拡大化し、価値の多様性が生まれ、国際化が進み、高速度で電子技術の革新が進むなど、大きな変化が生じています。そのような中で、現在ある法を運用する能力を身につけるだけではなく、未来志向的に「これからあるべき法」を模索し、社会に提言できるようになることは、法学部生の社会的役割でもあるのです。
中央大学は、1885年に英吉利法律学校として創設されました。法学部は、140年近くの間、その精神を受け継ぎつつ、発展を遂げています。研究者教員だけでなく、多くの実務家教員をも擁する充実した人的資源を持つとともに、法的素養を持つ学生を養成するための豊富なカリキュラムを持ち、類稀なる奨学金制度、留学制度、資格取得支援制度などを兼ね備えている、研究・教育環境が整った学部となっています。今後も、伝統を重んじつつ、変化の激しい未来へ向かって前進し、社会的な責任を果たし続ける所存です。