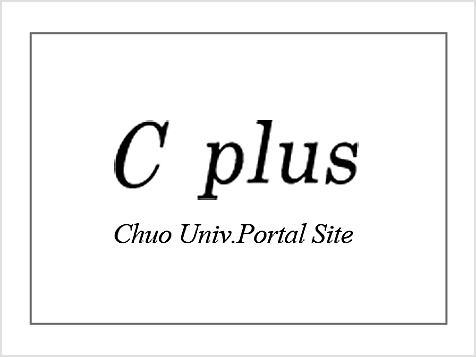法学部
【活動レポート】吉原 若菜 (法学部政治学科3年)
「やる気応援奨学金」リポート(3) 3度訪問、インド!葛藤記(上) NGO活動に参加し試行錯誤
始まりの始まり
私が法学部の「やる気応援奨学金」を受けたのは2003年、2年生の夏である。それが夏休みの2ヶ月間、インドのデリーで活動するNGOでインターンシップをすることを可能にしてくれた。
これは、3度目のインド滞在である。インターン先は、プラヤス(Prayas)という名の、デリーを中心に活動するNGOだった。子供の権利と教育にかかわる活動をしており、規模が大きくデリーでもよく知られている。有名企業家が理事に名を連ね、巨額の寄付金を受けて、映画スターを招いた大規模なチャリティーコンサートも開催する。以前、NHKがドキュメンタリーを撮ったこともある。
プラヤスに行く前に持っていたのは、資金が潤沢だというイメージだった。順調に活動しているように見えるこのNGOを、内側から見てみたかった。彼らの一部になってその仕組みを理解したかったのである。更に、この旅は「里帰り」でもあった。インドには、大好きな人たちがいて、帰りたい場所が幾つもあるからである。多くの疑問、刺激、課題を投げ掛けてくれるそれらの人たちを原動力に、私は動き続けているのだと思う。
プラヤスでのインターンシップに至るまでに、葛藤、出会い、挑戦、衝撃の日々があった。今回は、まずそれを紹介し、次回、プラヤスの話をしたいと思う。この報告を通して、悩んで、考えて、試行錯誤している一人の学生のことを知ってもらえたらうれしいし、この記事の目的は果たされる。
インドに「戻る」理由
高校1年の時、日本人のインド観光ツアーに参加して初めてインドを訪ねた。ツアー一行を乗せた車はサファリパークのライオンバスのように思えた。危険だから勝手に歩き回らないようにとガイドさんに言われていた。車が信号で止まると窓ガラスをたたく物ごい、観光名所の入り口で物をねだる子供たち、道を歩いて感じる視線。この視線がたまらなく嫌だった。彼らの目に映るよそ者の自分、お金を持っている自分、言葉も分からない自分がやり切れなかった。
この時、もう1度自分の力でインドに来よう、人々と近くなれる距離まで来ようと決めたのだった。
それから4年後、ラジャスターン州の東の端、クティナ村でスクール・プログラムとHIV/AIDSプログラムで働いていた。2度目のインド行きである。そこで、求めていた心地良い視線に出会うことが出来た。現地のNGOオフィス、一室を借りていた村の家族の家、学校、一歩入ればそこには私の場所があった。そして、4年前に感じていた違和感は自分が作っていた壁だったのだと気付いた。何も出来ない自分への後ろめたさだった。
怒涛の13ヶ月

参加したのはNGOの13ヶ月間のプログラムで、大学1年生終了後、1年休学して参加した。6ヶ月のトレーニングとファンドレイジング(資金開拓)期間を経て、6ヶ月のフィールドワーク、そして1ヶ月のフィードバック・調査期間から成っていた。
私は順にアメリカ、インド、南アフリカ共和国で過ごした。インドで働くにあたっての「準備」をアメリカで、「フィードバック・調査」を南アフリカで、という位置付けだった。多くのことが起こり、数え切れないほどの人と出会い、別れた。
このNGOは、私のような参加者をDevelopment Instructorと呼んでいた。ボランティアともいえるが、日本語のボランティアとはイメージに多少のずれがあると思う。私たちに期待されていた役割は、自分の視点で新鮮な提案をしていくことだった。専門家である必要はなかった。

アメリカでは、ミシガンにあるNGOのセンターで、世界中から集まるボランティアとNGOのスタッフが共同生活をしていた。私たちの部屋も台所も教室もスタッフの職場もそこにある。このNGOは、世界各地にこのようなセンターを持っていて、私は「ミシガン校のインドチーム」にいたことになる。
ここにいる期間に、ファンドレイジングをしたわけである。一人一人に達成目標額が設定されたファンドレイジングがどんなにつらかったか、インドに行く者はヒンディー語を、ザンビアに行く者はトンガ語を、中南米に行く者はスペイン語を、限られた時間で学ぶのがいかに大変だったか、ここでは書き切れない。

アメリカで6か月を経た後、いよいよそれぞれ準備してきたプロジェクトのある国に行く。「インドチーム」は、一緒に行くはずだったアメリカ人のジェイコブが途中でリタイアしたため、私1人になってしまった。1人といっても、現地に行けば同じNGOのメンバーであるプロジェクトのスタッフがいるので、心配はなかった。アフリカチームは人気が高く、4、5人が1つのチームで出発していった。
最後に、フィードバック・調査期間を過ごした南アフリカ共和国にも、「ミシガン校」と同様な「ダーバン校」があり、私がアメリカでやっていたようなことを多くのボランティアがやっている。つまり、これからプロジェクトで働く者と、私のように終了した者が出会う仕組みになっているのである。
南アのプロジェクト自体は、ソウェト(アパルトヘイト時代の名残で、今も黒人のスラム街が多くある地域)にある。ここでは、職のない地元の若者がどんな思いで毎日を過ごしているか、陽性の結果を恐れて、無料にもかかわらずHIV/AIDSの検査を受けたがらない人々がどんな生活を送っているか、それまで知りえなかった事実を知って衝撃を受けた。しかし、ここではインドの話に焦点を当てるために、その内容は割愛したいと思う。
小さい村

さて、ここで触れたいのはインドでの活動と私の葛藤である。ここでの経験が、その後の関心と行動に最も大きく影響しているからである。クティナ村というラジャスターン州の東の村が、インドにいる間住み、働いていた場所である。ここでの活動は学校の英語の授業を手伝うことと、さまざまなテーマでワークショップをすること。テーマは主に「健康と衛生」だが、たまに「地図作り」や「グリーティングカード作り」といった小学校の社会科や美術の時間にやったような共同作業も採り上げた。
また、唯一の女性スタッフとしての私の役割は、HIV/AIDSワークショップで女性参加者の手伝いをすることだった。インドの、特に農村部では性の問題は扱いにくく、ただでさえ人前で口を閉ざしがちな女性は一層静かになってしまうからだ。

数多くの活動のうちで、「地図作り」を採り上げて感じたことを書きたい。私がこれを計画したのは、子供たちが自分の住む場所に対して持っている地理感覚やイメージを知ること、いつも英語を教えている彼らのことをより深く知ること、そして子供たちの好きなカラーペンや大きな紙で楽しんでもらうことが目的だった。
農村開発プロジェクトのプロセスの中で、村人の意識や知識から学ぶという意図で「地図作り」の作業が行われることがあるが、ここではもっと気楽に、子供たちと「クティナ村」を共有することを目指した。
11歳から14歳の女の子のクラスである。5つのグループに分かれ、2時間掛けて各グループが思い思いの村の地図をかき、最後に発表会を行ってこの騒がしい時間は終了した。私はといえば、地図とは何かについて説明をした後は、彼女らを観察し、必要があればアドバイスし、ペンの取り合いの仲裁と進行役に徹していた。
この作業を通して、面白いことに気付いた。それは、彼女らにとっての「村」はクティナ村のうちのとても限られた空間であること、そしてかかれたものの大きさやかかれた順番を見ると、彼女らの価値観が分かるということである。
もっとも、既に何となく気付いていたのだ。私にとっては決して大きくないクティナ村、端から端まで歩いても20分くらいの村も、村の女の子に言わせれば「まさか、歩き回るには広過ぎる!」距離なのである。

地図にもそれは表れていて、ごく限られた「学校の周り」や「家の周り」が中心にかかれていた。彼女らがかく順番を観察してみると、どのグループも真っ先にかくのは「寺院」。そこに「学校」「親戚の家」が続く。無意識に生活の中の大事な部分からかいているのだろう。距離感については、かき手が女の子であることも関係していたに違いない。男の子と違って村中を探検したり遊び回ったりすることを許されない彼女たちが見る村は、私が想像するよりもずっとずっと小さいのかも知れない。出来上がった地図には、生活に密着した部分をかき出しており、彼女たちがそこで生きていることを示していた。
生活・理想・NGO
村での生活とプロジェクトでの活動を通じて、それまで私が持っていたNGOに対する見方に変化が生じた。それ以前からNGOや開発協力といった分野に興味があり、村の人とより近い位置で視点を共有出来るような存在としての期待は大きかったが、かといって、NGOが完璧であると思っているわけではなかった。
しかし実際に参加してみると、NGOがその特徴を生かすも殺すもやり方しだいであるということを痛感した。スタッフがどんな理念を持っているか、知識と経験をバランスよく持ち合わせているか、村人と対等な立場に立とうとしているか、運営資金がうまく回っているかなどである。
特にお金の問題は深刻だった。一緒に働いていたインド人スタッフが、仕事は理想を追い求めるためだけにするのではない、という意識でいることは明白だった。それは一家を養っていく立派な就職先でもあったのである。
また、世界各地から来ていた私のような参加者のそれぞれの動機に目を向けると、興味深い意識の差があった。
欧米や日本からの参加者の動機は「国際協力に興味があるから、異文化体験がしたいから、物に囲まれた生活に嫌気がさしたから」というのが主であるのに対し、インドやアフリカからの参加者のほとんどは「このプログラム後に雇用の可能性がある」ことが大きな理由だと答えたのである。NGOやキャリアに対する考え方も、それぞれの社会事情を映していることを実感した。
しかし、皆、トレーニングとファンドレイジング期間を終えてフィールドに出れば、同じように悩み、試行錯誤しながら自分の役割を見付け出そうとする。私も例外ではない。どうしたら村の人の役に立つことが出来るかを必死に考え、そしてある時、自分の小ささと彼らから学んでいることの大きさを知るのだった。

初めてインドに来た時、「お金持ち」の国から来て何もすることが出来なかった自分が悔しかった。彼らの気持ちも分からない自分が悔しかった。しかし、村に住んで、豊かさはお金や物だけでは測れないことを肌で感じた。インフラ・教育・衛生状態……改善すべき課題は多いが、夕暮れの井戸端会議にも、熱々のチャパティにも、教室のざわめきにも、女の子たちの地図にも、彼らにはずっと昔から続いているゆっくりとした心地良い時間が流れているのを感じながら私はクティナ村にいたのだった。
まだまだ続くインド葛藤記
私を包む村の空気がどんなに心地良くても、私を含めNGOスタッフの間で、毎日議論や意見の対立は尽きなかったし、どうしても納得出来ないことは数え切れなかった。村の人々とNGOの関係で、素晴らしい可能性を見いだすと同時に、疑問に思うことも多かった。例えば、NGOの資金繰りにも疑問を持った。プロジェクトマネージャーの資質に対してスタッフが抱いている疑問や、プロジェクトにおける意思決定過程も気になった。
クティナ村の6ヶ月は、多くの課題を投げ掛けてきた。その課題解決のヒントを探るべく、再びNGOでのインターンシップを考え始めた。戻ってこよう、と思った。ここで、冒頭で述べたプラヤスへ話は戻る。
休学して参加したNGOで問題意識を募らせ、復学後、本を読み、人に会って問題を整理してきた。そして、数ある疑問のうち、「NGOのファンドレイジング」に絞って問題を探ってみようと、私はプラヤスにインターンシップに行くことにした。
このインターンシップが実現した背景には、さまざまな偶然や周囲の理解が重なった。親しい先輩が応援してくれたこと、インドでの友人がプラヤスにかかわりを持っていたこと、学部で「NGO/NPOインターンシップ」を履修していて、夏休みのインターンシップが単位取得の条件となっていたこと、「やる気応援奨学金」が受給出来たこと、更には「もう好きなようにしてくれ」と行かせてくれた家族の理解(?)などである。
草のみどり 177号掲載(2004年7月号)
「やる気応援奨学金」リポート(4) 3度訪問、インド!葛藤記(下) プラヤスでの活動と将来の道
三度インドの地へ
前回は、大学2年の夏にNGO・プラヤス(Prayas)に「やる気応援奨学金」でインターンシップに行くまでの経緯を書いた。今回は、私のプラヤスでの活動内容と、今に至る挑戦「第2波」をお話ししたいと思う。
研修生としての仕事

プラヤスでの私の立場は「リソース・マネージメント・ユニットの研修生」だった。この部署は、プラヤスのファンドレイジングを企画、実施している。私の具体的な活動は4つだった。①デリー市内の市立学校への協働のためのアプローチ②プラヤスから資金援助を受けて公立の学校へ通う子供の調査、報告書作り③シェルターホームに住む子供たちとの交流④チャイルドライン・インディア(子供のフリーダイヤル・24時間ヘルプライン)の調査――である。
NGO営業活動
プラヤスでの研修生としての時間は学ぶことの連続であることはもちろん、まだまだ学ぶべきことが限りなくあることを思い知らされる日々でもあった。①のデリーの学校へのアプローチの活動では、自信を持って行動すること、自分から動くこと、交渉するのに「最適な」人を見極めること、そして動き出す前に事前準備が不可欠なことを身をもって感じた。
言葉にしてしまうと平凡で、十分にその重みを伝えることは出来ないが、これらはすべて課題に臨む「態度」の問題だった。それに加え、立場の異なる人との交渉の仕方など新鮮なこともたくさん経験することが出来た。
学習センターの子供たち
②の子供たちの調査では、彼らの新しいことを知る意欲の高さを見せ付けられた。
プラヤスは学校に通えない子供たちのための学習センターを数多く持っている。学習センターによって子供たちの意欲と出席状況に大きな違いがあるが、プラヤスの本部に近いセンターほど、子供たち、更に先生の意欲も高いようである。
理由は、1つには本部から近いために、ほかのセンターに比べ私のように本部の建物に滞在する外国人研修生や、本部の来賓が見学に来ることが断然多いことが挙げられる。子供たちは「自分たちは気にされている。プラヤスがちゃんとこのセンターを覚えているのだ」と、意識している。それはセンターの先生も同様で、怠けることが出来ない(実際、先生たちが手を抜いているセンターも多い)。

更にもう1つの理由。学習センターでは簡単な昼食が出るが、これは本部の台所で作られて運ばれてくる。昼食が時間通りに来ることは非常に重要である。教育の重要性を理解して子供をこの学習センターに送る親ももちろん多いが、もし昼食サービスがなかったら、実際何人の親が子供をここへ送るだろうか。あるいは、子供自身が来たいと思うだろうか。
もちろん食べ物で誘っているわけではなく、学習内容にも工夫してはいるが、何よりも最低限の生理的欲求――おなかを満たしたいという欲求にこたえられずに教育の重要性を語るのでは現実味がないのである。少なくとも、デリーのこのコミュニティーにいて私はそう感じた。
どう生きる
③のシェルターホームや④のチャイルドラインを通じてかかわった多くの子供たちからは、彼らを取り巻く環境の厳しさと精神的な強さ、そしてその強さも時にはささいなことで崩れてしまうことを直接教わった。

幼いうちから働いて、虐待を受けたり、家に戻れなくなったり、結婚させられたり、子供が出来たり、仕事を探したりと、一生のうちのさまざまなステージが、私たちが当たり前だと思っている何倍もの速度で進んでいるのだ。親に売春を強要されて逃げてきたこと、虐待を受けたこと、駅に置き去りにされたこと、貧しくて家で養ってもらえないことなど、子供たちは私に、親しくなるにつれてゆっくりとプラヤスに来た経緯を話してくれるようになっていった。
これが現実で、しかもほんの一部に過ぎない。私は、彼女たちの過ごしてきた時間とこれからの時間を思い、自分はどうすべきかと自分に問い掛け続けた。
ファンドレイジング

さて、私が抱えてきたテーマの「NGOのファンドレイジング」への答えは得られたのであろうか。観察によって少なくとも以下のようなことが分かった。
デリーの中でも規模が大きいプラヤスは、動いている資金の額も大きい。なぜ、資金作りがうまくいっているのか。これが当初の私の疑問だったが、その理由が少し理解出来たと思う。
第1に、プラヤスの創始者がデリー警察の権威で、その人脈が物を言っている。例えば、政治家対象のチャリティーゴルフ大会を開く、チャリティーコンサートに映画スターを呼ぶ、有名クリケット選手との対談を企画する、政府とのつながりが強い、など。

しかし、大きなお金が動く分、それを有効に使うことも期待される。政府とのつながりが大きい分、その癒着を心配する内部スタッフの声もある。良くも悪くも、創始者の顔の広さが、プラヤスが成功した第1のかぎであろう。
第2には、プラヤスのスタッフはアピールの仕方を心得ている、という点である。効率良く自分を見せるすべを知っている。マスコミや話を持ち掛けるべき人、社会への見せ方など、要領がいい。これと、第1の理由が重なって、ものすごい額の資金が動いている。NGOには、誠実な活動を懸命にしていても、活動をアピールするすべを知らなかったり、その余裕がなかったりする所も多いと思う。プラヤスはそれらを要領良く同時並行でやっている。
現場に行けば行くほど新しいことが見えてくるのは事実である。しかし他方で、行けば行くほど分からなくなってくることもまた事実である。それは、「NGOとは何か」という根本的な問いである。国連憲章にも登場するこの「非政府組織」には、政府にも、企業にもない役割が期待されている。私は、NGOがその期待に十分にこたえる可能性を備えていると考える。だが、「NGO」という語の響きに身を隠し、実態が見えない団体もある。
政府の要人や官吏が、退職後あるいは現職中に「非」政府組織を立ち上げることもある。この場合には、その財源力と人脈が大きく働き、政府との関係も強いケースが多い。こうなってくると、「非」政府と呼ばれる意味はいったい何なのであろうかと考えずにはいられない。
また、NGOは「非政府組織」ではあるが「反政府組織」ではない。政府と協働して問題に取り組む姿勢はもっと強調されて良いと思う。同時にNGOは「非営利組織」でもある。しかし活動のための資金作りの過程において、その戦略の立て方などは「営利組織」と根本的な違いはないのではないかと思う。ただし、事業収益の使途が異なることを、認識すべきだろう。
終わりなき課題
さて、プラヤスでのインターンシップを通して私が直面した大きな疑問の1つに、「プロジェクトをどう評価するか」というものがあった。

プラヤスに資金援助を行っているある国の大使館の担当者が、私の働いている施設に視察に来たことがある。視察は形式的なもので、支援している事業の問題点を共有するわけでも、互いの認識を話し合うわけでもなかった。援助する側、受ける側の関係はこれでいいのだろうか。そもそもだれが、いつ、どこで、何をもって事業の善しあしを決めるのか。事業を始める段階で、評価の視点は組み込めないのか。疑問が次々とわき上がってきた。
私が今持っている問題意識は、NGO活動に対する評価方法はどのようになされるべきか、また、NGOがその評価からどう学んでいくか、ということである。これらの疑問への答えを得たくて日本の国際協力分野で活動しているNGOで、長期のインターンシップを開始した。
「意味」のある言葉を話す
最後に、私が使っていた言語について少し触れておきたいと思う。インドを中心としたこれまでの私のNGO活動において、重要な役割を果たしていたのはヒンディー語である。そのほとんどは、これは、実質六カ月のクティナ村での生活で覚えた。赤ん坊が自然に言葉を覚えるように覚えたものである。何しろ、村の外国人は私だけで、スタッフ以外は英語を話せないという状況だったから。
ヒンディー語を知らなくても生活は出来る、見学には行ける、スタッフに英語での通訳も頼める、子供と遊ぶことも出来る。しかし、直接自分で交渉し、質問し、けんかし、議論し、説得・説明出来ることが、確実に生活の質を変えると思う。もちろん、私のヒンディー語は完璧にはほど遠く、通じない時のじれったさも何度も味わった。だからこそ、自分でヒンディー語を使って生活出来ることの意味をかみ締めている。
では、英語はいったいどこで覚えたか。私の英語習得に一役買ったのは、アメリカでの6カ月間だったことは間違いない。ファンドレイジング活動の期間は、毎日100人以上の見知らぬ人と話をする、NGO活動の説明をする、議論をする、この「修行」(苦行?)の日々が、私にコミュニケーションの道具としての英語と、かなりの度胸を付けてくれた。一方、今、私が補うべきものは学術的な英語力であることも自覚している。
今、自分の将来を
今、自分の将来の姿を思い浮かべてみる。数年前に思い浮かべていた将来像とは比べ物にならないほど、より具体的に、そして現実的になってきていることに気が付く。数年前、私の頭の中にあったのは、漠然とした国際協力へのあこがれと、高校の時に初めて訪れて以来頭から離れなかったインドへの思いばかりだった。今では、あこがれは決意に変わり、思いは行動に移すことを通してより現実味を帯びてきている。
もちろんだが、今でも「自分の将来」という大きなテーマを前に模索を続けている。全体から見れば、まだまだほんのスタートに過ぎない私の「道」は、しかし確実に将来につながっていると思う。たどるべき絶対的な一本道はない。ふと振り返った時に、自分の歩いてきた場所がつながって、まるでもともとあった道のように見えるだけである。
今、大学3年という重要な学年にいて、具体的な進路の選択に直面している。近道に固執したり、絶対的な道があると思い込んだりしないように心掛けている。多くの人に助けられ、刺激を受け、模索してぶつかっていく過程で、道は築き上げられていくものだと信じるからである。
草のみどり 178号掲載(2004年8月号)