11月20日、NGO/NPO論の授業(担当:山田恭稔教授)では、東北大学グローバルラーニングセンターの楊殿閣 特任講師を招き、「社会的課題に対するNGO/NPOの活動と可能性:地域づくり」と題して、昨年まで勤務された国際NGOのSolidaridadでのご経験を通した小農支援の事例を中心に据えて講演いただきました。
Solidaridadは、1969年にオランダ・ユトレヒトで設立され、農業と農民の持続可能性を中心に置いて、全世界に8つの地域センターを有し、現在42カ国で活動を展開している国際NGOです。そして、2020年には、一般社団法人Solidaridad Japanが設立され、公的機関や企業、NGOやNPOなどの市民社会団体と協力して、小規模生産者を支援する取り組みを行なっています。
楊氏はチョコレートのバリューチェーンを事例に挙げて、生産地コミュニティに対するイメージを学生達に想起させつつ、近年(特にSDGsの採択以降)の企業によるサステイナブルなビジネスの指向が、原料(カカオ、サトウキビ、パーム油)の生産に携わる小農の支援に必ずしも結びついていない現状(環境課題、人権課題、経済課題)を紹介してくださいました。さらに、これらの課題ならびに国際開発とビジネスの合流が進んでいる現状を踏まえて、NGOに求められている役割についても学生達の間で議論してもらいました。
グループワークによる双方向性をも含んだ本特別授業では、学生たちの集中力のみならず、当事者意識持って考えるという姿勢を促し、知的刺激と効果を及ぼした。参加した学生からは、「自分の生活と世界の問題が繋がっていることを考える良いきっかけになった」、「『私たちの豊かな日常生活が途上国の生産者たちによって支えられている』というお言葉が印象的だった」、「グローバルなサプライチェーンへの具体的な理解、そして、NGOがそこで果たし得る重要な役割に対する認識を深めることができた」、「NGOは単に『支援』を与えるのではなく、さまざまな関係機関と連携を図りながら、革新し続ける組織だと学んだ」など、私たちの消費生活と途上国の小規模生産者をつなぐNGO活動の現場で実際に活躍されている専門家からのお話が大変に好評でした。

グループワークの最中に考えるヒントを与える楊講師

グループワークで意見を出し合う学生達
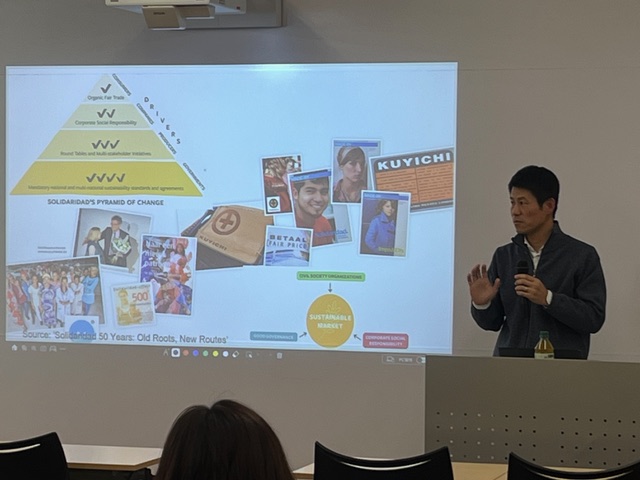
熱の入った講義の楊講師
