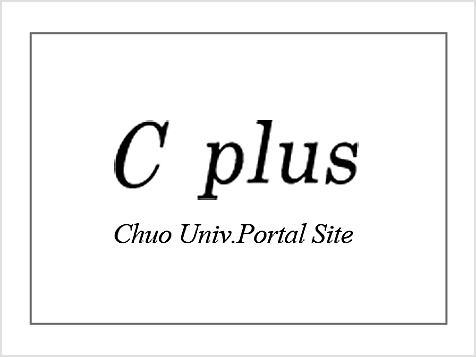法学部
【活動レポート】シュタルフ 新菜 (国際企業関係法学科2年)
「やる気応援奨学金」リポート(66) ドイツで難民支援活動を体験 ボランティア通し自分も成長
難民収容施設での研修
私を研修生として受け入れてくれたのは、ドイツとスイスの国境、風光明媚なアルプス地方にあるボーデン湖の湖畔の町リンダウのNGOエグジーリオ(Exilio e.V.)です。実を言えば当初予定していたNGOから、短期研修生は受け入れ不可との最終回答が届いたため、「難民支援」というテーマで研修出来る組織を改めて調べ直して、やっと見付けた団体でした。問い合わせの電話に応対した担当のフープマーさんは、その場で私の受け入れを快諾してくれたばかりか、必要書類も大至急作成してくれたおかげで、私は期限内に提出書類を整え、無事に奨学金の選考を通過することが出来ました。
なぜ経歴書などの書類もなく、電話でのやりとりだけで受け入れを快諾してくれたのか―当初はフープマーさんの御厚意にひたすら感謝するばかりで疑問すら覚えませんでしたが、現地入りしてすぐその疑問は氷解しました。エグジーリオで2日間実務を担当しただけで、私は日本の母に「もう帰りたい」とべそをかきながら電話を掛けたのです。
余りにも過酷な現実
夕方到着したリンダウ駅には、フープマーさんが出迎えてくれました。宿舎は、エグジーリオの事務所近くのスタッフ用家具付きアパートの一室です。翌日、事務所で建物内の説明のほか、業務内容のブリーフィングを受けただけで、私は実戦の現場に放り出されました。

人手が足りなかったのです。正規の職員も研修生も、スタッフの絶対数が圧倒的に不足しており、ほかのスタッフは皆、代表者のマルティッツさんとの打ち合わせやら事務所外での業務やらに追われ、私は初日からいや応なく1人で電話番をさせられました。「電話番」と言っても、ひっきりなしに掛かる電話の用件は、その1つ1つが通常の電話番の手には負えない、単なる「取り次ぎ」で済む内容から懸け離れた緊急のものばかりでした。掛けてくる相手は、リンダウ市内と郊外の二カ所の施設に収容されている、アフガニスタン・イラク・パレスチナ・トルコ・セルビア・コソボ・ロシア・シリア・コンゴ・ソマリア・ギリシャ出身の約200人の難民です。

当然、着いたばかりの私に適切な対処など出来るはずもなく、相手の名前と用件、連絡先をメモし、責任者や担当者に伝えるのが関の山。ところがつたないドイツ語で電話を掛けてくる当人にとっては、すべて緊急な用件ばかり。それなのに事務所側のスタッフは余りにも忙し過ぎて、実際に強制送還や生死にかかわる重大な用件でない限り、即応態勢が整備されていないという状況。電話番は必然的に苦情受付係も兼ねざるを得ず、丸2日、難民たちのごうごうたる非難・批判の集中砲火を浴び続けた私は、思わずその場から逃げ出したくなり日本へSOSの電話を掛けてしまったのです。
ドイツ・リンダウに住む難民
そんな電話相談の中に「無賃乗車」問題がありました。ドイツの公共交通機関には日本のような改札システムはなく、乗客は目的地までの乗車券を事前に購入して、駅や車内に備え付けの一種の小型改札機にそれを通し支払い済みの「証印」を受けなければなりません。運悪く見回りの係員に乗車券の提示を求められ「無賃乗車」が発覚すると、その場で有無を言わせず高額な罰金を科せられます。
難民が現物やクーポン券として市から支給される食料・衣料・日用品以外に受給する現金は、大人1人当たり毎月約40ユーロ(約4500円)に過ぎません。難民の中には、限られた現金の支出を惜しむあまり無賃乗車をしてしまい、それが発覚して罰金を請求されたのに支払わず、更に追徴金を請求され、ついには裁判ざたとなり、難民資格を喪失する危機に陥る人がいます。私が受けたのも、無賃乗車が発覚して駅長室に連れていかれた難民からの電話でした。エグジーリオでは、このように違法行為を犯した人も含め、難民のさまざまな法律手続上の支援も、生活・文化交流支援やコンサルティング(セラピー)と並び重要業務の1つとなっています。初めて収容施設を訪れた時に受けた衝撃も、忘れられないものとなりました。幼い子供たちが「戦場ゲーム」に夢中になり、マシンガンを抱え平然と殺りく現場を再現していたのです。
私が最初に支援業務を担当したのは、内戦状態にあるソマリアから逃れてきた、私と同年の19歳の女性でした。彼女が4人の子供の母親だと聞き、私は思わず自分の耳を疑いました。初産が12歳の時、4人ともレイプで妊娠し出産、父親は不明。彼女は子供と一緒に一家5人で、収容施設の10畳ほどの狭い部屋で生活していました。子供たちを安全な場所で育てたかった―彼女がドイツへ逃亡した1番の理由です。
身重の母親がウイルス感染!?
エグジーリオに収容されて間もないソマリア出身のAさんの12歳の娘モニーラの具合が悪いとの連絡を受け、私はもう1人の研修生と一緒に宿舎に急行しました。妊娠九カ月のAさんは、片足が不自由で、いつも足首まで届く丈の長い民族衣装をまとっています。宿舎を訪れると、モニーラは生気のない顔色で嘔吐を繰り返しており、直ちに病院に運びました。難民仲間のソマリア出身でケニア育ちのYさんも同行してくれました。
モニーラは、ウイルス性の胃腸炎らしく高熱と嘔吐で苦しんでおり、点滴を受ける彼女の傍らに私たちは付き添いましたが、嘔吐は治まる様子を見せません。その最中に今度はAさんが突然倒れてしまったのです。彼女をストレッチャーに乗せる際に、たまたま民族衣装のすそがまくれ、不自由な左足があらわになりました。それを見て、その場にいた者全員が凍り付きました。彼女の左足は、足であって足の形をもはやなしていなかったのです。
後でYさんから聞いた話によると、アフリカからの逃避行で彼女が乗った車両が事故に遭い、その時に受けた傷とのこと。その事故で彼女は息子を失い、自身も重傷を負いながらも、治療を受ける機会もなく、そのまま娘と共にヨーロッパまで逃げてきたそうです。
モニーラの症状は、脱水症状と栄養不足が原因で、一両日入院して点滴を受け休養すれば快復するとのこと。懸念されたのはむしろAさんの方で、彼女の顔色や発汗状態から、医師は流産の恐れもあるノロウイルスの感染を疑いました。いずれにせよ、そこの病院には小児科がなく、隣町の病院へ母娘を搬送することになりましたが、そこでまた新たな問題が生じました。

それを怠ると、最悪の場合は母国に強制送還される恐れもあります。そこで私たちは代表者のマルティッツさんの指示を仰ごうとしましたが、連絡が取れません。あたふたしている私たちを見て、また傍らで吐き続ける娘を見て、Aさんはとても心配そうな様子でしたが、いかんせん言葉が全く通じないのです。同行のYさんも、母語は英語でAさんの母語のソマリ語は片言だけ。通訳者に電話しAさんとの意思の疎通を図りましたが、電話越しではさほど励ましにもならず、また居合わせた私たちでは、彼女の不安を取り除くことも十分に支えてあげることも出来ませんでした。
結局は医師が機転を利かし、市が発行する許可証に代わる移動証明書を作成してくれて一安心。手配された小型救急車で最初にモニーラ一人が搬送され、取り残されたAさんはとても不安そうですが、どうすることも出来ません。そんな時1人の看護師が近寄ってきて、Aさんに声を掛けました。するとAさんが、ほほ笑んだではありませんか。尋ねた私に看護師は、イスラム教徒なら誰もが知っている言葉で「大丈夫ですよ。元気出して!」と声を掛けたと教えてくれました。ソマリ語でなく、イスラム教徒に通じる共通の言葉―このたった一言で、彼女の不安は大いに和らいだ様子で、まるで奇跡を見ているかのようでした。
言葉が通じないむなしさ
この日の出来事を通して、私は言葉の大切さを痛感しました。1人でも多くの人の力になりたいと願っていた私でしたが、リンダウでは、言葉という大きな壁に突き当たりました。どれほど意識が高くても、言葉が通じない相手とはコミュニケーションが図れません。どれほど志が高くても、難民保護法に関する知識がなければ、助言すら出来ません。それどころか、知識が不足していたり、誤っていたりすると、難民を逆に悪い立場に立たせてしまう恐れすらもあるのです。
私は、知り合った難民1人1人のデータに目を通して、その人がどのような経験をしたのか知ろうと努めました。また、必死に何かを伝えようと訴えてくる人の言葉を1つも聞き逃さないようにと集中しました。しかし私は、難民関係のドイツ法の知識を持ち合わせていなかったばかりか、ドイツ語の法律用語にも疎く、政府からの難民あての通知書ですら、内容を理解するのに一苦労する有り様です。そのような私の姿を目の当たりにした難民の中には、私に面と向かって「あなた嫌だ。ほかの人にお願いする」と言い放った人も少なからずいたのです。
エグジーリオでは、アフガニスタン出身のFさんが八カ国語の通訳として雇われ、セラピーでの同時通訳はもちろん、日常的な意思の疎通のためにも活躍しています。実は彼も難民でドイツに既に10年以上も暮らしています。彼はほかにも仕事を持ち、経済的に自立し、仕事の合間にわずかな時給でエグジーリオの活動を支えてくれています。
Fさんは、ドイツにたどり着く前に多くの国を転々とし、いずれの国でも迫害を受け、殺人を目の当たりにしながらも、妻を連れて必死に生き抜いてきたそうです。彼が難民として歩んだ経歴から、今の暮らしを手に入れるためにどれほど苦労したかが手に取るように分かりました。滞在国の言語の習得―これ1つ取っても、彼が並々ならぬ努力をしたことが分かります。ドイツに何年暮らしても、ドイツ語はほんの片言しか話せない難民もたくさんいるのが現状です。
ボランティアとは?
難民は、祖国を捨てて逃げざるを得ないほど過酷な目に遭い、中には情緒不安定になる人もいます。大半は、ただひたすら生きることだけに必死である一方で、自分たちがどれほどつらい不条理な境遇にあるかを嫌というほど自覚しています。だからこそ逆に、自分たちがこれだけつらい思いをしてきたのだから、幸せな人々から救いの手が差し伸べられて当然だと考える人もいます。これは裏返せば、ボランティアに対して感謝の気持ちを素直に表わす難民はほとんどいないという、別の過酷な現実を示しています。
難民仲間から「ビッグママ」と慕われるMさんが、ささいな出来事を契機に突然豹変して荒れ狂い、仲裁に入った研修生にも八つ当たりし怒鳴り散らす場面に居合わせたこともあります。この1件にショックを受けた私に、別の研修生仲間は「難民全員が彼女みたいな人じゃない。10人に1人感謝してくれたら、とても素晴らしいことよ。難民は心に余裕がないから『ありがとう』と言えないの。何よりも彼らを責めてはいけない。私たちは、ありがとうと言われたくて働いているわけではないでしょう? 正しいと思うから頑張っているのでしょう? そう思えないなら、この仕事には向いていないよ」と声を掛けてくれました。
この時に改めて、ボランティア活動は、正しいと信じるからこそ行うのであり、感謝されることが目的ではないことに気付きました。ボランティア活動を行う側は、とかく何かをして「あげる」と思い込みがちです。私自身、幼いころから人に「ありがとう」と言われるのがとても好きで、それを言われたいために他人が満足しそうなことを故意に行うこともありました。何かをして「あげた」のに、「ありがとう」が戻ってこないと不満に思う自分、「ありがとう」と言えない人はごう慢だと勘違いをしている自分がいることに気付いたのです。

厳しい生活環境に置かれた、経済的にも精神的にもゆとりのない人は、生半可なことに対して「ありがとう」とは決して言いません。だから、「ありがとう」と言われることを目標にすると、いつか必ずくじけます。自分の無力さを思い知らされ、仕事への情熱が薄れ、新しい朝の訪れをおっくうに感じるようになります。実際に、眠れない夜も1晩2晩ではありませんでした。どんなに頑張っても、何1つ達成感が得られない時もありました。すべてを投げ出し日本に帰りたいと思ったことも何度もありました。
エグジーリオでの研修を経て、難民支援は決して楽な仕事ではないこと、またボランティアは自分が成長するために行う活動であることを私は学びました。今回の2カ月間では、難民から感謝されないことが日常でしたが、自分なりに一生懸命に取り組み、手伝った事柄に対して時々発せられる「ありがとう」には、格別の重みがあります。そんな幾つかの「ありがとう」によってまた次の日も頑張れた自分がいました。
この留学はいきなり実戦の現場での研修で本当に大変でしたが、無駄だと感じたことは1度もありません。それどころか、活動する機会を得られたことに対して、今でも感謝の気持ちでいっぱいであり、将来はやはり難民支援関係の仕事に携わりたいと考えています。この仕事を続けることで、難民が1日も早く新しい環境に溶け込み、笑顔で安定した平和な暮らしを送れるように、微力ながらも手助けが出来たら、またそれにより難民からいつか心から感謝されることがあれば、それに勝る喜びはないと思います。
草のみどり 240号掲載(2010年11月号)