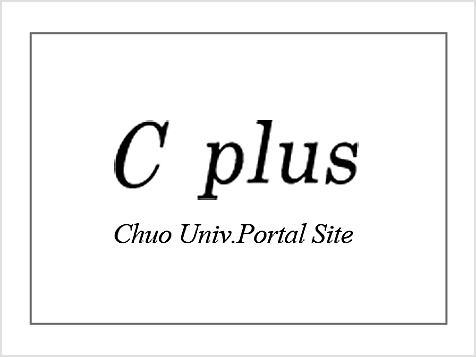法学部
【活動レポート】シュタルフ 新菜 (国際企業関係法学科3年)
「やる気応援奨学金」リポート(79)
ドイツ留学で独語と法律学ぶ ICC見学や地裁研修も体験
はじめに
二〇一〇年の春休みを利用した、南ドイツの難民収容施設での二カ月間の研修に続き、九月には再び「やる気応援奨学金」を受給して、今回はドイツ北部のオスナブリュック大学法学部に留学するために、私は再度ドイツに旅立ちました。
一年間の留学を思い立ったそもそものきっかけは、私自身のバックグラウンドにあります。私は日独のハーフで、日本でもドイツでも外見から外国人だと思われます。電車の中で日本語の本を読んでいると、それを見た高校生たちが「わぁ、外国人が日本語読んでいる!すごいね!」と内緒話をする始末です。中央大学の語学の授業でもネイティブと間違えられ、外国語は完璧に話せて当たり前と思われがちです。今回の留学が決まった時にも、何人かの学生には「えっ、留学先はドイツなの?自分の国に行ってどうするの?」と驚かれました。ところが私は、残念ながらドイツ語も英語もネイティブのように満足には話せないために、そのような周囲の反応に対して不快感や劣等感を覚えることがしばしばあり、せめてもう一つの祖国の言葉であるドイツ語だけでも完璧に話せるようになりたいと、常日頃から強く願っていました。

オスナブリュック大学11号館
四月に帰国して、間をあけずに更に一年間の留学を希望した理由は、もちろんそれだけではありません。二カ月間の研修でせっかく会得した語学力を、次はドイツの大学の法学部でドイツ人大学生と肩を並べて学ぶことにより、更に向上させたいという気持ちに加え、難民収容施設での実体験を、大学での専門的な研究により更に深化させたいという真摯な気持ちがありました。更にもう一つの背景事情として、日独の普通教育制度の違いを挙げることが出来ると思います。私は幼稚園から小学校六年まで、東京横浜ドイツ学園に通学していました。中学一年の二学期より日本の学校に転校して、日本の普通教育を受け高校を卒業して中央大学に進学しました。今回の奨学金に応募した時、私は大学二年生でしたが、ドイツ学園のかつての同級生たちはまだ日本の高校四年生に相当するギムナジウムの一三年生であり、アビトゥア(大学入学資格試験)を五月に終了して、高校の卒業式を終えたばかりでした。つまり彼らが大学生活のスタートを切るのは、私が留学を希望していた二〇一〇年の秋から始まる冬学期からであったのです。このため私と同い年のドイツの若者が、ドイツの大学の法学部に入学して、果たしてどのような初年度を送るのか、またドイツの大学では、法曹を志す者にどのようなカリキュラムが用意され、実際にどのような講義が行われるのか、身をもって体験することで日独の大学生活を比較したいという思いもありました。
一年間を振り返って
オスナブリュックに到着してからは、住民登録、銀行口座の開設、入学・入寮手続き、そして履修講座の登録等々、留学生活の開始に備え、慌ただしい準備期間を過ごしました。
オスナブリュック大学の創立は一九七四年であり、世界最古のハイデルベルク大学を擁するドイツの中では比較的新しい大学といえます。大学のキャンパスは、日本の通常の大学のイメージとは大きく異なり、各学部や研究機関の建物が市内に点在しています。私が入寮した留学生用の学生寮も、民間アパートが立ち並ぶ一角にありました。寮といっても、造りは通常のアパートと変わらず、家具付きの三LDKの一住戸をドイツ人学生二人と留学生二人の合計四人でシェアしました。めいめいに鍵付きの個室が割り当てられ、それ以外のキッチン・バスルーム・廊下はすべて共有です。

同居人三人で訪れたTecklenburg
新学期がスタートしてからは、連日の講義やゼミへの出席、そして留学生を対象とする大学主催のさまざまなプログラムへの参加など、実に濃密で有意義な時間が流れました。でも実際には、ドイツへ到着してから最初の半年ほどは、重苦しい、とてもつらい時が流れました。想像していた以上にドイツ語の専門用語が理解出来ず、授業にほとんど付いていけなかったのです。この言葉の障壁は、春休み期間の研修をきっかけに最終的には乗り越えることが出来ました。その一方で、国際企業関係法学科で履修が義務付けられている語学の授業で課されていた膨大な課題や部活動からは解放され、スケジュール的には日本にいた時よりも余裕が生じていました。また三月に発生した東日本大震災・福島原発事故の影響もあり、ドイツで過ごした一年間では、勉強だけではなく、自分自身の生きざま・在り方、そして将来の進路についても、じっくりと考え直すことが出来ました。個人的には、そのような時間を持てたことも今回の留学の最大の収穫の一つであったと思いますが、このリポートでは、留学の本来の目的に立ち返り、ドイツの法学部の授業や学生から受けた印象、二〇一〇年一一月のオランダのデン・ハーグにある国際刑事裁判所(ICC)の見学、そして二〇一一年の春休み中に受けたオスナブリュック地方裁判所における研修について、簡単に報告して一年間の留学生活を振り返りたいと思います。
ドイツの大学法学部
学生の平均履修科目数は各学期とも四-七こまと、いわば「少数精鋭主義」のカリキュラムが組まれています。必修科目は最小限に限定され、語学を始め特に興味を抱いている科目については、必要に応じて各自が自由に選択するシステムです。私自身は、この一年間で、「刑法1」、「刑法2」、「家族法1」、「家族法2」、「ドイツ基本法」、「民法1」、「比較法」、「EU憲法比較」などを受講したほか、以前より関心を抱いていた難民問題を更に深く研究するために、特別受講許可を受けて大学付属の国際移民・異文化研究所(IMIS)(修士課程)の「社会学的移民研究」、「異文化対応能力」、「コードスイッチング」、「教育学における多様性」、「イスラム入門」などにも参加させていただきました。

オスナブリュック大学食堂にて
法学部の学生はおしなべて向学心・探究心に燃え、大教室での講義であっても、末席で居眠りしている学生を見掛けることはほとんどありません。講義の大半で、担当教官が指定した著作物の内容を巡り、教官と学生の間、そして学生同士の間で熱い論戦が繰り広げられます。例えば、読後に求められるのは、そこに書かれている内容そのものに対する理解だけではなく、それに対する疑問点であり、作者のバックグラウンドとそれを著した理由であり、更には、それを批判する論理的な思考方法です。この点、ひたすら受け身で「課題に追われる」日本独自の詰め込み教育や、「代案なくして批判なし」がまかり通る日本の風潮とは対照的に、「議論が出来るようになるための知識を学ぶ」ことがドイツではいかに重視されるかを痛感させられました。疑問点はその場で納得行くまで解決します。裏を返せば、内容を正確に理解出来ずに、講義にいったん付いていけなくなってしまうと、それを取り返すのは至難の業となります。当然ながら最初のころは、想像していた以上にドイツ語での授業内容が難解で、知らない単語を書き留めることやノートを取ることもままならなかった私は、当然授業に置いていかれることになりました。予習復習をしようと必死に教科書と向き合っても、一頁分の単語を調べるだけで最低三〇分掛かります。その後で内容を理解するためにテキストを読み直すのですが、それに更に三〇分、つまり一頁読解するのに合計で一時間を要するという有り様でした。ところが毎回の授業では、何と約二〇-四〇頁分進んでしまうのです。それらすべてをカバーするのは、到底不可能でした。ドイツ語の法律用語に悩まされ、一こま分集中力を保てずに、授業に付いていけずに半分上の空になってしまうようなこともありました。日常生活ではコミュニケーションに何の不便も感じなかったのに、授業では、自分のドイツ語能力不足にいらだち、いつまでも進歩を実感出来ない日々に焦りを感じ、不安や劣等感にさいなまれながら、最初の半年がむなしく過ぎていきました。

オスナブリュック大学中庭にて
自分のドイツ語能力が伸びたと実感出来たのは二〇一一年の四月、ドイツに到着して半年が過ぎたころでした。前期と同じ先生の刑法2の授業で、一こま分、最後まで集中し通すことが出来て、分からない単語も聞き取ってノートに書き留めることが出来るようになったのです。二月に行われた期末テストでは、準備期間も試験当日も涙を流す日が続いていたのに、後期になってどうして急に伸びたのか……。一大転機となったのが、後述する春休みに参加した地方裁判所での一カ月間の研修だと思います。裁判所での研修では来る日も来る日も資料読解に追われ、その内容について少人数でディスカッションを行いました。頻繁に使われる法律用語は繰り返し登場するので、自然と脳裏に焼き付いていきました。その一カ月間を通して、法律用語に対する理解力が格段と向上して、大きな壁を乗り越えられたことを実感出来るようになりました。
ICC見学で裁判を傍聴
アジア最大規模の国際法学生団体である「ALSA」は、中央大学にも支部がありさまざまな活動を繰り広げています。そのヨーロッパ版に当たる団体が「ELSA」です。私はオスナブリュック大学に到着して早々、この団体のメンバーに声を掛けられて、一年間に期間を限定して入会し活動に参加することになりました。ELSAが企画した二〇一〇年冬学期の二泊三日の視察・調査ツアーの目的地が、オランダ・ハーグの国際司法裁判所でした。私を始め四カ国・八人の交換留学生を含め計二七人で、バスをチャーターしてオスナブリュックからオランダ・ハーグに向かいました。
初日はICCとドイツ大使館を、二日目には旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷(ICTY)を訪問し、施設や沿革についての説明を受け、現役の裁判官と直接話したほか、実際に開廷中の裁判も傍聴しました。
ICCの建物内に入るためには厳しい身体検査・身分調査を通過しなければなりません。イメージとしては、空港の検査よりも一人一人に時間を掛けてチェックしている感じです。ポーランド人の友達の上着のポケットに小型アーミーナイフが入っていたのですが、それを見付けた警備員はすさまじい剣幕でなぜそのような物を持ち歩いているのかと問い詰め、その威圧感には間近にいた私も身がすくむ思いをしました。入館自体が誰にでも認められているわけではなく、事前に予約した、正当な理由がある、セキュリティーチェックをクリアした者だけが入館を許されます。また、入館後も手荷物はすべてロッカーに入れなければなりません。携行を許されるのは、ノートとペンと貴重品のみです。

デン・ハーグの国際司法裁判所の前で
所内ではまずICCの裁判官を務めるドイツ人から、ICCに赴任するまでの経緯を始め、ICC創設のいきさつやさまざまな内部情報について話を聞きました。休憩を挟み、午後は裁判を傍聴しました。案内されたのは、日本の裁判所のように後ろ側に傍聴席が設けられている法廷ではなく、傍聴席が分厚い防弾ガラスで仕切られていた調停場であり、場内の会話を聞くためにはオーディオガイドをオンにする必要がありました。私たちが傍聴した裁判の被告は、コンゴ人で当時のコンゴ解放運動(MLC)の指導者であったジャン=ピエール・ベンバ氏です。彼が訴えられていた内容は、裁判犯罪としての殺人と強姦、そして、人道に対する罪としての殺人と強姦です。審議では、当時、彼が自らの意思で団体を主導し、メンバーにそれらの行為を率先してやらせたのか、それとも彼自身が当時の政府から相当の圧力を掛けられて動かざるを得なかったのかが争われました。私たちが傍聴したのはその第二回公判でした。ですから証人が召喚されたりして、大変興味深かったです。証人(当時のMLCの一メンバー)は、ベンバ氏が自らの関心・興味に駆られてそれらの犯罪を行ったと証言していました。しかし第一回公判では、ベンバ氏に圧力を加える政府の手紙などが証拠品として採用され、被告人の関与した殺人行為は、自らの意思によるのではなかったのでは、という議論がなされていた、とのことでした。今回の公判でも決着はつかず、次回には被害者の一人が証人として召喚されることが決まり閉廷しました。

私の誕生日パーティーにて
審理はすべて英語で行われ、必要に応じて通訳が入ります。また、証人が入廷する際には、証人の身の安全を保証するために、傍聴席と調停場とを仕切るガラス板がカーテンで覆われるほか、証人が通る場内の通路自体もカーテンで隠され、更に、オーディオガイドにより音声も変えられます。紛争当事者は基本的に検事と被告人です。裁判では、関係者の人種が偏らないように配慮がなされます。このため弁護団、検事側とも、黒人・白人がほぼ同数となり、またその三分の一は女性です。裁判官は三人列席しています。傍聴席では私語は一切禁止されており、銃を所持した警備員も配備され、異様な空気が漂っています。この日は、五〇〇万人以上の犠牲者が出たといわれるコンゴ内戦の反カビラ勢力(MLC)のリーダーが被告席に座り、彼が率いる団体の行動の裏に政府の意向があったかどうか、審理が行われていましたが、私は、警備の厳重さにあぜんとし、威圧感に完全にのみ込まれて、そこにただじっと、一人の人間が裁かれるというその事実の重みを再認識しながら、座っているだけでした。
今回の視察旅行は、二泊三日と限られた日程ではありましたが、内容的にはとても濃いものでした。留学前には、ICCを見学出来る機会が訪れるとは、夢にも考えていませんでした。実際にこの目で見た裁判所の威容と傍聴した法廷の威厳は、この先も私の中で、何らかの影響を与え続けることになると思います。
地方裁判所での研修
ドイツの学生にも、当然ながらさまざまなインターンシップの場が提供されています。特に法学部の学生の場合は、裁判所で研修を受けることが大学卒業の要件となっており、それをサポートする国の意向により、裁判所は毎年、法学部の学生を四週間ほど研修生として受け入れることを義務付けられています。今回は私を始め六人の交換留学生が裁判所でのこの実地研修に応募しましたが、オスナブリュック大学の法学部学生担当のチューターの支援もあり、無事受け入れられることになりました。オスナブリュック大学の法学部の学部長も留学生のために裁判所に直接お願いしてくださったと聞きました。このため私は春休みの四週間を利用して、ドイツ人学生に交じりオスナブリュック地方裁判所における研修に参加することが出来ました。

学生寮のキッチンにて
私を含め外国籍の研修生六人には、実際の研修が始まる前に五日間の準備期間が設けられ、一-三人から成る小グループに分かれて、予備研修が行われました。裁判官を始め裁判所でさまざまな職務を担当する職員の話を聞いたり、実務を見学したり、実際の仕事の手助けをしたりと、盛りだくさんのプログラムが組まれていました。例えば遺言執行人の職務室で、実物の遺言状のほか、無効な遺言状、有効な遺言状の例を見せてもらったこともあれば、裁判官と一日行動を共にすることもありました。私が同行した裁判官は、朝一番に、二時間以内に目を通すようにと、彼が担当している二つの事件の記録を手渡してくれました。そのうちの一件は、認知症を患う高齢女性の後見人である娘が、拘束ベルト付きの介護ベッドの使用許可を求めた案件であり、夜間の身体拘束が患者の行動を制限する自由剥奪に当たらないか、裁判所に判断が求められていました。ドイツでは、「身体の自由を奪う」行為の是非について、すべての事例において、裁判官が直接判断を下し、許可する場合は指定の書式にその旨を記入することになっています。当事者は、この許可証がない場合、実際に行動に移ることが許されないことになります。裁判官は、ただ単に書類を審査して判断するのではなく、患者本人の現在の症状を実際に自分の目で確認します。日本のように調査官を利用することはありません。その日は私も裁判官に同行して患者が居住する老人介護施設を訪問しました。患者本人と施設職員に対する審問は、私も同席の上で行われました。
外国人留学生を対象とした予備研修であるのに、しかも私は、法律を学び始めたばかりの学部生に過ぎないというのに、そんな私を、現役の裁判官が「生」の事件現場に帯同する……日本の裁判所では、果たしてこのような研修が行われた試しがあるのでしょうか。
今回の四週間の研修本番には、約一〇〇人の研修生が四つのグループに分かれて参加しました。私のグループを担当したのは、研修前半の二週間が民事訴訟法を専門とする現役の裁判官であり、後半二週間も同様に、今度は刑事訴訟法を専門とする現役の裁判官でした。

訪れたオランダのマーストリヒトにて
裁判所での一日は、基本的には午前中の学習時間から始まります。判事を始めとし裁判所の書記官や職員、そして弁護士などによる講義やブリーフィングが行われたり、裁判所のさまざまな部局の実務を実際に間近で見学したりなど、ドイツの法体系や裁判所の業務全般に関して理解を深める機会が設けられていました。午後は主に全体ミーティングが開かれ、午前中の活動内容に関して意見交換したり、今後傍聴が予定されている裁判の事件記録を閲覧する時間に当てられたりしました。事件記録はすべて所外への持ち出しが禁止されていたために、所内にいる時間を利用して閲覧する必要があったのです。
中でも特に強く印象に残っているのは、家族法を専門とする女性判事の講義です。彼女によると、家事事件では一方の当事者に到底納得の行かない決定を下す場合もあるそうですが、過去にそのようなケースにおいて、担当裁判官に後日嫌がらせや脅迫の電話が掛かってくることがあったというのです。最悪の場合、裁判官の娘の後を付け回したり、裁判官の自宅前で張り込んでいたりと、想像も出来ないようなことが起こるそうです。このため今では、何と家事事件を担当する裁判官の本名や住所を伏せて審理が行われているとのことです。
またある事件の裁判を傍聴した時には、面白い場面に遭遇しました。法廷に召喚された証人が、明らかに矛盾する証言を行ったのです。傍聴していた私は、それに気付きながらも、何かおかしいなと思っただけでそのまま聞き流していました。ところが裁判官は、この証言を受けて、証人の召喚を求めた原告に対して、その場で次のように言い放ったのです。
「今すぐ退廷して、代理人と相談の上、方針を決めなさい。このままだとどうなるのか、ご存じですね」
それを聞いた原告側の二人は顔面蒼白となり退廷し、しばらくして再度入廷するや否や、「訴訟を取り下げます」と申し出たのです。
私のグループの担当裁判官が後から説明してくれましたが、訴訟を取り下げた理由は証人の虚偽の証言にあったそうです。証言が虚偽であったことが後日判明した場合、敗訴は当然として、証人も実際問題として偽証罪に問われ禁固刑に処せられることがあるそうです。この事件の証人は、原告の妻であり、原告は、妻が偽証罪に問われるのを回避するために、弁護士と相談の上、訴訟を取り下げ、被告の主張をのむことにしたとのこと。また、原告が妻に偽証を求めたことが万一発覚した場合は、更に重い罪が課せられるそうです。今回の事件では、どうやら証人である妻が、もとから夫に対してもうそをついていたようでした。
証人の偽証を見抜き、その場で善処した裁判官の機転には、深い感銘を受けました。
またドイツの司法試験制度についても、とても貴重な詳しい情報を得ることが出来ました。
ドイツの法学部の学生は、一次司法試験の合格が、卒業のための必要条件となります。法曹を志望する場合は、一次司法試験に合格した上で、二次司法試験を受験し合格しなければなりません。ドイツでは司法試験制度の運用が極めて厳格に行われています。一次も二次も、受験機会は二回だけ、二回不合格になった時点で、司法試験の受験資格が永久に剥奪されます。このため最初の試験で不合格になると、かなりのプレッシャーを感じ、二回目の受験に臨めないほど精神的に追い込まれて結局受験を断念する学生も多々いるそうです。実際には司法試験の合格率は、約八割であるといわれています。しかしこの高い合格率を別として、ドイツの司法試験と日本の司法試験との最大の相違点は、司法試験の成績が合格者に一生付いて回る点にあるといえます。このため、たとえ司法試験に合格しても、その成績によっては裁判官・検察官・弁護士の法曹三者に就く道が完全に閉ざされることになります。実際にドイツの裁判所で勤務している職員の大半は、司法試験の合格者です。司法試験に合格しながらも抜群の成績をあげられなかったために、本来の希望職に就くことが出来ずに、企業の法務部や管理部、カウンセリング部門で働いている人がたくさんいるそうです。
ドイツでは、前述のように二回不合格になると受験機会は生涯二度と与えられません。一方日本の新司法試験では、確かに五年間に三回と受験回数が制限されてはいるものの、再度受験資格を取得するために法科大学院に入り直すことをいとわない限り、基本的には何度でも受験機会が与えられることになっています。この点で、法曹三者を目指す限り、ドイツの司法試験の難易度は、日本の司法試験と変わらないのかも知れません。日本の司法試験があまりにも難関であると評されているが故に、欧米での受験を考えたこともある私にとっては、貴重な情報でした。
夏学期

ワイマール近くの橋の上にて
四週間にわたる充実した地方裁判所での研修を終え、留学後半の夏学期を迎えた私は、知らぬ間に、自分でも意外なほどドイツ語能力が向上していたことに気が付きました。授業前にプレッシャーを感じることもなく精神的にゆとりが生じ、授業にも熱が入り、プレゼンテーションもこなせるようになりました。これは生活面にも反映され、学生の誘いを受けたら一緒に食事に出掛けたり、週末・休日を利用して隣国へ出掛けたり、渡独後九カ月間も休んでいた部活動の練習を再開したりと、大学以外での活動も充実してきたことにより生き生きした生活が送れるようになりました。前期には一度も顔を出したことがなかった、毎週水曜日の夜に英文科の学生が主催する英語の映画観賞会にも参加するようになりました。ドイツ語能力が向上したことで、自分から積極的に自然に話し掛けることも出来るようになり、地元の方との交流も始まりました。日本に興味がある方々とお会いし、談笑することもありました。彼らは私よりも日本の古い文化や東京の下町のことをよくご存じで、お話しするのがとても楽しかったです。
帰国して
二〇一一年の秋から本学に復学し、必修の語学の課題の多さと部活動に再び悲鳴を上げる毎日が始まりました。私がオスナブリュック大学で履修した単位・成績を証明する成績証明書の発行・送付が大幅に遅れ気をもみましたが、先日ようやく法学部事務室に提出し、面接を終えることが出来てほっとしています。今はオスナブリュック大学で取得した単位が本学で認定されるかどうか、国際交流委員会・教授会の審議・決定を待ちわびているところです。
二〇一〇年春、南ドイツの難民支援団体での研修を終えた後、私は、将来は難民支援関係の仕事に携わりたいと、一時的に真剣に考えていました。しかし今回の留学で得たさまざまな知見と体験から、改めて自分自身の将来について、難民支援関係に限定するのではなく、大学院への進学や就職の可能性も含めて、総合的に見直す時期に来ているのではと感じています。いずれの道に進むにしても、留学で得たものすべてが今後の私の糧になることは間違いありません。最後に、立て続けに二度も留学の機会を与えて支えてくださった関係者の皆様に心からお礼を申し上げます。
草のみどり 253号掲載(2012年2月号)