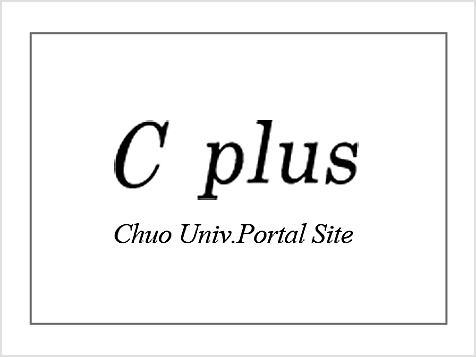法学部
【活動レポート】植竹 淳 (法律学科2年)
「やる気応援奨学金」リポート(29) オーストラリアで英語を学ぶ 日本を飛び出し自信を付ける
はじめに
私は中学生のころから「いつか海外へ1人旅をしてみたい」と漠然と夢見ていた。だがしかし、いつかいつかと先延ばしにしているうちに、気が付けば大学2年生になっていた。というのも、きっかけがなかったのだ。いや、きっかけがないと決め付け、自分の心に都合の良いようにうそをついていたのかも知れない。本当は、自分自身に自信がなかったのだ。大学入学時に、法学部の「やる気応援奨学金」の話を耳にした時も「自分には無理だ」と勝手に決め付け心の奥底にしまい込み、しまいには忘れていた。
私がこの奨学金の話を次に耳にしたのは、私の友達からである。友人が奨学金の審査に通り、留学したのだ。そこで経験してきたさまざまな事柄を生き生きと話すその姿に、私は感化された。素直にうらやましいと思った。そして私の身近な人が審査を通ったことによって、今まで遠い存在であった「やる気応援奨学金」が、ほんの少し近いものに感じられるようになった。私の海外へ行きたいという漠然とした思いは、違った世界に飛び込みたい、日本では味わえない経験をしたい、異文化に触れたい、外国の人々と意見を交換したい、というはっきりとしたものへと変わり、留学への願望は次第に強まっていった。そこで、自分に挑戦するうえでも、海外へ行くためにもこの奨学金に足を踏み出す決心をしたのだ。
私は夏季休暇を利用し、5週間オーストラリアのメルボルンへ行ってきた。以下では、この「やる気応援奨学金」を利用して実施した語学留学とボランティア活動を通して私がどのような経験をしてきたのかを述べたいと思う。
スタートのスタート地点

私は最初、いわばスタートのスタート地点であるアプリケーション(奨学金の申請書)の作成段階から何度も壁にぶち当たっていた。なぜなら、正直にいって私は英語が苦手だからだ。アプリケーションフォームを英語で作成しなければならないのは、私にとってはものすごく高いハードルであった。そのうえ、活動計画作成に当たって、まず何から調べるべきなのか全く見当が付かなかったのだ。それでも、先生やリソースセンターの方々、そして時には以前同じ奨学金を得て短期留学を経験した友達に相談し少しずつ少しずつ前進していった。不思議なことに、最初は悩みの種であったこの作業が、時間と共に楽しくなっていったのだ。自分の活動を自分自身の手で作り上げるこの作業は、自然と私を夢中にさせたのであろう。語学学校の講師の方から、英語のメールが返ってきた時に感じたあの興奮は今も覚えている。そして、やっとの思いでアプリケーションフォームを完成させた。この作業を通じて、以前にもまして海外へ行きたいという気持ちが高まっていったように感じる。それだけに合格者名簿に自分の名前が載っているのを見た時の喜びは格別だった。この奨学金は私にとってはただの奨学金ではない。ある意味では自分の殻を破るうえでの課題でもあったのだ。
始動
奨学金を得て、海外へ行けるということが決まり、私はやっと留学という自分の目標のスタートラインに立つことが出来たのだ。日本をたつ日が近付くにつれて不安感も募っていったが、それと同時にこれから始まる人生で初めての留学生活に胸が躍っているのも事実であった。
日本を飛び立ち16時間という長い空の旅を経て、ついに私はオーストラリアの地を踏んだ。日本語の標識はどこにも見当たらない。当然のことなのだが、私にとってはとても新鮮であった。まさに新天地に来た気持ちである。
空港で語学学校のスタッフの方と合流し、これから約1カ月間お世話になるホームステイ先へと向かった。30分もたたないうちに目的地に到着した。家の前に立ち、恐る恐るブザーを鳴らす。応答を待っている間、私の心臓は緊張のために激しく鼓動していた。すぐにドアが開き、まずは元気良く犬のグリフィーが飛び出し、それを追うような形でホストマザーのメルと、ルームメートのスーファンとヤンミンが笑顔で出迎えてくれた。私はあまりにもアットホームなこの光景に、どこか肩の荷が下りほっとした。とはいうもののやはりまだ私の表情は硬かったのだろう。メルは「疲れているの?」としきりに私のことを心配してくれていた。長時間のフライトのために疲れているのは事実であったがそれよりも、これから始まる生活や言葉の壁への不安が表情にも表れていたのだと思う。そんな私の心理を察したのか、ルームメートの2人が積極的に話し掛けてくれた。この2人は非常に英語が上手で、会話に付いていくのが必死だった。そのため、せっかく話し掛けてきてはくれるものの私が英語に慣れていないために、会話はどこかちぐはぐであった。それでもこの2人は親切にも、私のペースに合わせてゆっくりと話してくれた。
このように、私の留学生活はぎこちないながらもスタートしたのだ。
いざ、語学学校へ
語学学校の初登校日はオーストラリアに着いた次の日であった。この日私はどこか浮き浮きしていた。トラム(路面電車)の中から新天地の景色を見ていると、いよいよ私は海外へ来たのだという実感がわいた。何げなく眺める木々や道路、英語で書かれたショップの看板など、何もかもが私の目には新鮮に映るのだ。目立つ建物が私の横を通り過ぎるたびに、隣に座っているヤンミンがその建物についての説明をしてくれた。外の景色に見とれているうちに目的の駅に着き、そしてそこから少し歩くとほどなくして、これから1カ月間通うことになる語学学校に到着した。この日の予定はテストを受けた後、その結果に応じて自分のレベルに適したクラスへ参加することになっていた。クラスを分ける重要なテストであるだけに私は少し緊張していたのだが、語学学校の先生方が皆非常に優しくて安心した。

テストの後、初めて生の英語による授業を受けた。そこでの授業は私が想像していたよりもかなりシビアなものであった。なぜなら、授業形式は先生が生徒を指名して答えさせるのではなく自分から進んで答えるといったもので、能動的に授業に参加するという姿勢でなければ取り残されてしまうからだ。これは日本で私が受けていた授業形式とは大きく異なっていた。この日の私は授業中に発言するどころか、流れに付いていくのでさえ必死であった。慣れない環境に置かれ、必死で英語を聞き取る作業は精神的に疲れる。そして一言も発言出来なかったことに対して、私はもどかしさと悔しさを感じた。「明日こそ、少なくとも3回はみんなの前で発言しよう」と自分に小さな目標を課しこの日の授業は終了した。
そして次の日から私は自分の気持ちを引き締めて、恥をかくつもりで授業に臨んだ。そして翌日の授業中、見事にちんぷんかんぷんな英語であったのだろう、先生は意気込み勇んで発言する私を見て不思議そうな顔をし、クラスメートたちもそれを見て静まり返った。自分の顔が赤くなっていくのを感じた。しかしどうにか私の伝えたいことを把握出来たようで、先生は熱心に教えてくれた。1回恥をかいてしまえばこっちのもので、分からないことがあればその都度先生やクラスメートに聞き、当初のノルマである「3回発言計画」は十分に達成された。日を追うごとに授業形式にも慣れ、能動的に授業に参加出来るようになっていった。そして、心にゆとりが出来たためなのだろう、徐々に英語で話すことに楽しみを見いだせるようになっていった。
「日本人はスピーキング能力がない」ということをよく聞くが、まさしく私もその日本人の中の1人であるだろう。同じクラスメートでほかの国から来ている人はべらべらと英語を話すのにもかかわらず、文法のこととなると正答率が低かった。私はその逆である。まず自分の頭の中で日本語を思い浮かべ、次に文法を意識して英語へと変換してから話す。これでは、正しいかそうでないか分からない英文が出来上がったところで、その場の話題は次のものへと変わってしまっているだろう。スピーキング能力が低いという問題の理由には、日本語と英語の文法が全く違う、ということも挙げられるだろうがやはり何よりも大きな要因は、日本の教育方式にあると感じた。中学・高校では主にリーディングとライティングの勉強ばかりで、英語を話すという機会がほとんどない。もちろん、単語や文法を学習することも重要であるとは思うが話せなければ元も子もないだろう。文法と単語さえ学べば英語が話せるようになるといったことは絶対にないように感じた。単語を素早く頭の中で結び付け文章にし、それを発する能力は今の日本の教育体制ではなかなか育まれないのではないだろうか。
語学学校に通うのに慣れる一方で、今までは気付かなかったことも見えてきた。それは、休み時間になると出身国ごとにグループ化するというものである。特に日本人においてはそれが如実に表れているように感じた。私はそれが嫌いである。同じ国の人同士で固まって、母国語で話すことはそんなに楽しいのであろうか。少なくとも私はそうは思わない。単身で海外へ来て寂しいという気持ちも分からないではないが、英語を学ぶために語学学校に通っているのだからそれでは本末転倒である。私は出来る限り日本人との交流は避け、グループの中に日本人がいても、日本語で話すといったことはしないように心掛けた。ここでの共通語はあくまでも英語である。

放課後は同じ語学学校の友達と遊びに行くこともあったが、主にルームメートと共に過ごした。彼らは本当に親切で、慣れない私を気遣ってかよく遊びに誘ってくれた。時には彼らの友達のホームパーティーにまで連れていってくれたのだ。そして家では映画を見たり互いの文化について語ったり悩み事や将来の夢などについて、ああでもないこうでもないと夜遅くまで話した。私は彼らに比べて英語が話せないのだけれども、だからこそ英語を学ぶ意欲を得た気がする。友達ともっと話したい、相手に自分の気持ちをもっと伝えたいという素直な気持ちが自然と英語を学ぶ意欲につながったのだ。
私が思うに英語で意思の疎通をするうえで、もちろん「語学力」というものは絶対的に必要なのだが、それと同じくらい必要なものは「ユーモア」ではないかと思う。英語を話せてもその会話がつまらなければ、相手はそれ以上話したいとは思わないであろう。日本語と同様、英語においても「ユーモア」や、会話により深みを持たせるための幅広い知識が必要であるように感じた。
惜別の時
楽しく、充実している日々は早く過ぎ去るもので、あっという間に1カ月が過ぎた。そして待っているのは、別れである。
私が家をたつ前日、韓国人のルームメート2人が私に“Jun, you are our best friend, you are our brother. We miss you so much.”(淳、お前は俺たちの最高の友達だ、俺たちの兄弟だ。別れるのが寂しいよ。)と言ってくれた。屈強な男2人が目に涙をためているのだ。客観的に見たら少し気持ち悪い絵であったのかも知れないが、私は非常にうれしく目頭が熱くなるのを感じた。当初は外国の友人が出来るのか心配に思っていただけに、この言葉は私の胸に響いた。自分が心を開けば相手はそれに応じてくれる。たとえその相手が日本人でなくても、だ。この1カ月で私はそう感じた。相手に求めるのではなく、まず第1に自分自身が変わることが相手へ近付く1番の近道だ。最後の最後まで別れを惜しみながら、私は次の目的地へと向かった。
大自然の中で
語学学校を卒業した後、私はボランティアに参加した。そのボランティア団体は、CVAと呼ばれ、オーストラリアで1番大きな環境保護団体である。1チームあたりリーダーを含めて10人程度で編成されており、その活動中は簡易ホテルなどに寝泊まりする。私たちが寝泊まりしていた施設は暖房器具が故障していて、夜になると非常に寒かった。何しろ日本が夏の間、南半球に位置するオーストラリアは極寒の冬なのである。更に悪いことにシャワーを浴びる際にはお湯を使うことが出来ず、体を洗うためには毎晩外にある簡易浴場で水を浴びなければならなかった。仕事が終わった後に浴びる冷水シャワーは身にしみた。
私たちが担当した仕事は、植物プランティングであった。この仕事は単純な作業で、まず穴を掘りそこに木々を植えた後、植えた植物が動物に食べられてしまうのを防ぐためにビニールで囲いを作るというものである。毎日午前9時から午後4時まで活動し、1日あたり600本以上の苗木を植えていった。

単純な作業を淡々とこなすのは、非常に骨の折れる仕事である。だが、やはり汗をかくことは気持ちが良かった。そして、私たちの植えた苗木が20年後には森林となって地球の環境をより良くしてくれるのだ、ということを思い描くと自然と心が弾んだ。このボランティア期間中には、仕事だけではなく「オーストラリアの環境を知る」という理由でリーダーが私たちをさまざまなロケーションへと連れて行ってくれた。そこで見た壮大な景色は今も目に焼き付いている。
実際に体を動かすことで、自然を守ることの大切さやその厳しさを身をもって感じることが出来た。このボランティアを通じて、精神的にも肉体的にも強くなったように感じる。
最後に
私はこの活動を通じて、夢が明確なものとなった。その夢とは、弁護士になることである。オーストラリアへ行き、語学学校で英語を学んだことと弁護士になることには何の関係があるのか、と疑問に思うかも知れない。しかし、この留学で得られたものは語学力だけではない。むしろ、私は「語学力」にも勝る大事なものを得た気がする。それは自分の可能性を信じる力、すなわち「自信」である。
以前までの私だったら、たとえ弁護士になりたいと思っても、その夢に向かって行動を起こせていなかっただろう。だがこの留学を成し遂げたことにより「もっと自分の可能性を信じてみよう」と思えるようになった。もちろん流れに身を任せるだけではなく、自分から積極的に行動しなければこの結果は得られなかっただろうと思う。この留学で得たたくさんの経験や知識は、私の貴重な財産となった。そして、その財産を輝かせられるかは私の手に委ねられている。
留学を終えてすぐに私は予備校に通い始め、現在も夢に向かって勉強をしている。必ずしも弁護士になれるという保証はない。そしてこの先、私にはつらく長い道のりが待ち構えているだろう。しかし私はこの道を突き進もうと決心している。絶対に後悔したくないからだ。自分の可能性を最初から否定したくはない。自分を信じ、挑み続けようと思う。私の人生の壮大な旅はまだ始まったばかりだ。常に問われるのはこの奨学金と同じく「やる気」であろう。
そして最後になってしまったが、この留学は決して私1人の力によって成し遂げられたものではないと思っている。この機会を提供してくださった学校関係者の方々、悩んでいる時に相談に乗ってくれた友達、留学期間中に知り合った人々、私のことを心配しながらも応援してくれた親など、さまざまな人の支えがあってこその成功である。私を支えてくださったすべての人々に感謝している。
草のみどり 203号掲載(2007年2月号)