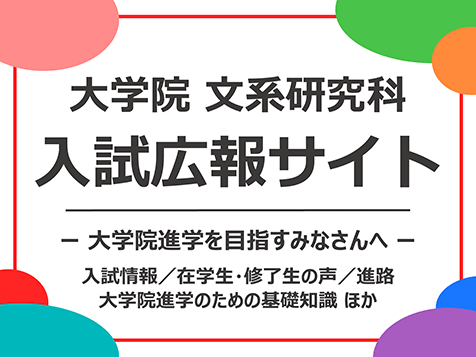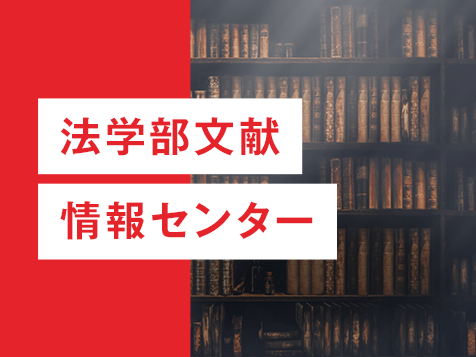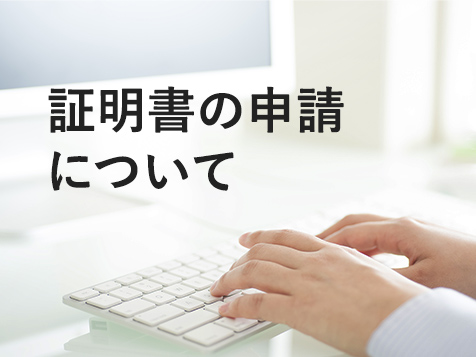法学研究科
法学研究科委員長挨拶
― 大学院での法学研究への誘い ―

只木 誠 法学研究科委員長
大学院制度が発足した1951(昭和26)年に設置された中央大学大学院法学研究科は、以来、半世紀を超えて、研究者、実務家等、多くの優れた人材を社会に輩出してきました。1885(明治18)年に「英吉利法律学校」として創設された際の「實地應用ノ素ヲ養フ」という建学の精神は、本学における法学研究・教育の根幹をなすものとして現在に受け継がれる近代的な法治主義、経験に基づく自由主義、社会性を伴う実用主義そのものであり、法学研究科における研究・教育の目的もまたそこにあります。その後、2004(平成16)年には、法曹養成に特化した法務研究科が新たに設置されましたが、法学研究科、法科大学院それぞれに別個の特性を有するなか、法学研究科が従来負っていた研究者養成と高度専門職業人の育成という目的はいささかも変わることなく存しています。
公法、民事法、刑事法、国際企業関係法の法律系4専攻と政治学専攻1専攻の5専攻からなる本学法学研究科では、各専攻分野それぞれに多様な専門科目が設置されており、大学院生ひとりひとりの多様な学問的ニーズに柔軟に対応することが可能です。研究指導に携わる約70名の専任教員(法務研究科所属の専任教員も含む)の専門分野も多彩で、法律学をはじめとして経済学、財政学、政治学、行政学、社会学といった多分野にわたっており、社会のグローバル化に伴ってますます進展している法律、経済、政治など各分野の相互依存関係、ボーダーレス化のなか、各教員ひとりひとりが、複雑化した社会現象を把握するために求められている専攻分野以外のオルタナティブな視座を大学院生とともに模索すべく力を傾けています。
さらに、本学には、公法研究会、基礎法学研究会、民事法研究会、刑事法研究会、国際関係法研究会、政治学研究会、国際関係研究会などの専門研究会があり、これらの研究会には大学院生も自由に参加することができます。また、日本比較法研究所、社会科学研究所、政策文化研究所の各プロジェクトに参加し、学内外の研究者の先端的研究に触れ、将来につながる学問的交流を深める道も開かれています。
大学院における法学、政治学研究の実践は、自分の研究テーマを設定し、文献を集め、検討を加えつつ自己の考えを論文にまとめ上げることですが、その際、みなさんにはふたつのことが求められることになるでしょう。そのひとつは、広い周辺知識によって得られる確固とした視点のもと、異なる解釈に立つ解決策からもたらされる利益の相違を突き詰め、問題解決にまつわる種々のベクトルを総合することのできる能力、すなわちリーガルマインドであり、そして、もうひとつは、正義の実現を標榜する法学者として、社会を直視し、法の解釈を通じて社会的正義の実現に貢献しようとする高い志と熱い情熱です。
フランスの作家アンドレ・ジッドが語ったといわれる「真実を探している者を信じよ。真実を⾒つけた者を疑え」という箴言は、よく引⽤される⾔葉です。いくつもの要素が複雑に絡み合う、その部分集合とでもよぶべきところに真実を⾒いだそうとする法の研究という作業にあって、他の学問においてもそうであるように、求める真実は容易には⾒えて来ませんが、しかし、社会においてより妥当する「真実」を探究することの意義は深く計り知れません。
みなさんには、ぜひ、本法学研究科において、法学研究者としての資質をより高め、深めた知識をスキルとして大きく羽ばたいていただきたいと考えます。本学法学研究科は、そのための万全の環境を整え、みなさんをお待ちしています。