経済学部
経済学部「交通経済論」にて全日本空輸株式会社(ANA)様による特別講演が行われました
2025年08月25日
2025年7月7日(月)、「交通経済論(担当:後藤 孝夫)」にて、全日本空輸株式会社経営戦略室企画部事業戦略チームの石田さまをお招きし、「ANAグループの歩みと経営戦略」というテーマでお話しいただきました。
石田さまは入社以来、伊丹空港の旅客係員や客室乗務員の人員計画・働き方の検討などに従事されていましたが、現在は企画部事業戦略チームに所属し、ANAグループの事業戦略の立案に携わっておられます。
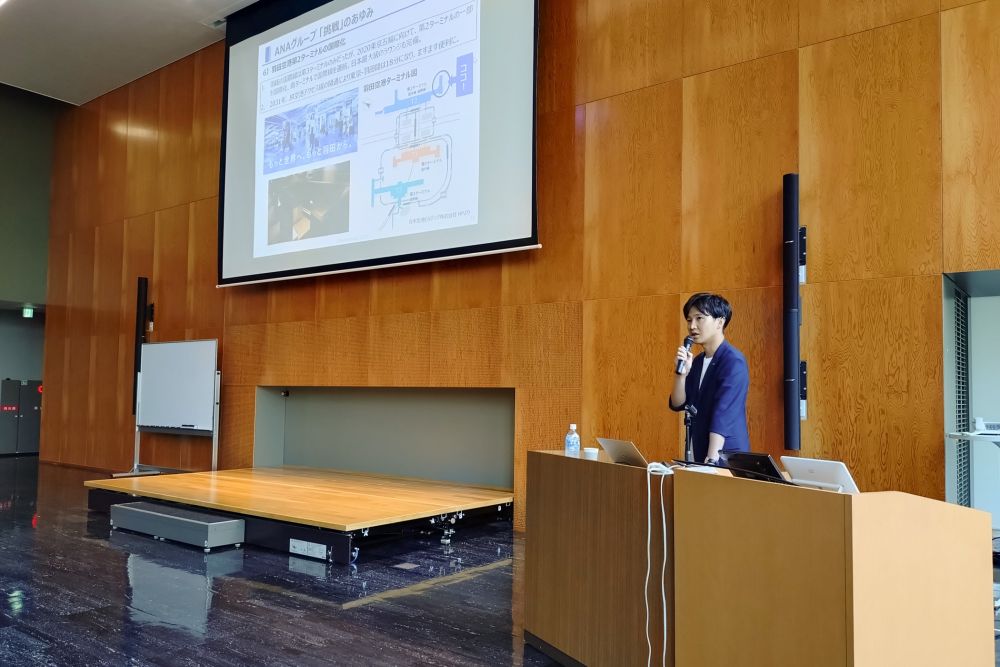
講演ではまず、経営理念、安全理念ならびに新経営ビジョンについてご説明いただきました。ANAグループは「安心と信頼を基礎に世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献する」ことを経営理念に掲げ、航空事業、航空関連事業および旅行事業など多岐にわたる事業を展開しています。2024年度のグループ全体の売上高は2兆2,618億円に達し、日本有数の大規模なネットワークを誇る航空会社です。しかし、前身となる日本ヘリコプター輸送株式会社が1952年に発足したときは、2機のヘリコプターと役員12名、社員16名の小さな会社でした。
創業からいまに伝わるベンチャー精神を表した「まずはやってみよう!」という思いのもと、大きな成長を遂げたANAグループ のこれまでの「挑戦」のあゆみもあわせてご説明いただきました。
規制や制限の多かった戦後の日本の航空市場のなかでも、1986年の国際線定期便初就航、1999年のスターアライアンス加盟によるネットワーク拡充、2010年の羽田国際化を通じてANAグループは国際線事業を拡大しました。コロナ禍では、邦人退避や医療関連物資の輸送といった公共交通機関としての使命を果たし、社外出向などの施策で自社の雇用を維持しました。これにより、アフターコロナの成長段階への対応を可能にし、2023年度からはグループの航空事業における第3ブランドであるAirJapanを始動させ、アジアを中心としたインバウンド需要獲得を目指しているということです。
そして、航空業界を取り巻く環境の今後の変化について、①コストの増加、②国内線事業、③国際線事業、④航空貨物事業および⑤深刻な人材不足の5つの側面からご説明をいただきました。
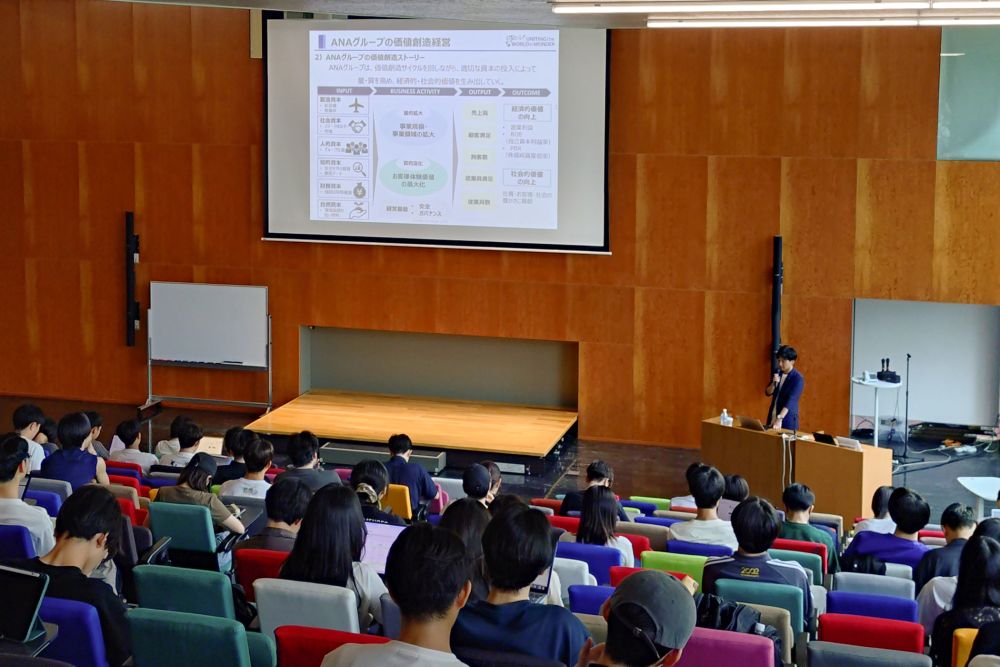
さらに、グループが現在推進している「価値創造経営」についてもご紹介いただきました。これは、人財への投資、基本品質・生産性の向上、お客様の喜び、ANAグループの社会的・経済的価値向上、グループ社員のエンゲージメント向上というサイクルを循環させるものです。特にDX(デジタルトランスフォーメーション)を経営の基盤と位置づけ、業務変革、省人化、効率化ならびに生産性向上を目指しているとのことです。
具体的には、最新鋭訓練施設である「ANA Blue Base」での教育や、DXを活用した空港・貨物ハンドリング業務の自動化により、基本品質と生産性を向上させています。また欧州3都市への新規就航で新たな旅の選択肢を提供し、大阪・関西万博のPRサプライヤーとして機運醸成に貢献しました。さらにドローン物流やエアモビリティといった新たな移動サービスの事業化への挑戦についてもご説明いただきました。
社会的・経済的価値の向上では、GXの観点で、2050年までのカーボンニュートラル実現を目指したSAF(持続可能な航空燃料)の活用や大気中のCO2を直接回収する技術への投資に取り組んでいます。また、地域創生の観点では、遊休農園の運営や地域への人財派遣を通じた地域課題の解決への貢献についてもお話をいただきました。
さらに、社員エンゲージメント向上のため、「Human Capital Story Book」の発行や「ANA’s Way AWARDS」による社員表彰、社内兼業インターンシップや新規事業提案制度「Da Vinci Camp」といった多様なキャリア形成機会の提供状況についても教えてくださいました。
最後に、ANAグループが求める人財像として、「「空の繋がり」から世界や日本に新たな価値を届けたいという熱い想いを持って主体的に行動し、チャレンジできる人財」とご説明いただきました。
学生も大変熱心にご講演を聴講し、多くの質問が寄せられました。石田さまは、時間の許す限り、その一つひとつに丁寧かつ詳細にご回答くださり、学生にとっても貴重な学びの機会となりました。
