2025年6月17日、経済学部 近廣准教授が担当する入門演習にて、丸紅ご出身で現在はNPO法人に勤務されている渡辺昭彦さまをお招きしての特別講義が行われました。
渡辺さまは若い頃から海外に憧れ、また船会社勤務の父親から「資源のない日本では貿易が命だ」と聞かされていたこともあって商社を志したといいます。43年間の商社人生を振り返りながら「商社の仕事」 ~(私の経験した)「商社金融の流れと金融ビジネス(PEファンドビジネス)」~と題して商社の意義や事業領域についてまとまったお話をしてくださいました。
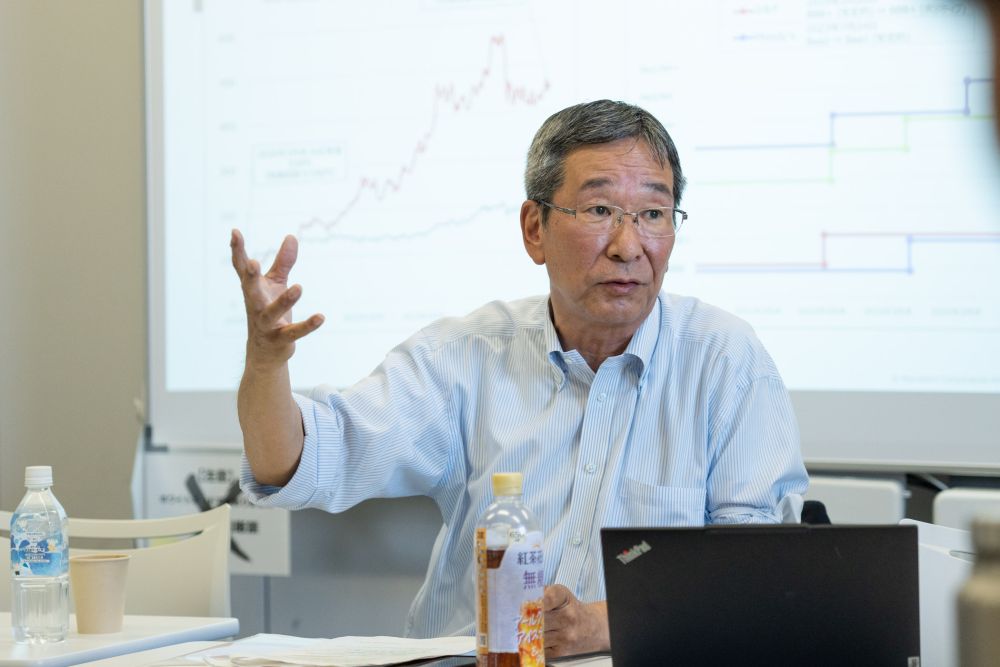
入社当時は過去栄華を誇っていた繊維部門のピークは過ぎており、台頭してきたのが鉄鋼部門、特に石油採掘用のシームレスパイプの輸出は大きな利益を生んでいたといいます。そんな導入から丸紅の事業の全容を、そして商社不要論にも触れながら商社の役割を解説してくださいました。単なる輸出入の仲介業ではなく、金融、物流・在庫管理、与信、許認可等の事務手続きなど多様な機能を持つ組織であると強調され、古くは日本鋼管とトヨタ等、大企業間での薄板の商売でデリバリー管理業務を担い、サプライチェーンの安定に貢献していた例も紹介されました。
続いて丸紅のバランスシートを示してその見方を説明され、その流れの中でかつての9大商社から5大商社への淘汰の歴史や、それぞれが得意とする事業分野なども教えてくださいました。丸紅の強みの一つが電力やアメリカの農業資材事業など非資源分野で、特に伝統的な国内電力会社への燃料供給は財閥系商社に抑えられていた中、新たな分野としての海外における発電所の建設・運営事業を先駆者的に開拓していったとのことです。

渡辺さまはバブル期の終わりごろからロンドンに駐在し金融・投資に従事。帰国した1995年は、震災や地下鉄サリン事件などが続いており、日本の方が怖いと感じながらバブル崩壊後の後始末にも携わりました。その後は丸紅から出向する形でPEファンドの役員を務められ、いくつもの企業買収を行いました。
「ハゲタカと言われることもある」というPEファンドについてその事業を簡潔に説明くださいましたが、けして揶揄されるようなものではなく、産業の再編や事業承継の一助として社会的意義を持つものだということが学生たちにも納得のいくお話でした。
講義の中で商社のPBR(株価純資産倍率)についても触れられましたが、近年上昇している要因について学生から質問が挙がりました。過去よりコングロマリットディスカウント等言われていた商社業態ですが、ここにきて商社の事業モデルが再評価されてきており、そのことは数年前にバークシャー・ハサウェイが日本の商社株を購入した事によって更に見直されてきているのではないかとのことです。
商社の事業ポートフォリオの変遷や、売上から純利益へという評価軸の変化などが、時代背景・思い出話を交えることでより立体的になった講義で、学部1年生たちが商社というものを知るこれ以上ない機会となりました。

