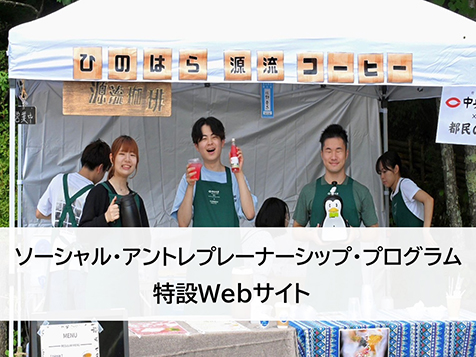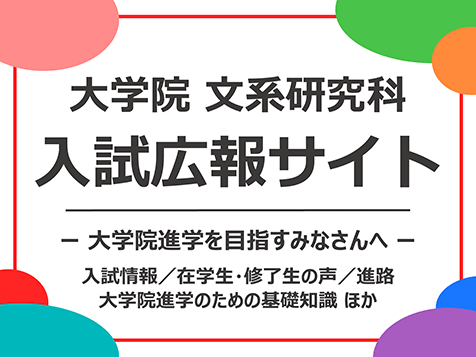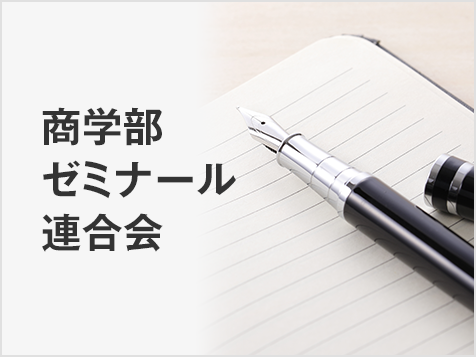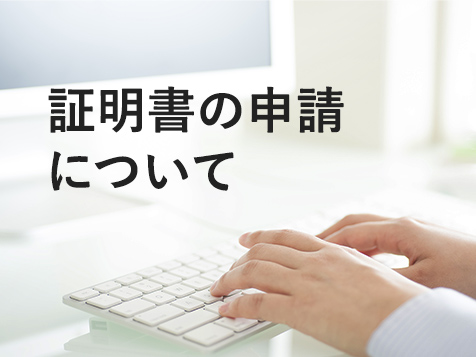商学部
Vol.4 原田 喜美枝 教授
―Profile―
原田 喜美枝

大阪大学経済学部卒業後、東京大学経済学研究科現代経済専攻において、修士号と博士号を取得。
財団法人での研究員や他大学での教員を経て、2004年4月より中央大学大学院国際会計研究科、2011年4月より中央大学商学部に着任。
研究分野は金融・ファイナンス、経済政策、ワインエコノミクス。
出身地:滋賀県大津市
趣味:ワイン、パン・ケーキ作り
好きな本、アーティスト、映画:千葉敦子の著書
好きな休日の過ごし方:パン・ケーキ作り、K-popダンスを踊る
尊敬する人:ほとんどの人は尊敬に値する、強いて言えば努力する人
小さい頃の夢:世界に出て行きたい(田舎から逃げ出したい)
―Interview―

ここからは、商学部生の水谷さんとともに、インタビューをしていこうと思います。
水谷さん:本日はよろしくお願いいたします。
原田先生:よろしくお願いいたします。
水谷さん:早速、インタビューに入らせていただきます。
出身
水谷さん:出身地はどちらになりますか?
原田先生:大津市の出身です。県庁所在地ですが、かなり田舎のところの出身です。水谷さんはどちらですか?東京ですか?
水谷さん:生まれは静岡なんですけど、2歳で東京に引っ越しました。
原田先生:そうなんですね。ではほぼ東京育ちですね。私も今や東京が長くなりまして、人生の半分以上は東京なんですが、滋賀の田舎で生まれ育ちました。
趣味

水谷さん:先生のご趣味は何ですか?
原田先生:ワインとパン・ケーキ作りですね。特にワインがいちばん好きです。水谷さんは、ワインを飲まれますか?
水谷さん:たまに家族で外食する時にいただくことはあるんですが、私自身はあまり詳しくなくて……。でも、美味しいなと感じることはあります。
原田先生: 私はワインが好きで、これまでにワインに関する本を2冊書いています。1冊目は4人の共著で、日英バイリンガルの本でした。左ページが日本語、右ページが英語という構成で、東京オリンピックの前に、海外から訪れる方々に向けて日本のワイン産業を紹介しようという目的で書いたんです。けれども、ご存じのようにオリンピックは無観客開催となってしまって……。日本のワイナリーを巡る外国人観光客を期待していたのですが、それは残念ながら実現しませんでした。
そして昨年、今度は私ひとりで書いたワインの本を出版しました。経済学者の視点でワインに関するデータをまとめたりしたものです。
好きな本、アーティスト、映画
水谷さん:お好きな本や音楽、アーティスト、映画などの中から、何か一つご紹介いただけますか?
原田先生:本でいうと、千葉敦子さんという方の書籍が印象に残っています。フリーランスのジャーナリストとして、ニューヨークを拠点に活動し、キャリアウーマンとしての生き方や、がんとの闘病生活を綴った著書で知られている人です。……千葉敦子はご存じなくても、水谷さんに響くか分からないのですが(笑)、実はK-POPが好きで、ダンスも習っています。好きなアーティストは「SEVENTEEN」です。ご存じですか?
水谷さん: はい、名前は知っています!
原田先生: 良かったです。映画も好きでよく観ますが、ひとつあげるとすると昔の作品です(笑)。「追憶」という映画、ご存じないですよね?
水谷さん: はい、知らないです(笑)
原田先生: やっぱりそうですね。英語のタイトルは “The Way We Were” といって、ロバート・レッドフォードという当時とても有名だった俳優と、歌手としても成功したバーブラ・ストライサンドが主演の映画です。この映画も、千葉敦子さんの著作も、どちらも「女性の自立」をテーマにしていて、私はそういったテーマのある作品に心を動かされることが多かったです。
水谷さん:ちょうど今、自分もLGBTQに関する授業を取っていまして。
原田先生:そういった授業があるんですね。多様性などについて学ぶ内容ですか?
水谷さん:はい。おそらくどの学部でも履修できるもので、さまざまな方をお招きしてお話を聞く機会もあって、とても興味深いです。
原田先生:どんな内容が一番印象に残っていますか?
水谷さん:女性として差別を受けた経験をもとに、今では同じような境遇の人たちのためにコミュニティを立ち上げて、日本国内外で広く活躍されている方のお話でした。
原田先生:貴重なお話ですね。私も思い出すことがあります。オーストラリアで知り合った知人がいたのですが、出会った当時は女の子でした。でも卒業して1、2年後くらいに、Facebookの名前が男性の名前に変わりました。それから、自分の抱えている心の問題について少しずつ発信するようになって、数年後には性別適合手術を受けたようです。今ではアメリカで働いていて、見た目も完全に男性という印象だそうです。日本では生きづらかったようです。そうした葛藤を思うと、本当に大変だっただろうと感じます。だからこそ、LGBTQに関する授業があるのは意義深いことですね。

水谷さん:はい、本当に学ぶことが多かったです。
原田先生:そうですよね。私が子どもの頃には、そういう授業はもちろん存在しませんでしたし、誰にも言えないような空気はあったと思います。SNSもなかったので、書くことも言うこともできず、バレてはいけないというタブー感が強かったです。でも今は、少しずつ状況が変わってきているように感じます。本の話題から少し逸れてしまいましたが、LGBTQのようなテーマを話し合えるのは素敵なことです。
好きな休日の過ごし方
水谷さん:次に、休日の過ごし方について教えてください。
原田先生:研究者は自由業の側面もあり、私に限らず、週末も仕事をしている人は多いと思います。でも、休日の楽しみはパンを焼いたりケーキを作ったりすることですね。昨日の午後はパン屋さんのように大量のパンを焼いていました。今日は第2体育館で、1年生のベーシック演習の学生さんたちがバレーボールを楽しんだので、その差し入れとして焼いたパンを持っていきました。パンはよく焼くのですが、まれに学生さんたちに差し入れをして「お母さん役」をしています(笑)。ケーキ作りも同じで、嫌なことがあってもパンやケーキに集中している間は忘れられる時間になるんです。
水谷さん:週末もお仕事をされているとのことですが、具体的にはどのようなお仕事をされているのでしょうか?
原田先生:月曜日に2限から5限まで授業があるんです。3限は大学院の専門科目を英語で行っています。英語の授業は、日本語で行う授業より準備に時間がかかるので、週末はまず月曜の英語授業の準備をしています。学部の授業でも、できるだけ新しいニュースを取り入れて行いたいので、ニュースを参考にした教材は授業の直前に作ることが多いです。そうした準備も週末のうちに進めています。 私は商学部で「金融システム論」という授業を担当していますが、金融制度は頻繁に変わりますし、金融関連のデータも常に更新されるため、最新の数字かどうかの確認もしています。こうした作業も含めて、週末は翌週の授業準備に時間を割いていることが多いです。あとは締切が近い雑誌や新聞の原稿を書いたり、論文のための作業もします。ただ、休日の過ごし方は?と質問されて仕事の話をしてしまうのは、学生の皆さんにあまり良いメッセージにならないかもしれませんね(笑)。
水谷さん:ありがとうございます。
尊敬する人
水谷さん:次に、先生が尊敬されている人についてお聞きしてもよろしいでしょうか?
原田先生:私は、基本的にどんな人にも尊敬すべき点があると思っているんです。たとえば、頭が良い人、スポーツに秀でた人、幅広い知識をもつ人、歌やダンスの上手い人など、それぞれに素晴らしい魅力があって、すごいなと思う人は世の中に本当にたくさんいます。学生の皆さんにも尊敬に値する人は多いと思っています。不真面目な学生さんも中にはいますけど(笑)、それでもなお良いところがあるはずと思います。
水谷さん:このインタビューでは、学生がキャリアプラン形成や学習意欲の向上につなげることも目的としているのですが、キャリアの面で影響を受けた人や、尊敬している先輩などはいらっしゃいますか?

原田先生:それなら、印象に残っている元ゼミ生の話をさせていただきます。中央大学商学部に来てからもう15年近くゼミは続いていますが、個性的で面白い学生さんたちが何人かいました。
たとえば、中卒でイタリアンレストランのシェフとして働いていたものの、腰を痛めて料理の仕事を続けるのが難しくなり、大検(現在の高卒認定試験)を受けて中央大学に入学してきた元ゼミ生がいました。商学部を卒業した後、一橋大学の大学院に進学しました。 中卒のイタリアンシェフから一橋大の大学院卒へという、違う道を歩んだ方がいます。最近は連絡が取れていませんが、社会でしっかり活躍されていることと思います。
また、私のゼミから医学部へ進んだ人が2人もいます。お二人とも現在30歳前後の方々ですが、1人は中央大学を3年で早期卒業して国立大学の大学院に進学して修士号を取得し、データサイエンティストとして働いた後、社会人入試で医学部に入りました。
もう1人は、学生生活を楽しく過ごした学生さんで、証券会社に就職後、数年経過した時点で人生について考え、社会人入試で医学部へ進学し、国家試験に合格し、今は研修医をしています。
水谷さん:えっ、商学部の学生さんから医学部生へ……しかも2人もですか?
原田先生:そうなんです。商学部から医学部へ進んだ学生が、2人おられます。珍しいですね。可能性はいつでも存在していて、いろんな人生があるんだなと彼らを見ていて思います。日本で働きながらアメリカの大学院に通いMBAを取得した元ゼミ生もいます。「いつから考えていたの!?」と思うようなキャリアの転換をしていて、驚かされることは多いです。そういう意味でも、私はゼミ生たちのことを尊敬していますし、彼らの存在が私にとっても刺激になっています。……ちゃんとキャリアの話になっていますか?(笑)
水谷さん:なっています!(笑)ありがとうございます。
小さい頃の夢
水谷さん:次に小さい頃の夢についてお伺いできればと思います。
原田先生:小さい頃、小学校、中学校、高校ぐらいまでは田舎から出たかったというのがあります。高校生の終わりぐらいからは国連職員になりたかったと記憶しています。最初、外国語学部に入ったんです。国際機関で働くためには語学ができないとダメだと思ったのがきっかけだったんですけど、3年生になって国際機関職員の応募資格を見てみると、応募できない学部が体育学部と外国語学部だったんですよ。それでダメなんだと思って、専門科目を学ぶ必要があるということが分かりまして、法律か経済かでどっちにしようかなと思った時に経済を選んだんです。外国語学部に4年、経済学部に2年、合計6年いて学士号を2つ持ってるんです。その後、大学院に行ったんですけど、大学院に行った理由というのもやっぱり国連にアプライする人は大学院を出ている人が多いということが分かったからでした。大学院に行ってからは国連という夢がだんだん薄くなってしまって、まずは博士号が欲しいと思うようになりまして、そのまま大学院に残って大学院生をしながら就職をしてしまったんです。今の自分は小さい頃の夢からはだいぶずれてしまっていますけれども、いつも頑張ってきたので後悔はありません。
水谷さん: そうなんですね。ありがとうございました。
原田先生の幼少期から学生時代について教えてください
幼少期
原田先生:ワインが大好きと言ってると、都会の裕福な家で育ったようなイメージを抱かれることがありますが、ど田舎の中流家庭で生まれました。本当に田舎でして、兼業農家でした。農業に携わるとわかると思いますが、夏はすごい勢いで雑草が生えるので、草刈りは夏の日課でした。手伝った記憶はあまりないのを申し訳なく思い出すと同時に、夏は家族で旅行に行くものだ、なんで連れて行ってくれないという不満を抱いていたことは今でも思い出します。そんな子供時代でした。でも可愛がって育ててもらった記憶はあります。
中高生
原田先生:田舎ですので、選択肢はなく、地元の学校でした。学校に行くのに小学生の時からバス通学だったんです。しかも、パスが1時間1本なんですよ!一度、目の前で横断歩道の向こうでバスが行ってしまって、1時間に1本のバスが行っちゃった、仕方ないから歩いて帰ろうと思って歩いて帰っていたら、途中で次のバスに追い抜かれて、うちは遠いんだなと思った記憶があります(笑)。 高校は、延暦寺学園比叡山高校を卒業しました。延暦寺は最澄が開いたお寺なので、体育館でイベントがあるとお線香のにおいが漂い、ステージにあるカーテンが開くと大きい祭壇があるんです。 悪いことしたりすると反省文の代わりに般若心経を書くとか、冬休みの宿題が般若心経とか、そういった高校で過ごしていました。
大学生~大学院生
原田先生:大学時代は片道2時間かけて大阪まで通っていました。私は、外国語学部と経済学部という2つの学部を卒業していて、通学時間も含めて結構ハードな日々でした(笑)。 外国語学部は定員が少なくて、出席もほとんど必須のような環境で、留年する人が何割もいたので、真面目に取り組んでいました。経済学部に移ってからは、大きな教室での講義が増えましたが、大学院に行くつもりだったので、こちらも手を抜かずに勉強しました。大学院を目指すなら、やっぱりそうなりますよね。
水谷さん:私も、興味のあることにすぐ夢中になってしまうタイプで…。今はデータサイエンスに関心があって、東京大学の松尾研究室から来ている社会人の方も受講できる授業を取っています。
原田先生:それはすごいですね。プログラミングもやるんですか? Javaとかですか?
水谷さん:いえ、私はPython(パイソン)を使っています。実は最初は全くの初心者だったんですが、最近はなんとなく理解できるようになってきました。
原田先生:話を戻すと、私は学部を終えて大学院に進もうと思っていたので、まずは大阪の大学院を受けました。でもちょうどそのころ、東京大学の大学院に進学していた友達に「遊びに来ない?」って誘われて。大学院の入試を受けるという名目で遊びに行ったのです。夜中の3時くらいまで友達としゃべって翌日に試験を受けたら……なぜか受かっちゃったんですよ(笑)。それで東京大学の大学院に進学したんですが、正直、大学院時代はとても辛かったです。成績も良くなかったですし、何より数学が苦手だったんです。大学院に入ってからも、学部レベルの数学の授業に出たりしていて、なかなか追いつけなかったんですよ。とにかく数学では苦労して、他の面でもいろんな困難がありました。
研究・専門分野について
なぜ研究者の道へ進まれたのですか。
原田先生:大学院生の頃、将来の進路として「博士号を取って国連で働く」というのも、一応頭の中にはありました。でも、「自分は本当に博士号をとれるのか?」という不安がすごくあって……。ある時、指導教官の先生に相談したんです。そうしたら、証券系の研究所を就職先として紹介していただけて、そこに就職することになりました。ちょうどその頃は、大学院と仕事を両立する“二足のわらじ”がまだ許されていた時代で、正規の大学院生として学びながら、フルタイムの研究員として働いていたんです。
水谷さん:それはすごく忙しそうですね……!
原田先生:はい(笑)。授業のある時は研究所を抜けて大学に行って、授業が終わると研究所に戻る、という日々でした。でもそのおかげで、衣食住に困らず大学院生活が送れるようになって。本当にありがたかったです。そんなふうにしているうちに、最初に夢見ていた“国連職員”という夢がだんだん小さくなっていきました。結局、博士号を取って、そのまま研究所に残り、証券業界や学界とのつながりもできてきたので、自然と研究者になっていたという感じです。
原田先生が金融に興味を持たれたきっかけを教えてください。

原田先生: 最初は、紹介してもらった証券系の研究所に就職したのがきっかけです。金融と一口に言っても、大きく分けると銀行・証券・保険がありますが、その中でも証券は圧倒的に面白いと思いました。というのも、証券の世界にはクリエイティブな要素が多く、「こんなに自由で面白いことができるんだ」と感じたんです。
就職した年の11月に、4大証券の1つである山一証券が自主廃業したのですが、それも大きな転機でした。「世の中って、こんなに一瞬で変わるのか」と強く実感しました。
それだけでなく、日本の銀行が外貨を調達する際、海外の銀行よりも高い金利を課される「ジャパンプレミアム」という現象も身近に起きていて、そのデータを自ら入手して分析することができました。その研究が学会でも高く評価され、ますます金融の面白さに引き込まれていきました。
今振り返ると、証券系の研究所に就職したことが大きなきっかけではありますが、「やりたいか・やりたくないか」で聞かれたら、間違いなく「やりたい」と思えた分野でした。 それが、金融への関心を持ち続けてこられた理由だと思います。
水谷さん:なるほど。実体験と分析の両面から、金融の奥深さを実感されたのですね。
授業について
現在教えている授業について教えてください。
原田先生:学部では「金融システム論」という講義を担当しています。金融学科の2年生向けの選択必修科目です。授業では、株式市場や債券市場などの金融市場、銀行・証券・保険といった金融機関、それに加えて主要な金融商品などについて、理論的な側面も併せて説明しています。内容が難しくなりすぎないよう、学生が興味を持てる工夫をいろいろしています。たとえば、授業中に(Responという)レスポンス機能を使って問いかけをしたり、3択で「どれだと思う?」と意見を聞いたり。また、新聞記事を宿題で読んでもらって、感想をレポートで提出してもらうこともあります。ただ受け身で聞くだけでなく、「これは将来役に立つ」と実感してもらえるような構成を心がけています。
大学院では「ジャパニーズ・エコノミー(日本経済)」という科目を英語で教えています。中大では開講がない年もあるのですが、開講時は少人数で、和気あいあいとした雰囲気で授業ができています。他大学での経験も活かしつつ、毎回チャレンジしながら取り組んでいます。
また、ゼミも担当していて、ベーシック演習と3・4年の演習があります。以前は、タイ、韓国、中国など、アジア諸国にゼミ合宿にも行っていました。コロナ後はまだ実現していないのですが、また行けたらいいなと思っています。
1年生のベーシック演習では、学生同士が仲良くなることを大切にしていて、プレゼンの練習をしたり、英語を使ったりしながら、さまざまなアクティビティを取り入れています。たとえば、最初は日本語・英語の自己紹介プレゼンをやってもらい、その後はグループプレゼンに取り組んでもらいます。今日は体育館でバレーボールをしたのですが、ずいぶん打ち解けてきた様子でした。友達ができると大学生活も楽しくなるので、そういった環境づくりも意識してゼミを運営しています。
水谷さん: とても工夫されていて、学生にとって充実した学びの場になっているのが伝わってきます。
大学で金融を学ぶ意味とはなんでしょうか。

原田先生:「金融リテラシー」という言葉を耳にするかと思います。これは、金融に関する基本的な知識や判断力のことで、語源の「リテラシー(literacy)」は本来「読み書き能力」を意味します。
残念ながらこの金融リテラシーがあまり高くないのが日本の現状です。でも、大学で金融を学べば、このリテラシーは確実に高まります。
たとえば、経済学の世界では「ノー・フリー・ランチ」という言葉があります。「タダより高いものはない」「うまい話には裏がある」という意味で、日常生活でもとても大事な考え方です。また、金融詐欺がますます巧妙になっている現代では、正しい知識を持っていることが自分の身を守る手段にもなります。
金融の知識は、特別な人だけに必要なものではなく、誰の人生にとっても日常的に関わってくる知識です。だからこそ、大学でしっかり学ぶ意味があります。もちろん、商学部には将来金融機関に就職する学生も多くいますから、専門的な内容にもしっかり対応しています。
そういった意味でも、「大学で金融を学ぶこと」には、大きな意義があると感じています。
水谷さん:確かに、日常生活の中でも金融リテラシーは欠かせないですね。
商学部教員である原田先生の考える「ビジネス」とは何ですか。
原田先生:ビジネスとは何かと聞かれると、やはり「株式会社」がその中心にあると考えています。たとえば、ものを作って売ることも、サービスを提供することも、基本的には利益を上げるための活動です。
現代のビジネスは単に利益だけを追求すればよいというものではありません。たとえば、環境への配慮や地域への還元、従業員のウェルビーイング(幸福)など、さまざまな視点から社会と調和することが求められています。最近は特に、ESG(環境・社会・ガバナンス)やSDGsなどの観点も重視されていて、営利と社会的責任の両立が大切になっています。だからこそ、「ビジネス」という言葉そのものが、とても幅広い意味をもちますね。
水谷さん:ですよね。でも、やっぱりビジネスを考えるうえで「会社経営」という視点は外せません。とくに上場企業の場合は株主がいるので、「どう株主に還元するか」も重要な課題です。
原田先生:利益を上げて株価を下げないようにすることも経営者の責任のひとつですし、社会的責任とのバランスをとりながら、持続可能な形でビジネスを続けていく——それが今の時代に求められているビジネスの姿なのではないでしょうか。
在学生の皆さんへのアドバイスはありますか。

原田先生:「なんでも意欲的に学ぶ」ということです。勉強だけでなく、運動でもアルバイトでも、すべてが学びだと思うんです。だからこそ、学生時代はとにかく積極的にいろいろなことに挑戦してほしいと思います。うまくいかなかったことがあっても、それで終わりではありません。次につながる何かが必ずあると信じて行動することが大切です。
水谷さん: なるほど。なにか具体例はありますか?
原田先生:大学の学びって、実は全然悪くないと思うんです。金融に限らず、マーケティングでも会計でも、有意義な授業はたくさんあります。でも残念ながら、学生が重きを置いているポイントが、あまり「授業」には向いていないことも多いんです。とはいえ、何をどう学ぶかは結局その人の関心次第なので、なるべく多くのことに興味を持ってもらいたいと思っています。たとえば、水谷さんが取り組んでいる松尾研究室での活動は、とてもいい例です。自分から学びにいく姿勢、ほんとに立派だと思います。
水谷さん:ありがとうございます。実は、データサイエンスやフィンテック系に関心があるので、大学院進学も視野に入れて、そちらの方向で学びを深めていきたいと思っています。
原田先生:それは素晴らしいです!何にでも関心を持って、自分には無理かも……と思わずにチャレンジすることが本当に大切です。私の大学院進学は最たる例ですね。
もし結果がうまくいかなくても、そこから学んだことは次のステップにつながります。
ポジティブな姿勢を持って、自分の可能性を信じてほしい——これが私からのアドバイスです。
原田先生が先輩やメンターの方からのアドバイスで1番心に残っているものは何ですか。
原田先生:私がまだ学生の頃、外国語学部の指導教員の先生に「大学院に進学したいけれど、経済的に厳しいんです」と相談したことがあるんです。すると先生は、「勉強したらお金はついてくるから、心配するな」とおっしゃったんです。
その時は「なんて無責任な…」と思いました(笑)。でも、いざ大学院に進んでみると、奨学金が支給されたり、授業料が免除になったり、成績がよければ給付型の奨学金も受けられるなど、経済的な支援を受けることができました。
今振り返ると、「心配するよりもまずは勉強に全力を尽くせ」というメッセージだったのだと思いますし、あのとき先生にそう言ってもらえて、本当に良かったなと感じています。 経済的に厳しいと思う学生さんにも伝えたいアドバイスです。奨学金制度は今もたくさんありますし、真剣に取り組めば必ず道は開けると思います。お金の不安にとらわれすぎず、まずは自分のやりたいことに向かって努力を重ねてほしいと思います。
最後に・・・原田先生ご自身の「今の夢」を教えてください。
原田先生:そうですね……もう若くないので、あまり「これが夢です!」というものはないんですが、後ろ向きな夢と前向きな夢の2つがあります。
後ろ向きな夢は、「健康に過ごしたい」ということ(笑)。年を重ねると、誰しもが考えることかもしれませんが、やっぱり健康でいたいですね。体を壊すような量の仕事を引き受けてはいけないと考えます。
前向きな夢は、いろいろな学びを継続したいということです。韓国が大好きなので韓国語を学んだことがありますが、もう忘れたことが多いです。もう1回学び学び直したい、K-popダンスも引き続き習っていきたい、というのが前向きな今の夢です。
水谷さん:どちらも素敵な夢ですね、ありがとうございました!
原田先生:こちらこそありがとうございました!