国際情報学部
株式会社野村総合研究所に内定
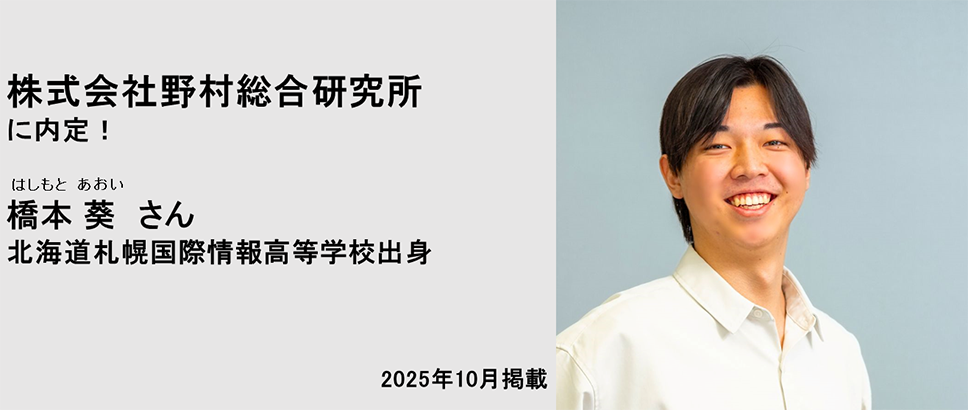
-
iTLを進学先に選んだ理由を教えてください。
-
私は大学進学にあたり「情報系の学問を学びたい」という強い軸を持っていました。その中でiTLに惹かれたのは、単なるプログラミングやシステム開発のスキル習得にとどまらず、情報通信技術が社会にどのような価値をもたらし、どのように活用されていくのかを幅広い視点から学べる点です。技術そのものを深めるだけでなく、それを社会や人々の生活に結び付ける姿勢を重視するカリキュラムに強く共感しました。文理融合的に情報学を扱い、社会課題に応用できる力を身につけられる環境が自分に最も合っていると考え、iTLを選びました。
-
iTLの授業科目の中で最も印象深かった科目を教えてください。
-
印象深かった授業は「情報政策ワークショップ」と「国際規約と国際標準化団体」です。
「情報政策ワークショップ」では、少人数で情報政策をテーマにディスカッションを行い、実際に政策提案を作成して発表しました。特に、省庁職員の方々に直接プレゼンを行う機会は大変貴重であり、自分の考えを社会に届ける責任感や実践的な力を身につけることができました。
一方「国際規約と国際標準化団体」では、情報通信における国際標準化の重要性を体系的に学びました。国際機関の役割や、国際標準化の形成過程を知るとともに、総務省や経済産業省の実務担当者の方々から直接講義を受けられたことで、標準化が国家戦略や企業の技術開発に深く関わっている現実を実感できました。これら二つの授業を通じて、国内外の政策や標準化を多角的に考察する視点を養うことができたと感じています。
-
ゼミでの研究テーマ、卒業論文・卒業制作のテーマを教えてください。
-
私の卒業研究として1つ、ゼミでの研究として2つの合計3つのテーマに取り組みました。
卒業研究のテーマは「リポグラム生成プログラムの開発と評価」です。リポグラムとは、ある文字を一切使わずに文章を書く言葉遊びで、小説や詩の中でも使われてきた表現手法です。私はAIと文学的な言葉遊びの組み合わせに興味を持ち、禁止された文字を避けながら自然な文章を自動で作る仕組みを研究しました。日本語では表記や助詞の制約があるため、難点も多かったのですが、工夫を重ねて読みやすく面白い文章を生み出すことを目指しました。この研究を通して、AIが人間の創作を助ける可能性や、言葉が持つ新しい表現の形について深く考えることができました。
ゼミでの研究テーマの1つ目は「介護現場における業務効率化のためのデジタルトランスフォーメーション(DX)提案」です。介護支援専門員(ケアマネジャー)は日々多くの書類業務や情報共有に追われており、その負担が大きな課題となっています。そこで私は、現場の方へのヒアリングを行い、どの業務に最も時間がかかり、どの部分が非効率なのかを丁寧に分析しました。その上で、デジタル技術を活用して業務を効率化できる仕組みを提案しました。研究を通じて、単にシステムを考えるだけではなく、実際に現場で働く人の声を取り入れる重要性を学びました。この経験は、人に寄り添った形でITを活用する姿勢を身につける大きなきっかけになったと感じています。
ゼミでの研究テーマの2つ目は、「AI時代のHTML再設計」です。現在のWebは人間には読みやすい一方で、AIには理解しづらい部分があります。そこで、HTMLの中に「これは何の部分か」「今どういう状態か」をはっきり書く“名札付け”のルールを作り、AIが正確に情報を読み取れるかを試作サイトで検証しました。AIに記事を検索させたり、フォームを送信させたりして、成功回数や必要なステップ数を比べると、はっきり書いたページの方がうまく動作することが分かりました。この研究から、人間とAIのどちらにも意味が伝わりやすい文章の書き方と両者に優しいデザインを学ぶことができ、そして数字で確かめて改善する姿勢を身につけることができました。
-
ゼミの中で自分が成長できたと思うところを教えてください。
-
個人での研究活動を通じて成長できたと感じるのは、日常の中から小さな疑問を見つけ出し、それを研究として掘り下げる姿勢です。卒業研究は、「ある文字を使わずに文章を書く」という遊び心ある表現に興味を持ち、「AIで自然に生成できるのではないか」という発想から研究を始めました。研究を進める中では「日本語でどこまで自然に文章を作れるか」「特定の文字を避けつつ意味を損なわないにはどうすればよいか」といった課題を仮説として立て、検証を繰り返しました。この過程で、課題を具体的に捉え分析する力や、思考を柔軟に修正する力、そして仮説を形にする力が身についたと思います。日常の「問い」を形にし、実際に成果として示す喜びと成長を実感できた経験でした。
ゼミでの研究活動を通じて成長できたと感じるのは、「現場の声を踏まえて課題を捉え、解決策を考える力」と「チームをまとめる力」です。介護DXの研究では、単に効率化の仕組みを考えるだけでなく、介護支援専門員の方々にインタビューを行い、実際に困っている点を見極める必要がありました。当初は机上の発想にとどまりがちでしたが、現場の意見を聞くことで、自分の考えを柔軟に修正し、より実用的な提案へとつなげられるようになりました。また、ゼミ内での議論や役割分担を進める中で、メンバーの意見を尊重しながら議論を整理し、方向性をまとめる役割を担いました。その結果、協働して研究を進める力が身につき、リーダーシップと調整力の両方を成長させることができたと思います。
-
アルバイトやインターンシップ、サークル等、正課外の活動について教えてください。
-
私は大学入学後、複数の企業で長期インターンシップに参加し、実務の最前線で経験を積みました。約4000人規模の社内業務支援システムや大手インフラ企業のAIエージェントを活用したサービスの開発、新規アプリの設計・実装、R&D業務などに携わり、技術力だけでなく、要件定義や課題整理、チーム開発といった実践的な力を磨くことができました。
高い要求水準の中で成果を出す過程は、自信と成長につながりました。また、ゼミでは3つの研究テーマで学会発表を行い、課題設定から検証、発信までを一貫して行う力を培いました。インターンと研究を通じて、技術を使って社会に価値を届けるという軸が明確になり、主体的に学び続ける姿勢が自然と身につきました。
-
大学生活を経て、なぜその内定先に応募しようと思ったのか教えてください。
-
私は大学での研究やインターンを通じて、技術によって社会の課題を解決し、自らのアイディアを形にすることに強いやりがいを感じてきました。たとえば、リポグラムやAIエージェントを活用した研究では、アイディアを理論に昇華し、世の中にない仕組みとして構築できたときに大きな達成感を覚えました。インターンでも、大規模な社内システムやAIを活用したプロトタイプ開発に取り組み、高い期待に応えることで技術力と実行力を磨いてきました。
私が最も魅力を感じるのは、「0から1」を生み出す過程です。複雑な課題を構造的に整理し、最適な仕組みを考え抜いていくプロセスにこそ楽しさがあり、コードはそれを形にする手段だと考えています。チームで課題を議論しながら「これだ!」というアイディアにたどり着く瞬間にも大きな価値を感じます。
野村総合研究所のインターンに参加した際には、課題の分析から解決策の立案、実装まで一貫して担える環境に強く惹かれました。社員の方々も、私の考え方や価値観に共感してくださり、自分の実力を存分に発揮できる場所だと確信しました。今後は、技術と創造性を武器に、社会に価値ある仕組みを届けられる人材として成長していきたいと考えています。
-
iTLでの4年間はいかがでしたか。
-
iTLでの4年間は、技術だけでなく、それをどう社会に活かしていくかを深く考えられる、とても実りある時間でした。AIや政策、標準化など幅広い分野を学ぶ中で、社会課題への視点や応用力が自然と身についたと思います。特にプロジェクト型授業やゼミの研究では、自分で課題を見つけて考え抜いたアイディアを形にして発表するという経験が印象に残っています。仲間と議論したり、現場の声を聞いたりしながら学べたことで、視野も広がりました。技術と現実社会をつなぐ力を養えた4年間だったと感じています。
-
受験生へのメッセージをお願いします。
-
iTLは、技術を学ぶだけではなく、「それをどう社会に活かすか」を本気で考えられる場所です。最初からすべてができる必要はありません。むしろ、「こんなことに挑戦してみたい」「社会に価値を届けたい」と思う気持ちがあれば、必ず力になります。私自身、興味のあることを深掘りしていく中で、多くの人と出会い、視野が広がり、自分の成長を感じる場面がたくさんありました。
自分の好奇心を信じて、ぜひ思い切って飛び込んでみてください。iTLでの4年間が、きっとあなたの可能性を広げてくれるはずです。







