国際情報学部
トヨタ自動車株式会社に内定
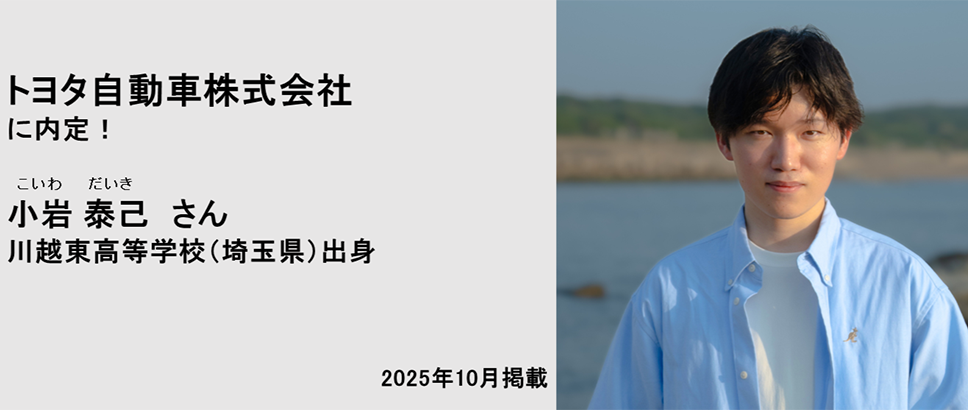
-
iTLを進学先に選んだ理由を教えてください。
-
情報法を専門的に学ぶことができると考えたからです。
高校当時から法学に興味があり、iTLに入学する以前、私は1年間他大学の法学部に在籍していました。法学部で学んでいた当時、ちょうど生成AIが普及し、同時に多くの法的・倫理的な問題も露見し報道されていました。一連の報道を見るなかで、新しい技術の登場により生じた新たな問題に対して法律が後手に回っている状況に疑問を感じ、情報法に興味をもちました。
もちろん、法学部でも履修科目の一部として情報法を学ぶことはできましたが、AIに限らず最先端の情報技術がもたらす影響は良くも悪くも年々大きくなっており、より専門的に情報技術に関する問題や法律などを学ぶことで、将来的にこうした分野の問題解決に関わりたいと考えるようになりました。iTLであれば、情報法を専門とする著名な先生方から直接講義を受けることができるほか、情報法が扱う対象となる情報技術についても学べるため、より専門的にこの分野の法律を学ぶことができると考え、「ここしかない!」と思いiTLを受験しました。
-
iTLの授業科目の中で最も印象深かった科目を教えてください。
-
「情報判例研究B」と「ICT留学」です。
「情報判例研究B」では、数十年前の判例や通説などが、情報化社会である現代の法律問題を議論する際の重要な根拠になりうる点が印象的でした。この授業は、各回で情報通信分野の判例を評釈して受講生同士で議論する形式で、数十年前の判例から比較的最近の判例まで様々な判例を扱います。実際に扱った判例では、スマートフォンが登場する以前の判例で示された考え方が、現代で大きな問題となっているSNS上の誹謗中傷問題に対応するためのコンテンツモデレーション(投稿監視)の検討に関わることがありました。現代の問題解決のために必要となる判例の考え方を数多く知ることができた点で、非常に印象深い科目です。
また、「ICT留学」では、留学先のオーストラリアの大学で文化や考え方が異なる様々な国の友人と交流できた点、オーストラリアにおけるAIのルールメイキングがどのように行われているかを州政府機関の職員の方と直接お話できた点で印象的でした。特に後者については、日本とオーストラリアで課題とされている問題や優先事項が異なり、それによって検討されていた規制も大きく異なっていた点が印象的でした。こうした視点は、卒業論文や今後の活動にも活かせるものだと感じています。このほか、現地の友人達と行ったEKKA(現地の農業祭)やゴールドコースト、モートン島への旅行、また留学先のQUT(クイーンズランド工科大学)の学生としての学生生活など、日本では得られない経験が数多く得られた点でも一生忘れられない科目です。
-
ゼミでの研究テーマ、卒業論文・卒業制作のテーマを教えてください。
-
生成AIに関するプライバシー上の法的課題を扱っています。
企業などの事業者は、Webサイトやアプリなどを通して私達から取得した個人情報を扱うときに個人情報保護法の規制を受けますが、当然、そうした情報を生成AIで活用して分析する場合も同様に規制を受けます。そうした生成AIの利用のなかでも、私は特に生成AIに個人データを入力するとき生じる法的課題に着目して研究しています。
日本の個人情報保護制度は、原則として他国と比較して非常に緩やかな規制である一方、「第三者提供」など一部では明らかに厳格な規制が行われています。生成AIの利用にあたっても、こうした一部の厳格な規制が問題となる可能性が高いです。一方で、そうした厳格な規制を緩和すればよいかというと、すでに日本は他国と比較して非常に緩やかな規制であることから、規制の緩和により個人情報やプライバシーの保護が十分にできなくなる可能性があります。もちろん、反対にEUのように規制を強化すると、事業者がAIを利用できる場面が少なくなり技術の利活用が阻害されるおそれもあります。こうした規制のあり方について、他国の制度との比較を通じて、どのような規制であればAIの利活用とプライバシーの保護のバランスがとれるのかを検討しています。
-
ゼミの中で自分が成長できたと思うところを教えてください。
-
法学独自の考え方ができるようになった点が一番大きな成長だと感じています。また、私の所属する小向ゼミでは、持ち回りで発表を行い、発表を聞いたゼミ生が質疑を行う形式で進むことが多く、発表に慣れることはもちろん、ゼミ生同士の質疑や先生のコメントから新しい気付きや視点を多く得られた点でも成長できました。このほか、学会での発表や学部独自の奨学金であるiTL先端的プロジェクト奨学金など、ゼミの活動を通して様々な挑戦ができた点でも成長できたと感じています。
-
アルバイトやインターンシップ、サークル等、正課外の活動について教えてください。
-
SaaS(インターネット経由でソフトウェアを利用できるクラウドサービス)やニュースサイトを運営するIT企業の法務部で長期インターンシップを行っています。具体的には、法務相談業務の補佐や法律に関するリサーチを中心に行っています。
活動の動機としては、ITの実務の現場で働くなかで、AIをはじめとする新しい技術の利活用にどのような課題があり、どのように解決しようとしているかを知り、ゼミでの活動や研究に活かしたいというものでした。実際に働くなかで、大学で学んできた情報法の知識が実社会で必要とされていることや、法律などの規制が技術の発展に対応しきれていない現状などを実感しました。こうした経験を経て、あらためて就職活動の軸として、法律(特に情報法)の観点から、社会をより便利なものにできる技術を安全かつ適切に社会に広げていくための仕事がしたいと確信することができました。大学での学びだけでなく、実務の現場を経験することで新しい気づきが多く得られると感じており、2年以上経った今でもとても楽しく活動させていただいています。
-
大学生活を経て、なぜその内定先に応募しようと思ったのか教えてください。
-
大学で学んだことを活かして、モビリティにおける個人情報に関わる法的課題の解決に取り組めると考えたからです。
私は、もともと入学当初から卒業後は情報技術の利活用における法的な問題の解決に関わりたいと考えていました。トヨタ自動車(トヨタ)に興味を持ったきっかけは、3年次の法律系合同ゼミでトヨタのプライバシーガバナンスを担当する部署の方にしていただいた講演でした。特に、自動車業界が「100年に一度の大変革期」に入り、スマートフォンとクルマが通信で繋がったり、車載センサー・カメラの情報をもとにクルマが運転を支援してくれたりするなど、CASE領域(コネクテッド・自動化・シェアリング・電動化)と呼ばれる領域での技術革新が急速に進んだこと、またそれによって新たにクルマから収集されるようになったデータの利活用で様々なプライバシーの問題が生じうるという点に興味を持ちました。こうした講演のお話に加えてインターンシップなどにも参加するなかで、トヨタにはプライバシーのリスクを減らしながらも技術を活用していくための仕事ができることも知りました。そうしたプライバシーガバナンスの仕事に専門的に関わっていくことで、iTLで学んできた情報法などの知識を活かしながら、コネクテッド技術や自動運転などモビリティに関する技術を適切に社会に展開し、人々の移動のあり方をより便利で安全なものに変えていくことに繋げられるのではないかと思い、トヨタへの応募を決意しました。
-
iTLでの4年間はいかがでしたか。
-
振り返ると、やりたいと思ったことが全部できた4年間でした。学会発表や学部独自の奨学金を活用した研究、短期留学などiTLには挑戦したいと思ったときにすぐ挑戦できる環境があり、ゼミの先生を中心とした教職員の方々がそうした挑戦を支えてくれる環境もあると感じています。また、学びの内容としても、入学当初から学びたいと考えていた情報法を中心に、法学・情報学ともに実社会で必要とされている内容を深く学ぶことができたと感じています。
-
受験生へのメッセージをお願いします。
-
iTLを進路選択の候補とされている受験生の皆さんは、おそらく情報学や法学の学びに興味をお持ちの方が多いことと思います。他の情報系学部や法学部と比較して「結局どちらがよいのだろう?」となることも多いかもしれません。
iTLでは法学、情報学、そしてグローバル教養の3領域を幅広く学ぶことができます。もちろん、それぞれ法学部や情報系の学部などと比較すると、各領域の専門的な学びは、履修できる科目数としてどうしてもやや劣る面もあります。ですが、法学部とiTLの両方を経験してみて、特に法学と情報学の両方を専門的に学べる環境はiTL以外にはなく、両方を学べるからこそ得られる学びも多いと感じています。例えば、情報法を学ぶ人であれば、情報法の対象となる情報技術の知識があることで情報法の内容をより深く理解でき、また情報学を学ぶ人であれば、その技術を使って何ができる(してよい)のか、法学の知識があることで判断することができます。皆さんが法学と情報学どちらか一方に少しでも興味があれば、iTLは良い選択肢になると私は思います。
たくさん悩むかと思いますが、皆さん自身が何を学びたいのか、将来どんなことがしたいのかをよく考えてみてください。そのうえで選んだ進路であれば、きっと後悔なく進めると思います。もちろん、iTLがその進路になれば在学生として大変うれしく思います。
今は苦しい時期かと思いますが、諦めずに頑張ってください!応援しています!







