国際情報学部
アビームコンサルティング株式会社に内定
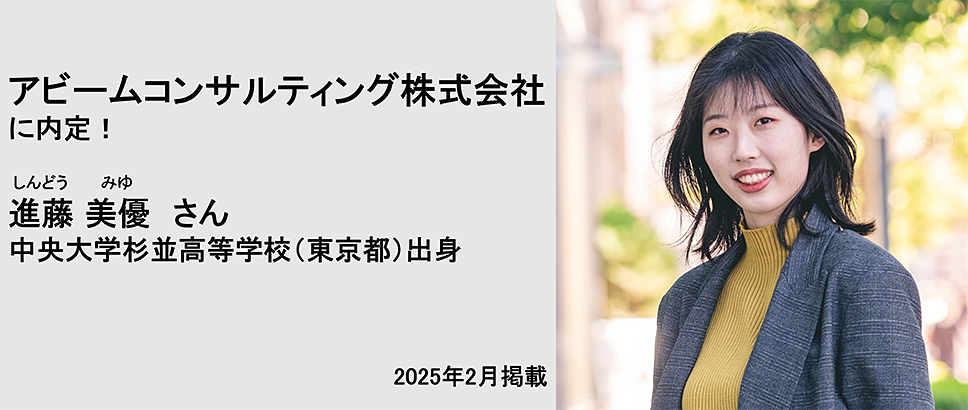
-
iTLを進学先に選んだ理由を教えてください。
-
iTLを進学先に選んだ理由は、3つあります。1つ目は、法律への関心です。法律は社会の秩序を維持し、個人の権利を保護する重要な分野です。私は、法律の仕組みや規範がどのように形成され、適用されるのかを学ぶことに興味がありました。
2つ目は、情報技術への挑戦です。DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉に象徴されるように、情報技術の発展が現代社会において重要な役割を果たしています。高校生の頃の私は、情報技術に自信がありませんでした。しかし、社会の変化に対応するために、情報技術を身につけることの重要性を実感していました。
3つ目は、他の人とは異なる研究領域に取り組みたいという思いです。情報技術と法律の融合分野では、どのような問題が生じているのか、探求したいと考えました。これらの理由から、iTLを進学先として選びました。iTLという環境は、私の関心と目標に合った、知識とスキルを身につけることに特化しており、今では最適解だと思っています。 -
iTLの授業科目の中で最も印象深かった科目を教えてください。
-
「情報プライバシー権法」では、プライバシー権や個人情報保護法の発展過程を学びました。国際的な個人情報保護法の枠組み「GDPR(一般データ保護規則)」に定められた権利やその適用範囲について、深く理解することができました。この講義を通して、プライバシーや個人情報保護法のあり方を客観的に分析できるようになりました。特に、個人情報保護法の第一人者である堀部政男先生がゲスト講師としてお越しくださり、現代の情報社会における個人情報保護の課題についてご意見を伺えたことが印象に残っています。
「情報教育論」では、学びのデジタル化によって、教育コンテンツそのものが情報化していることを学びました。最終回では、学習成果の集大成として、テクノロジーを活用した教育のための事業企画書を作成し、発表しました。教育に関連する事業の立案により、教育分野における課題解決の視点や企画力を養うことができました。起業経験のある講師による講義は、実体験をもとに構成されており、最も新鮮かつ強烈な印象を受けました。 -
ゼミでの研究テーマ、卒業論文・卒業制作のテーマを教えてください。
-
2年次の研究テーマは、「倫理的消費に関連する心理的要因」です。大学生を対象にアンケート調査を実施し、倫理的消費への関心と心理的要因の関連性を分析しました。
3年次の研究テーマは、「児童の図書館利用状況の可視化」です。複数のオープンデータを用いて、東京都の地図上に児童の利用状況を可視化しました。この時点では、卒論のテーマは決まっておらず、可視化に関する研究を進めたいという思いから、技術習得の側面もあって、このテーマを選びました。
4年次の研究テーマは、「SSBJ基準による非財務情報の可視化」です。就職活動をしていく中で、企業の統合報告書を読む機会があったのですが、ESGデータ(環境、社会、ガバナンスに関するデータ)は数値として開示しているものの、活動の成果は文章での説明にとどまっていることを目の当たりにしました。さらに、サステナビリティ・ブランド国際会議に参加した際、企業価値とESGデータの関係性を示す回帰モデルに関する説明を聞きました。そこで、両者の関係性を可視化するための方法を提案したいという思いに駆られました。そこで、卒業制作として企業間の非財務情報のデータ比較ができるシステムを開発しました。データの収集の改善点が残っているため、今後も継続的に取り組んでいきたいと思います。 -
ゼミの中で自分が成長できたと思うところを教えてください。
-
ゼミの海外研修に参加したことで、国際的な視野の拡大につながりました。2年生のときタイを訪問し、KMITL(モンクット王工科大学ラートクラバン校)の学生と交流をしました。この活動を通じて、多様なバックグラウンドをもつ人々と交流することの意義を実感するとともに、国際的な問題に対処するには、多様な価値観や文化的背景の理解が不可欠であることを学びました。帰国後は、より深いコミュニケーションを図るため、語学力の向上にも努めており、自己の成長を感じることができました。
3年生のとき、学会へ初参加しました。知らない人だらけの場所で発表すること自体、はじめての経験でとても緊張しましたが、練習の甲斐もあってスムーズに発表することができました。質疑応答では、盲点となっていたことを指摘していただき、大変参考になりました。ゼミの指導教授は、「研究成果だけではなく、研究途中のものを発表することにも意味がある」と仰っていました。様々な分野を専門とする研究者の方々から助言を得られたことで、その後の研究活動に活かして、成長するきっかけになりました。 -
アルバイトやインターンシップ、サークル等、正課外の活動について教えてください。
-
ICT支援員として、教育機関の課題解決に従事していました。主に、ICT研修の実施、ICT活用授業の提案、授業の操作支援、機器の整備など、先生や児童が快適にIT機器を利用できるようにサポートしました。
ICT支援員は、先生からの要望に応えるだけでなく、自ら校内の課題を把握し、改善のために働きかける必要があります。潜在的な課題を把握するためには、日頃のコミュニケーションに加えて、観察力が必要であることに気づきました。指導要領の確認や授業の見学を通して、この場面では、どのようなことを児童に考えさせたいのか、そのために、先生はどのような声かけをしているのかなどを、注意深く観察することに努めました。職員室の会話や児童の様子を参考に、提案を考えることもありました。
はじめの頃は、大学生に提案されても受け入れてもらえないだろうと、勝手に思い込んでいました。しかし、担当校の先生方は、私の提案にも熱心に耳を傾けてくださり、授業に取り入れていただけることもありました。また、提案に対して教育的な視点でのアドバイスをいただき、より良い形で児童たちが取り組めるように協力してくださりました。
最近では、先生から「この授業でタブレットを使うから支援に入ってもらえますか」、「研究授業でこの単元のグループワークをやる予定だけど、良い方法はありますか」などとお声がけいただくことも増え、信頼していただけることに感謝しています。この経験を糧に、コンサルタントとしての一歩を踏み出していきたいと考えています。 -
大学生活を経て、なぜその内定先に応募しようと思ったのか教えてください。
-
コンサルタントは、様々な企業の課題解決に取り組みます。そのため、幅広い業界のプロジェクトを経験できます。一方、プロフェッショナルとして、クライアントの課題解決に携わるため、その業界の知識やトレンドに精通していなければならず、常に新しいことを取り入れなければならないという大変さもあります。しかし、課題解決を通じて、クライアントの企業価値を高めることで、自分にできることよりも大きな価値の創造を実現できると思いました。それは、クライアントのパーパス実現を後押しすることにより、間接的に社会変革に貢献することです。
内定先の企業は、日本発のコンサルティングファームで、世界各地に拠点があります。外資系の日本支社では中々経験できない、海外プロジェクトに挑戦する機会があることも、魅力的に映りました。さらに、内定先の企業は、課題把握、問題解決、結果検証などの場面で、一貫してデータ活用できる点において、クライアントからも高い評価を受けています。一般的に、データサイエンティストとコンサルタントは、異なる職種として分けられていることが多いです。そのため、どちらのスキルも身につけられて、活躍することのできる環境が整っている企業を選びました。 -
iTLでの4年間はいかがでしたか。
-
iTLの4年間では、2つのつながりを感じることができました。1つは、自分の中でのつながりです。大学は、分野横断的な科目が多いため、ある講義で学習した内容が違う講義でも扱われます。特に、この学部では情報学的な観点から取り上げられた事例が、法律学的な観点で取り上げられることが多々あります。勿論、すべてを覚えている訳ではないので、記憶を頼りにノートを遡ることもあります。その結果、同じ言葉に対する情報量が増え、深い知識を習得できたと思います。
もう1つは、他者とのつながりです。友人たち、教員の先生方、職員の方々など、様々な人に支えられていたことを実感しています。友人たちとは、授業で分からなかったことを教え合い、私生活でも互いに励まし合うことで、大学生活を乗り越えることができました。ゼミの指導教授には、学術面と人間的な面の両方において成長する機会を与えていただき、感謝しています。学内行事や調査活動を実施できたのは、職員の方々のご尽力のおかげです。今後は、後輩のサポートや講演などに携われるように、日々研鑽していきます。 -
受験生へのメッセージをお願いします。
-
受験生の皆さんへ、進路選択に悩まれている方も多いことと思います。私自身、どの学部に進学すればよいのか、たくさん迷いました。最終的に、国際情報学部に進学することを選んで良かったと、心から思うことができています。それは、自分が掲げた目標を実現できたからです。 進路を決める時点では、選択した進路が正解(結果として適切)かどうかは、誰にも分かりません。しかし、意志をもっている人は、どのような環境でも力を発揮することができるものです。どのような進路を選択しても、そこへ進むことを強く願い、努力し続けた人は、自分の力でその選択を正解にできると思います。
そのためには、大学で達成したい目標を明確にし、それに向けて日々取り組むことが大切です。ぜひ、これからの目標をしっかりと掲げ、期待を胸に進学してください。皆さんの大学生活が充実したものになることを、心からお祈りしています。







