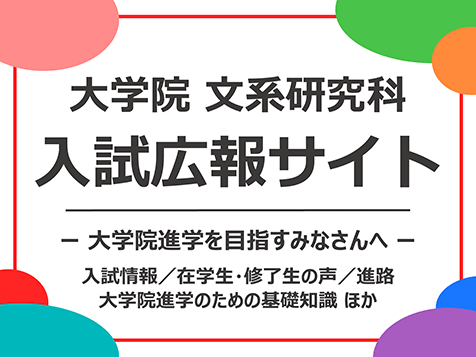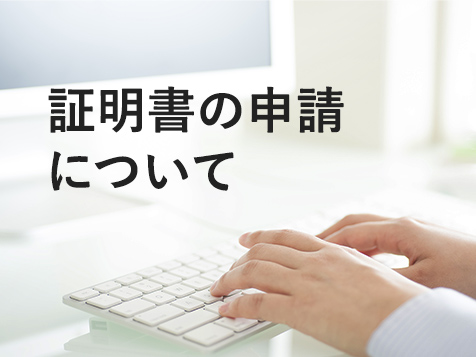文学研究科
文学研究科委員長挨拶
不透明な時代思潮に新たな展望を

中尾 秀博 文学研究科委員長
文学研究科は、13の専攻(国文学、英文学、独文学、仏文学、中国言語文化、日本史学、東洋史学、西洋史学、哲学、社会学、社会情報学、教育学、心理学)で構成されています。研究領域は人文科学系から社会科学系に亘り、一部には自然科学系に隣接する分野も含まれ、古今東西の言語・文化・地域・社会などに通暁した専任教員が所属しています。哲学・文学などの人類最古からの学問分野もあれば、社会情報学のような最先端の学問領域もあります。「研究者養成」と「高度専門職業人養成」の二本の柱を建て、「研究者養成」では、文学研究科全体で既に200人以上が博士号を取得し、研究者として着実な成果をあげているだけではなく、教育者として後進の研究指導にも多大な貢献をしています。「高度専門職業人養成」は、本研究科で磨いた高度な実践力を活かし、教職・公務員・民間企業などの実務的な分野で活躍する修了生を輩出しています。
「9.11」から20余年、「3.11」から10余年が経過し、ウィズ/アフター・コロナの新しい規範とともに生きるわたしたちは、気候危機に象徴される地球規模の課題に即応することができず、ウクライナやガザの無惨な戦禍になす術もなく、「不透明なVUCA*時代」に直面し続けています。文学研究科の根幹にあるのは、このような状況にこそ必要な〈教養〉、即ち、問題の本質を洞察し、新たな展望を切り拓く〈想像力/創造力〉の涵養です。
文学研究科では、根源的/革新的な〈知〉を13専攻それぞれの縦軸として培ってきていますが、その〈知〉と〈知〉を有機的に結びつけるために、専攻の境界を越えた横断的な授業科目も開設しています。領域横断的な「知の越境」が促す広い視野の獲得が、縦軸の〈知〉の探求の意義を再認識し、〈教養〉の深化を導くヒントにもなっています。**
智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。***
漱石『草枕』のあまりに有名な一節です。昨今の「不透明」な時代が「住みにくさ」に拍車をかけている感は否めませんが、このような時勢だからこそ、まずはその「住みにくさ」そのものの本質を洞察することが肝要であり、その任を果たすことこそが文学研究科の存在意義にほかならない、と自負しています。わたしたちは、かねてよりの「角が立つ」ことを疎まず、「流される」ことに怖じず、「窮屈」を厭わない姿勢を堅持していく所存です。「不透明」な時代思潮に新たな展望を切り拓くという試みに、研究者仲間として参加していただけることを心から願っています。
*VUCA とは、 Volatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性)という4つの単語の頭文字を並べた頭字語。最近のビジネス業界で使われている元軍事用語で、時代の「不透明性」の構成要因を示している。
**文学研究科で開講されている専攻横断的な授業科目に加えて、中央大学大学院では他研究科で開講されている科目も履修することができる「オープン・ドメイン制度」も整備されている。
https://sites.google.com/a/g.chuo-u.ac.jp/newbunkeidaigakuin/c
***文中の「智・情・意地」は「知性・感情・意志」と読み替えられる。文化庁の月報「言葉のQ&A」に拠れば、「流れに棹さす」の意味を尋ねた「国語に関する世論調査」の結果、本来の意味ではない「傾向に逆らって、ある事柄の勢いを失わせる行為をすること」と答えた人が6割強だったとのこと。