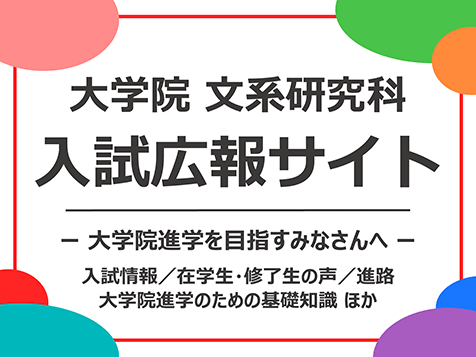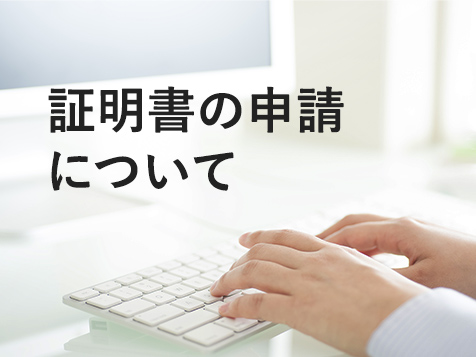文学研究科
文学研究科委員長挨拶
知の世界の13通りの歩き方 ──海図を手に学問の旅に出よう

阿部 成樹 文学研究科委員長
雑学と学問の違いはなんでしょうか。雑学は、互いに関連のない、あるいは関連の薄い情報の雑多な集積を指す言葉だと考えられます。それゆえ、『日本国語大辞典』によれば、雑学とは「系統、組織立てて専門に研究していない」知識ということになります。雑学の知識と体系立った学問研究によって得られる学知とは、本質的に異なるものです。
今、知識を得る手段として、ネットワーク上の情報検索が全盛であるように見えます。AIによって得られる「解答」もまた、一見したところ首尾一貫した知識に見えるものの、ネット上に無秩序に散らばる情報を元にもっともらしく組み立てられているという意味では、雑学の域を出るものとは言えません。そして、いくら検索を重ねAIに尋ねて知識を集積したとしても、能力が向上するのは検索サイトのアルゴリズムであって、検索する側ではありません。つまり、目の前の現実に対応する処方箋を創案したり、未来を展望する視野を開いたりする見識を身につけることはできません。
ところで、アルゴリズム algorithmという言葉は、9世紀前半に活躍したアラビアの数学者にして天文学者、アル・フワーリズミー(al-Khwārizmī, 780頃-850頃)に由来します。彼はアッバース朝のカリフに仕えながら、古代東方からインドに至る数学の伝統を受け継ぎ、その業績は12世紀になるとラテン語に訳されて、中世ヨーロッパの数学に大きなインパクトを与えました。「代数」を意味するalgebraという語もまた、彼の著作のタイトルに起源を持っています。今から1200年も前のアラビアの数学と、ネット検索の用語に繋がりがあるというわけです。しかし、このことはけっして空中に浮かんで孤立した事象ではないのです。諸先学の研究を紐解いてフワーリズミーから視野を広げていくならば、アラブ-イスラーム世界の数学や天文学、医学などの高度な研究が、ヨーロッパにおける科学の礎を築く上で果たした意味深い役割が見えてきます。フワーリズミーは、この大きな構図の中に位置づけられるひとつの事例なのです。
「アルゴリズム」の語源がアラビア語である、という情報は、ネット上の検索からも得ることができるでしょう。しかしそこで立ち止まってしまえば、それは単なる雑学にとどまります。一方、イスラーム世界とヨーロッパ世界が長く紡いできた複雑な関わりを幅広くかつ系統立てて知ることで、現在混迷を極めているように見えるこれらふたつの世界の角逐に別な角度から光を当て、その根底を見ることができます。このように、系統立てられた知の体系、学知は、現実を新たな目で見直し、未来を展望する力をもたらします。
文学研究科は13の専攻を擁し、人間とその社会についての広大な研究領域をカバーしています。各専攻に準備された精緻な海図を頼りに学問の世界を探究することで、行き当たりばったりの情報のつまみ食いではけっして得られない、世界を読み解き的確に判断する力を身につけることができるでしょう。そうした冒険にご一緒できることを、心から楽しみにしています。