2025年6月24日(火)、経済学部准教授 近廣昌志が担当する入門演習にて、元三菱銀行で現在は某企業年金基金の運用管理責任者である下山 泰生さまをお招きし、「銀行融資・審査と企業財務」と題した特別講義が行われました。
下山さまは京都大学経済学部出身で、学生時代はボート部とESSに所属。「入学時身体がなまっていると感じ、身体を鍛えよう」との思いで部活に励んだというエピソードや、地元・大分県国東地方の歴史文化についてもお話くださいました。
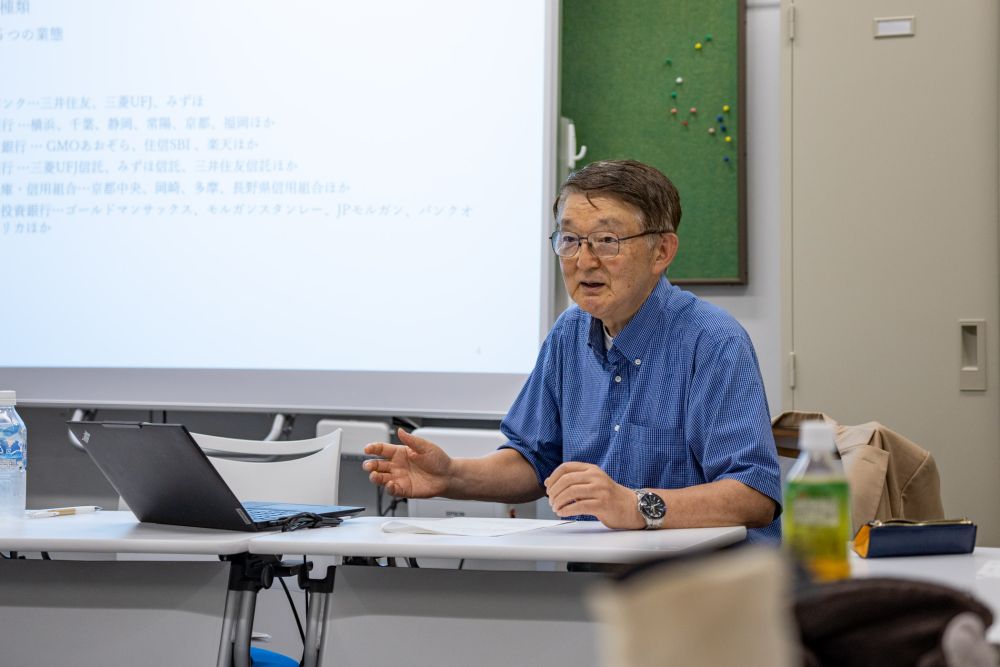
入行後は資金や預金等支店の基本業務を経験後に融資業務を担当、良い取引先との出会いもあって実績を積まれ、海外赴任のチャンスを得て中国に赴任。米国と合わせて18年の海外勤務を含め、約22年間を国際金融の場で活躍されました。バブル崩壊後の金融再編などの歴史的な背景、さらにインターネットの普及によって変化した銀行の姿についても触れられました。窓口業務の縮小や手数料の変化をはじめ、昔の実体験をもとにしたエピソードには説得力がありました。
講義中盤から、金融の基礎として5つの業態の解説、間接金融と直接金融の違いの解説を皮切りに、銀行業務に就いての詳細な説明をいただきました。
証券会社は直接資金を調達する手段を提供し、株式発行を通じて企業と投資家を結びつけ(=直接金融)、関節金融である銀行は「お金が余っている人」から集めた預金を「お金を借りたい人」に貸し出し、その金利差=利鞘で利益を得るのが基本構造ということです。 こうした違いを押さえたうえで、銀行業務の三本柱である「預金・融資・送金」について具体的に説明され、特に融資については、ご自身の経験を交えて、契約書の作成や審査の流れ、そして担当者としての心得について詳しくお話しくださいました。
下山さまは担当者に求められる3つの原則として、「法令やルールの遵守」「スケジュールを守ること」「企業秘密を口外しないこと」を挙げました。また、融資において最も大切なのは「返済能力の見極め」であり、それを判断するために企業の財務諸表を読む力、特に簿記の知識が役に立つとアドバイスされました。

企業の安全性を分析する際には、回転期間などを指標として用い、現場を見たり経営者と徹底的に話し合うことが、机上の数字だけでは見えない情報を補完する鍵になるとのことでした。本社の審査部と意見が合わないときには、自ら出向いて現場の実態を伝え、取引の必要性を粘り強く説明することもあったそうです。「銀行を代表してこの企業と向き合っている」という覚悟で臨むことで、企業に対して改善提案をする立場にもなるという、責任感と誠実さのある姿勢が印象に残りました。
社会に出る前の学生にとって、金融リテラシーの重要性や職業人としての心構えを学ぶ貴重な時間となりました。
