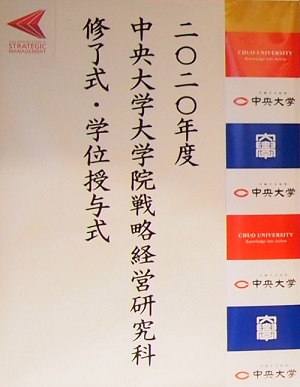ビジネススクール
研究科長から令和2年9月の入学生と修了生へのお祝いメッセージ
2020年09月23日

<令和二年秋入学生への祝辞>
みなさん、中央大学ビジネススクールへのご入学おめでとうございます。入学に際して、みなさんを励まし、背中を押し、支えてくださっているご家族・ご友人・関係者のみなさまにも、心からのお慶びを申し上げます。
中央大学ビジネススクールは、2008年に設立され、今年2020年で13年目を迎えます。この4月は、新型コロナウィルス感染拡大期で入学式を行うことができませんでした。しかし、本日は、ささやかでも入学のお祝いができることを、教職員一同、心から嬉しく思います。
他の大学と同じく中央大学も前期はオンライン授業を余儀なくされました。CBSでも5月の連休明けから、開講科目すべてをオンライン双方向授業に切り替え、教員も学生も慣れないZoomでの授業に戸惑いながらも、試行錯誤を積み重ね、なんとか前期を乗り越えることができました。
一方、授業はオンラインで実施することが可能になりましたが、みなさんがCBSに入学した大きな理由の一つであるネットワーキングを実現することは、オンラインだけでは限界がありました。そこで、前期後半のM2からは対面授業をとり入れて、ハイブリッド型の授業にも挑戦してきました。教室もオンラインと対面の両方での参加で可能になるように作り替え、学生の協力を得て実証模擬講義なども行いました。研究科長主催のオンライン懇親会では、学生諸君の協力もあり80名もの学生が集まり、親交を深めました。
全員必修であるリーダーシップコアの授業では、最後の発表会に対面受講の学生が20名くらい集まって、同期の仲間たちと初めてリアルにあう場ができました。そのときの受講生の感想は、「ただ、ただ楽しい」、「遊園地に来ているよう」といった、無邪気な子供ようなものでした。ずっとパソコン上の枠の中でしか会えなかった仲間と会えた喜び、それは何にも勝るように感じました。
本に書いてある理論を学ぶだけであれば、オンラインだけでも良いのかもしれませんが、そこから何を読み取るか、そのからくみ取った意味を深めていくには、やはり「対話」が不可欠です。「対話」とは、単に言葉のやりとりだけではなく、言葉の背景にある感情のやりとりでもあります。人間は五感を使って周囲の環境から、ありとあらゆる情報を受け取っています。そして、言葉の背後にある人と人との感情のやりとりが場の雰囲気をつくり、それを左右します。
新型コロナ禍に見舞われて、われわれは、オンラインでも仕事ができるということに気づき、それと同時に、リアルに会うことの意味や価値について再認識しました。ハイコンテクスト社会である日本では、テキストのやりとりだけでは誤解を招くことも多く、また、知らないところでコミュニケーションの穴が生まれ、そこからトラブルになることも多々あります。また、ルーティンワークはオンラインでできても、創造性は人と人とが出会うことなしには生まれてきません。そのことを実感したこの6ヶ月間だったように思います。
新型コロナウィルスとの共存はこれからしばらく続くでしょう。われわれも少しずつですが、このウイルスとの付き合い方がわかってきたように思います。これからの半年、1年でわれわれに求められるのは、コロナ禍を理由にして歩みを止めることではなく、コロナ禍をテコにして、今までできなかったことに向き合ったり、今までの常識を疑って新しいことにチャレンジすることです。それが、われわれが育成を目指すチェンジリーダーとしての態度です。
みなさんがオンライン授業を前提として入学したこと、その勇気とチャレンジ精神に敬意を表します。CBSでの学生生活が多くの学びや気づきの場なるように、ぜひともみなさんに協力をお願いしたいと思います。単なる教育サービスの受け手としてではなく、一緒によい学びの場をつくっていく仲間としてみなさんをお迎えしたいと思います。
今日から新しい学びの始まりです。CBSへようこそ!
令和2年9月19日
中央大学大学院戦略経営研究科 研究科長 露木恵美子

<令和二年修了セレモニー 研究科長祝辞>
みなさん、本日は、修了おめでとうございます。みなさんをお支えくださったご家族・ご友人・関係者のみなさまにも、心からのお慶びを申し上げます。
2年前の入学式の日を思い出してみてください。あの時のご自分の思い、何が起こるかという期待や、本当に続けられるかという不安などが入り混じった、それでいて、前向きで明るいワクワクした気持ちを。それから2年が経ちました。アッという間だったと思う方も、長かったなと思う方もいらっしゃると思います。たぶん、みなさんに共通しているのは、本当に大変だったという思いと、やり切ったという充実感であり、2年前には想像しなかった新しい自分との出会いだと思います。
いろいろな人との出会いを通して、自分とは異なる意見や経験を持つ人がたくさんいることを発見し、驚き、時には反発し、時には落ち込み、そして励まされ。社会人として仕事をするなかで、知らず知らずに身についた仮面を捨てて、年の差や境遇の差を超えて向き合えた経験は、これからのみなさんの宝になると思います。
さて、世界では新型コロナウイルスが猛威を振るい、あらゆる活動が制限されています。新型コロナウイルスが怖いのは、人と人との関係を分断するウイルスだということです。このウイルスのために、人は外出を控え、会いたい人に会いたいときに会えなくなり、人と人とがお互いに警戒しあっています。社会の雰囲気が悪くなり、それによって社会全体病んでいるかのようです。みなさんも、最後の半年はオンラインでの受講を余儀なくされました。
新型コロナ禍に見舞われて、われわれが遭遇したのは、「リアルに会うことの意味は何か」という根本的な問いでした。定型化されたルーティンワークはオンラインでできても、創造性は人と人とが「出会う」ことなしには生まれてきません。本に書いてある理論を学ぶだけであれば、オンラインだけでも良いのかもしれませんが、そこから何かを読み取り、そのくみ取った意味を深めていくには、「対話」が不可欠です。「対話」とは、単に言葉のやりとりだけではなく、言葉の背景にある感情のやりとりでもあります。人間は五感を使って周囲の環境から、ありとあらゆる情報を受け取っています。そして、言葉の背後にある人と人との感情のやりとりが場のコンテクストをつくり、そこから意味が生まれてくるのです。
従来のルーティンが通用しなくなったこの時代だからこそ、「ことが起こっている最前線」で考え、実行し、前に進む力が必要です。日々変わる状況に適切に対応するには、トップダウンの判断だけではうまくいきません。現場での柔軟性と適応力が必要です。しかし、それぞれがバラバラに判断して動いてしまっては、逆に混乱を招きます。その時に必要となるのが判断の「軸」となるビジョンやミッションです。今、問われているのは、ビジョンやミッションや戦略がどのくらい、組織のメンバーひとりひとりに浸透しているか?具体的に腹落ちしているのか?ということです。日ごろ顧客志向と謳っていても、今のような状況になったときに顧客の立場に立って考えることができなければ、立派なビジョンやミッションも絵にかいた餅でしかありません。
また、このような状況だからこそ、今までは見えてこなかった組織の優れた側面や、逆にシステムの問題点も見えてきます。平時には見えない組織の底力や欠陥があぶりだされます。そして、今は組織が抱えるさまざまな課題を改善していくチャンスでもあるのです。そこに切り込んでいくのが、二年間CBSで学んだチェンジリーダーとしてのみなさんの使命だと思います。
新型コロナウイルスによる社会不安は、これからも続くと思いますが、その不安は「自分たちがどのように生きたいか」、「どういう未来をつくりたいか」という「意志」でしか乗り越えることはできません。怖れる気持ちは「行動」でしか克服できません。身をかがめて元に戻るのを待っているだけではチャンスはこないのです。
日本では、社会の目を恐れて「やる選択よりもやらない選択」をすることが多く、それが組織の中でも正当化されています。しかし、無難な選択をするよりも、「誰のために」、「何のために」をよく考えたうえで、自分の意志で決定する。周りをみるのではなく、自分が「生かされている場所」に立って、慎重かつ大胆に行動することが、この難局を乗り越える秘訣だと私は思います。
今日の修了式はみなさんにとっての通過点でありゴールではありません。「行動する知性」、チェンジリーダーとしてのスタートの日です。われわれは、チェンジリーダーとして、みなさんが飛躍されることを心から信じています。そして、これからも、みなさんが迷った時や羽を休めたくなった時に、いつでも気軽に帰ってこられる学びの場でありたいと思います。
みなさん、本日は修了おめでとうございます。
令和2年9月19日
中央大学大学院戦略経営研究科 研究科長 露木恵美子