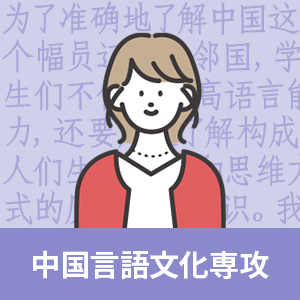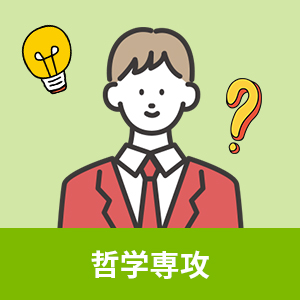- HOME
- 時間割から知る 文学部
- 心理学専攻
心理学専攻
- Department of Psychology
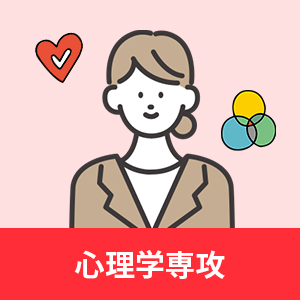
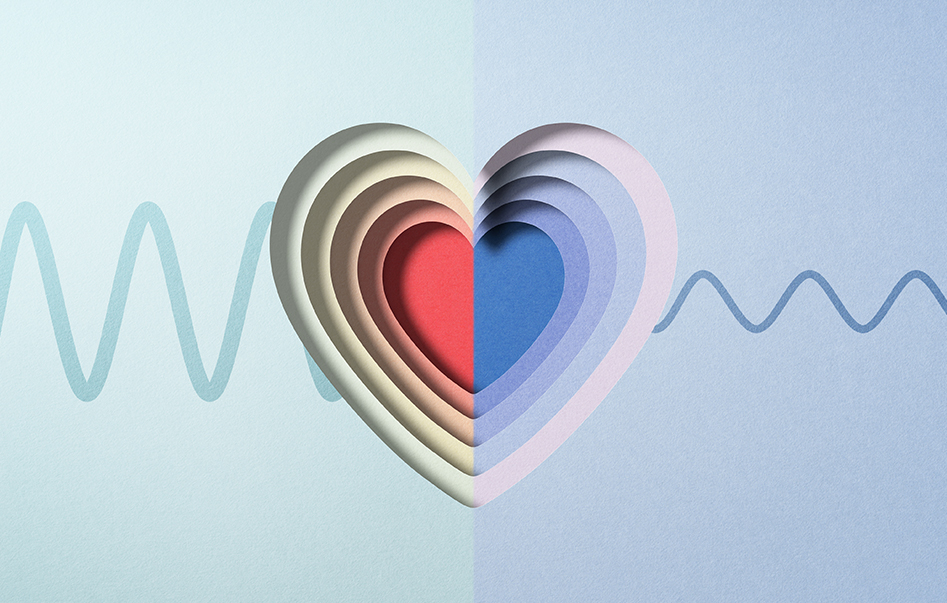
自分の中にある常識を根底から覆し、新しい「知」を提供する。
心という目に見えないものを客観的に捉えるために、心理学では実験・観察・質問紙調査などの方法や数学を用い、科学的な真実を追究します。その一方で、心理学では一人の人間を、 対話を通して深く理解しようとします。あなたは科学的な「知」を身につけつつ、実践の中で出会った他者の言葉に対し思索を重ねることになるのです。
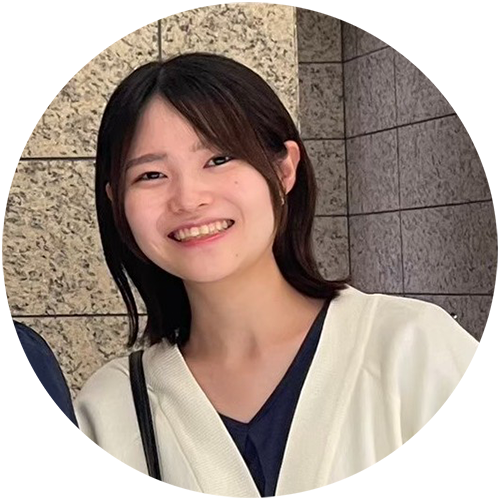
-
- 畠 ゆりあ(はた ゆりあ)
- 心理学専攻 3年 / 中央大学杉並高等学校 出身
- 新しい価値観に触れることが好きなので、人の行動や背景を理解するためのさまざまな視点が身につく心理学専攻で日々楽しく学んでいます。趣味は旅行で、大学に入ってからは海外旅行も経験しました!音楽も大好きなので、移動中はいつも音楽を聴いています。
時間割を教えてください
3年次の時間割です。
| 1 | 前期 | 生涯発達心理学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後期 | 司法・犯罪心理学 | ||||||
| 2 | 前期 | 社会言語学概論 | |||||
| 後期 | 聖書からキリスト教へ | 福祉心理学 | |||||
| 3 | 前期 | 認知心理学 (知覚・認知心理学Ⅱ) |
言語心理学 (学習・言語心理学Ⅰ) |
||||
| 後期 | 西洋美術史(近現代) | 学習心理学 (学習・言語心理学Ⅱ) |
発達相談 | ||||
| 4 | 前期 | 心理学的支援法 | 障害者・障害児心理学 | 心理学特殊研究(1) | 大脳生理学 (神経・生理心理学Ⅰ) |
||
| 後期 | 心理学特殊研究(1) | 神経心理学 (神経・生理心理学Ⅱ) |
|||||
| 5 | 前期 | ||||||
| 後期 | |||||||
| 6 | 前期 | ||||||
| 後期 |
★上記の時間割に加え、夏季集中講座(4日間)の「心理的アセスメント」も履修していました。
時間割の中から1つ曜日を選び、1日のスケジュールを教えてください
-
8:30
起床
2限スタートの日の朝は、少しゆとりがあります。
-
9:30
登校
自宅から最寄り駅まで30分歩いて行くのが、大学生活で唯一の運動習慣です。
-
10:50
2限 福祉心理学
児童や障がい者、高齢者に対する支援について学ぶ授業です。適宜メモをとりながら聴講します。
-
12:30
友人と昼食
2限後の昼休みは学食が混雑しますが、フラット(ヒルトップ)では比較的すぐに買えるうえ、パンがおいしいのでお気に入りです!
-
13:20
3限 発達相談
昼食をとったら、すぐに次の授業です。講義に加え、映像なども見ながら発達障がい等について理解を深めます。
-
15:10
4限 神経心理学(神経・生理心理学Ⅱ)
学部長による授業です!ディスカッションなども交えながら、脳の機能や疾患について学びます。実は脳科学と心理学は密接に関連しています…!
-
18:30
帰宅
そのままアルバイトへ向かう日もありますが、今日はシフトが入っていないので帰宅します。
-
21:00
夕食&フリータイム
基本的にはテレビを見ながらリラックスしています。小テストのための勉強や課題も夕食前後の時間を使って少しずつ進めます。
-
25:00
就寝
今日は少し早めの就寝です。

印象的な授業があれば教えてください
2年次で必修の『心理学実験』です。心理学の研究方法のうちの「実験法」と「質問紙調査法」の2つを実習を通して経験できます!通年で2時限続きかつ課題のやりごたえもあるので、心理学専攻の全授業の中でも存在感の大きな授業だったと感じています。
レポート作成やグループでの発表に取り組むにあたり、クラスのメンバーと議論する機会があっただけでなく心理学専攻の先輩や他クラスの友人からヒントをもらう場面もあり、専攻全体で協力する一体感のようなものが感じられた点が印象的でした。
この授業を通して実践的に学んだ基礎(心理学研究の進め方、レポートの書き方、論文の読み方など)は、その後のレポート作成や卒業論文執筆に間違いなく役に立っています!
受験勉強(特別入試の対策等も含む)はどのようにおこないましたか?重要なポイントは?
私は中央大学の附属高校出身なので大学受験は経験していないのですが、学業に取り組む際に心がけている自分なりのポイントがあります。
まずは、自分に合った学習方法を見つけることです。学習方法について、「こんな勉強法が効果的」というようなさまざまな情報が入ってくるかと思いますが、それらに惑わされずに自分なりに定着しやすい方法を見つけることが大切だと感じています。
もうひとつは、疑問に思ったことをその場で解消することです。分からないことや気になったことが生まれたら、その時点で自分で調べてみたり友人や先生に質問してみることで、その後の学習内容の定着率アップにつながります。学習する姿勢を習慣化することで、根を詰めすぎず学業に取り組めるのではないでしょうか。
現在所属している専攻(プログラム)を選んだ理由は?
人の行動や心理について追求する心理学が最も興味を惹かれる学問分野だったからです。日常生活に応用できそうな理論や、一風変わった研究が多いところに魅力を感じていました。また心理学といえば「他者理解」のイメージも強かったので、それまでの生活のなかで自分のものとはちがった価値観に触れるたびに視野が広がるようなおもしろさを感じ、興味をもつことが多かったことも心理学に興味を持った背景かもしれません。
実際に入学してみてどうですか?
まず、心理学に関しては理系的な側面が強い点におどろきました。心理学の研究は科学的な方法で行われるので、統計の知識なども必須です。分析スキルやものごとを定量的に捉える力が身についた点はうれしい誤算でした…!また心理学のさまざまな授業を通して人の行動やバックグラウンドについての理解が深まったことで、他者に寄り添う姿勢がより強くなったと思います。
また自分が専攻する学問以外の学問分野の授業も履修することができるので、ほんとうに様々な視点や考え方の引き出しが増えたと感じています。異なる学問分野のあいだで重なる部分を発見する場面も多く、横断的な学びも得られました。
これから学びたい・研究したい分野(卒業論文テーマなど)は?
ストレスや健康心理学を扱うゼミに所属しているので、健康について心理学的観点から研究したいと考えています。大学生は生活スタイルが自由なぶん、食生活が乱れがちという現状があります。このような課題に対して、健康的な食生活を送っている大学生の行動傾向を調査することで健康な食生活のヒントを見出したいと思っています。
今後、挑戦したい・挑戦中のこと(資格課程や留学など)は?
1年生のときに国際交流のためのプログラムに参加してベトナムへ行き、東南アジアの学生たちと英語での交流を経験しました。しかしそこでは、語学力が足りず思っていることをうまく伝えられない葛藤も生まれました。そこから語学力を向上させるため、TOEICを中心に英語の勉強をしています。また英語力を実践的に試す意味でも、英語圏への旅行に挑戦してみたいです!
卒業後の進路や将来の夢についてお聞かせください
卒業後は民間企業へ就職予定です。私の進路は心理職ではありませんが、文学部での幅広い学びを通して身についた広い視野と、心理学を通して身についた他者を尊重し寄り添う姿勢は、どのようなフィールドでも応用できると考えています。将来は文学部での学びを大切にしながら、周囲の人にとっての拠りどころとなれるような存在になりたいです。
多摩キャンパス内のおすすめスポットを教えてください
-
生協の向かいのエリア
文学部棟からは少しだけ距離がありますが、四季を感じられるのでお気に入りです。ベンチやテーブルもあり、とくに春や秋には心地よく過ごせる場所です。すぐ横にはテミス像もあります。 
学生生活の必需品を教えてください
-
ノートPC、イヤホン(2代目)
ノートPCは、Excelなどの出番が多い心理学専攻の講義や課題・レポート作成に欠かせません。就職活動などの学業以外の場面でも大活躍しています。イヤホンはキャンパス内でのオンデマンド講義の視聴や通学中の音楽鑑賞の必需品です。 

-
- 野口 璃音(のぐち りね)
- 心理学専攻 3年 / 私立日本航空高等学校 出身
- 受験勉強の合間は家のうさぎに癒され、チョコを食べて元気を出しました。『心理学実験』は自分が気になっていることを実際に調査できるため、やりがいがありました。
時間割を教えてください
3年次の時間割です。
| 1 | 前期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後期 | 司法・犯罪心理学 | 関係行政論 | |||||
| 2 | 前期 | English Reading | |||||
| 後期 | English Reading | ||||||
| 3 | 前期 | 西洋美術史 (近代以前) |
認知心理学 (知覚・認知心理学Ⅱ) |
言語心理学 (学習・言語心理学Ⅰ) |
|||
| 後期 | 学習心理学 (学習・言語心理学Ⅱ) |
||||||
| 4 | 前期 | 心理学的支援法 | 心理学特殊研究(1) | 大脳生理学 (神経・生理心理学Ⅰ) |
|||
| 後期 | 日本の美学 | 心理学特殊研究(1) | 神経心理学 (神経・生理心理学Ⅱ) |
||||
| 5 | 前期 | ||||||
| 後期 | |||||||
| 6 | 前期 | ||||||
| 後期 |
時間割の中から1つ曜日を選び、1日のスケジュールを教えてください
-
6:00
起床
-
8:50
登校
通学時間は1時間半程度です。
-
9:00
1限 司法・犯罪心理学
この授業は3年生以上でないと履修できないのですが、1年生の時から受けてみたいと思っていた授業でした。1限は朝が早くて大変ですが、頑張って起きて大学に向かいます!
-
10:50
2限 空きコマ
Cスクエア(リーフ・カフェ)で課題をしたり、予習をしたりしています。友達に分からないところを教えてもらったりもします。
-
12:30
学食(リーフ・カフェ)で昼食
多摩キャンカレーがおすすめです!
-
13:20
3限 学習心理学(学習言語心理学Ⅱ)
この授業では人の学習や記憶、思考の過程などについて学びます。それらに関する沢山の研究が紹介されるのですが、面白い研究ばかりで改めて「心理学って面白いな」と感じられる授業です。
-
16:30
アルバイト
大学からそのままアルバイトに向かいます。
-
22:00
帰宅
課題が溜まっていたりすれば帰宅後に行いますが、火曜日は帰宅が遅いので、できるだけ課題は空きコマの時間や他の曜日に行うようにしています。
-
25:00
就寝

印象的な授業があれば教えてください
2年次の必修科目となっている『心理学実験』が印象に残っています。この授業では前期(クラスによっては後期)に心理学研究における実験法、後期(クラスによっては前期)に質問紙調査法を学びます。
前期には知覚、記憶、学習に関する実験を実施し、データの収集、統計的な分析、考察を行い、実験レポートを作成します。さまざまな実験を行うので、実験の日はいつもわくわくしていました!
後期には自分でテーマを立案して、質問紙調査を実施し、統計的な分析、考察を行い、レポートを作成します。データの収集が大変でしたが、自分が気になっていることを実際に調査できるため、やりがいがありました。
この授業を通して、心理学研究の基礎を学べたと感じます。
受験勉強(特別入試の対策等も含む)はどのようにおこないましたか?重要なポイントは?
何事もコツコツ、そして早めに取り掛かることが重要だと思います。特に日本史の一問一答や英単語帳、古文単語帳などはできるだけ早く、そして毎日1ページでもいいから覚えようとするべきだと思います。自分が受験本番までに単語帳を何周したいのか逆算してコツコツ進められると直前になって焦るということがないと思います。また、高3の秋冬は過去問を沢山解くことが非常に重要だと思います。解いていくなかで、問題の傾向が掴めると思いますし、何より時間配分が上手くなると思います。
現在所属している専攻(プログラム)を選んだ理由は?
私は大学では心理学を学びたいという明確な希望があったため他の専攻を受験することは全く考えませんでした。
中央大学の心理学専攻は公認心理師受験資格に対応するカリキュラムとなっているため、資格取得を目指すことができる点、また、心理学を基礎から臨床まで幅広く学べる点に魅力を感じ、中央大学心理学専攻の受験を決めました。
実際に入学してみてどうですか?
選んだ理由としても挙げましたが、1年次、2年次で幅広く心理学を学べることが中央大学心理学専攻の魅力のひとつだと思います。
実際に私は1年次、2年次に『知覚心理学』『学校臨床心理学』『発達心理学』『人格心理学』『家族心理学』『社会心理学』『産業・組織心理学』『福祉心理学』などさまざまな心理学の授業を受けました。
また、中央大学心理学専攻は文学部の中にあるため、心理学以外にも哲学や社会学、教育学などさまざまな領域の授業を受けることができ、より広い教養を身につけることができると思います。
これから学びたい・研究したい分野(卒業論文テーマなど)は?
現在は過剰適応に関心があります。過剰適応とは、自分の行動や考えを過度に周囲に合わせようとしてしまうことです。近年、不登校の要因のひとつとして過剰適応は注目されています。私はこの過剰適応と家庭環境、家族関係との関連について研究したいと考えています。
今後、挑戦したい・挑戦中のこと(資格課程や留学など)は?
私は1、2年次に第二外国語として中国語を学んだのですが、新しい言語を一から学ぶことはとても楽しく、中国語の勉強が心理学の勉強の合間の息抜きにもなっていました。 そのため、4年次にまた新しい言語の勉強をしてみたいと考えています。 KPOPが好きなので、韓国語に挑戦しようと思っています!
多摩キャンパス内のおすすめスポットを教えてください
-
Cスクエア(リーフ・カフェ)
文学部はヒルトップという多摩キャンパスのメインの学食からは少し遠いので、すぐ隣にあるリーフ・カフェで昼食をとります。ヒルトップに比べるとメニュー数は少ないですが、毎日とても美味しい学食が食べられます!机と椅子も沢山ありますし、勉強している人も多いです。私も空きコマはここで過ごします。 
学生生活の必需品を教えてください
-
ノートパソコン
1年次、2年次はオンライン授業も多かったのでパソコンで授業を受けていました。このパソコンで課題を作成したり、授業でメモを取ったり、発表資料を作成したり、統計ソフトを使った分析をしたりします。なくてはならない必需品です。