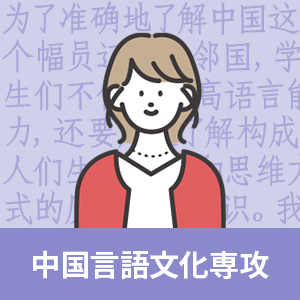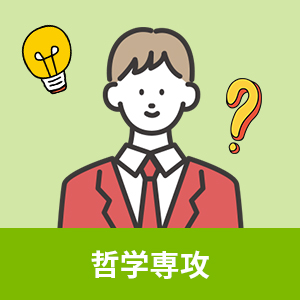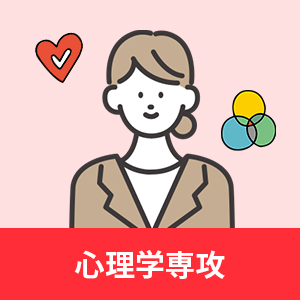- HOME
- 時間割から知る 文学部
- 学びのパスポートプログラム
学びのパスポート
プログラム- Interdisciplinary Studies Program

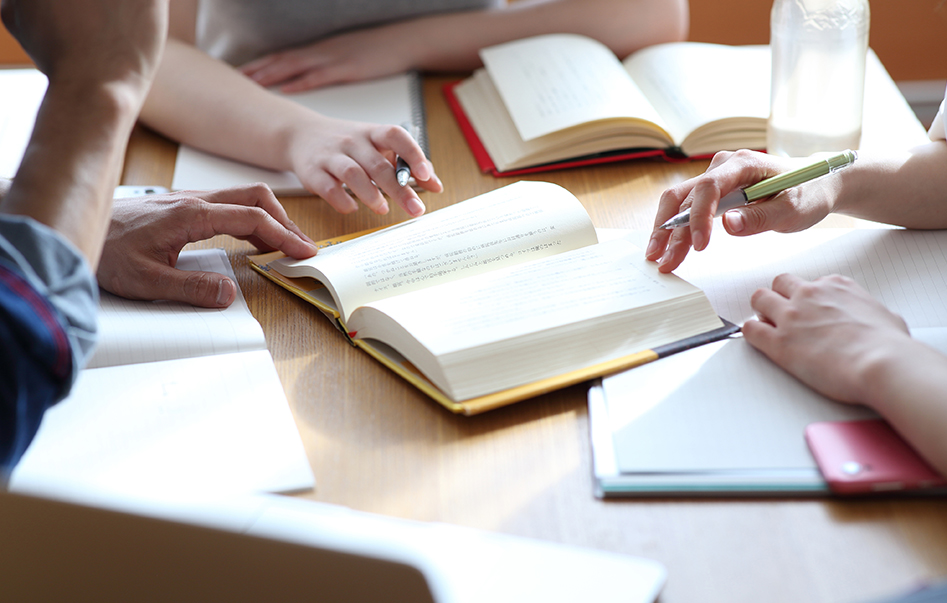
領域を横断しながら自ら学びをデザインし、人や社会を読み解く。
激変する現代社会の諸課題を読み解いていくには、さまざまな学問分野の基礎を学び、それらを相互につないでいく自由な発想が必要です。そのような発想をもつ人を育てようとするのが、この「学びのパスポートプログラム」です。入学時に「社会文化系」と「スポーツ文化系」どちらかの系統を選択し4年間自分だけのオリジナル・カリキュラムで学びます。

-
- 小野 祐司(おの ゆうじ)
- 学びのパスポートプログラム スポーツ文化系 4年 / 東京都市大学附属等々力高等学校 出身
- 家が遠いので通学時間は貴重な睡眠時間。大学のクラスは部活に全力で取り組む人がほとんどでいい刺激を受けます。卒業後は、小さい頃から好きなテレビとスポーツに携わる仕事に就きます。
時間割を教えてください
2年次の時間割です。
| 1 | 前期 | 人体の構造と機能及び疾病 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後期 | |||||||
| 2 | 前期 | 運動と食事の科学 | 生涯スポーツ演習 | 学びの基礎演習A | ニュースポーツ・ミニサッカー(体育) | ||
| 後期 | ジャーナリズム論 | 学びの基礎演習B | 情報社会と倫理 | ||||
| 3 | 前期 | スポーツビジネスプログラム | 政治学 | 社会心理学(1) | |||
| 後期 | スポーツ史 | 近世文学B | English Reading | ||||
| 4 | 前期 | 入門・歴史 | 日本の思想の歴史 | ||||
| 後期 | |||||||
| 5 | 前期 | ||||||
| 後期 | |||||||
| 6 | 前期 | ||||||
| 後期 |
時間割の中から1つ曜日を選び、1日のスケジュールを教えてください
-
8:00
起床
-
9:00
通学
電車で1時間ぐらいです。通学中は睡眠時間に充てます。
-
10:00
2限 ニュースポーツ・ミニサッカー
体育でサッカーをします。朝のいい運動になります。
学びのパスポートスポーツ文化系は体育が3単位必要なので2年の時も履修します。 -
12:30
学食
ヒルトップか文学部棟近くのCスクエアで友達とご飯を食べます。
-
13:20
3限 社会心理学
オンデマンドなので場所を見つけて授業動画を見ます。
-
15:10
4限 日本の思想の歴史
これもオンデマンド授業なので自分のペースで動画を見ます。
-
18:30
帰宅
-
23:00
取材準備
次の日取材の予定があれば、取材の準備をします。
-
25:00
就寝

印象的な授業があれば教えてください
情報社会と倫理
メディアコミュニケーションがどのような社会状況の中で生み出されてきたのかを分析する授業。バラエティ番組がどのように変化していったかを授業で学べておもしろかったです。授業内の資料で、ドリフ、俺たちひょうきん族、電波少年といった番組の映像が出てきてテレビ好きにはたまらない授業でした。
障害者スポーツ
東京パラリンピックに出場された車いすバスケの選手が授業に来て、パラスポーツを取り囲む現状や見る側がどのような視点を持って見るべきなのかということを講演してくださったのでとても印象に残っています。
受験勉強(特別入試の対策等も含む)はどのようにおこないましたか?重要なポイントは?
自己推薦入試で入学したので、自分が大学で何を学びたいのかを文章で伝えられるようにする練習をしていました。あと小論文の対策にも時間をかけていました。
就活とも似ていますが、志望理由書に記載する自分が学びたいことが大学でちゃんと学ぶことができるかが重要だと思います。
現在所属している専攻(プログラム)を選んだ理由は?
中央大学内で唯一スポーツに関して専門的に学べるプログラムだと思ったから。
実際に入学してみてどうですか?
入学して最初の顔合わせの時、同じクラスの子の出身高校で甲子園のトーナメント表が作れるのではないかというぐらいスポーツの強豪校出身の人ばかりで最初は入る所間違えたかなと思ったのですが、今まで接することのなかったスポーツの第一線で活躍してきた人の話などは貴重で、またスポーツに関する授業でもアスリート視点の意見が聞けて充実した授業でした。
これから学びたい・研究したい分野(卒業論文テーマなど)は?
卒業論文テーマは「新国立競技場はレガシーとしての役割を果たせているのか~味の素スタジアムと比較~」というテーマです。大好きなオリンピックから派生させて卒業論文を執筆しました。
卒業後の進路や将来の夢についてお聞かせください
卒業後はテレビ局で働くので、オリンピックや世界卓球の現地取材に行くのが夢です。
多摩キャンパス内のおすすめスポットを教えてください
-
フォレストゲートウェイ
学内で課題や授業を受ける時によく使いました。 
学生生活の必需品を教えてください
-
iPad
1~2年の時はオンデマンド授業も多かったのでiPadで授業動画を見ていました。
またこれ1台あればノートとしての役割も果たせるのでよく使っていました。 

-
- 田中 采美(たなか ことみ)
- 学びのパスポートプログラム 社会文化系 3年 / 私立東海大学菅生高等学校 出身
- 学びのパスポートプログラム一期生。前例がないので不安でしたが、自由に自分のやりたいことを追求でき、とても有意義な時間を過ごすことができています。学食メニューは八王子ラーメンがおすすめ!
時間割を教えてください
3年次の時間割です。
| 1 | 前期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後期 | |||||||
| 2 | 前期 | 西洋中世史 | 経済学 | 聖書の思想と歴史 | 倫理学 | ||
| 後期 | 教育相談と進路指導 | ジェンダー/ セクシュアリティ |
|||||
| 3 | 前期 | 社会科・ 公民科教育法1 |
社会科・ 地理歴史科教育法1 |
Oral Communication | |||
| 後期 | 社会科・ 公民科教育法2 |
社会科・ 地理歴史科教育法2 |
Oral Communication | ||||
| 4 | 前期 | 後期教養演習 (人文知の饗宴) |
English Writing | 総合講座(スポーツ・ビジネス−競馬の世界)JRA協力講座 | イギリスの文化(1) | English Writing | |
| 後期 | English Writing | アメリカの文化(2) | English Writing | ||||
| 5 | 前期 | 専門演習(1)A ※1 |
|||||
| 後期 | 比較文学 | 専門演習(1)B ※2 |
政治学 | ||||
| 6 | 前期 | ||||||
| 後期 |
冬季集中開講科目:文化政策論
※1「西洋史特別演習A」と同内容
※2「西洋史特別演習B」と同内容
時間割の中から1つ曜日を選び、1日のスケジュールを教えてください
-
9:30
起床
朝に弱いので起きるのはゆっくりです。
-
10:50
2限 教育相談と進路指導
2限は教職課程の授業です。
-
12:30
昼食
八王子市出身で、八王子ラーメンが大好きなのでよく食べています。学食で食べることができるのが本当に嬉しいです!
-
13:20
3限 社会科・地理歴史科教育法2
教職課程の実践的な授業です。授業の仕方を学んだり、模擬授業に取り組んだりしています。
-
15:00
4限 アメリカの文化(2) 図書館で課題
4限はオンラインなので図書館で課題に取り組んでいます。図書館が1番静かで集中できる場所です。
-
17:00
5限 専門演習(1)B(西洋史特別演習B)
私は学びのパスポートプログラムですが、西洋史専攻のゼミに所属しています。研究発表の準備が大変ですが、とてもやりがいがあります。仲間の発表を聞くことも楽しいです。
-
19:00
帰宅
家が近いのでさっと帰ります。
-
20:00
夕飯
料理が好きなので自炊もしています。
-
22:00
課題
3年生になると発表や模擬授業などの機会が増えるので、その準備をしています。課題がない時はリラックスする自由時間です。
-
24:00
就寝
翌日がアルバイトなので夜更かしすることは少ないです。

印象的な授業があれば教えてください
私が1番印象に残っているのは、「後期教養演習(人文知の饗宴)」です。
この授業は、文学部13専攻の枠を超え、文学部のそれぞれの専攻の先生方が自身の研究内容やなぜそれを研究し始めたのかなどを語ってくださるオムニバス形式の授業です。普段自分が興味を持っている分野ではない先生の話を聞くと、その分野の面白さに気付き、また自分の興味のあることに対して別の視点から見ることで新たな発見ができました。また「文学部は役に立たない」と考えられている現代において、人文学を学ぶことの意義を考えることは、私や人文学の未来を考えるきっかけにもなりました。文学部に所属する全員におすすめできる授業です。いくつもの発見の機会を与えてくれた「後期教養演習(人文知の饗宴)」は私が3年間で受けてきた授業の中でも特に印象に残っています。
受験勉強(特別入試の対策等も含む)はどのようにおこないましたか?重要なポイントは?
私が受験勉強で1番重要だと考える点は誰かに頼ることです。私は塾に通っていなかったのですが、その分高校時代の先生にお世話になりました。当時コロナ禍真っ只中(2020〜21年)であったため、人に会うこともできず、とても孤独を感じていました。そのような状況ではなくても、受験勉強は孤独です。特に一般入試の人は、友人が先に推薦入試などで進路が決まることもあるでしょうし、私がそうでした。当時は友人が先に進路が決まったことも、それを心から祝うことができなかったことも、とても辛かったです。そのような状況でも味方になってくれる人を探すこと、その人に頼ることがとても重要だと考えています。私にとっての味方は高校時代の先生でした。勉強方法のアドバイスや個別の指導などの勉強面に限らず、メンタル面でも支えてくださいました。親・兄弟・祖父母・学校の先生・塾の先生・友人、誰でもいいので信頼できる人を見つけて、合格が何よりの恩返しになりますから、その人を遠慮なく頼って、支えてもらってください。
勉強の内容面であれば、効率よく勉強することです。特に塾に通わない場合、誰かからの指示を受けないため、何から手をつけて良いかわからなくなると思います。今やっている勉強が何を習得するためにやっているのかを正しく理解できていれば、自ずとその勉強が必要か必要じゃないかを判断することができます。時間が有限なので、必要ではない勉強に取り組んでいる時間は受験勉強にとって無駄です。反対に、それが必要であるならば、時間をかけて勉強するべきです。例えば、私は高校3年生の間に世界史の教科書を隅から隅まで4周しました。時間はかかりましたが、その後の世界史の理解につながりました。
人にはそれぞれ自分に合った勉強方法があると思いますが、息抜きの時間を作るためにも効率よく勉強しましょう。
現在所属している専攻(プログラム)を選んだ理由は?
私がこの学びのパスポートプログラムを選んだ理由は、高校生時代に大学で学びたいと考えていたことがはっきりしていなかったためです。
世界史の授業が好きだったため、ぼんやりと西洋史学を学びたいとも考えていましたが、その時はまだ4年間西洋史学を学び続ける覚悟が決まっていませんでした。大学で学ぶことを決める際には、入ってみて合わなかったらどうしよう、あまり興味を持てなかったらどうしようと不安でいっぱいでした。
学びのパスポートプログラムであれば、西洋史学の授業を受講しながら他の分野の授業も受講することができるので、仮にその分野が合わなくても他の分野に進むことができる点で、このプログラムを選びました。
実際に入学してみてどうですか?
実際に入学した一年生の時はかなり不安でした。特に私たちは学びのパスポートプログラム一期生であったため、先輩や前例がなく、何をどのように取り組めば良いのかがわからないことが1番不安でした。必修科目が他の専攻よりも少ないため、履修登録は何時間も頭を悩ませました。しかし、本当に自由に自分のやりたいことを追求できるというが分かってからはとても有意義な時間を過ごすことができています。
私はこの3年間、本当に様々な授業を受講しました。西洋史を中心とした歴史系の授業、移民や国際理解に関する授業、文化や宗教に関する授業、教育に関する授業、美術史、地理学、哲学、心理学、経済学、社会学スポーツ科学、プログラミング言語…。自分でも驚くほど多岐にわたる授業を受けてきました。
このプログラムの良い所は授業を受講してから自分に合わない・興味がないと感じたら半期で全く違う方向へ転換できることです。自分の興味の赴くまま、学びたいと思った方向へ行くことができる環境でのびのびと学ぶことができているので、私はこのプログラムに入学して良かったと心から感じています。
これから学びたい・研究したい分野(卒業論文テーマなど)は?
私は2年次の後期から研究テーマを「馬・競馬」に定めています。私は元々動物が大好きなのですが、様々な歴史の授業を受講している中でかなり「馬」が登場することがあるなと感じたことがきっかけです。現在は西洋史専攻のゼミに所属し、イギリスの競馬文化と社会の関わりについて研究しています。今年9月末~10月上旬には中央大学の学外活動応援奨学金を利用した、約二週間にわたるイギリス・フランスでの実地調査を行いました。競馬場や博物館、市中での実地調査では、ヨーロッパの競馬文化や馬文化の根強さを感じ、より一層深く知りたいと感じました。
今後、挑戦したい・挑戦中のこと(資格課程や留学など)は?
私は現在、教職課程を履修しています。小学校から高校まで受けてきた「教育」というものを教える側から学んでみたいというのがきっかけでしたが、教育はとても奥が深く、面白いものだなと感じています。今年の夏休みには学校応援ボランティアに参加し、中学生向けに大学での研究についての授業を行いました。来年は教育実習もあるので、実践的に教育について学び、準備を進めています。

ヨーロッパでの調査の様子

研究テーマは「馬・競馬」です

学校応援ボランティア
多摩キャンパス内のおすすめスポットを教えてください
-
ヒルトップ
大好きな八王子ラーメンがあるからです。八王子市出身でラーメン好き・ネギ好きの私にとって八王子ネギラーメンを超える学食のメニューはありません。一度は食べてみてほしいです。 
学生生活の必需品を教えてください
-
スマートフォン
もちろん日常生活でも欠かせないものですが、大学においても課題を提出したり、写真を撮ったりするのに使います。