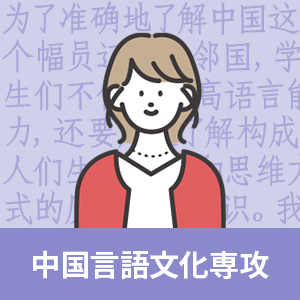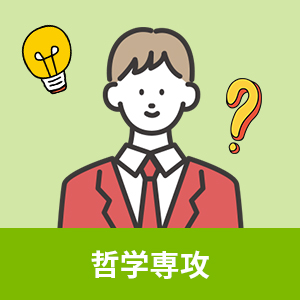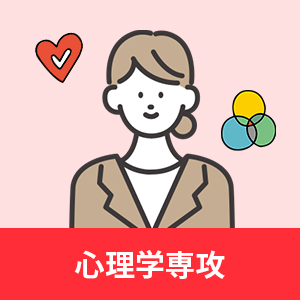- HOME
- 時間割から知る 文学部
- 東洋史学専攻
東洋史学専攻
- Department of Asian and African History


現代社会の成り立ちを、アジアから、歴史から考える。
歴史学とは、現代社会が今ある姿になった経緯を理解するための学問です。国際社会が抱えている多くの問題を解決するために、そして、これからの世界で日本の国や企業・人が真に成功するために、アジアの社会を形づくった歴史への深い理解が望まれます。その手段となる語学力の向上と、透徹した歴史認識の養成に力を注いでいます。

-
- 千野 萌(ちの もえ)
- 東洋史学専攻 4年 / 相模女子大学高等部 出身
- 高校時代は水泳部。高2の時にボランティア活動でタイの方と出会ったことをきっかけに東南アジアの歴史や文化に関心を持つように。大学時代はタイでのインターンシップやオーストラリアでの語学留学を経験。
時間割を教えてください
3年次の時間割です。
| 1 | 前期 | 日本文化史B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後期 | |||||||
| 2 | 前期 | Oral Communication | 世界の英文学(1) | 広告論(1) | |||
| 後期 | ジャーナリズム論 | Oral Communication | 南アジア史 | ||||
| 3 | 前期 | ||||||
| 後期 | イスラーム近現代史 | ||||||
| 4 | 前期 | 日本思想の歴史 | 西洋テーマ史(5) | アメリカの文化(1) | |||
| 後期 | 日本の美学 | メディア文化の社会学(1) | 南アジア史演習 | ||||
| 5 | 前期 | 民俗学A | 東南アジア史演習 (1)B |
インド仏教の教 | |||
| 後期 | 民俗学B | 東南アジア史演習 (1)B |
|||||
| 6 | 前期 | ||||||
| 後期 |
時間割の中から1つ曜日を選び、1日のスケジュールを教えてください
-
7:00
起床
-
9:00
登校
授業前に大学図書館を訪れ、読書をしています。
-
10:50
2限 Oral Communication
外国人講師による実践的な英語を学びます。英語のプレゼンテーションを定期的におこないます。
-
12:30
昼食
コープカフェテリアのお弁当をよく食べています。
-
15:10
3限 メディア文化の社会学(1)
オンライン授業です。翌日中に課題を提出するため、授業動画を視聴し、授業課題を作成・提出します。
-
17:00
4限 東南アジア史演習
ゼミの授業です。東南アジアの歴史や社会に関する知識を深めます。
-
19:00
バイト
大学の帰り道でアルバイトをしています。
-
20:30
帰宅
-
22:00
課題
翌日の小テストの準備や課題レポートの作成します。課題がない日はアニメやドラマを観てのんびり過ごします。
-
24:00
就寝

印象的な授業があれば教えてください
ゼミの東南アジア史演習が印象に残っています。毎回の授業で3年生と4年生が各自の研究成果を発表し、全員で批評します。みなさん、研究する地域やテーマが異なるため、毎回の授業がとても新鮮で東南アジアに関する知識を深めることができます。
受験勉強(特別入試の対策等も含む)はどのようにおこないましたか?重要なポイントは?
指定校推薦だったので、日々の授業や試験をコツコツと真剣に取り組みました。入試対策では、高校の先生に志望動機や小論文の添削、面接練習をお願いしました。大学卒業後の進路も考えながら志望理由を書き進めました。中央大学には他学部の授業も履修可能なので、将来の目標を達成するためにどのような学びが必要なのかを逆算し、面接で伝えるように意識しました。
現在所属している専攻(プログラム)を選んだ理由は?
高校時代に参加したボランティアでタイの方と出会い、タイと日本の生活様式や考え方の違いを知り、東南アジアの歴史や文化に関心を持つようになりました。東南アジアの近現代史に精通し、海外の大学でも勤務経験のある高橋宏明先生のもとで学び、海外も視野に入れて働ける人材になりたいと思い中央大学の東洋史学専攻を選びました。
実際に入学してみてどうですか?
高校の教科書で習った範囲に加え、あまり詳しく勉強しなかった中央アジアやインドの歴史や文化についても深く学び、幅広い知識を身につけることができました。アラビア語やインドネシア語、経済学部の海外インターンシップの授業など、一人一人の目標達成に必要な科目を履修することができ、大変満足しています。中央大学の実践的な学びにより、多様な経験を積み視野を広げたことで、就職活動では希望の進路に進むことができました。

海外インターンシップの様子
これから学びたい・研究したい分野(卒業論文テーマなど)は?
卒業論文のテーマは「19世紀後半におけるタイ農村の経済格差について―バウリング条約がもたらした影響を中心に―」です。
今後、挑戦したい・挑戦中のこと(資格課程や留学など)は?
英語力向上を目指し、TOEICの勉強と英会話に取り組んでいます。
卒業後の進路や将来の夢についてお聞かせください
卒業後は総合建設業界で事務職として働きます。将来的には海外の案件に携われたらと思います。
多摩キャンパス内のおすすめスポットを教えてください
-
3号館から駅に向かう道の木
冬になるとライトアップするので、とてもきれいです。 
学生生活の必需品を教えてください
-
パソコン
授業資料や課題の作成・提出、オンライン授業など大学生活を送るうえで必要不可欠なアイテムです。卒業論文で使用する論文探しや就職活動でも最大限活用しました。 

-
- 田村 まりん(たむら まりん)
- 東洋史学専攻 4年 / 私立聖園女学院高等学校 出身
- 高校時代に読む&観た小説・映画『図書館戦争』に影響を受けて、司書課程を履修しています。ゼミ終わりは、よくゼミ仲間とご飯に行きます。
時間割を教えてください
4年次の時間割です。
| 1 | 前期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後期 | 図書館サービス概論 | ||||||
| 2 | 前期 | 放送論 | |||||
| 後期 | |||||||
| 3 | 前期 | イギリス詩(1) | 図書館 情報資源概論 |
||||
| 後期 | Practice for TOEIC (上級クラス) |
||||||
| 4 | 前期 | メディア文化の 社会学(1) |
|||||
| 後期 | メディア文化の 社会学(2) |
||||||
| 5 | 前期 | アジア地域史演習 (3)A |
|||||
| 後期 | アジア地域史演習 (3)B |
||||||
| 6 | 前期 | ||||||
| 後期 |
時間割の中から1つ曜日を選び、1日のスケジュールを教えてください
-
8:00
起床
-
12:00
登校
12:30を過ぎると学食が混むため、早めに登校します。
-
12:15
友人と学食で昼食
毎週メニューが変わるため、いろんなお店を巡っています。趣味の話やドラマの話など、楽しくおしゃべりしています。
-
13:20
東洋史学研究室へ
卒論指導があるため、研究室に行きます。先生に相談がない日は、ひたすら卒論を書いています。たくさんの史料をすぐ手に取れる環境が最高です!
-
16:00
ゼミ前に休憩
友人とスタバやセブンで何か買って、おしゃべり休憩しています。
-
17:00
5限 アジア地域史演習(3)B
ゼミの授業です。発表に耳を傾け、コメントや質問を考えます。
-
20:30
帰宅
-
21:30
オンライン授業・課題
4限の「メディア文化の社会学(2)」は、オンライン授業で翌日中に課題提出のため、授業動画を視聴し、コメント記入などを行います。
-
24:00
就寝

印象的な授業があれば教えてください
アジア地域史演習(3)A、アジア地域史演習(3)Bはゼミの授業で、毎回3・4年生が課題となる史料に関する発表、卒業論文で扱いたいテーマなどの発表を行います。東南アジアの歴史に関するゼミですが、それぞれが扱う国や地域・テーマが異なり、毎回新たな発見があるため、とても楽しいです。
受験勉強(特別入試の対策等も含む)はどのようにおこないましたか?重要なポイントは?
私は英語運用能力特別入学試験で受験したため、過去問を何度も解いて塾の先生に指導していただきました。
限られた時間でテーマに沿った小論文を書くことが重要だったため、ポイントは自分が確実に覚えている知識を使って、他の人が読んでも伝わるように書くことを意識する点だと思います。
面接については、聞かれるであろう質問に関する答えをキーワードで書き出し、覚えておくことが重要だと思います。
※文学部 注:英語運用能力特別入学試験は2020年度で終了となりました。
現在所属している専攻(プログラム)を選んだ理由は?
もともと世界史の授業が好きで、東洋史学専攻ではアジア・アフリカの広い地域・時代について学べるからです。
受験時は中国史とエジプト史、東南アジア史に興味があり、オープンキャンパスの模擬授業でグローバル・ヒストリー入門についての授業を受けて、とても楽しかったため、東洋史学専攻を選びました。
実際に入学してみてどうですか?
中国史の他にも、高校ではあまり詳しく勉強しなかった中央アジアや東南アジアについても学べたため、とても満足しています。
また地域史だけでなく、史料購読、歴史地理学、歴史とは何かを考える授業、東洋史学の方法、サンスクリット語やアラビア語の授業など、多様な科目を履修でき、幅広い知識を身に付けることができたと思います。
他専攻の授業を履修できたことも、学びを深めるきっかけになりました。
これから学びたい・研究したい分野(卒業論文テーマなど)は?
現在執筆している卒業論文のテーマは、「海峡植民地時代のシンガポールにおけるプラナカン文化の形成について」です。
今後、挑戦したい・挑戦中のこと(資格課程や留学など)は?
現在、司書の資格課程を履修しています。
多摩キャンパス内のおすすめスポットを教えてください
-
3号館から駅に向かう道
大きな木が、季節によって表情を変えるのを見るのが楽しいからです。特に、冬になると、イルミネーションが綺麗です。 
学生生活の必需品を教えてください
-
ノートパソコンとマウス
授業資料のダウンロード、課題の作成・提出、オンライン授業の受講、論文探しなどなど、大学生活で本当になくてはならないものだからです。コロナ禍も卒論も一緒に乗り越えてくれた相棒です。