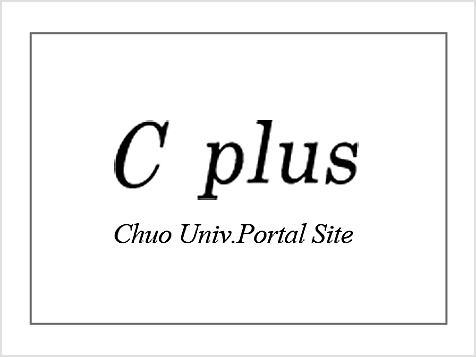法学部
【活動レポート】岡嶋 美和 (政治学科2年)
「やる気応援奨学金」リポート(80)
インドのNGOでインターン 貧困・発展・持続性など再考
はじめに
私は昨夏、法学部の「やる気応援奨学金」をいただき、国際インターンシップとして南インドのチェンナイに二週間滞在した。
この度のインターンシップでは、活動・規模の異なるNGOを訪問し、それらの問題点と社会的意義を検討した。また、在チェンナイ日本国総領事館という日本外交の生の現場に足を運ばせていただいた。BRICSの一国として、世界からの注目を浴びるインド。わずか二週間の滞在であったが、私はこの国に魅了されてしまった。
NGO大国インド
NGOは、国際・国内社会において日々その重要性が高まっているアクターである。NGOは政府・市場・共同体というアクターが抱えきれない問題(スペース)を埋めるために誕生し、機能している組織であり、その潜在的可能性は非常に大きい。
インドでは、国内すべてのNGOを管轄する組織が存在しないことから、実情の把握は難しいとされる。しかし、インドは資金規模と実在数から見て、NGO大国である。年間約三五〇〇億円以上の寄付金があり、その約半分は海外からである。また、外国からの献金を得るにはインド内務省所管の外国貢献規制法に従わねばならず、これに登録しているNGOだけでもその数は約二万にも及ぶ。
そもそもインドのNGOは、日本の定義と大いに異なる。日本では危ぶまれる宗教性の強いNGOはインドではごく当たり前のように存在している。また、政府から独立し、かつ営利を目的としていなければ、私的企業さえも含まれるのである。マザー・テレサの活動に示されるように、「貧困大国」としてのイメージが強いこの国では、福祉や教育面において政府がNGOに「依存」しているというのが現状である。
Don Bosco Anbu Illam
Don Bosco Anbu Illamとは、子供の権利保護と女性の自立支援を行う、キリスト教系のNGOである。活動内容は主として、ストリートチルドレンの保護・子供議会の開催・スラム街での女性の自立支援などが挙げられる。今回は二つのスラム街に赴きDon Bosco Anbu Illamが行っている夕方学校(児童館)やその周辺を見学した。彼らは、経済的貧しさから学校に通えない子供たちのために自由に出入り出来る憩いの場を提供し、夕方からは簡単なタミル語(国語)や英語などを教えている。そこでの目的は、教育の重要性を説くことによって学校に行ける子供を増やすことである。なお、あくまでも子供たちや家庭の自主性を尊重しており、決して強制的ではない。活動の動機となっているキリスト教の教義も、全くと言って良いほど押し付けていなかった。

スラム街の子供たち
スラムという語から、「薄暗い」「汚い」「不潔」「貧しい」という語を想像する人は多いだろう。私もそう思っていた。実際、人々が使用した水を通す下水道は解放状態である。スラム中の汚水がすべて同じ川に流れるため、近くの川は汚染された排水と山積みのごみによって異臭が漂い、発生したガスによりプクプクと泡が出ていた。このような環境が子供たちに与える影響は、想像を絶するであろう。最悪の場合、公害として多くの人に被害が及ぶ可能性さえもある。
しかしその一方で、人々は皆驚くほど明るい。子供たちは興味津々に顔をのぞかせてくる。私たちの名前を聞き、何度も握手を求めてくる。物すごい人だかりと熱気であった。また、私たちが手を合わせてあいさつをすれば、みけんにしわを寄せて怖そうにしていた大人たちもにっこりと笑い返してくれる。人々の穏やかな雰囲気は、スラム街だということを忘れてしまうほどであった。
The Children's Garden School
The Children's Garden Schoolは、事実上私立学校のNGOである。Don Bosco Anbu Illamに比べ、The Children's Garden Schoolは資金面でも教育の質においても高い位置にある。ここでは貧しい家庭以外から教育費を徴収し、制服や給食を提供している。先生方は皆大卒の女性であり、非常に教育熱心だ。先生が一言発すれば、子供たちは一斉に"Yes teacher!"と元気に返事をする。一国でこれだけの差があることに驚きを隠せなかった。
一方、この学校の教育方針の特徴として、「障害のある子供への配慮」が挙げられる。各クラスには一人または二人の障害のある子供が在籍し、先生が付きっきりでサポートをする。彼らの教育を支援する一方、周囲の子供たちにも幼いころから「助け合いの精神」が育まれるようになっていた。私はこのような方針に対し、カースト制度を念頭に置いているような印象を受けた。
カースト制度は一九五〇年に憲法上では廃止された。しかし、五〇〇〇年以上続いた慣習は今もなお伝統として残っており、差別はごく当たり前のように存在している。一方で、カースト制度を超える事例も増えている。インドがIT産業を通じて経済成長を実現した背景には、その分野がカーストに影響されないという側面がある。カースト制度は、異なるカースト同士であつれきを生む一方、同じカースト同士の相互扶助を促進する機能を有していた。今日では、所属を不問とする新たな職業分野の増加や経済成長に伴う人々の価値観の変化によって、その相互扶助機能が形がい化していると見る人もいる。他者、とりわけ弱者を思いやる心の育成は、カースト制度の影響が残っているインドにおいては特に重んじられるであろう。
Reaching The Unreached

家庭環境付与制度
Reaching The Unreached(RTU)は、Don Bosco Anbu IllamとThe Children's Garden Schoolに比べて活動・資金規模の大きい地域開発のNGOである。RTUUK(イギリス本部)代表のJames Kimpton氏が一九七四年に南インド郊外で診療所を開いたことに始まる。キリスト教系のNGOに多い「子供の保護」の理念の下、孤児や貧しい子供への家庭環境付与や、教育、井戸掘り、学校や住居の建設、職業訓練まで、本来ならば政府が行っている仕事をすべてNGOが担っているのである。以前は資金の大半を海外からの献金に頼っていたRTUであったが、現在では域内での工芸品や織物などの売り上げを通じて、自立して運営出来る状況にある。また昨年辺りから創立者のKimpton氏に代わってPaul Samuel氏が取り仕切っており、RTUUKから自立した、現地の人々による運営が行われている。政府からの援助を拒み、自立性を貫き通す姿勢こそ、この地域の成功の秘けつといえるだろう。
在チェンナイ日本国総領事館
総領事館では、総領事を始めとする職員の方々と質疑応答の時間を設けていただいた。ここでは最優先の邦人保護のほか、州政府への日系企業の要望伝達、ODAを使用したインフラ整備、そして「草の根の資金協力」を行っている。
デリーを中心とする北インドが飽和状態の中、南インドでは現在投資ブームが起きており、日本のみならずたくさんの海外企業が進出してきている。総領事館ではそのような日系企業の要望を聞き入れ、道路などのインフラ整備を南インドの州政府に要請している。一方、ODAを使用したインフラ整備では、JICAを通じてチェンナイ市内の地下鉄敷設に取り組んでいる。「草の根の資金協力」とは、ODAの資金を現地の人々に直接使用する支援方法である。NGOの設立を試みる人々が総領事館に援助を要請し、長期的に運営出来るかなどの厳しい審査を通過することで、上限一〇〇〇万円の援助を受けられる仕組みである。
インドでは約束の突然の放棄や、遅刻、わいろの要求は日常茶飯事であることから、計画や交渉が中断することがよくあるという。また、権力闘争が激しいことも特徴の一つだ。実際、チェンナイの州議会のために設計された近代的な建物は、現政権に代わってからは病院として使用予定とされており、前政権の腐敗の象徴として広大な土地を占めている。歴史的に培われた民主主義の精神が根底に流れるインドにおいては、その時の政権との関係を大切にする一方、現地の人々への直接的かつ継続的な支援によって親日感情を育むことこそ、長期的観点からして日印関係に有効なのではないかと感じた。
「貧困」に立ち向かうNGO
三つのNGOでの経験を通じて、数々の疑問がわき起こった。「貧困」とは何か、それは誰の責任か、それを打開するためには誰が、どういった手段で解決していくべきなのかなどである。少なくとも私は、特にDon Bosco Anbu Illamでの体験を通じて、貧困には経済的側面だけではないことを再確認した。もちろん、経済的貧困の解決には一定の数値を設けて支援・保護していくことが、結果が分かりやすくかつ効率的な手段である。しかし、先進国においては仕事のストレスや日常の忙しさなどで心に余裕のない人が多い。心の豊かさといった精神的側面も貧困の一部であるのではないかと考えさせられるのであった。
貧困からの脱却には、原因の歴史的・構造的側面を打開しなければならない。前述したように、NGOは政府・市場・コミュニティーの手の届かない、もしくは届けようとしない問題を解決するために存在し、活動している。また、インドは団体数、資金の量からしてNGO大国であり、政府はそのようなNGOに依存しているというのが現状である。しかし、貧困状態からの脱却という問題には、彼らの活動だけでは金銭的、地理的、時間的な限界があると思われる。実際、Don Bosco Anbu Illamの経営状態はお世辞にも良いとは言えない。今の時点でこの問題を解決出来る資金・権力・手段を有しているのは政府であり、コミュニティーでもある。インドでは経済成長に伴い、裕福になる個人が増えている。インドのNGOへの資金源の約半分が海外からの献金である以上、インド国内におけるNGO以外のアクター、すなわち政府・コミュニティー・個人の責任を追及していく必要があると感じた。
インドの目指す「発展」
また、「発展」についても考えさせられることがたくさんあった。スラムにもテレビはある。そこでは欧米系企業による中産階級の理想像がCMで流され、幸せそうな家族が描かれている。子供たちはそれを目標として生きていくかも知れない。私たちが思い描く発展とは、先進的な建造物や交通機関であふれ、利便性を追求していくことである。しかしその結果、コミュニケーション能力や忍耐力の低下をもたらし、人間としての温かさが失われると指摘されることがある。RTUでは、時間がゆっくり流れていた。そして皆が幸せそうであった。朝起きては互いに髪を結い合い、学校へ行き、夕方は広場で遊び、夜は家族で輪になって御飯を食べる。規則上母親は携帯電話を持っておらず、家にはテレビもない。「発展」は人を幸せにするか。そしてそれは、「幸せとは何か?」という問いにつながっていく。
今回のインターンシップを通じて、持続可能な発展の重要性を、身をもって知ることが出来た。RTUは、成立してまだ一世代しかたっていない。現在良好な運営状態を、今後いかにして継続的に発展させていくか。彼らにとって「発展」とはいかなるものか。一般にインドは「発展途上国」である。しかし、私にはインドが「発展」とは異なる、「自国に適した発展」という未来像を模索しながら前に進んでいるように見えた。
インドに見る人間の根源
インドに来ると、好きな人と嫌いな人の両極端に分かれるとよく言われる。街は牛と牛ふん、それらのにおいであふれており、食べ物には絶えずはえが寄ってくる。地べたに座ってみんなで丸くなっては右手で食事をし、雨が降れば若者は外に出てシャワーを浴びる。今まで東南アジアをよく訪れていた私にとって、インドは一番人間くさかった。
その印象はヒンドゥー教からもうかがうことが出来た。現地ガイドのRanjithさんは、ヒンドゥー教は救世主や預言者のいない、比較的「民主的な宗教」であるとおっしゃっていた。なぜなら、人々は神々の人間関係から教訓を読み取り、日常に取り入れ、その解釈は地域や人によって自由だからである。例えば、胸が三つある女性像の由来は、個人の解釈に基づき六〇種類もの逸話があると言われている。また、神様の扱い方にもインドならではの特徴がある。今回訪れた時期は、ガネーシャを祝う期間であった。ガネーシャとは、象の頭をした商業と学問の神様であり、破壊の神シヴァの息子の一人である。人々はガネーシャの人形を作ってはお供えをし、そして最終的には川や海に投げ捨てていた。その扱いに驚き、疑問を持ったが、おそれ敬う傾向の強い他宗教とは異なり、それもインドの文化なのだと大変興味深かった。もちろん、今回のインターンシップでヒンドゥー教について理解出来たことはほんの一部であり、恐らく間違っている個所もあるであろう。しかし、寺院で祈る人々や街行く人々の姿を見るにしたがい、Ranjithさんのおっしゃっていた「民主的な宗教」という意味を理解出来た気がしたのである。特に私が一番感銘を受けたのが、その「寛容性」である。RTUで見た、ヒンドゥー教の家族が聖書を読み、コーランを読み、家にマリア様を飾ってこれでもかと豪華に装飾する姿は、人類としての普遍性が示されているようで、印象的であった。
インドでは、今もなお宗教対立が毎日のように表出している。RTUで見た光景は少数派であるかも知れないが、そこにインドの生に対する姿勢を見ることが出来たと思う。
おわりに
この度の経験は、今までで一番衝撃的であった。これまでは「観光客」として滞在していたために、貧しい人々や物ごいに遭遇しても、「この国の貧困対策はどうなっているのか」などと思うだけで、彼らと真剣に向かい合うことはなく、よくある一つの光景として過ぎていくだけであった。しかし今回は、もちろん道端で彼らに遭遇することは何度もあったが、スラムを訪れた際に直接交流する機会があった。恐らく私たちがただの観光客であれば、また違った接し方をされたかも知れない。そのようなことを踏まえると、今回の経験がいかに貴重なものであったかを痛感させられる。そしてこのような経験をしたからこそ、自分の将来に生かしていくことが大切なのであると実感した。
結びに代えて、この度このような機会を与えていただいた、「やる気応援奨学金」支援者の皆様、国際インターンシップの講師の皆様、法学部事務室の皆様、現地ガイドのRanjithさんとその御家族、そして昨夏共にインドで過ごしたインドグループに厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。
草のみどり 254号掲載(2012年3月号)