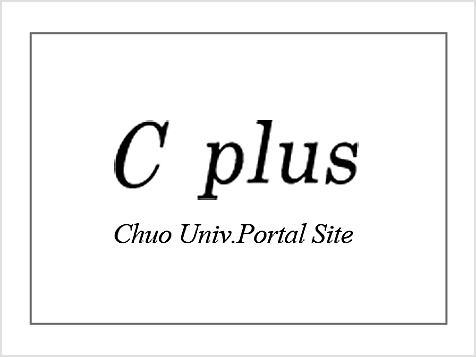法学部
【活動レポート】谷澤 明日香 (国際企業関係法学科4年)
「やる気応援奨学金」リポート(17) ニューヨーク、そしてケニア 〝顔の見える援助〟を求めて
2005年夏、法学部の「やる気応援奨学金」を受けてケニアでインターンシップをする機会に恵まれた。たった1カ月弱の短い期間ではあったが、これまでに自分が留学やインターンシップを通じて経験してきたこととはまた違う体験が出来、多くの人と出会い、多くのことを学び、そして多くのことを改めて考えさせられた濃密な1カ月を過ごすことが出来た。
ここではケニアでのインターンシップの概要、そしてこのインターンシップを行うに至る基盤となった私の経験について紹介したい。
後の下地となる経験
「やる気応援奨学金」に応募する切っ掛けとなった国際インターンシップ講座の受講を考えた2004年の秋、私はアメリカ、ニューヨークにいた。3年次終了後に1年休学しての語学留学。将来に対する漠然としたイメージの中でも感じていた語学習得の必然性や狭く限られた世界からの脱却、そして親戚も知人もいない見知らぬ地に自分を放り出すことで自分の可能性を試したい、という思いから実現したものだった。
その際あえて大学留学ではなく現地でのインターンシップを選択したのは、現地に溶け込み人々と接することで、より生きた言葉や文化、彼らの世界観を身近に感じられるのではないかと考えたからだった。この時はまだ、後に自分がアフリカへ行くことなど考えてもいなかった。

約半年間の語学学校での準備を終え、私はシニアセンターでインターンシップを始めた。シニアセンターというと老人ホームのような施設を想像される方が多いようだが、ここでいうシニアセンターとは日本でいうデイ・ケアセンターのイメージに近いだろう。
比較的元気な高齢者が毎日を楽しく過ごすために利用する場所で、食事代に1ドルの寄付をプラスして提供されるランチや、ここに通う高齢者を含むボランティアによって運営されるカルチャークラスなど、さまざまなサービスが行われている。
また、このシニアセンターには複数のソーシャルワーカーが常勤しており、外出出来ない在宅高齢者に対しての食事配達サービスや病院への付き添い、定期的な家庭訪問などのサービスも行われている。多岐にわたる仕事の中でも、病院の付き添いに際して私は大変多くの経験が出来た。話好きな高齢者と接することで基本的な会話能力が上達したのはいうまでもないが、普段とは全く違う心理状態の人と接することで得たものはそれ以上に大きい。
極度の緊張が彼らに与える影響は大きく、道端で泣き叫ぶ人、病院で怒鳴り付ける人、パニックのあまり自分の名前すら書けなくなってしまう人……などさまざまな場面に遭遇した。そういった場合に必要とされるのは、英語力よりも人としての思いやりや気遣いであり、彼らが抱える思いを共有することだった。
世界経済の中心ともいわれるニューヨーク、さまざまなことが目まぐるしく変化する刺激に富んだ街では、高齢者もつえやウオーカー、車いすを使ってはせっせと外出し、どことなく日本の高齢者よりも活発な印象を受ける。しかし彼らがこの社会において社会的弱者であることに変わりはなく、政府から受け取るわずかな年金以外に収入源を持たない多くの高齢者にとって、物価の高いニューヨークで暮らしていくことは容易ではないのだ。
警戒心の強い彼らが徐々に心を開き、色々なことを語ってくれるようになった時、私は自分にとって〝顔の見える援助〟がどれだけ意味を持っているかということを肌で感じたのだった。そしてさまざまな状況に対処し人と思いを共有することで、英語力を培ったのみならず、本当の意味でのコミュニケーション能力を養うことが出来たと思う。
なぜアフリカか
発展途上国の貧困や開発問題に興味を持っていた私だが、今回ケニアに行くまで実際に発展途上国に行ったことはなかった。そして発展途上国の中でどうしても行きたい国や地域があったわけでもなく、ただ自分の目で確かめてみたいという思いだけが強くあった。そんな中で私とアフリカの距離を急激に近付けたのが、帰国後間もなく参加した国連大学国際講座のインターンシップだった。

国際講座は5月から6月にかけて開講されるもので、国際協力・人権・紛争処理・環境の4つのコースから成る。私たちの仕事は主に受講者たちをサポートすることだった。世界中からさまざまなバックグラウンドを持った人々が参加しており、多くの人と交流を深めていく中でも、なぜか馬が合ったのがアフリカ諸国から来た人たちだった。
彼らはバックグラウンドを異にしながらも、〝アフリカの現状を変えたい〟という共通の熱い思いを胸に抱き、それぞれが考える方法で諸国が抱える問題に取り組んでいた。彼らの中にケニア出身の人はいなかったのだが、はるか遠くの大陸に友達がいるというだけでアフリカが身近に感じられ、私の中で一気にアフリカモードが高まったのだった。

英語圏だったこと、そしていい加減な団体が多いというアフリカの中でも私が参加したNGOの評価が比較的良かったことなどからケニアに絞り、コミュニティー・エンパワーメントが焦点のシスワプロジェクトに参加することになった。
シスワプロジェクト-人々の願いと現実
インターンシップ先となったキャンプ地は、ケニアの首都ナイロビからバスで北西に七時間ほど行った所にあるカカメガ(Kakamega)のシスワ(Shiswa)小学校だった。シスワはカカメガの中心からマタトゥと呼ばれる乗合バスに乗り、更にボダボダと呼ばれる自転車タクシーに乗って、1時間ほどの所にある。
大都市ナイロビとは全く違って、シスワには電気も水道もガスもなく、道路も全く舗装されていない。人々は頭にタンクを載せて川から水をくみ、まきや木炭を使い火をおこして生活する。また、シスワは日本人が持つケニアのイメージ、いわゆる〝サバンナ〟ではなく、豊かな自然に恵まれた緑深い地である。ほぼ毎日のように降る雨は作物を潤し、人々の大事な生活用水にもなる。
そんな小さな村の小学校に、ケニアを含め八カ国から20人のボランティアが集まった。多くがヨーロッパ各国からの参加者で、私たちのほとんどは学生だった。
小学校での主な仕事は、学校の敷地内に幼稚園を新設するための建設作業だった。シスワには小学校以外には幼稚園も中等学校(日本の中学・高校にあたる)もない。子供に良い教育を受けさせたいと願うシスワの人々にとって、小学校の準備段階となる幼稚園設立は悲願だった。
前半はれんが造り。土を掘ってそこに水を加え、ボランティア総出で踏んで泥にする。泥を型にはめ、地面に寝かせて3週間ほど日に干して乾かせばれんがの出来上がりだ。後半は教室作り。ここからは測量など専門家のボランティアも加わった。壁となる位置に溝を掘って石を敷き詰め、セメントを流しこんだ上に更に土をかぶせて固める。その土台の上にセメントで補強しながられんがを積んでいく。

地元の人々の心配をよそに、三週間の作業の後、レンガ8300個と20m×7m四方、高さ約1mの教室の基礎が出来上がった。
予想以上の成果を上げ、プロジェクトは短期ながらも一応の成功を見たといえよう。しかし問題も山積みだ。1つ1つの作業そのものは至ってシンプルだが、泥を造るにも石を運ぶにもセメントを造るにも、とにかくすべてが手作業で行われるため予想以上に時間が掛かる。段取りも決して良いとはいえなかったし、作業用具が不足していたことも効率の悪さに拍車を掛けた。
また、私たちボランティアが去った後は人手も足りず、セメントも底を突いたが新たに購入する資金はないという。コミュニティーの人々の意識の間にも温度差が存在し、幼稚園開園に至るにはまだまだ前途多難なようだ。
プロジェクトの焦点であるコミュニティー・エンパワーメントのために行われたのは建設作業ばかりではない。地元コミュニティーと交流を深めるためになされたさまざまな試みのうち、Home Visitといってシスワに暮らす人々のお宅を訪問するものがあった。伝統料理のもてなしを受けながら、文化的な面ばかりでなくエイズや教育、経済などの多岐にわたる分野で各々の国の違いなどについて意見交換をし、時には白熱した議論が繰り広げられた。
どの家庭にも壁に現大統領の肖像画が飾られており、シスワで政治について話す時、コミュニティーの人が現政権を批判することがなかったのがとても印象的だった。また、エリアチーフから現地ボランティアのお宅まで多くの人々のお宅を拝見するうちに、決して豊かとはいえないシスワの地であっても確実に存在する富める者と貧しい者の間の差をはっきりと見て取ることが出来た。
Home Visitで医師の家を訪問したことが切っ掛けで、エイズに関するイベントを開いたりもした。偏境の地のシスワでもHIV/AIDSはマラリアに並ぶ大変深刻な問題で、両親をエイズで亡くし、更に自らも母胎を通じて感染しているエイズ孤児が増えている。

イベントは学校の先生に掛け合って時間を割いていただき、6~8年生(11~15歳程度)を対象に行われた。先進国とのエイズ教育の方針の違い、例えばケニアでは婚前性交の抑制など禁欲を大きく掲げるが、そういったことも考慮し、医師や学校の先生にも相談して準備が進められた。
当日は医師に協力を仰いで講演が行われ、ボランティアメンバーはエイズに関する知識をクイズ形式で織り込んだ寸劇を演じた。クイズは基本的な知識を問うものがほとんどだったが、子供たちのエイズに対する知識は私たちボランティアが予想していた以上。驚いたと同時に、エイズ教育の浸透がケニアにおけるエイズの持つインパクトの大きさを物語っており、複雑な気持ちを覚えたのだった。
教育にアクセスする権利
ここでケニアの教育制度について触れようと思う。ケニアでは日本同様、六歳前後で小学校に通い始めるが、義務教育ではない。学年は1年から8年まであり、試験の結果次第で小学生のころから留年する仕組みになっている。公立小学校の学費は基本的には無料だが、制服を各自で用意しなければならないなど実際は年間1,500ケニア・シリング(2,300円前後)が必要となる。
そして中等学校(secondary school)が4年間、大学が4年間と続く。中等学校からは学費も有料となり、年間2万~3万ケニア・シリング(約3万~4万5000円)が掛かる。大学の学費は更に高額で、ほんのひとつかみの裕福な人々にのみ開かれた道であるといえよう。
こうした状況で小学校にすら通えない子供は依然として多く存在し、就学しても修了出来ないケースも多い。これを聞いて「無料なのにどうして通えないのか」と考える人もいることだろう。しかし、現実として制服代すら捻出出来ないほど貧しい家庭は多く存在するのだ。貧困層ほど大家族の傾向が強いことも1つの要因といえるし、ストリートチルドレンなどはそのすべを持たない。
また、多くの部族が暮らすケニアでは共通語の問題もある。ケニアの公用語は英語とスワヒリ語だが、多くの部族が固有の言語を持っている。学校で共通語として使われる言語は、シスワならルイヤ(luhya)語、というようにその地域に暮らす部族の言語が反映される。つまり、多くの部族が混在するケニアの都市部では、たとえ制服代を捻出出来て子供を学校に通わせることが出来たとしても、子供が理解出来ない共通語で授業を受ける可能性があるのだ。
ほかにも小学校無料化に伴って就学率が上がった結果、教室や教師の不足、教師の質も問題になっているなど、授業料が無料であるということが、〝すべての子供が等しく教育にアクセス出来る〟ことを意味するものではない、ということを痛感させられた。
〝貧しい〟とは
ケニア滞在中、ナイロビにあるスラムを訪れる機会に恵まれた。スラムの写真などは見たことがあったが、実際に友人の家に行ってその暮らしぶりを目の当たりにし、正直ショックを受けた。シスワでのキャンプ生活で電気・水道・ガスなどがない生活には慣れているつもりだったが、スラムでの生活条件はより厳しいものだった。〝貧しい〟の一言でくくられてしまう中にも環境や条件によって更に差が生じてしまう現実がある、ということを思い知らされたのだった。
ナイロビのような大都市では現金がなければ日々を暮らすことすら難しい。職を求めて国中から人々がやってきた結果、多くの部族が混在し、幾つもの言葉が行き交い、小競り合いも頻繁に起きる。衛生環境は劣悪を極め、トタン板で囲まれた小さなスペースに暮らす人々の間にプライバシーを尊重する余地はない。
スラムの人口増加はとどまるところを知らず、多くのホームレスが厳しい生活を強いられているニューヨーク同様、都市における貧富の差は容易に是正出来る程度を超えているのだ。
一方、シスワの人々は確かに貧しいが、人としてより尊厳のある生活をしていた。それぞれの土地に家を持ち、豊かな自然の中で作物や家畜を育てて暮らす。木炭を買うお金がなければまきを拾えば良いし、水は川からくみ放題。産業のないシスワは公害とも無縁で、毎日降る雨水が1番奇麗な水として飲料水に回される。同じ部族から構成されていることもあって相互扶助の意識も高い。
「決して豊かではないけれども、私たちは幸せだ」と笑顔で語ってくれたシスワの人々。他方、世界の現実を顧みることもなく、消費社会に身を預けて利益を享受し、毎日膨大な無駄を出しながら暮らす人々。〝貧しい〟とは何なのか、考えずにはいられない。
最後に

今回、短期ながらもケニアに行き、コミュニティー・エンパワーメントの一環としてのプロジェクトに参加出来たことで、多くのことを学んだと同時に将来に対する可能性はまた広がったと感じている。ニューヨークでのさまざまな経験が私を柔軟にし、コミュニケーション能力を高めてくれたこともあって、ケニアでの生活は毎日が新たな発見と刺激、そして出会いに満ちあふれていた。
バケツ1杯の水でシャワーを浴びたことも、雨上がりの泥道をはだしで歩いたことも、シスワの人々の好奇の目にさらされながら仕事をしたことも、照り付ける日差しのあまりの強さに日焼けを通り越してやけどを負ったことも、食べ物にあたって体調を悪くしたことすらプラスの経験であり、それらが多くのことを学んだり考え直したりするための切っ掛けとなった。
また、貧しい中でも笑顔を絶やさず強く明るく生きる人々を目にし、志を同じくする多くの人に出会ったことは、私が〝顔の見える援助〟を実行するうえでの最大の財産となり、これからも継続的にプロジェクトにかかわっていくためのモチベーションを与えてくれることだろう。
今後自分がどのような形で途上国の問題にかかわっていくかはまだ分からないが、ケニアがニューヨークに続く第3の故郷だといえるくらい素晴らしい経験をさせてもらった今、たとえ回り道をすることになったとしても、何らかの形で彼らに貢献しようと強く思う。
最後になりましたが、このような機会を提供してくださった中央大学法学部の関係者の皆様、そして小言を言いながらも理解を示してくれた両親に心から感謝いたします。本当にありがとうございました。
草のみどり 191号掲載(2005年12月号)