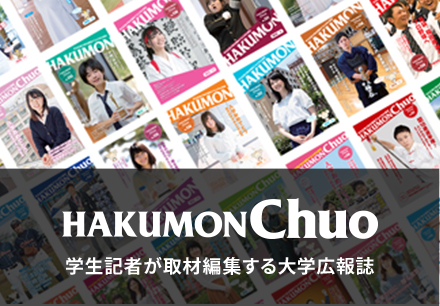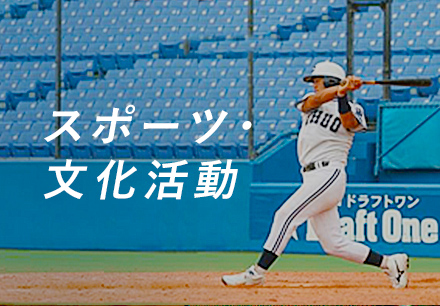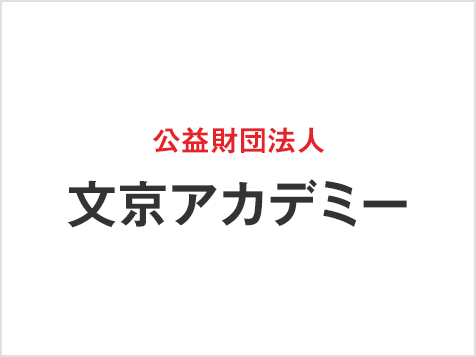更新日:2025年09月10日
総合講座
【満席受付終了】絵画を味わう -風景、神話、宗教、風俗画の世界-
- 対面式
- 芸術伝統
- 総合講座
講座番号:14111
- [秋期/全4回【満席受付終了】]
- 9/20、10/18、11/15、12/13
- 受講料:12,100円
講義概要
コーディネーター 小林 亜起子 講師
【講座内容】
毎年、国内では西洋絵画の展覧会が開催され、欧米のコレクションを所蔵する美術館も各地に広がりつつあります。このように芸術に触れる機会が増えている今、ただ鑑賞するだけでなく、絵画の奥深い魅力を味わうための「見る力」を養いたいと考える方も多いのではないでしょうか。そこで今学期の美術史講座では、鑑賞眼を磨くために、神話画、宗教画、風俗画、風景画という4つの代表的な絵画のジャンルに焦点をあて、それぞれの特質を掘りさげて学びます。
神話画や宗教画をよりよく理解するためには、まず神話や聖書の物語についての基礎知識を身につけることが重要です。そのうえで、絵画の表現伝統や登場人物を識別するためのアトリビュート(持物)についての知識が求められます。たとえば、愛と美の女神ヴィーナスは「バラ」や「つがいの鳩」とともに描かれることが多く、これらが女神を特定する手がかりとなります。
風俗画や風景画は、人々の日常や自然の景色といった身近な世界を題材としているため、予備知識がなくても楽しむことができます。しかし、さらに一歩踏みこんで、風俗画や風景画の成立・発展の歩みを紐解き、作品が描かれた時代の文化や社会、人々の価値観、自然へのまなざしを読み解くことで、これらの絵画ならではの魅力を堪能できるでしょう。
この講座は4人の講師によるリレー形式で進められます。各回の担当講師及び講義内容については、下記をご参照ください。1回目は風景画、2回目は神話画、3回目は宗教画、最終回は風俗画を詳しく見ていきます。西洋絵画の鑑賞方法をぜひごいっしょに学んでいきましょう。
【各回のテーマ・簡単な内容】
第1回 自然を描く -古代から20世紀へ 変わりゆく風景表現 9/20(小林亜起子講師)
人間の歩みはつねに自然とともにあり、その風景は古代よりイメージの歴史の中で息づいてきました。自然は、古代から中世にかけて、神話画やキリスト教絵画の背景として描かれました。やがてルネサンスの時代、人間の目線で世界が見つめ直されるようになると、日々の営みの舞台として、生き生きとした風景が描かれるようになります。17 ~ 18 世紀のフランスでは、理想的な風景を追求する表現が広まり、19 世紀になると、画家たちは新たな眼差しで身近な自然と向き合い、その表現は大きな変革を迎えます。
本講座では、古代から20 世紀に至るまでの風景表現のダイナミックな変遷をたどりながら、描かれた自然の多様な魅力を深く探求していきます。
第2回 神々を描く -古代から17世紀まで 10/18(山本樹講師)
古代ギリシャ・ローマ神話をテーマとする美術作品は、キリスト教美術と並び西洋美術の花形でしょう。古代に生まれた神々は、その後西欧世界がキリスト教化されてゆくなかで一時的に影をひそめますが、ルネサンスという古代復興の時代に至って美術の世界を再び闊歩するようになります。
本講義では、西洋美術における古代ギリシャ・ローマ神話主題の代表的作例を見ながら、神話画の歴史と基本的な見方を学びます。また、異教神話の神々がルネサンス以降の人文主義的環境のなかで再解釈された事例として、ローマのファルネーゼ宮殿の絵画装飾をご紹介します。ヘラクレスやヴィーナスといった現代にも知られる神々について、美術作品を通じて理解を深めましょう。
第3回 信仰を描く -中世からルネサンスまで 11/15(平井彩可講師)
キリスト教主題を描く宗教画は、西洋美術における一大ジャンルです。特に中世においては「芸術は教会のはしため(婢…召使いのこと)」とさえ言われたほど、すべての芸術はキリスト教のためにありました。
本講座では、中世からルネサンス期の宗教画に焦点を当て、その歴史と基本的な内容を概観するとともに、聖書の物語や教義を図解することを課された芸術家たちの努力と創造性をご紹介します。“神”一色に染まった中世から、やがて人間性と個性の発現をみるルネサンスに至る時代のなかで、多様化していった宗教画について理解を深めましょう。宗教画の見方、楽しみ方のポイントを学ぶことで、信仰のかたちをより身近に感じていただければと思います。
第4回 風俗画の確立と展開 -17世紀オランダから19世紀フランスまで 12/13(袴田紘代講師)
神話や聖書に題材をとった高尚な絵画ジャンルである歴史画にくらべ、身の回りの日常的な情景を描き出す風俗画は、長きにわたり下位のジャンルとみなされてきました。しかしながら同時代の風俗は古典古代から絵画で表され、17 世紀のオランダでは台頭する商工業市民の世俗的な関心を背景に、風俗画の専門画家たちが次々に輩出されます。
本講座では、風俗画のジャンルが確立した17 世紀オランダを起点に、18 世紀のロココ時代、さらに風俗画が現代生活の描写として新たな価値を見出す19 世紀後半のフランスまで、美術史における風俗画の展開をたどります。代表的な作品を鑑賞しながら、風俗画の発展を促した時代背景についても理解を深めていきましょう。
対象 どなたでも参加いただけます。
| 回 | 日付 | タイトル |
|---|---|---|
| 秋1回目 | 2025/09/20 | 【小林 亜起子 講師】自然を描く -古代から20世紀へ 変わりゆく風景表現 |
| 秋2回目 | 2025/10/18 | 【山本 樹 講師】神々を描く -古代から17世紀まで |
| 秋3回目 | 2025/11/15 | 【平井 彩可 講師】信仰を描く -中世からルネサンスまで |
| 秋4回目 | 2025/12/13 | 【袴田 紘代 講師】風俗画の確立と展開 -17世紀オランダから19世紀フランスまで |
日程
土曜日11:00~12:30
- 秋期全4回【満席受付終了】 :9/20、10/18、11/15、12/13
| テキスト | レジュメを配布します。 |
|---|

講師
多摩美術大学専任講師
小林 亜起子(こばやし あきこ)
パリ第十大学修士課程修了(修士・美術史)、東京藝術大学大学院博士課程修了(博士・美術)、ローザンヌ大学博士課程修了(博士・文学)。現在、多摩美術大学専任講師、東京藝術大学講師。
ローザンヌ大学文学部賞受賞。単著に『ロココを織る』(中央公論美術出版)、共著にArachné : un regard critique sur l'histoirede la tapisserie( Presses universitairesde Rennes)、『イメージ制作の場と環境』、『新古典主義美術の系譜』(2点ともに中央公論美術出版)など。

講師
国立西洋美術館主任研究員
袴田 紘代(はかまた ひろよ)
パリ第十大学修士課程修了(修士・美術史)、東京藝術大学大学院博士課程修了(博士 ・美術)。
国立西洋美術館での「北斎とジャポニスム」展学芸担当、「憧憬の地 ブルターニュ」展、「印象派̶室内をめぐる物語」展の企画構成・担当など。

講師
実践女子大学 助教
山本 樹(やまもと いつき)
東京藝術大学大学院美術研究科博士課程修了(博士・美術)。東京藝術大学教育研究助手、日本学術振興会特別研究員PD を経て現職。専門はカラッチ一族を中心とする近世ボローニャ派研究。
近年の論文:「ボローニャ、タナーリ家のアレクサンドロス大王伝‒ ルドヴィコ・カラッチの作品群とその「インヴェンツィオーネ」をめぐる一考察‒」(成城美学美術史紀要)

講師
東京藝術大学ほか講師
平井 彩可(ひらい あやか)
東京藝術大学大学院美術研究科博士課程修了。博士(学術)。
フィレンツェ大学留学(平和中島財団奨学生として)、東京藝術大学教育研究助手を経て現職。
主要業績:『サンドロ・ボッティチェッリの悔悛――後期作品研究』(中央公論美術出版)、「サンドロ・ボッティチェッリ「コンヴェルティーテ祭壇画」――ペゼッリーノ「ピストイア祭壇画」との比較から考える図像的要請」(Aspects of Problems in Western Art History)、「崇高の系譜――現代表象としてのゲームを例に」(文星紀要)
お問い合わせ
- クレセント・アカデミー事務室
-
- 開室時間:月〜金 9時~17時
- TEL:042-674-2267
- FAX:042-674-2268